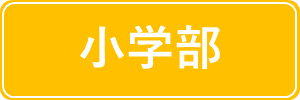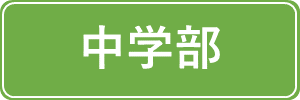あるB型事業所との懇談から
10月23日(金)
卒業生がお世話になっている事業所の方々とは、いろいろな機会でお話させていただくことがありますが、今日はあるB型事業所の管理者の方から伺った話を御紹介します。
その事業所には、「こだわり」の強い生徒が卒業後お世話になっていました。学校でも「こだわり」は随所に見られましたが、それほど大きな問題にはならず、在学中から何度か実習を行い、良い評価を得た上での利用開始でした。
通所を開始してしばらくは仕事にも頑張って取り組んでいましたが、徐々に特性である「こだわり」が出始め、さまざまな場面で他の利用者や職員を困らせることになっていきました。
管理者の方はこうおっしゃいました。『本人には障害があり、特性があることは理解しています。そのための就労支援施設でもあります。ただ、最も困ったのは、「こういう言動で周りが困っている」と保護者に伝えても「それは特性で、しかもうちの子は重度なので(施設で何とかしてください)」という態度でした。保護者の方が協力してくれる姿勢を示してくれないと、支援も行き詰ってしまいます。』
この話を伺い、また別のA型事業所管理者による言葉も思い出しました。その方は「その子自身の問題で手のかかる子になるのではなく、周囲の考え方、関わり方が問題をより大きくしてしまう場合がある」とおっしゃっていました。その方は、幼少期の関わりがその後の人生に特に大きな影響を与えることも、併せておっしゃいました。
自我を発揮し、思いを行動にすることは素晴らしいことで、「こだわり」も自己意思の表出の一種であると言えます。障害福祉の分野でも本人の「意思の自己決定」を最優先する支援がされています。ただ、社会は「集団」で成り立っていることもまた事実であり、他者との関係性は生きていく上で逃れることはできません。どんなにリベラル化が進んだ社会においても、残念ながらすべての「個性」「多様性」が無条件に許容されることはなく、他人の迷惑とならない範囲の「個性」でなければ容認されないのが現実でしょう。
子どもたちがより良い人生を送るために今できることは何か。私も進路指導について改めて考える機会となりました。
(C) 2013 Mashiko special needs School
(不許複製・禁無断転載)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
本校では、障害者スポーツ団体等によるスポーツ活動の振興を図るため、体育施設(体育館・グラウンド)の貸出しを行っています。
利用につきましては、本校までお問い合わせください。
【お問合せ】
平日9:00~16:30
TEL0285-72-4915