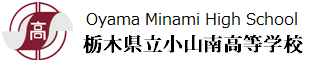本日、新型コロナウイルス感染防止に留意しつつ、令和3年度スポーツ大会が開催されました。
曇天ながらも蒸し暑さを感じる中、開会式が始まりました。
校長からの大会への取り組む姿勢等の話の後、大会委員長・大会運営からのそれぞれの注意点があり、体育委員長による選手宣誓が高らかに行われました。
生徒たちは、新型コロナウイルス感染症のためにほとんど行事を実施できなかった昨年度の経験と、今年度初めての学校行事ということもあって、生徒たちは朝から楽しみにして張り切っていました。
<そわそわしています>

<学校長挨拶>

<大会委員長挨拶> <大会運営上の諸注意>


<選手宣誓> <身体をほぐして…>


各種目の試合が始まると、生徒たちは熱のこもったプレーを見せてくれました。
劣勢からの大逆転や、力の差が圧倒的な試合、クラスを越えての応援のあった試合などなど…クラスで団結して他学年、他クラスとの交流をしていました。
「新型コロナ」による制約という限られた範囲の中でも、自分たちでいかに楽しむかを考えてそれを行動にうつす、生徒のたくましさや頼もしさを感じるスポーツ大会となりました。
<白熱の戦い!>