学習活動では、一般に教師側の評価と生徒自身の評価が一致していると効果的に学習を進めることができます。この意義が理解しやすいように、「情報」の実習において、「関心・意欲・態度」を評価する場合で考えてみます。
はじめに、生徒は教師から実習の要領や手順について説明を受けます。そして、実際に作業を始めると、画面やワークシートを前にして、じっと考え込んでいて作業が進まない生徒がいるとします。このような場合、教師は「作業が遅い・やる気がない」と受けとめて、「関心・意欲・態度」の観点で、低く見取ってしまうのではないでしょうか。しかし、実際には、この生徒は作業の段取りや構想をイメージするために一生懸命考えていたかもしれません。
この場合、生徒の自己評価(一生懸命やった)と教師の評価(やる気がない)は一致しませんから、このままでは、生徒の学びと教師の指導がかみ合いません。このように、教師が観察により見取った評価と生徒自身の評価が食い違っているために、指導が適切に進まないという場面を、日常の授業の中で経験していることではないでしょうか。これでは、生徒にとっても教師にとっても、評価が学習活動に役立っているとはいえません。
では、この場合に評価が生徒の学びや教師の指導として機能するためにはどうしたらいいでしょう。そのためには、教師は、この実習についての生徒自身の評価(自己評価)を的確に把握することが必要になります。そのことによって、教師は初めて、生徒の外面に現れない考えや悩みを掌握でき、生徒の誤りに気付いたり、問題を解決したりするための適切な指導が可能になってきます。また、生徒は自らを評価することにより、考えの問題点やつまずいている点を自覚することで、教師の指導や助言を参考にしながら、望ましい学習の方向性や問題の解決法を見いだしていくことができるようになります。このようにして、生徒自身が学習の状態を認識することを、学習のメタ認知といいます。
学習の途中で自己評価ができる場面を適宜取り入れていくことは、生徒に学習過程におけるつまずきを確認させたり、到達度を認知させたりしながら、その後の授業の方向性を見出させるための重要なポイントであると言えます。図6は、自己評価を取り入れた学習の流れを示しました。
また、普通教科「情報」では、知識伝達型の学習ではなく、生徒自身の創造的な思考や生徒自身からの情報発信など主体的・能動的な学習活動が求められています。そのためには、生徒自身が達成度を自身で認知できる能力や、考える筋道や検索の方法を考えたりできる能力を育てることが必要といわれています。そのためにも自己評価のための活動を取り入れていくことの意義は大きいと言えます。
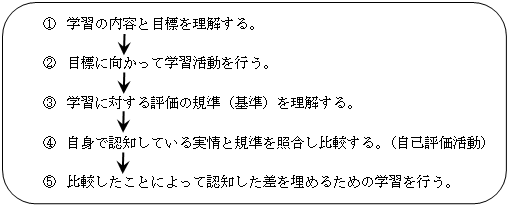
自己評価の目的は、生徒自らが学習の実情や到達度を認識することにあります。しかし、自らの学習の状況の評価が独りよがりになったり、自己満足であったりしては意味がありません。そうならないためには、できる限りルーブリックのような客観的な物差しを示し、それを規準(基準)として評価させていくことが必要になります。活動としては、教師があらかじめルーブリックのような形で到達目標や判断規準(基準)を示し、チェックリストなどで確認させたり、良くできたことや疑問点、改善点などを文章でまとめさせたりすると効果的です。また、自己評価は、レポートや作品、プレゼンテーションなどの実習の成果を、生徒同士で互いに評価し合う活動(相互評価)を取り入れるとより的確なものとなります。
このように、様々な評価活動、評価方法を工夫することにより、生徒のメタ認知能力を高めていくことができます。すなわち、自分の学習を見つめるもう一人の自分をもち、そのもう一人の自分の「自分を評価する力」が次第に育ってくるということです。
また、生徒が、目標に向かって向上している自分の姿を確認したり、学習に対する自信や興味・関心をもつことができるようにしたりするためには、このような評価活動を学習の経過とともに積み重ね、時には振り返ることも重要です。そのために、生徒自ら実習の作品やその評価などをファイリングして、集積していけるような工夫ができるとよいでしょう。