| 目 的 | 地域連携教員としての職務、今日的な教育課題、地域連携の進め方等について理解を深め、地域連携教員としての資質の向上を図る。 |
| 日 時 | 平成29年10月16日(月) 9:30~16:00 |
| 対 象 | 平成29年度の小・中・高・特の新任地域連携教員。社会教育主事有資格者(昨年度までに有資格者となった者)は、第2日を免除とするが、聴講することは可能。ただし、これまでにこの研修を受講した者を除く。また、昨年度中に新任地域連携教員になった者で、この研修を受講していない者を含む。 |
| 研修内容 | 1 シンポジウム「連携活動を円滑に進めるためにⅠ」
2 講話・演習「地域連携を円滑に進めるためにⅡ ~ビジョンの共有~」
3 研究協議「地域連携教員としてのマネジメントⅡ ~活動計画を見直す~」
|
| 講 師 | 地域コーディネーター(小・中・高)
県教委事務局生涯学習課職員
総合教育センター職員
|
| 研修の様子 | | | | 1 シンポジウム「連携活動を円滑に進めるためにⅠ」 | | | 2 講話・演習
「地域連携を円滑に進めるためにⅡ
~ビジョンの共有~」 | 3 研究協議
「地域連携教員としてのマネジメントⅡ
~活動計画を見直す~」 |
|
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度 | | 満足 | 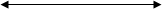 | 不満足 |
1 シンポジウム「連携活動を円滑に進めるためにⅠ」 【目標】 | 円滑な連携活動を推進するため、地域連携に関するコーディネートの工夫や留意点について理解する。 |
【講話を通しての主な意見・感想】
〈小学校〉 - コーディネーターの方が気を付けている点や留意点、学校側に求める点について、生の声を聞くことができ、今後の関わり方に幅が出たような気がする。
- コーディネーターの方がどのような意識をもって活動されているのかが分かり、大変よかった。本校ではコーディネーターの方が忙しいだろうとお願いを遠慮している部分があったが、積極的に相談し、地域ボランティアを活性化したい。
- 学校・家庭・地域が連携することで、心豊かな子どもを育成することになる。地域も活性化する。学校が地域とともに歩むことができるということを再確認した。
- 実際にコーディネーターとして活躍されている方々のお話をうかがい、違う立場での思い、留意点、課題など、学校側が受け取り改善できる事項が多々あると思った。自校の取組に活かしたい。
〈中学校〉 - シンポジストの方々の話の中で、実体験に基づいた「やらないでいいこと」「やってほしいこと」をはっきり伝え合える関係づくりは、WinWinの関係、信頼関係のもとで築かれる、ということが分かった。すべて継続が大切である。
- コーディネーターの方たちがどのようなことを具体的に行っているのか、また我々教職員がどう具体的に関わっていくべきか、わからないことだらけであったが、いろいろと理解することができた。1人で何かをしようというのではなく、管理職とも連携を図りながら、やれることからやっていけたらと思えた。
- 3名の方の、コーディネーターとしての姿勢に対して、まず頭の下がる思いである。学校はそういう方たちを財産として大切に対応していくこと、力を貸していただくという気持ちが何よりも大切だと思った。
〈高等学校〉 - コーディネーターの活動について知れたのは良かった。またコーディネーターが学校・教員に求めるものを知ることができたのは大きかった。事前にどのようなことを考えた上で話合いに参加すれば良いのかわかった。
- 地域コーディネーター、学校の地域連携教員、両者の良好な関係が、学校と地域を結びつける。
〈特別支援学校〉 - 学校・地域の信頼関係づくりの大切さを改めて考えさせられた。子どものためにコーディネート!忘れがちになっていた。もう一度、念頭において、地域との連携を図っていきたいと思う。
2 講話・演習「地域連携を円滑に進めるためにⅡ ~ビジョンの共有~」 【目標】 | 講話・演習を通して、教職員、地域住民が互いのビジョンを共有し、多様なアイディアを出し合いながら取り組むワークショップの模擬体験において、教員研修の必要性とそれを企画するための手法を理解する。 |
【講話を通しての主な意見・感想】 〈小学校〉 - 校内研修を職員だけで行うのではなく、地域の方々も交えてできるよう、管理職・教務に相談していきたい。
- 研修の場をこれまで十分に計画できなかったことを大いに反省するとともに、実情に合わせ、いろいろな内容を取り込み、現職教育や地域連携協議の一貫として取り組んでいきたい。
- 連携というと具体的なところにばかり目が行き、話してしまうが、互いのビジョンの共有が何といっても大切だと感じた。これは「学校と地域の連携~学校経営バージョン~」として活用できると思う。
- 各学年の取組を、全教員が共有するため、また新しい活動を考えるためにも、現職教育で取り入れていきたいと思う。
〈中学校〉 - 地域連携の必要性の認識は教員間に温度差がある。今後の活動を充実したものとするためにも、手法を生かしていきたい。
- 1人では限られたアイディアしか出ないが、職員みんなで考えれば、多種多様なアイディアが出る。地域との連携について、みんなで考えてみたいと思いました。特に地域のイベントに出て行くことを考えたい。
- ビジョンをしっかり持つことの大切さを再認識できた。また、話し合うことの大切さを感じられた。出てきたアイディアを持ち帰り、自校の取組にいかしたいと思う。
〈高等学校〉 - 計画を立て実施するためには、ビジョンの共有が重要であることを再認識することができた。
〈特別支援学校〉 - ファシリテーターとしてのスキルや役割を身に付けたいと思った。
3 研究協議「地域連携教員としてのマネジメントⅡ ~活動計画を見直す~」 【目標】 研究協議を通して自校の計画の見直し、今後の地域連携活動の充実を図る。
|
【講話を通しての主な意見・感想】 〈小学校〉 - まずは先生方のニーズをきちんと把握して、どんな場面で力を借りればよいのか考えて、コーディネーターの方と協力して活動していきたい。
- 校内での情報交換を常時行っていくことの大切さを学ばせていただいた。地域連携教員が一人で頑張るのではなく、全職員の協力のもと推進していけるようにしていきたいと思う。
- 年間計画をしっかり作成する。必要事項を朱書し、見直しを図る。積み重ねにより、よりよい地域連携活動が行えると感じた。
- コーディネーター不在の地域なので、開拓や整理、実践を行わねばならない。できる範囲でやっていきたい。
〈中学校〉 - 今以上にいろいろなことを実施するのは、教職員や生徒の負担が大きくなると思う。今、取り組んでいることを精査して、より活動的にやったり、何かプラスしていければいいのではないだろうか。
- 同僚への情報発信が不十分であることに、改めて気づいた。全職員が同じ認識のもとで行わないと、本来のねらいや目的まで理解を得られないことにもなりかねない。担当者として心に留めておきたいと思う。
- 現在の資源を利用し、地域を受入れ、地域に子どもを出していきたい。
〈高等学校〉 - コーディネーターを活用し、様々な人材を学校で活用する。どこにどんな人材がいるのか明確に把握し、教員からの要請があった時には、適切なアドバイスができるようにする。
- 全教員により共有したビジョンをもとに、校内における計画を立案したいと思う。
〈特別支援学校〉 - 地域連携教員として大きな仕事の一つにボランティアさんの活用というところがある。登録されたボランティアさんには、ボランティア保険(300円)に入っていただくが、調整するとボランティア活動が1度もない人が出てくる。そうならないための方策を考えたい。
|