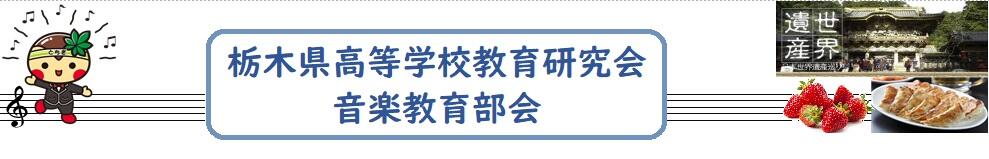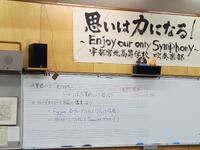文字
背景
行間
お知らせ
令和7年度前期研究会報告
令和7年7月1日(火)に、学校法人フェリス女学院学院長の秋岡陽先生をお迎えして、前期研究会を実施しました。
今回の研修のテーマは、「授業で愉しむ音楽学」ということで、秋岡先生の著書「秋岡教授の音楽学を愉しむ24の扉」より、「典礼と合唱」「ソナタ形式とは」「日本へのクラシック音楽の流入」の3つの内容で講義をしていただきました。
「典礼と合唱」では、聖務日課についてや一般的なミサと死者のためのミサのそれぞれの内容の違いや、当時のミサで使われていたクワイアブックに書かれている楽譜を読み解く面白さなどを教えていただきました。
「ソナタ形式について」では、作曲者や時代によってソナタ形式の捉え方が違っているということを前提に、いくつかの例を提示していただきながらその奥深さ、面白さをお話いただきました。
「日本へのクラシック音楽の流入」では、明治以降どのようにしてクラシックが日本に浸透してきたのかを、楽しく紐解いていただきました。
また番外編として、現代の音楽事情の多様性を踏まえて、今後の音楽教育等にどのように向かっていくことが必要なのかということについてのヒントをいただきました。
実りの多い研究会になりました。
令和7年度 栃高教研音楽部会事業計画
栃木県高等学校教育研究会音楽部会 令和7年度事業計画
令和7年 4月24日(木) 役員会
5月13日(火) 総会
7月 1日(火) 前期研究会 「授業で愉しむ音楽学」
講師:秋岡 陽 氏
(学校法人フェリス女学院学院長)
11月20日(木) 後期研究会 「研究授業」(栃木高等学校)
令和8年 1月22日(木) 役員会
令和6年度 音楽部会研究会報告
6月24日に今年度の前期研究会として、「鑑賞の言語化について」をテーマに、玉川大学芸術学部音楽学科教授の野本由紀夫先生をお迎えして研修を行いました。
2024年はベートーヴェンの「第九」が完成し、世界初演(1824年5月7日)されてから「200年」となる記念の年ということと、事前アンケートの結果で、鑑賞の授業で「第九」を扱っている先生方が多数を占めていたということから、「第九」を鑑賞教材として「感性を磨くためのアナリーゼ」について研修を行っていただきました。
アクティブ・ラーニングの学修構造や、鑑賞と表現は表裏一体であることなどをご教授いただき、その後、ベートーヴェン自身について、そして「第九」のアナリーゼを学びました。
11月19日の後期研究会では、ソプラノ歌手の隠岐彩夏先生とピアニストの有岡奈保先生をお迎えして、「歌曲を通して、生徒の豊かな感性を引き出す方法」についての研修を行いました。
前半は、隠岐先生と有岡先生による、コンサートを鑑賞しました。
コンサートでは、ヘンデル、シューベルト、フォーレ、プーランク、クィルター、ドヴォルザーク、オブラドルス、ガーシュイン、伊藤康英と、年代・国籍の異なる作曲家の歌曲を、説明を聞きながら鑑賞しました。
後半では、「Caro mio ben」「野ばら(シューベルト)」の2曲について、豊かな感性を引き出す歌唱指導について研修を深めました。
令和6年度 栃高教研音楽部会事業計画
栃木県高等学校教育研究会音楽部会 令和6年度事業計画
令和6年 4月25日(木) 役員会
5月14日(火) 総会
6月24日(月) 前期研究会 「鑑賞の言語化(仮題)」
講師:野本 由紀夫 氏
(玉川大学芸術学部音楽学科教授)
11月19日(火) 後期研究会 内容未定
講師:隠岐 彩夏 氏
(ソプラノ歌手)
令和7年 1月23日(木) 役員会
3月 下旬 音楽部会研究集録 第16号 発行
令和5年度 後期研究会報告
令和5年11月14日に、宇都宮北高等学校にて、後期研究会を実施しました。
今回の研修内容は、国立音楽大学音楽部准教授の瀧川淳先生をお招きして、「ICTを活用した音楽的な学びについて」の研修会と、宇都宮北高等学校の宮田先生による、「ICTを活用した旋律の創作」の研究授業でした。
まず、宮田先生の1年生の音楽Ⅰの創作の授業を見学しました。
宇都宮北高等学校では、年間を通してPC(タブレット)を活用した授業を行っており、今回の題材は、Web音楽学習プラットフォーム『Musicca』で演習した楽典の知識の応用実践として設定したもので、教育芸術社提供のWebアプリケーション『カトカトーン』を用いて旋律を作成する内容でした。
研究授業では、6時間扱いの授業の5時間目の授業で、前時までに生徒がそれぞれ作曲した作品について、「質問作り」により、「よい旋律」とはを考察し、他者の意見も聞き思考することで、実践への理解を深めること、他者の作品を鑑賞して得たヒントやもらったアドバイスを基に、自身の作品を振り返り、改善点を見いだしてより表現を深めることを目標とした授業でした。

生徒たちは、Webオンラインホワイトボード『Figjam』を活用して、「よい旋律」について問いをたて、思考を深めていく様子が見られました。


生徒が作った作品の鑑賞では、感想やアドバイスを『Figjam』の付箋に記入し、それぞれのグループのボードに貼り付け、活発な意見交換がなされていました。
午後からの瀧川淳先生の研修では、タブレットを活用することで深めることのできる学びについて講義をいただき、授業で活用できる、さまざまなアプリケーションをご紹介いただきました。
後半では、宮田先生の授業でも活用されていた『カトカトーン』を実際に使って、演習を行いました。
『カトカトーン』は、教育芸術社が作成した音楽Webアプリケーションで、2023年4月に試験公開版が公開されています。初心者にも分かりやすく音楽作成ができるものです。

『カトカトーン』を実際に使ってみて感じたことは、分かりやすく直感的に操作でき、作成した音楽をオーディオファイル・楽譜・MIDIファイルなどに書き出すことができることで、簡単に音楽を共有して楽しむことができるとても使いやすいものだなということです。
今回の研修会で瀧川淳先生にご紹介いただいたさまざまなアプリケーションや活用方法は、すぐにでも実践できる内容のものばかりでしたので、これからの授業で活用していけたらと思います。