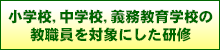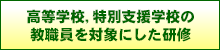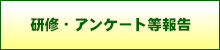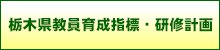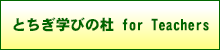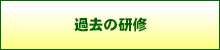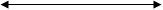令和6(2024)年度 新任主幹教諭研修(高等学校、特別支援学校)
| 目 的 |
主幹教諭としての職務、学校経営への参画の在り方等について理解を深め、主幹教諭としての資質の向上を図る。 |
| 日 時 |
令和6(2024)年 5月31日(金) 9:30~16:00 |
| 対 象 |
高等学校、特別支援学校の新任主幹教諭 |
| 研修内容 |
1 講話「主幹教諭の職務」
2 講話「主幹教諭に求められる役割」
3 演習・研究協議「主幹教諭に求められるマネジメント」
4 講話・ワークショップ「主幹教諭に求められるリーガルマインド~価値観の多様化と学校運営~」 |
| 講 師 |
大学等職員
県立学校職員
県教委事務局高校教育課職員
総合教育センター職員 |
| 研修の様子 |
|
|
|
|
講話「主幹教諭に求められる役割」
|
演習・研究協議「主幹教諭に求められるマネジメント」
|
|
|
|
|
講話・ワークショップ「主幹教諭に求められるリーガルマインド~価値観の多様化と学校運営~」
|
|
| 研修評価・振り返りシートから |
0 研修の満足度、活用度
本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。
| |
そう思う |
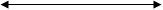 |
そう思わない |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 満足度 |
95.4% |
4.6% |
- |
- |
1 講話「主幹教諭への期待」
【目標】
| 国や県の教育改革の動きを踏まえ、主幹教諭に期待される役割を理解する。また、主幹教諭としての心得について認識を深め、主幹教諭としての自覚を高める。 |
【講話を聞いての主な意見・感想】
- 教職員のミドルリーダーとして、学校運営・教育活動の中核的な役割を担うこと、管理職を補佐するとともに、垂直的調整機能、水平的調節機能として動く必要があること、日頃から、管理職や先生方とコミュニケーションを多くとり、教育活動が円滑に進むように努めることが大切だと思いました。
- 学校運営全体に関わるためには視野を広く持つことが必要であり、情報収集がとても重要になると感じました。多くの先生と関わり、そこから得た情報を整理し管理職に伝えることと、管理職の考えを先生方に伝えることで、同じ方向に向かって学校課題に向き合えるように下支えをしていきたいと思います。
2 講話「主幹教諭に求められる役割」
【目標】
| 主幹教諭としての実践的な取組を聴くことによって、校内組織における主幹教諭に求められる役割を理解するとともに、自らの取組の参考とする。 |
【講話を聞いての主な意見・感想】
- 学校内での主幹教諭の役割が理解できました。求められる仕事は多岐にわたるので、多くの先生方と情報を交換したり、支援を受けたりしながら与えられた業務やこれから起こるだろう学校課題等について対応していきたいと思います。
- 学校の業務改善についてなど、さまざまな相談を受けることがあります。その際には傾聴し、業務担当者と協力することで、より良い学校づくりに取り組みたいと思います。まずは、欠席連絡をFormsに変更することに取り組みたいです。
3 演習・研究協議「主幹教諭に求められるマネジメント」
【目標】
| 主幹教諭として担当する校務における現状を振り返り、組織運営体制の改善についてヒントを得る。 |
【演習・研究協議を通しての主な意見・感想】
- いろいろな文書や資料を目にする中から気付き得た課題について、すぐに取り組める改善案を立案し周知したり、関係分掌部長と協議しながら実現可能な対応をまとめたりしていきたいと考えました。
- 主幹教諭としてコミュニケーションを円滑にしていきたいと考えました。そのために、日頃から職場のミッションや目標を教職員みんなで共有・確認し、それに向かって仕事を進めていく体制づくりをしなければならないと思います。教職員がお互いのノウハウや経験を共有し、自然とコミュニケーションがとれる職場環境づくりに力を入れていきたいです。
4 講話・ワークショップ「主幹教諭に求められるリーガルマインド~価値観の多様化と学校運営~」
【目標】
| 学校現場における危機管理の在り方を考えるにあたり、教育実践で必要となるコンプライアンスの視点を得る。 |
【講話・ワークショップを通しての主な意見・感想】
- 先生方の危機管理マニュアルの理解度を向上させることが重要だと考えました。事前の危機管理と発生時の危機管理、事後の危機管理の3つの視点について主幹教諭の立場で考えながら、学校教育を実践していきたいです。
- 行事での取組や学校からの通知、さらに有事の際の対応がどの法令に該当するか、保護者の御理解が得られるものであるか、学校外の方がどのように感じるかなど、根拠、保護者目線、第三者的視点をもって吟味し、未然防止や改善につなげていきたいと思います。
|