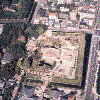 |
足利学校 |
|---|---|
| 足利学校はどのような歴史をたどってきたか |
(1)創設期~室町(むろまち)中期
足利学校の創建についてはいくつかの説があり、いまだにはっきりしたことはわかっていません。
奈良時代(ならじだい)の国学が起こりとされる説、平安時代(へいあんじだい)の小野篁(おののたかむら)による創建説、鎌倉時代(かまくらじだい)の足利義兼(あしかがよしかね)の創建説などがありますが、歴史がはっきりしてくるのは上杉憲実(うえすぎのりざね)(室町時代)によって学校建設、制度の整備などが行われてからです。
室町時代に入り、永享(えいきょう)4年(1432年)、関東管領上杉憲実が足利の領主になって自ら学校の再興にあたり、鎌倉円覚寺(かまくらえんかくじ)の僧快元(かいげん)を庠主(しょうしゅ)(校長のこと)に招いたり、数多くの蔵書を寄贈したりして学校建設を進めました。
その成果があって全国から学生が集まり、代々の庠主も全国各地の出身者に引き継がれていきました。
教育の中心は儒学でありましたが、易学においても有名であり、また兵学、医学も教えました。
戦国時代(せんごくじだい)には、足利学校の出身者が易学等の実践的な学問を身に付け、戦国武将に仕えるということがしばしばあったといわれています。
学費は無料で、学生は入学すると同時に出家して僧侶になりました。学生のための宿舎はなく、近くの民家に寄宿し、学校の敷地内で自分たちが食べるための菜園や薬草園などもつくられていたといわれています。
(2)室町後期~江戸(えど)期
享禄(きょうろく)年間(1530年頃)には火災で一時的に衰えましたが、第7代庠主、九華(きゅうか)が後北条氏(ごほうじょうし)の保護を受けて足利学校を再興し、学生数は3000人を数えると記録されるほどでありました。
この頃の足利学校の様子を、キリスト教の宣教師フランシスコ・ザビエルは「日本国中最も大にして最も有名な坂東(ばんどう)のアカデミー(坂東の大学)」と記し、足利学校は海外にまでその名が伝えられました。
ザビエルは、「国内に11ある大学やアカデミーの中で、最大のものが足利学校である。学校自体は、寺院の建物を利用し、本堂には千手観音(せんじゅかんのん)の像があります。本堂の他に孔子廟(こうしびょう)が設けられている。」などと伝えています。
しかし、天正(てんしょう)18年(1590年)の豊臣秀吉(とよとみひでよし)による小田原征伐(おだわらせいばつ)の結果、後北条氏と足利・長尾氏が滅び、足利学校は重要な保護者を失ってしまいました。
学校の財源であった所領が奪われ、豊臣秀次(とよとみひでつぐ)によって蔵書の一部が京都(きょうと)に持ち出されるなど、この時期の足利学校は大きな打撃を受けました。
しかし当時の第9代庠主・三要(さんよう)は、関東の新領主である徳川家康(とくがわいえやす)に近づき、家康の保護を得ることによって足利学校は再び復興しました。
江戸時代に入ると、足利学校は100石の所領を寄進され、毎年の初めにその年の吉凶を占い、幕府に提出することになりました。
また、たびたび異動があった足利の領主たちによっても保護を受け、足利近郊の人々が学ぶ郷学(ごうがく)として、江戸時代前期から中期にかけて二度目の繁栄を迎えることになります。
しかし、その後、京都から関東に伝えられた朱子学(しゅしがく)が幕府の学問の中心になったり、平和な時代が続いて易学、兵学などの実践的な学問が好まれなくなったりしたため、足利学校は徐々に衰えていきました。
こうして学問の中心としての性格は薄れ、江戸時代の学者たちは、貴重な古典を所蔵する文庫として足利学校に注目していました。
(3)明治期~現在
明治維新後、足利藩は足利学校を藩校とすることで復興を図りましたが、明治4年(1871年)、廃藩置県(はいはんちけん)の実施により足利藩校である足利学校の管理は足利県〔のち栃木県(とちぎけん)に統合〕に移り、明治5年(1872年)には廃校になりました。
廃校後、方丈などがあった敷地の東半分は小学校に転用され、建物の多くは撤去されました。
地元足利市は明治36年(1903年)、足利学校の敷地内に、栃木県内初の公共図書館である足利学校遺蹟図書館を設立し、足利学校の旧蔵書を保存するとともに、一般の図書を収集して公開するようになりました。
また大正(たいしょう)10年(1921年)には足利学校の敷地と孔子廟や学校門などの現存する建物が国の指定史跡となり、保存されることになりました。
1980年代になり、史跡の保存整備事業が始められ、平成(へいせい)2年(1990年)には建物と庭園の復元が完了し、江戸時代中期のもっとも栄えた時の様子が再現されました。



 前のページへ
前のページへ
