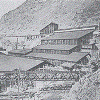 |
足尾銅山の歴史 |
|---|---|
| 明治(めいじ)・大正時代(たいしょうじだい)の足尾銅山はどんなようすだったか |
(1)明治・大正時代の略年表
| 明治元年(1868年) | ・足尾銅山は明治新政府に没収されて、県の管轄になります。 |
|---|---|
| 明治10年(1877年) | ・古河市兵衛(ふるかわいちべえ)により銅山を民営化して、組織的開発と技術革新を図ります。 |
| 明治18年(1885年) | ・渡良瀬川(わたらせがわ)の魚類の大量死が始まります。 |
| 明治19年(1886年) | ・通洞、本山とともに銅山の3本柱として、小滝坑が開かれます。 |
| 明治20年(1887年) | ・全国の銅生産量の40%を生産します。 | 明治29年(1896年) | ・渡良瀬川沿岸の大洪水による被害から、足尾銅山から流出する鉱毒の問題が明らかになります。 ・通洞が完成します。 | 明治30年(1897年) | ・足尾鉱毒予防工事命令が出されます。 ・政府の命令を受け、集塵処理(しゅうじんしょり)などの鉱毒予防工事を行います。 | 明治40年(1907年) | ・足尾銅山(あしおどうざん)暴動(ぼうどう)が起こり、施設が機能停止に追い込まれます。 | 大正3年(1914年) | ・足尾式鑿岩機(さくがんき・・・岩をくだく機械)を完成させます。 | 大正5年(1916年) | ・足尾銅山の最盛期です。人口が県内2位の約3万8千人余りとなります。 |
(2)銅山のようす
①明治10年、古河市兵衛により民営化され、最新の技術や設備によって鉱山施設の電化、近代化が進められみごとに復活しました。
②明治20年代には国内全産銅の40%以上を産出する日本一の銅山となり、日本の近代化に大きく貢献しました。
③その一方で、鉱毒事件を起こし、周辺地域に大きな被害を及ぼしました。
④大正時代には、足尾式鑿岩機が考え出され、手堀りから機械堀りへと変わり、作業が早くできるようになりました。



 前のページへ
前のページへ
