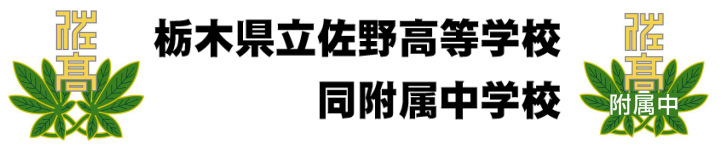文字
背景
行間
ブログ
校長室(自宅)便り⑤
今日は、また本を紹介しようと思います。
郡司芽久(ぐんじ めぐ)著 「キリン解剖記」(ナツメ社、2019年8月発行)

これまでに紹介した「佐高ミュージアム」でも、ブタの眼球や脳の解剖について書いたことがありましたが、生徒は基本的に「解剖」は大好きです。「今度、解剖をやるからな」というと、最初は「えー?」と声を上げますが、内心は楽しみでワクワクしている、という生徒が多かった、という印象があります。
実は、私は佐野高校で最初に教壇に立ってから、毎年、生物の授業でニワトリの解剖を見せてきました。生物の教科書は、たいてい「細胞」の単元から始まり、細胞の集まりである「組織」(筋組織、神経組織等)、さらには「器官」(胃、小腸、脳等)、「器官系」(消化器系、循環器系等)という風に進んでいきます。器官や器官系を理解してもらうには、実物に勝るものはない、と考えていたからです。
当時、親しくさせていただいていた市内の肉屋さんを通じて、卵をあまり産まなくなった「廃鶏」を業者から譲ってもらい、授業の直前にさばいたニワトリを生物室に持ち込み、解剖を行いました。そのことは、生徒たちの印象にも残ったらしく、当時高校生だった生徒が、いまや佐高や附属中の生徒のお父さんになっていて、「あの時の解剖は覚えています。」とか「先生、解剖やってたこと覚えています」と、今年の入学式で何人かの保護者から声をかけられました。
当時、親しくさせていただいていた市内の肉屋さんを通じて、卵をあまり産まなくなった「廃鶏」を業者から譲ってもらい、授業の直前にさばいたニワトリを生物室に持ち込み、解剖を行いました。そのことは、生徒たちの印象にも残ったらしく、当時高校生だった生徒が、いまや佐高や附属中の生徒のお父さんになっていて、「あの時の解剖は覚えています。」とか「先生、解剖やってたこと覚えています」と、今年の入学式で何人かの保護者から声をかけられました。
さすがに今はできないですが、その伝統?は生徒に脈々と引き継がれています。科学部では、旭城祭の展示の中で、毎年、カメの解剖のデモンストレーションを行っています。かならず、部長が執刀する「ならわし」があり、解剖の開始を校内放送で告知すると、大勢のお客さんが集まってきます。なかには、解剖が終わった後も、そのまま残って部員を質問攻めにするお客さんも毎年何人かはいるようです。
また、科学部には、「私は解剖がやりたい」という理由で入部する生徒も何人もいました(いずれも女子です)。「解剖女子」たちはみな行動力があり、道端に動物の死体が落ちていると、ためらわずに拾ってきます。タヌキ、カラスなど、見つけると家の方に車を出してもらって、佐高まで運んできて、自分たちでてきぱきと解剖をしていました。自分で本を探して解剖の仕方や骨格標本の作り方を勉強しており、顧問の私が何かを教える、といった余地は、ほとんどありませんでした。
また、科学部では、2013年から2017年までは、カメの繁殖を研究テーマとしており、多くのカメを解剖し、卵巣の状態や体内の卵の成長の様子を詳細に計測しました。1年間で数十体以上は解剖しました。これらの研究成果は、日本学生科学賞のみならず、カメに関する学会の発表でも高く評価されました。そうした研究を支えていたのは、卓越した技術と信念を持って取り組んていた「解剖女子」の存在を抜きにしては語れません。
一般的に、「解剖が好き」というと、「あいつ、あぶないんじゃないか?」といった周囲の偏見の目もありがちですが、「解剖」は、生物の体の仕組みを理解する方法として、最も基本的な手法で、今後もその必要性や意義は不変です。研究活動や学習としての「解剖」はとても重要であると思っています。
前置きが長くなってしまいましたが、著者の郡司さんは、1989年生まれの「解剖女子」で、現在、国立科学博物館で「キリンの解剖」を仕事にしています。
郡司さんは、幼少期からキリンが好きだったそうですが、中学高校時代は部活や勉強が楽しくて、キリンに夢中といったわけではありませんでした。そして、転機は18歳の春に訪れました。2008年、大学(東京大学)に入学し、4月半ばに大学主催の「生命科学シンポジウム」に参加し、「この先生たちみたいに一生楽しめる大好きなものを仕事にしたいなあ」という思いが生まれました。そして、ふと思い出しました。「そういえば、私、動物の中でも特にキリンが好きだったなあ」
それから、大学の数十人の先生の話を聞き、「キリンの研究ができないか」聞いて回りました。当然のことながら、日本には野生のキリンはいるはずもなく、生物学の本流は、分子生物学にあったことから、「キリンの研究ができますよ」という先生には全く出合えませんでした。
ところが、チャンスはやってきたのです。入学から半年たった2008年の秋、後期の授業で、「博物館と遺体」という名前のゼミナール(少人数のゼミ形式の授業)が開講されることになりました。担当教授は、「解剖男」を自称する遠藤秀紀先生で、受講者を決める選考用紙の最後に一言、「キリンの研究がしたいんです。」と書きました。
選考を通過した後、最初の実習の休憩時間、遠藤先生から「キリンの遺体は結構頻繁に手に入るから、解剖のチャンスは多いよ。研究できるんじゃないかな」と、さらっと答えられ、彼女のキリン研究者への道が開けてきたのでした。
この本は、全くのシロウトの「解剖女子」が、周囲の人たちを巻き込みながら、「キリン研究者」となっていくまでの頑張りを時間の流れとともに、具体的に説明してくれています。これを読むと、「ああ、こうやって研究者になっていくんだな」と納得させられます。
ところで、人間を含めて、哺乳類の首の骨の数は7個と決まっています。一方、キリンは長い首を持っているため、高い木の上の葉っぱを食べたり、地面に口をつけて水を飲んだりもします。彼女は、なぜこのような上下の首の移動(可動範囲が大きい)が可能になるかに目を付け、多くのキリンを解剖した結果、キリンは胸の骨の一つが、首の骨と同じように動かすことができる8番目の首の骨に相当し、下向きに首が折れやすくなっていることを発見したのです。
この発見を聞いて皆さんはどう思いますか?「これは大発見だ。すごいぞ!」と素直に思う人もいると思いますが、「それがわかったことが、何の役に立つの?」と感じる人もいるかもしれません。おそらく、前者はこの本を手に取り、後者はスルーしてしまうでしょう。
ところで、博物館には、「3つの無」という理念があるそうです。「3つの無」とは、無目的、無制限、無計画、です。「これは研究につかわないから」「もう収蔵する場所がないから」「今は忙しいから」 そんな人間側の都合で、博物館に収める標本を制限してはいけない、という戒めのような言葉だそうです。たとえ、今は必要がなくても、100年後、誰かが必要とするかもしれない。その人のために、標本を作り、残し続けていく。これが博物館の仕事なのだそうです。
今の世の中、「それが何に役に立つのか」が問われ続けています。「キリンの首の骨」の秘密が解明されたからといって、どこかに経済的な利益がもたらされるものではありません。役に立つかどうかと言われれば、100%役に立つことはないでしょう。
でも、研究はそれでもいいと思います。それでもいいと保証されるから、研究が世代を超えて繋がっていくのではないかと思います。研究は、役に立つからやるのではなく、好きなことだからやるんだ、という当たり前のことをこの本は教えてくれました。
でも、研究はそれでもいいと思います。それでもいいと保証されるから、研究が世代を超えて繋がっていくのではないかと思います。研究は、役に立つからやるのではなく、好きなことだからやるんだ、という当たり前のことをこの本は教えてくれました。
さらに、関連本を紹介します。


②遠藤秀紀著 「解剖男」(講談社現代新書、2006年2月発行)
③遠藤秀紀著 「パンダの死体はよみがえる」(ちくま新書、2005年2月発行)
③遠藤秀紀著 「パンダの死体はよみがえる」(ちくま新書、2005年2月発行)
→「キリン解剖記」の著者(郡司さん)の師匠である自称「解剖男」遠藤先生の著書です。さらにコアな「解剖の世界」へあなたを誘います。
④養老孟司著 「解剖学教室へようこそ」(ちくま文庫、2005年10月)
→附属中の必読図書100冊の中に入っています。中学生の各教室に置いてありますから、一度手に取ってみてください。
緊急情報
特にありません。
カウンター
0
9
9
0
6
7
1
5