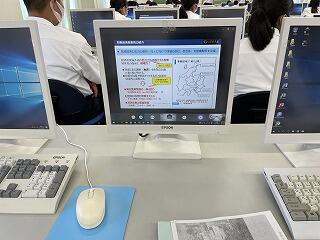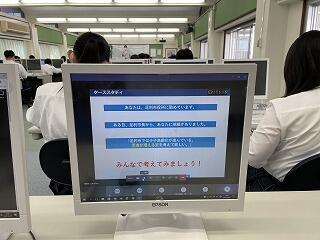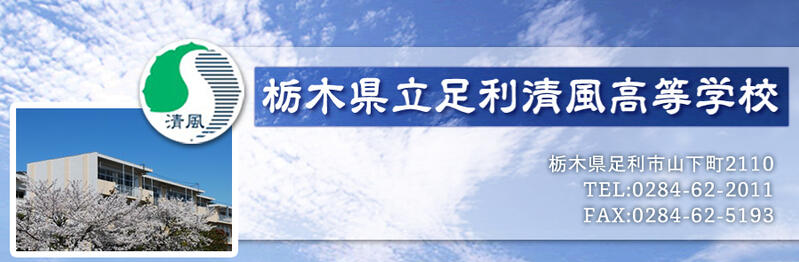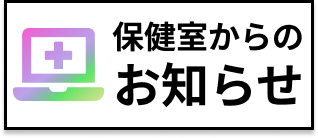令和3年度入学生 商業科
4/27 企業を知る(1)
4/20 インターンシップ オリエンテーション
インターンシップの趣旨や目的、実施時期、注意事項等、進行計画に沿って話がありました。
令和4年度 4/13 オリエンテーション
まとめ:発表会へ向けて
3月15日(火)⑤⑥⑦ アイデアをまとめる
2月に予定していた活動を延期して午後の授業3時間を使い授業を行いました。
当初予定した「対面でのポスターセッション」から、「動画による発表会」へ変更したことを伝え、3年生が作成した課題研究発表会の動画を視聴しました。
その後、オンライン等を活用し、話し合っていたアイデアを班ごとにまとめ、発表用のポスターを制作しました。
現状把握ではデータに基づいた分析となるように、根拠としたデータを見やすい形で提示する。必ずそのデータの出店についても明示する。生徒はこの一年間で学んだことに気を付けながら、発表会に向け準備を進めました。各班とも仕事を上手に分担し、協力して進めており、発表がとても楽しみです。
※1・2学期に商業科の授業を探究の時間に振替実施していたため、3学期まとめて探究の授業となっています。
3月17日(木)⑤⑥⑦ 動画撮影
予定していたSDGsカードゲームについても感染リスクの高い活動と考え、次年度への延期としました。
今日は自分たちの発表の動画撮影を行いました。動画は3分から5分程度で、声の大きさや、ポスターの配置など見る人の立場に立って撮影を行うよう注意しました。全員が発表に携われるよう分担を決め、主にスマートフォンで撮影し、編集を行いました。なかなか授業の時間だけでは時間が足りず、放課後残る班もありました。各班18日(金)までにTeamsに動画をアップすることになっています。
3月22日 1年生商業科探究の時間まとめ発表会
「足利の地域課題」を解決するための提案を動画形式で発表しました。当初は体育館にて対面でのポスターセッションを計画しておりましたが、コロナウィルス感染症の影響もあり、動画での発表に変更しました。総合実践室(2クラス全員が入れる大きさで、企業の模擬取引を実際に行うことができる特別教室。)で動画を視聴し、それに対するコメントや疑問点を付箋に記入しました。教室の壁面にそれぞれの班のポスターを掲示し、最後は各自が記入した付箋をポスターに張り付け、自分たちの班に張られた付箋を見ながら振り返りを行いました。
動画に字幕をいれたり、見えにくいポスターを拡大したり、各班とも発表に工夫が見られました。データに基づいた発表ということでRESASを活用しましたが、やはりデータの分析となると難しかったようで、多くの班が「足利の観光地」についての提案となりました。
しかし、限られた時間や環境の中でよく努力し、各班の足利愛にあふれる発表会となりました。ぜひここでのアイデアを3年生の課題研究で実践研究としてほしいと思います。

アイデア発表会に向けての準備
2月21日(月)3時間目 振替で実施
今日は久しぶりの探究です。計画はなかなか計画通りに進まず、調整の日々です。
今日は今後の予定、今やるべきことについて段取りを行いました。
当初は22日の午後3時間を利用して集中して探究学習(アイデアをまとめる)を行うことを計画していました。また、24日の午後はSDGsカードゲームを活用した授業も計画していました。しかし、コロナ感染症の影響で予定していたグループワークを実施することができず、3月15日・17日に計画を延長することとしました。
各班に担当教員が割り振られ、生徒はグループ毎に入試休み期間にもスマホなどを活用しグループワークが行えるよう、LINEのオープンチャットやグループを作成し、3月22日の発表会に向けて話し合いが持てるよう班長を中心に準備を行いました。
なかなか計画通りに進みませんが、3月22日のポスターセッションでの各班の足利愛にあふれる発表が楽しみです。
アイディア出し
今回は「RESAS 地域創生政策アイディアコンテスト」で受賞した学生の動画をみました。発表会の参考としてみましたが、立派すぎる発表に生徒たちは発破をかけられた様子でした。
その後は、演習として「アイディア出しの練習」を行います。
今回は『ユニークなマラソン大会』として、「10代~20代」を対象に、「絆を感じられる」ことを目的としたマラソン大会を班で考えてもらいます。
「豪華景品がある」
「二人三脚マラソン」
「有名人が応援に来てくれる」
「マラソンに縁結びの効果があるうわさを流す」
「四人一組でエビフライ作り」
などユニークな発想が飛び交いました。
それを参考にし、「足利の地域課題」解決のアイディア出しを宿題としました。
「足利の地域課題」について
12/15、今年最後の探究は、「足利の地域課題」を一つにしぼり、アイディア出しの準備を行いました。
12月までの探究授業では足利の地域について調べてきました。
人口・産業・事業所・景観・少子高齢化・学校の魅力・観光地 などなど
そこから、「足利の地域課題」で自分たちの班が興味を持ったものを一つにしぼり、その原因と考えられるものを考えていきます。
「観光地の魅力」について実施した班は、観光資源が少ない・観光地同士が離れている・若者向けのものが少ないなど様々なことを挙げていきました。
次回は、今回の地域課題の原因をもとに、どのようなアイディアがあれば地域課題が解決されるか考えていきます。
講演会「足利の魅力と困りごと」
2021/11/24
10月20日,11月17日の総合的な探究の時間で、足利の魅力と課題についてマンダラートを活用して、項目やキーワードを書き出す作業をしていましたが、なかなか難しいようです。
今回は、足利市総合政策課 まちの魅力創出課 小林孝之助様を講師としてお迎えし、「足利の魅力と足利の困りごと」について講演していただきました。まず、足利市の概要について説明していただき、足利市の課題、行政的な課題について教えていただきました。生徒たちも課題と感じていた「人口の減少」について話題にされていました。
講話の中で地域課題が5つ挙げられ、そのうち2つの解決策の事例として「あしもり隊」の活動や、子猫がゴミステーションのゴミをあさっていることについての解決策について話していただきました。生徒は、残りの3課題「地域住民が職を求めて転出していくことに対しての解決策」や「太陽光パネルが増えている地域での景観の損失を心配する声に対する解決策」、「高校生たちが求める教育、学校とは」について考えました。
生徒たちは一生懸命考え、出した解決策は「若者を増やす」「優良企業をつくる」「生徒と教員の雑談会を開いて意見を言う」などでした。
今後の探究の時間で検証する課題の手助けとなる講演会となりました。
足利市の魅力と課題(マンダラート)
これまでのグループを解散し、新たな4人班での実施となりましたが、積極的にコミュニケーションを図り、マンダラートを意欲的に埋めていました。
今後は、マンダラートに記述した「足利市の魅力と課題」について、興味を持った内容を深掘りしていく活動を行っていきます。
足利市の魅力を、より一層高めるようなアイデアや足利市の課題を解決するための方策を考えてくれることを期待しています。
<マンダラートを記入している様子>

RESAS出前講座
この講座を行う前、1年商業科の探究の時間では、生徒自身で探究のテーマを設定し、テーマに対する仮説→調査→整理・分析→まとめ→発表というサイクルを実践しました。
探究のサイクルの中で「調査」という点に焦点を絞り、『根拠』のあるデータに基づき、生徒たちに今後探究活動を行って欲しいという点から、RESASというシステムを1年商業科でも活用していきたいと考えました。
RESAS(地域経済分析システム)とは、地方自治体の様々な取り組みを情報面から支援するために、まち、ひと、しごと創生本部事務局が提供する「産業構造」、「人の動態」、「人の流れ」などのビックデータを集約し、可視化するシステムです。
Webを開けばすぐに活用できる点や、無料で提供している点、地域を指定すれば自動的に地図やグラフを作成してくれる点など様々な利便性があり、生徒たちも9/28(火)に行った事前オリエンテーションで、すぐに活用できるようになりました。
RESAS出前講座の当日は、生徒たちが様々な地域間のグラフを見て地域の課題や現状分析、改善策を一生懸命考えていました。今後の探究活動でも、RESASを活用し『根拠』のあるデータに基づき、深い探究活動をしていきたいと思います。
RESAS出前講座をリモート開催して下さった職員の皆様、本当にありがとうございました。
<講座を真剣に聞く生徒達>