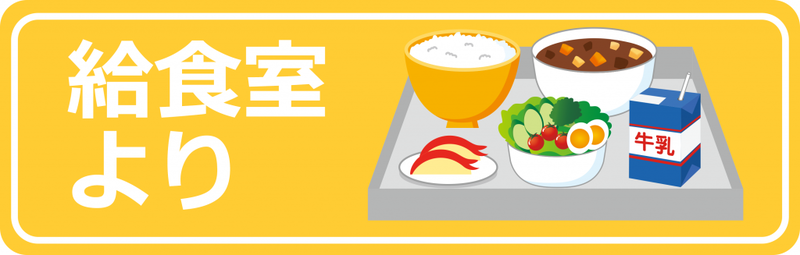文字
背景
行間
【定時制】本校創立記念日
4月18日(金)講堂に、佐藤務同窓会長様、千葉県美術会理事長で陶芸家の神谷紀雄様をお迎えし、創立記念式及び記念講演会が挙行されました。
加藤校長は挨拶の中で、「今日は本校の伝統を再確認し、これまでの歩みを振り返る日だ。当時の芳賀地区には尋常小学校卒業後の進学先がなく、地域の熱意ある嘆願に栃木県が動かされた。周辺地主22名が敷地を寄進、資金の半分を町民の私財寄付により、明治33年(1900年)に本県3番目の旧制中学校が開校し、今年で126周年を迎える。創立3年目には台風によって本館が半壊したが、学びを求める熱い意志をもった若者の熱意に答えて、明治37年に再建された。昭和44年に現校舎が完成して今日に至る。数多の著名な卒業生の中でも、野澤一郎氏(明治39年卒)は大正7年巴組(現・株式会社巴コーポレーション)を設立、考案したダイヤモンドトラス構造はディーゼル機関に匹敵する発明とされる。昭和32年には私財から野澤一郎育英会を創設した。氏の胸像は本人の遺志により上半身裸で校庭の南面に建つ。氏は『裸の私は真実の姿、人としての本質はその地位ではなく、生き方にある。志をもつことにより、いかなる困難にも立ち向かう気概をもって、みなさんが新しい光を添えてくれることを祈念する。』この言葉には、ここで学んだ『至誠』の精神が根底にある。君たちも校訓の具現化に努めてほしい。」と言葉を掛けられました。『至誠』とは「人を欺かず、己を欺かず、自己の良心を尊び、善と信ずることは必ず実行する。」ことであり、5つの時代に渡って脈々と受け継がれてきました。職員生徒一同、今後も実践していきたいものです。
佐藤同窓会長様(昭和37年度卒)は、「今年は創立126周年、温故知新(故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る)、本校の歴史の光と影を紹介する。昭和8年は日本が国連を脱退し、戦時ムードにシフトした頃、旧制5年生数名が鉄拳制裁の上、操行(生徒の品性や行動、道徳的な行いの総称とされ、日々の言動にも優劣がつけられた)丙と査定され、中退を余儀なくされた。生徒の学校に対する不信感は極まり、学校側と対立した(同盟休校事件) 。昭和10年には卒業生が当時の大金108円を集めて2名の権威に依頼して完成した校歌は、戦前戦後と歌い継がれている県内唯一無二である。このように紆余曲折を経て今日に至る。みなさんは今日の記念の日に、先人たちの歴史を知り、自己確立を目指して勉学に励んでいってほしい。」と述べられ祝辞とされました。
記念講演会は、神谷紀雄様(昭和34年度卒)により、『出会い…その先に』と題してご講演をいただきました。自己紹介で「講演会に呼ばれるのは超一流大学卒の優秀な人だけだと思っていた。」と切り出され、会場は和やかな雰囲気に包まれました。「美術の世界は、いいものを数多く見て、感性を磨くことが肝心である。良い作品は表面的な美しさだけではなく、奥に何かを感じさせるものである。多くの出会いによって、優れた師匠から多くを吸収できた。真面目に一つの道を歩んできたから、この機会を得た。出会いを大切にしていってほしい。」と結ばれました。先生の作品制作のプロモーションフィルムは映像美の極致で、多くの職員生徒が感銘を受けていました。先生の陶芸作品「鉄絵銅彩梅文大鉢」をご寄贈いただきました。