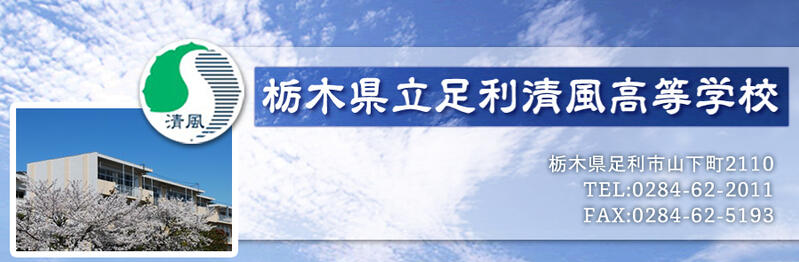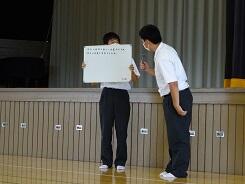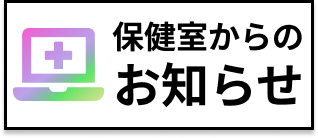令和3年度入学生 普通科
普通科1年生探究第10回「なぜふりかえりをするの?」
7月14日(水)のテーマは「なぜふりかえりをするの?」でした。
今回の探究は、1学期最後の授業ということでふりかえりを行いました。
その前に、そもそもなぜふりかえりを行うのか、生徒たちには班ごとに考えてもらいました。毎月の目標設定とふりかえり、毎回の授業後のふりかえり、たくさんのふりかえりを行ってきた1年生。どんな意見が出てきたのでしょうか。以下抜粋です。
Q.なぜふりかえりをする?
・次をより良くするため。
・その時の状態を確認するため。
・自分が学んだことを言葉にして理解を深めるため。
【生徒のふりかえりから】
・ふりかえりをしてみると、過去の自分と今の自分を比較して成長を実感できるし、言葉にまとめて自分の状態を把握できていいなと思った。
・自分の目標を再確認できた。
・ふりかえると1学期の間に実は色々なことをやっていたんだなと思った。
普通科1年生探究第9回「なぜ発表をするの?」
7月7日(水)の探究テーマは「なぜ発表をするの?」でした。
七夕に行われた探究活動は、7月中旬に普通科2年生で実施される探究Weekに1年生が参加するにあたって、そもそもなぜ発表をするのか考えること・ポスターセッションとはどんな発表形式か知ることができるような活動を行いました。
7月16日に、2年生の個人研究の中間発表に1年生は聴き手として参加します。
その前に発表の意義を班で考え、別の班と共有しあい、理解を深める活動を行いました。
「自分の考えを知ってもらうため」というような意見はどの班も出ていました。
そしてポスターセッションとは、どのようなものか口頭発表と比較しながら教員と対話する形式で、知っていきました。
あとは、探究Weekで実践あるのみ。たくさん贈り物(ふせん)をおくって、先輩たちの研究の糧となることを期待しています。
【生徒のふりかえりから】
・発表するのは自分の考えを共有したり、他の人から意見を聞いて自分にはなかった意見を知るためだと、班の人の意見をきいて、なるほどなと思った。
・自分は社会人になったときのプレゼンの練習だと思ったけど、他の人は理解を深めるためとか違う意見が出て面白かった。
普通科1年生探究第8回「何を言いたいの?」
6月24日(水)の探究テーマは「何を言いたいの?」でした。
ペアの人にイラストの説明を言葉のアミアで行い、そっくりそのままの絵をかいてもらうという活動を通して、人に分かりやすく物事を伝える方法を学びます。
お題となったイラストはイチゴとパイナップルの2種類。
完璧なイラストが完成するペアもあれば、個性的な果物が完成するペアも・・・。
細部まで正確に物事を伝えることは難しいのだなと気づいた生徒も多かったようですが、何より楽しみながら学んでいる様子がみえて良かったと思います。
【生徒のふりかえりから】
・全体像から行ってくれたおかげで、何を描くのかイメージできて、簡単だった。
・自分ではしっかり伝えたつもりでも伝わっていないことがあることが分かった。
・説明を集中して聞くことも大切だなと思った。


普通科1年生探究第7回「きみの“考え”は無限大」
6月16日(水)の探究は「きみの“考え”は無限大」をテーマに行いました。
あるテーマについて、シンキングツールを活用しながら考えの広げ方を知ること、自由な発想で考えたことを自他ともに認め共有することを目的に活動をしていきました。
今回は「新型コロナウイルスが収束しない」ことを問題点とし、この原因と対策を考えるということにしました。以下生徒のアイディアの抜粋です。
<原因>
・マスクをしない。
・三密になっている。
・他人事に感じている。
<対策>
・マスク着用の徹底。
・ワクチンを全員打つ。
・(密閉されるので)宇宙服を全員着る。
・海底に町を作って逃げる。
・オリンピックを開催しない。→リモートオリンピック
・空から消毒液をまく。
・過去に戻って原因を取り除く。→タイムマシン開発
原因はニュースなどでも普段見聞きするような内容大半を占めていましたが、対策は可能不可能にかかわらず自由に発想することを目的としたため、おもしろい考えが多くみられました。それじゃあ、実現させるにはどうしたらいいか・・・?と探究していくのも楽しいですね。
【生徒のふりかえりから】
・自分の意見をちゃんと聞いてもらえてうれしかった。
・他の人の意見をきいたら、原因への対策がたくさん出てきたので、考えを共有できて良かった。
・ある人が出した、1つの考えに周りの人がつけ足したりして、大きな考えになって、あらたな疑問が生まれたりして、とても良い活動をすることができた。


普通科1年生探究第5・6回「情報モラル①②」
6月2日・9日の探究は「情報モラル」をテーマとして扱いました。
もちろんモラルについて理解を深めてほしい目的もありますが、
探究で行う「情報モラル」には、物事の見方や考え方など、探究に必要なエッセンスが散りばめられています。
今年も、元TBSアナウンサーの下村健一氏考案の「大切な4つのおまじない」を参考に、活動していきました。
4つのおまじない=ソウカナ
ソク断しない、ウ呑みにするな、カたよらない、ナカだけ見るな
この4つに即して、リポーターになりきってみたり、「コロナ禍で騒ぐ若者」について考えてみたりして活動を進めました。
生徒は、デマの信じやすさに驚いたり、自分のSNSの使い方を見直したり、反応はさまざまでした。
【生徒のふりかえりから】
・自分の考えだけで判断すると、他の人にとっては間違っていたり、違う捉え方をされてしまうことが分かった。
・立場が変われば見方が変わって、正解も1つじゃなくなると感じた。
・ニュースを見るときに、画面に映っていないところについても意識しようと思った。


(参考:下村健一『10代からの情報キャッチボール入門』岩波書店、2015年)