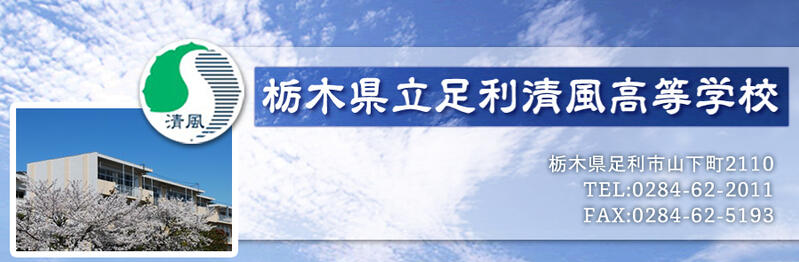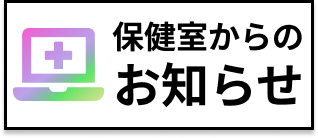日誌
令和3年度入学生 普通科
令和4年度 探究Week
2学年普通科「探究Week」を実施しました
☆実施日
令和4年7月12日(火)~14日(木)
☆探究Weekとは?
探究的な考え方を使って自分の今までをふりかえり、これからの道・未来を見据える3日間のことです。昨年度から実施し始め、今年度で2回目の開催となりました。
☆実施の目的
・2年生の探究での個人研究のきっかけ、やる気アップ、アドバイスにする
・少し年上の先輩の経験を聞き、対話する活動を通して「ナナメの関係」を体感する
・本物を知る・見る(正解のない世界で生きていくにあたり、これからの生き方、決断の仕方などを知る)
☆実施報告
【1日目】7/12(火)
初日は、探究Weekのオリエンテーション・探究活動に関する講義・ナナメのセッションを行いました。
オリエンテーションでは3日間の目標を立て、講義ではインタビューの方法・研究レポートのまとめ方について授業を行いました。
ナナメのセッションは、少し年上の先輩である卒業生の経験や人生を語ってもらい、生徒と対話をすることで「ナナメの関係」を体感する活動です。親や教師のタテでもなく、友人同士のヨコの関係でもない、ナナメの位置にいる先輩は、生徒にとっては憧れをもちやすく、実は自分の話をしやすい存在であると考えます。
そんな先輩と対話することで、生徒たちは自分をふりかえり、自分の少し先の未来を見据え、そして今後どのように頑張っていくか、決意をしました。
(生徒のふりかえり)
・先輩一人ひとりが自分の意志や大事にしていることを持っていてすごいと思った。
・先生や親とも、友達との違う距離感でナナメの関係の良さを知れた。
・自分のやりたいことや何をしたいかを具体的に考えていくことが大切で、やっぱり自分自身でしっかり考えて決断することが大切だと教わった。



【2日目】7/13(水)
午前中は3日目の準備を行いました。午後は講演会を実施しました。
講演会の講師は、足利市出身のネイリストである尾花晶さんでした。演題は「好きな物に囲まれて生きていく -得るもの失うもの-」です。尾花さんの、高校時代の話から現在の話まで、人生の節目でどのようなことを考え行動してきたのか、お話をいただきました。途中で尾花さんから生徒に逆インタビューをしていただいたりと、対話を行いながらの講演となりました。現在も自身の目標に向けて行動している尾花さんのお話から、生徒も刺激をうけたようです。
(生徒のふりかえり)
・色んなことがあっても自分のやりたいことをやるのはすごいと思った。将来尾花さんみたいな人になりたい。
・好きな事をやったり、好きな事を仕事にすることは自分のやる気にも繋がるんだと思った。
・私も自分らしさを大切に生きていきたいと感じた。また、色々なことに挑戦そして経験していくことで自分の未来の扉をたくさん見つ
けることができると思った。
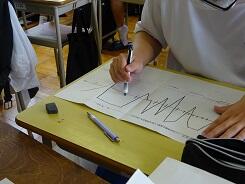


【3日目】7/14(木)
最終日は、普通科1年生との合同活動でした。午前は2年生の個人研究の発表についてポスターセッションを行い、午後は2年生の人生について1年生と対話するナナメのセッションを行いました。
ポスターセッション形式の発表を1年生は入学してから初めて経験することになります。どのようにきくのか、付箋をどのように使うのかなどについて2年生から説明を受けることからスタートしました。
ポスターセッションでは、一方的な発表になるのではなく、対話することを重視しています。2年生は1年生が対話しやすいように考えながらの発表となりました。難しい!と言いながらも楽しむ様子が見えました。
ナナメのセッションでは、2年生が1年生に自分の人生について語ることを通して、1日目に体感した「ナナメの関係」を今度は自分が作り出す側となりました。これまでの自分や、現在の高校生活について1年生に問いかけながら語り合いました。
(生徒のふりかえり)
・去年の探究Weekと比べて、積極的に自分から話すことができたし考えることができた。ポスターセッションでは聴く側から話す側に
なって成長を感じることができた。
・相手を知るためには自分から質問しないといけないと思った。自分がやりたいと思って、できなそうだなと思っても、とりあえずやっ
てみることが大切だと思った。
・ナナメのセッションも楽しく対話できて、最後にふさわしい日をむかえられた。



探究Weekは、短いようで長い3日間、探究スイッチを入れ続けた3日間、「学び楽しむ」3日間だったのではないかと思います。
ここからまた、自分なりの正解に向かって進んでいこう!よーい、はじめ!!
☆実施日
令和4年7月12日(火)~14日(木)
☆探究Weekとは?
探究的な考え方を使って自分の今までをふりかえり、これからの道・未来を見据える3日間のことです。昨年度から実施し始め、今年度で2回目の開催となりました。
☆実施の目的
・2年生の探究での個人研究のきっかけ、やる気アップ、アドバイスにする
・少し年上の先輩の経験を聞き、対話する活動を通して「ナナメの関係」を体感する
・本物を知る・見る(正解のない世界で生きていくにあたり、これからの生き方、決断の仕方などを知る)
☆実施報告
【1日目】7/12(火)
初日は、探究Weekのオリエンテーション・探究活動に関する講義・ナナメのセッションを行いました。
オリエンテーションでは3日間の目標を立て、講義ではインタビューの方法・研究レポートのまとめ方について授業を行いました。
ナナメのセッションは、少し年上の先輩である卒業生の経験や人生を語ってもらい、生徒と対話をすることで「ナナメの関係」を体感する活動です。親や教師のタテでもなく、友人同士のヨコの関係でもない、ナナメの位置にいる先輩は、生徒にとっては憧れをもちやすく、実は自分の話をしやすい存在であると考えます。
そんな先輩と対話することで、生徒たちは自分をふりかえり、自分の少し先の未来を見据え、そして今後どのように頑張っていくか、決意をしました。
(生徒のふりかえり)
・先輩一人ひとりが自分の意志や大事にしていることを持っていてすごいと思った。
・先生や親とも、友達との違う距離感でナナメの関係の良さを知れた。
・自分のやりたいことや何をしたいかを具体的に考えていくことが大切で、やっぱり自分自身でしっかり考えて決断することが大切だと教わった。



【2日目】7/13(水)
午前中は3日目の準備を行いました。午後は講演会を実施しました。
講演会の講師は、足利市出身のネイリストである尾花晶さんでした。演題は「好きな物に囲まれて生きていく -得るもの失うもの-」です。尾花さんの、高校時代の話から現在の話まで、人生の節目でどのようなことを考え行動してきたのか、お話をいただきました。途中で尾花さんから生徒に逆インタビューをしていただいたりと、対話を行いながらの講演となりました。現在も自身の目標に向けて行動している尾花さんのお話から、生徒も刺激をうけたようです。
(生徒のふりかえり)
・色んなことがあっても自分のやりたいことをやるのはすごいと思った。将来尾花さんみたいな人になりたい。
・好きな事をやったり、好きな事を仕事にすることは自分のやる気にも繋がるんだと思った。
・私も自分らしさを大切に生きていきたいと感じた。また、色々なことに挑戦そして経験していくことで自分の未来の扉をたくさん見つ
けることができると思った。
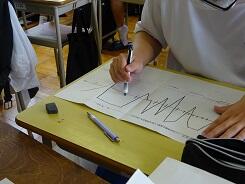


【3日目】7/14(木)
最終日は、普通科1年生との合同活動でした。午前は2年生の個人研究の発表についてポスターセッションを行い、午後は2年生の人生について1年生と対話するナナメのセッションを行いました。
ポスターセッション形式の発表を1年生は入学してから初めて経験することになります。どのようにきくのか、付箋をどのように使うのかなどについて2年生から説明を受けることからスタートしました。
ポスターセッションでは、一方的な発表になるのではなく、対話することを重視しています。2年生は1年生が対話しやすいように考えながらの発表となりました。難しい!と言いながらも楽しむ様子が見えました。
ナナメのセッションでは、2年生が1年生に自分の人生について語ることを通して、1日目に体感した「ナナメの関係」を今度は自分が作り出す側となりました。これまでの自分や、現在の高校生活について1年生に問いかけながら語り合いました。
(生徒のふりかえり)
・去年の探究Weekと比べて、積極的に自分から話すことができたし考えることができた。ポスターセッションでは聴く側から話す側に
なって成長を感じることができた。
・相手を知るためには自分から質問しないといけないと思った。自分がやりたいと思って、できなそうだなと思っても、とりあえずやっ
てみることが大切だと思った。
・ナナメのセッションも楽しく対話できて、最後にふさわしい日をむかえられた。



探究Weekは、短いようで長い3日間、探究スイッチを入れ続けた3日間、「学び楽しむ」3日間だったのではないかと思います。
ここからまた、自分なりの正解に向かって進んでいこう!よーい、はじめ!!
普通科1年生探究第13回「ステージ図からの自分の変化の発表」
9月15日(水)の探究の時間はポスターセッションを行いました。
1年生にとっては、自分が発表者となるポスターセッションは初めてのことでした。
発表内容は、ステージ図をふりかえり、自分が最終目標に向けてどのような行動を起こしてきたのか、自分にどのような変化があったか、そしてこれから目標に向けてどのように頑張っていきたいか、ということをまとめたものでした。
発表者は、3回連続で自分の発表を行いました。どの発表者も1回目の発表は緊張した面持ちで始まり、回数を重ねるごとにリラックスして発表を行っていました。
聴き手も、付箋に何を書いたらいいのか最初は戸惑いもありましたが、徐々に自分がもっと知りたいと思ったことや、発表方法へのアドバイスなどを書いて発表者に贈ることができていました。付箋は相手の今後のためになるものです。その意味で贈り物と呼んでいます。
生徒の最終目標は様々です。将来の職業に関する目標、こんなに人になりたいというような人間性に関わる目標、進学に関する目標などなど。それぞれの目標に向かって自分が何をしてきて、何ができるようになって、何が足らないのか、自分を見つめ直す機会にもなったのではないでしょうか。
【生徒のふりかえりから】
・自分の発表を聴いてくれた人たちが、いいコメントをたくさんくれたので、思わずにやけてしまいそうになった。
・他の人のポスターがカラフルで見やすかったので、次回の参考にしたいと思った。
・最初は上手く伝えることができなかったけど、回数を重ねるうちに伝えたいことの補足やポスターを使って伝えたいことを伝えることができた。
<ポスターセッションの様子>



普通科1年生探究第12回「論理的とは?」
9月8日(水)の探究は、「論理的(な伝え方)とは?」でした。
フェイスシールドが全校生徒に配布されたこともあり、対話を入れての活動も少しずつ取り入れての活動になりました。(しかし、フェイスシールドをつけて意見共有しているところの写真を撮り忘れてしまいました・・・。)
個人研究を行っていくにあたって、「論理的」であることは重要な要素です。
研究内容はもちろんの事、それを発表するときにも論理的であることが、納得や理解を得る第一歩になります。
今回はカレーに関する文章が成り立つかどうかについて考えていく活動を通して論理的とはどういうことか、理解を深めていきました。
考えていった文章は以下の3つです。
①私はカレーが嫌いだ。だからクラスのみんなもチョコレートが嫌いだろう。
②アンケートによると、国民の90%はカレーが好きだ。だから国民の多くはカレーが好きと言えるだろう。
③今日の夕飯はカレーだ。だから、明日の夕飯もカレーだろう。
③については、一見成り立ちそうですが、条件が明確ではないので論理的ではないと言えます。2日目まで残るくらいカレーを作ることなどが前提になってくるからです。この「隠れた前提」ですが、実は②のところでも意図せず発生してしまっていたんです。
②は事実に基づいた理由があるから論理的であるという文章でした。アンケートは国民全員が答えたことを前提としてこの文章を考えていたんですが、それを提示しなかったために、「アンケートに何人答えたか分からないので論理的ではない」と考えた生徒がちらほら。いや全くその通り。というよりも、「アンケートの罠」に気づけた点が本当に素晴らしいと思いました。反省しつつも嬉しいなあと感じた探究でした。
【生徒のふりかえりから】
・論理的とは、全ての人がああそうだなど納得し理解できることなのかなと思いました。
・人によって言葉が成り立っていても、他の人にとっては成り立っていないものもあることが分かったので、自分が話すときに心がけたい。


(参考文献:山田剛史・林創『大学生のためのリサーチリテラシー入門』ミネルヴァ書房、2011年)
普通科1年生探究第11回「ポスターセッションとは?」
9月1日(水)の探究は「ポスターセッションとは?」をテーマに活動を行いました。
探究Weekでの先輩とのポスターセッションなどを思い出してもらいながら、
発表者としての心得、ポスターの工夫、聴き手の役割について理解を深めること。
そして、9月15日(水)に行われる1年生のみのポスターセッションについての
説明を行いました。
1学期最初の探究は、緊急事態宣言下での活動となりました。
意見の共有をどのように行っていくか・・・。
生徒4名でA3の紙を回しながら、付箋を貼って意見を共有していくという方式を取りました。確かに他の人の意見を知ることはできますが、そこからの発展が少ないと感じました。この方法にも改善の余地がありそうですね。
ポスターの工夫については、改善点てんこ盛りのポスターを教員が作成。
どこが改善できそうか考えていく活動を行いました。
シャープペンシルで書いただけのポスター。見えにくそうに目を細める生徒。
その感覚を忘れないで、自分のポスターに生かしていってほしいです。
【生徒のふりかえりから】
・ペンで書いたり、図を使ったりして相手に伝わるポスターを作りたい。
・素朴な疑問でも、あったら積極的に質問して理解を深めていきたい。
・緊張すると早口になってしまうので、しっかりと準備しておこうと思う。
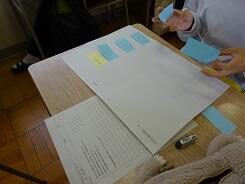

(参考文献:山田剛史・林創『大学生のためのリサーチリテラシー入門』ミネルヴァ書房、2011年)
普通科1年生探究 「探究Week」
7月16日(金)、探究Weekの最終日に参加しました。
探究Weekの詳細は、普通科2年生総合的な探究の時間のページをご覧ください。
最終日、午前中は2年生のポスターセッションに参加しました。
午前中は、興味関心からのさまざまな研究テーマの発表に対して、1年生は最初は緊張しながらも質問をしたり、感想を言ったりと聴き手としての役割をはたしていました。
また、先輩たちの発表をきいたことにより、来年の自分たちのイメージをつかめた様子の生徒もいました。
午後は、センパイたちとナナメのセッションを行いました。
センパイたちの人生についての話を媒介として、センパイと対話し、お互いに気づきを得たり、目標とすることを見つけたりと、普段関わりの無いセンパイとの交流がとても印象深かったようです。あまり知らないセンパイにだからこそ、ちょっとした悩みを吐露できたり、これからの進路について聞けたりと、とてもとても学び楽しんでいる様子が伝わってきました。
【生徒のふりかえりから】
・あまり関わったことの無い先輩とも、気軽に話せるような雰囲気を先輩が作ってくれたので質問もしやすかった。仲良くなったので、また話したい。
・ポスターセッションで、どんな風に発表すると伝わりやすいか分かったので、自分のときにもまねしたい。
・先輩の経験をきいて、自分も前向きに頑張ろうと思った。
・知らない先輩だったけど、進路や部活など参考になる話がたくさん聞けて良かった。