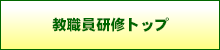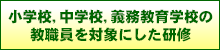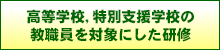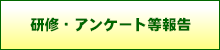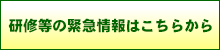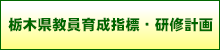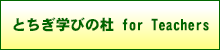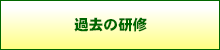研修報告
令和 7(2025)年度 英語専門研修(高)
| 目 的 | 研究協議と講話・演習を通して、高等学校段階における英語教育の在り方について理解する。 | ||||||||
| 日 時 | 令和 7(2025)年 7月30日(水) 9:30~16:00 | ||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校(高等部)の英語科を担当している教員 | ||||||||
| 研修内容 | 講話・演習「今求められている外国語教育と授業づくり」 講話・演習「『論理・表現』の指導の在り方と実践」 |
||||||||
| 講 師 | 群馬大学共同教育学部講師 津久井 貴之 氏 総合教育センター職員 |
||||||||
| 研修の様子 |
|
||||||||
| 受講者の声 |
|
||||||||
| 研修担当者からの メッセージ |
今年度の英語専門研修は『論理・表現』にスポットを当てており、一日を通して『論理・表現』の授業の在り方について考えました。
午前は『論理・表現』の科目の目標や内容について確認し、グループごとに単元の計画や個々の授業について協議しました。どのグループも活発な議論がなされており、テーブルごとの模擬授業では、言語活動について様々なアイディアを共有することができました。 午後は群馬大学共同教育学部講師の津久井貴之先生により「『論理・表現』の指導の在り方と実践」と題した講話を頂きました。具体的な指導法についてもご教授いただき、受講者も大変熱心に耳を傾けていました。津久井先生が実際に『論理・表現』の授業で使われたワークシートも共有して頂き、授業の在り方について具体的にイメージすることができました。 受講された先生方、一日の研修大変お疲れ様でした。この研修を通して学んだことを、日々の授業改善に役立て、各学校の同僚の先生方と共有して頂ければ幸いです。 |
||||||||