
~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~
〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236
数理科学科ロゴマーク
クリックすると校歌が流れます

文字
背景
行間

~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~
〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236
数理科学科ロゴマーク
クリックすると校歌が流れます

平成28年6月8日(水)に数理科学科1,2年生対象の特別授業が行われました。帝京大学から関根久先生、飽本一裕先生、平澤孝枝先生の3名の先生方を講師としてお招きし、機械系、環境系、生物系の3分野についての特別授業をしていただきました。
機械系:演題『会話、12段梯子登りする170 cm人型ロボット』
講師 帝京大学 関根久 先生環境系:演題『地球環境最前線』
講師 帝京大学 飽本一裕 先生
生物系:演題『体のでき方を考える』
講師 帝京大学 平澤孝枝 先生

今回の特別授業において、生徒一人一人にとっての新たな発見もあり、より理科の学習への関心を深めることができました。




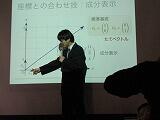

平成28年1月26日(火)本校視聴覚室にて、日光自然探究合宿報告会が行われました。初めに大豆生田校長の挨拶があり、その後それぞれのグループで工夫をこらした研究報告がありました。報告会の終わりに数理科学科主任の峯先生、川田教頭先生から講評があり終了しました。


1,2班:日光の動物①,②
3,4班:日光の植物①,②
5班:日光の昆虫
6,7班:日光の鳥①,②
8,9班:日光の菌類・地衣類①,②
10班:地質
生徒の感想
・はきはきしていて良かった。
・岩石の実物をもってきたところがとてもよい。
・テンポが良くて図があってわかりやすかった。
・シンプルで見やすかった。
・鳥の鳴き声が聞けて良かった。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
小山高校・若木小学校東側の道路はスクールゾーンのため、朝7:00~8:30まで車両進入禁止です。