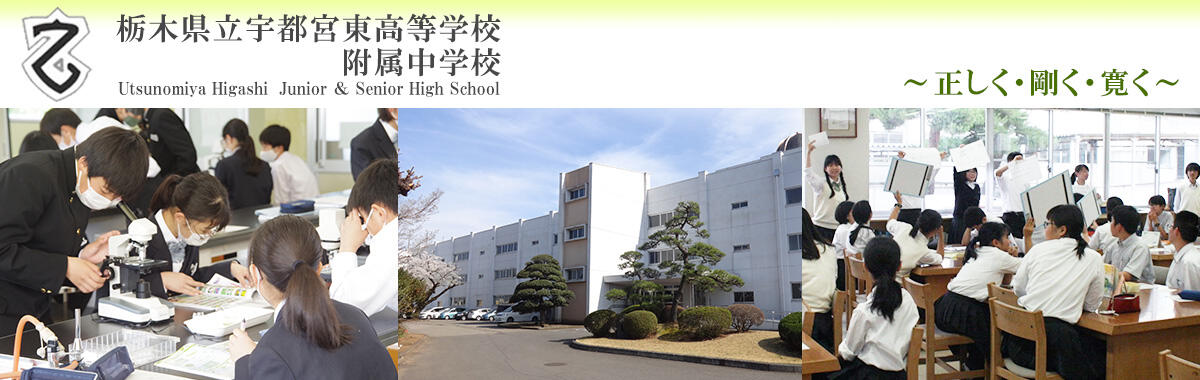文字
背景
行間
News
【高校】校内球技大会
9月に予定されていた高校の球技大会でしたが、台風のために延期されていました。
その日とは打って変わり、爽やかな秋晴れに恵まれた10月12日(木)、校庭と南・北の体育館で熱戦が繰り広げられました。
今年の種目は「バレーボール」「バスケットボール」「卓球」「ソフトボール」です。


各競技の優勝クラスは……
男子バレーボール → 2年2組
女子バレーボール → 3年2組
男子バスケットボール → 2年3組
女子バスケットボール → 2年2組
卓球 → 3年2組
ソフトボール → 3年2組


そして、総合成績は、
優 勝:3年2組
準優勝:3年1組
第3位:2年2組、2年4組
実に3種目で優勝した3年2組が他クラスを圧倒しました!
3年1組は種目優勝こそなかったものの、準優勝が2種目、その他の競技も全てベスト8進出と、総合力が総合準優勝に繋がりました。
今年度も折り返し地点を過ぎ、特に3年生は進路決定に向けた追い込みの時期に入ってきました。合唱コンクールや宇東祭、そしてこの球技大会で培った団結力で、団体戦と言われる受験も乗り越えていってほしいと思います。
【高校】教育実習体験が行われました
本校では附属中学校併設という特長を生かし、将来教員を志望している高校2年生を対象に、附属中における教育実習体験を実施しています。
今年は9名の2年生が、6月と10月の2度にわたって体験を行いました。
6月の体験は授業参観のみでしたが、10月には教壇に立って、先生役となり授業を行いました。
<高校生の感想>
・授業の始めは緊張と不安からおどおどしてしまいましたが、クラスの生徒が積極的にたくさん発言してくれたことにとても救われました。実習体験をすることで、今まで気がつかなかった「教師」という職業の魅力にもたくさん気づくことができました。
・1時間分の授業を1人で行うというのは、責任を感じました。準備にはかなり時間が掛かりましたが、その分、授業が終わった後の達成感は大きく感じられました。一生懸命考えて行った授業を、中学生が真剣に取り組んでくれて、とても嬉しかったです。
・準備で大変なところもあったが、準備した分だけ生徒の理解度は深まるのだなと思った。この先、勉強をもっと頑張って、自分の生きたい大学へ行き、また栃木に戻ってきて、母校である宇東高or宇東附属中で数学を教えられる日を目標にして、教師になるための努力を積み重ねていきたい。
・事前の準備で1番悩んでいた「どのタイミングで板書をすれば良いのか」ということについて、やはり上手くいかず、授業後の先生からのアドバイスは大変参考になった。今回の体験で、さらに魅力を感じて「教師になりたい」と強く思った。中高一貫教育校でしか経験できない、本当に貴重な経験ができたことに感謝して、今回得たことを今後の生活に生かしたい。
また、県の教育委員会の先生が来校され、教員の仕事内容や魅力の紹介、また免許取得および採用試験に関する説明会を行ってもらいました。「小学校・中学校」「高等学校」「特別支援学校」それぞれの立場の先生方からの説明で、参加した生徒は新たな視点を持つことができたようです。
今回お忙しい中にもかかわらず協力してくださった中学校の先生方、また教育委員会の先生方、本当にありがとうございました。また、附属中の生徒の皆さんも、普段通り集中して授業に参加してもらい、高校生はみんな感謝しています。
今回体験をした高校生の皆さん、この経験を忘れず、次は本物の教師として授業をする日に向けた努力をしていって下さい。
また高校1年生や中学生も、次の機会があったらぜひ参加してほしいと思います!
【中学校】生徒会専門委員会の様子
10月12日(木)6限の自彊タイムに、後期最初の生徒会専門委員会を行いました。
後期の組織づくり、活動目標などを決めました。また、12月に予定されている生徒集会に向けての話し合いも、活発に行われていました。






【中学校】授業参観・PTA学年部会(3年生)
10月10日(火)に3学年の授業参観とPTA学年部会を行いました。
3年生にとっては、中学校最後の授業参観になります。
たくさんの保護者の皆様にご来校いただきました。ありがとうございました。
【高校】修学旅行に向けて②
広島・関西の修学旅行まであと1か月を切りました。
今日は、NPO法人PCV(Peace Culture Village)の協力をいただき、広島市の1945年8月6日前後の状況を追体験するプログラムに参加しました。
被爆者の体験講話を聞いたり、平和記念公園近辺のCGによる再現を見たりするなどして、戦争と人権侵害について考えました。また修学旅行で広島市に訪れたとき、とくに重点を置いて見学するポイントを事前把握することも目的にしています。

現在においても、世界では戦争状態にあると言われている場所が数多くあります。
今回の修学旅行で、生徒のみなさんには、被爆地・広島における戦争の痕跡を見学し、現地でしか感じることのできないコト・モノを学ぶ機会にしてほしいと思います。