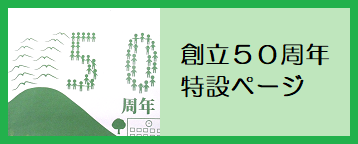文字
背景
行間

2
2
4
8
8
9
5
日誌
「ツタンカーメン王副葬品エンドウ豆」の栽培
平成30年の夏、「とちぎ環境みどり推進機構」からいただいた数粒の種、
これは、ツタンカーメン王副葬品だとのこと。
そこで、慎重に種を増やしてから学校で栽培することとし、
教材研究の一環として、とりあえず職員の自宅の畑で育ててみました。

昨年の11月、畑の片隅で育てました。(普通のエンドウ豆と
交配しないよう、遠ざけて栽培)
すると、どうでしょう! 実ったサヤの色にびっくり!
ご存じの通り、現在食用のエンドウのサヤ色は黄緑ですね。
なんと、このエンドウ豆は、写真のように若いサヤのうちから
黒に近い茶褐色でした。(ツタンカーメン王副葬品エンドウ豆の特徴)
このエンドウ豆の由来は、(高橋 潔様による)
「野木町の生田目 光世様よりいただいた記録によるもので、
この一粒から摂れたエンドウ豆が多くの方々の手に渡り栽培される
ことを記念する次第です」とのこと。
<由来>
1922年(大正11年)イギリスの考古学者カーナー・B・カーターが
エジプト・ナイル川上流ルクソール市郊外、王家の谷の墳墓発掘の時、
ツタンカーメン王(在位BC1359~1349)の墓を発見した。
王の柩に副葬されていた様々な日用品に混じって、
エンドウ豆が発見された。
この豆は、古代エジプト人が食用にしていたものであろう。
カーターは、それをイギリスに持ち帰り、栽培に成功した。
その一部がアメリカに渡り、栽培が続けられた。
日本へは、1956年(昭和131年)「世界友の会水戸支部」の
大町武雄氏が数粒入手して栽培し、これをもとにして、
水戸市内の小・中学校で教材として栽培するようになった。
たまたま、1983年(昭和58年)水戸市立三の丸小学校で
「全国小学校理科研究大会」が開かれた時、
同校では、参加者のうち希望者に少量ずつ配布した。
本県では、藤原町立下原小学校の杉本昌夫先生が2粒入手し、
同校で教材として栽培したのが始まりで、
この種子を1985年(平成6年)1月、石橋町・国分寺町。小山市
野木町の現職校長・退職校長の研修会の時、
この種子を参加者に少量ずつが畏怖した。
同席の野木町立新橋小学校長の金沢尚武先生が20粒ほど入手した。
うち5~6粒を野木町の「生田目光世」が入手し、
同町老人福祉センターで栽培した。
翌年から、自宅の畑で栽培し現在に至っている。
県下での愛好家の人数等は明らかではないが、
野木町内には、数人の愛好家がおり、
細々と栽培しているようである。
平成11年12月13日
生田目 光世 記
とちぎ環境みどり推進機構の資料より
このような経緯から、このほど本校にやってきた不思議な種。
今年の4月に収穫した種は、100粒にも増えました。

いよいよ今年の秋に、学校で栽培する準備は整いました。
特色ある学校づくりの一環としての環境教育。
児童生徒たちにとって、生命の尊さとたくましさが感じられる
貴重な教材となるといいですね。
これは、ツタンカーメン王副葬品だとのこと。
そこで、慎重に種を増やしてから学校で栽培することとし、
教材研究の一環として、とりあえず職員の自宅の畑で育ててみました。

昨年の11月、畑の片隅で育てました。(普通のエンドウ豆と
交配しないよう、遠ざけて栽培)
すると、どうでしょう! 実ったサヤの色にびっくり!
ご存じの通り、現在食用のエンドウのサヤ色は黄緑ですね。
なんと、このエンドウ豆は、写真のように若いサヤのうちから
黒に近い茶褐色でした。(ツタンカーメン王副葬品エンドウ豆の特徴)
このエンドウ豆の由来は、(高橋 潔様による)
「野木町の生田目 光世様よりいただいた記録によるもので、
この一粒から摂れたエンドウ豆が多くの方々の手に渡り栽培される
ことを記念する次第です」とのこと。
<由来>
1922年(大正11年)イギリスの考古学者カーナー・B・カーターが
エジプト・ナイル川上流ルクソール市郊外、王家の谷の墳墓発掘の時、
ツタンカーメン王(在位BC1359~1349)の墓を発見した。
王の柩に副葬されていた様々な日用品に混じって、
エンドウ豆が発見された。
この豆は、古代エジプト人が食用にしていたものであろう。
カーターは、それをイギリスに持ち帰り、栽培に成功した。
その一部がアメリカに渡り、栽培が続けられた。
日本へは、1956年(昭和131年)「世界友の会水戸支部」の
大町武雄氏が数粒入手して栽培し、これをもとにして、
水戸市内の小・中学校で教材として栽培するようになった。
たまたま、1983年(昭和58年)水戸市立三の丸小学校で
「全国小学校理科研究大会」が開かれた時、
同校では、参加者のうち希望者に少量ずつ配布した。
本県では、藤原町立下原小学校の杉本昌夫先生が2粒入手し、
同校で教材として栽培したのが始まりで、
この種子を1985年(平成6年)1月、石橋町・国分寺町。小山市
野木町の現職校長・退職校長の研修会の時、
この種子を参加者に少量ずつが畏怖した。
同席の野木町立新橋小学校長の金沢尚武先生が20粒ほど入手した。
うち5~6粒を野木町の「生田目光世」が入手し、
同町老人福祉センターで栽培した。
翌年から、自宅の畑で栽培し現在に至っている。
県下での愛好家の人数等は明らかではないが、
野木町内には、数人の愛好家がおり、
細々と栽培しているようである。
平成11年12月13日
生田目 光世 記
とちぎ環境みどり推進機構の資料より
このような経緯から、このほど本校にやってきた不思議な種。
今年の4月に収穫した種は、100粒にも増えました。

いよいよ今年の秋に、学校で栽培する準備は整いました。
特色ある学校づくりの一環としての環境教育。
児童生徒たちにとって、生命の尊さとたくましさが感じられる
貴重な教材となるといいですね。
学校風景
連絡先
〒326-0011
栃木県足利市大沼田町619-1
電話 0284-91-1110
FAX 0284-91-3660
ナビを利用して本校に来校される場合には、
「あしかがの森足利病院」で検索されると便利です。
リンクリスト