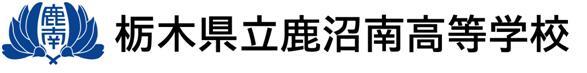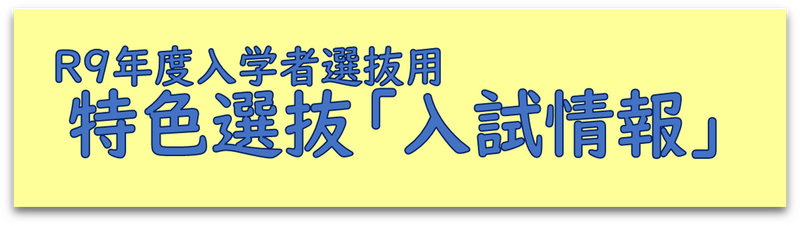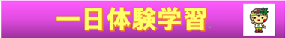文字
背景
行間
科学部活動記録
ホウネンエビと謎の水生生物!?
農業の先生方から「水田にエビがいる」と教えていただき、6月7日(月)に本
校の第一農場の水田に行ってきました。
水田にはホウネンエビ(豊年蝦)がたくさんいました。体長約2cm程度の小さ
なホウネンエビですが「大量発生する年はお米が豊作である」という言い伝えがあ
るそうなので、今年の収穫が楽しみです♪
↑ 仰向けで足を動かしながら泳ぐ姿がかわいいホウネンエビ☆
↑ ホウネンエビと一緒に捕まえた謎の水生生物☆
ホウネンエビと一緒につかまえた体が大きく丸みを帯びたこの生物はヘビトンボ
の幼虫でした。ヘビトンボは沖縄以外の日本各地で見られるようですが、幼虫がき
れいな水でしか生息できないため近年数が減少しているそうです。
今後は、ホウネンエビやヘビトンボを観察しながら、いつまでも本校の水田でこ
れらの生物が生息できるよう環境についても考えていきたいです。
夏の課外活動
8月12日 鹿沼にある板荷リバーサイドランド(黒川せせらぎプール)にて、水性生物の観察をしてきました。
猛暑日が続いていたため、川に入って生き物を探すのはとても気持ちがよく、
部員たちも楽しそうできました。
水量が多かったこともあり、観察できた生物はわずかでしたが、
保護者の方のご協力により、アカハライモリやナナフシなど貴重な生物も観察することができました。
部員たちにとって、鹿沼の自然の豊かさを再確認するとともに、
生き物への興味も深まった一日となりました。




夏休み中の課外活動



夏休み中の科学部活動報告
はじめに、沼尾校長先生の計らいで水産試験場内を見学することができました。水産試験場では那珂川でとれる夏の魚「鮎」についての講習や、天然記念物「ミヤコタナゴ」を見ることができ、生徒共々とても感動しました。


?那珂川の鮎漁は日本一であるということ。鮎は自然環境が整備された場所に産卵し、栄養豊富なプランクトンを食べて成長します。このことから那珂川は自然が豊かな素晴らしい川であることが分かります。
? 天然記念物「ミヤコタナゴ」は水底に産卵するのではなく二枚貝に産卵するということ。貝に産卵するというのは希です。川が汚染され貝が絶滅するとタナゴは産卵できず子孫を残せないために天然記念物となってしまいました。水産試験場では二枚貝の見学もできて興味深かったです。



一日を通して水中生物に触れることができ、とても癒されました。癒されたいときやリフレッシュしたいときに、とてもおすすめです。
8月9日(火) 宇都宮大学生との環境整備活動参加
今日の天気は曇りです。環境整備活動は天然記念物「ミヤコタナゴ」が保全されているという川の草刈りを行いました。外での作業でしたので汗だくになりましたが、生徒共々一生懸命活動し川が美しく整備されました。活動をした場所は天然記念物が保全されているということでサワガニや植物も多く自然豊かな場所で、とても癒されました。驚いたことは作業中にマムシを発見したことです。毒を持っているということで危険ですが地元の方が駆除してくださいました!


8月24日(水) 国立科学博物館「恐竜博2011」見学
上野にある国立科学博物館に行ってきました。夏休みも終盤ということで大勢の人々で混雑していました。なかでも恐竜博は入場までに長蛇の列ができていました。内容としては三畳紀恐竜の起源(植物食の開拓)→ジュラ紀恐竜の多様化(外への進出)→白亜紀→絶滅までを恐竜の展示とともに巡るものです。なかでもトリケラトプスとテイラノサウルスの展示は迫力満点でした。



科学部
最近は宇都宮大学の中庭で釣れたザリガニと、生物を愛する農業の先生から頂いたドジョウとタニシを飼育していました。
どうしてザリガニ?と思われる方も多いでしょう。
ザリガニにサバなどの青魚を餌として与え続けると体表が赤から青に変色するらしいのです。
それが本当なのかを調べるために科学部で飼うことにしたのです。



ザリガニの脱皮を初めて見たので感動しました☆
不思議なことや疑問に感じることを部員たちと一緒に解決していきたいと思っています。
ありがとうございました。
医療機関にて、新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・感染性胃腸炎・溶連菌感染症の診断があった場合には、こちらの申し出書を保護者の方が記入し、学校にご提出ください。