文字
背景
行間
生き物LIVE
生き物LIVEーアカマツ
校舎3階から望む西体育館の奥に、
アカマツが赤く輝いていてはっとすることがあります。
アカマツ
Pinus densiflora
マツ科
清陵の森周辺に3本ほど見られます。
お隣の清原中にもアカマツの群落の名残があります。
清原50年史をひもとくと、昭和20年代頃は清原中の教室が薄暗くなるほどアカマツが茂っていた様子がうかがえます。
清陵の敷地にもかつてはアカマツ林があったかもしれませんね。
アカマツは文字通り樹皮が赤色を帯びたマツの一種です。
樹皮が黒っぽいクロマツPinus thunbergiiが海岸沿いに多いのに対し、
比較的内陸部の、明るく乾燥した、栄養の乏しい場所に生えることが多いようです。
マツの切り口からべたべたした樹液が出ているのを見たことがありますか?
アカマツの材は松ヤニを多く含み、松脂(ショウシ)とよばれる薬や、天然樹脂の一種ロジンを産出します。
ロジンは、身近なところでは野球などで使う滑り止め、バイオリンなど弦楽器の弓線への塗布、
そしてハンダ付けに用いるフラックスとして利用されます。
清陵生の皆さんは、基板に塗布するフラックスを知っていますよね?!
エッチングの後に基板にスプレーしている、あれですよ!
もっとも、実習で使っているフラックスは合成樹脂ですが…。
他にも、建築材や燃料(一例として松明(たいまつ)など)として重宝されたほか、
共生菌としてマツタケを周囲に生やすことが知られています。
多くの恵みを人にもたらし、強健な樹体と冬でも変わらない緑の葉は、長寿や神のシンボルとして(一例として門松など)、古くから愛でられてきました。
こんなにありがたいアカマツですが、
近年は全国的に、マツ材線虫病による枯死が大きな問題となっています。
清陵の森のアカマツが、いつまでも美しく学校を見守ってくれることを願います。
生き物LIVEーサザンカ
両者はとてもよく似ている上、交雑種や園芸種も多く、区別するのは難しい部分もありますが、大雑把に言うと…
花弁がバラバラに散るのがサザンカ。ツバキは花がまるごと落ちるので、武士には嫌われたと言われています。
サザンカの葉はやや小型で、葉の裏や葉柄に細かい毛があるのに対し、ツバキは厚くてつややかな感じ……等の違いがあるようです。
最も分かり易いのは、晩秋から咲くのがサザンカで、ツバキは少し遅れて、早春の気配がするころ咲きはじめます。
ですから、いま咲いているのは、ほとんどサザンカと言えますね。校内にもたくさん見られます。
サザンカ
Camellia sasanqua
ツバキ科
よく見ると、様々な美しい品種があります。

探してみて下さいね。
一方、ツバキはまだ蕾(つぼみ)の状態で春を待っています。
清陵のツバキはこれまた美しいので、咲きましたらまたレポートします。
寒い日が続きますが、季節は着実に春に向かっていますね。
生き物LIVEーコナラ

テニスコートの向こう、
清陵の森に行ったことはありますか?


11月にはまだ緑陰が残る森でしたが、


一ヶ月後には枝先まで露わとなりました。
この森を構成する主要な樹木、コナラをご紹介します。

コナラ
Quercus serrata
ブナ科の落葉高木。
この失敗したロールケーキのような樹皮、
他でも見たことがあるのでは…。
公園などによくあるコンクリートの擬木柵、明らかにこのコナラだと思いませんか。
それほど身近な樹木だということが言えるのではないでしょうか。
関東の里山では古くから薪炭林として、燃料(薪や炭)の供給源になっていました。
環境汚染や地球温暖化の心配のない、自然エネルギー源ですよね。

周囲には枯れ葉と共に、おなじみドングリが。
拾い集めた幼い頃の記憶が誰しもあるのでは。
古くから欧州では、コナラと同属のオークはローマの雷神ジュピターの神木であり、この樹には落雷しないという言い伝えがあるそうです。窓のブラインドなどのヒモの先に付いている丸い球は、本来は雷よけのドングリを模したものだったそうですよ。

是非、冬枯れの森を散策しに来てください。
初冬の小鳥達
葉が落ちた木々の枝にやってくる小鳥の様子が楽しめる季節になりました。

↑ メジロ
カエデ類の芽の蜜を吸いにくるようです。
にぎやかにさえずっています。

11月下旬のある日、
実習棟の廊下に、またヒナが佇んでいました。

↑ヒヨドリの幼鳥と思われます。
しばらくしたらいなくなっていました。
無事に独り立ちできたでしょうか。

校庭のトイレにも最近小鳥が入り込んで汚すので
(便器にフンをしてくれれば問題はないのですが)、
いらなくなったCDディスクを吊って様子を見ています。
清陵高校は周囲の自然に恵まれているため、
校内にはいろいろな鳥や動物がやってきますが、
今年はちょっと多い気がします。
学校の北側でLRTの工事がはじまっているので、
その影響もあるかもしれませんね。

実習教員研究会(地衣類)
地衣類もいくつかご紹介します。


↑ ツブダイダイゴケ
コンクリート上にひんぱんに見られます


↑ ロウソクゴケ
Candelaria concolor
ロウソクゴケ科
昔ヨーロッパで、ろうそくを黄色に染めるのに使われたそうです


↑ モジゴケ(属)
Graphis spp.
モジゴケ科
灰白色の表面に、アルファベットのような文字状の線(子器)が見えます
(皆さんは何に見えますか?)
このように、身近にあって気にもとめなかった所にも、
たくましく生き物たちが息づいていることが実感できました。
研究会に際しましてお世話になりました坂井先生はじめ、
たくさんの先生方にご協力いただきましたことを
この場を借りてお礼申し上げます。
実習教員研究会(コケ類)
県高等学校教育研究会理科部会実習教員研究会が、
本校を会場に開催されました。
県内の実習教員の先生方が集まり、
県博物館の坂井広人先生を講師に、
「あなたの知らないコケの世界」と題して研修を行いました。


そのほんの一部をご紹介します。


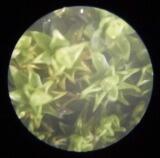

↑ カタハマキゴケ
Hyophila involuta
センボンゴケ科
コンクリート面などに普通に見られます




↑ コホウオウゴケ
Fissidens teysmannianus
ホウオウゴケ科
想像上の生き物、鳳凰の尾羽に見立てています
他に数種類のコケの採集と観察を行いました。
コケの小さな美しい世界をのぞき見ることができました。
生き物LIVEー植物図鑑(残念な名前)
ワルナスビ
Solanum carolinense
ナス科

もう何年もこの清陵の茂みで生きてるぜ
除草剤なんて俺には効かねえよ

↑ヒッコ抜こうとするやつにはこのトゲトゲでお仕置きだ
抜かれても抜かれても、地下茎でじゃんじゃん増えてやる

↑見ろよこのチャーミングな実
トマトやナスとは兄弟よ(ナス科)
北米の荒野からの流れ者だぜ
あっちでも「ソドムの林檎」てえ名前で恐れられているんだ

↑ お隣さんはまた残念な名前だ
ヘクソカズラ
Paederia scandens
アカネ科
臭うからってこの名前はないよな
生き物LIVEーカッコウ
学校の外廊下に佇むトリがいました。
茂みに逃げ込んだトリに近づいてみると…


↑ カッコウの幼鳥と思われます。
カッコウは『托卵』をする鳥として知られています。
このヒナも、小さい親鳥に育てられ、手狭になった巣から落ちてしまったのでしょうか。
その日はしばらく親鳥(養親)と思われる悲しげな鳴き声がしていましたが、やがてあきらめたのか、静かになってしまいました。
翌日、縞模様の羽根があたりに散乱していました。

かわいそうな結末でしたが、
自然界の秩序ですから手は出せません。
清陵の森の中では、日々いろいろな生物の営みがあるのでしょう。
その一端を垣間見た一件でした。
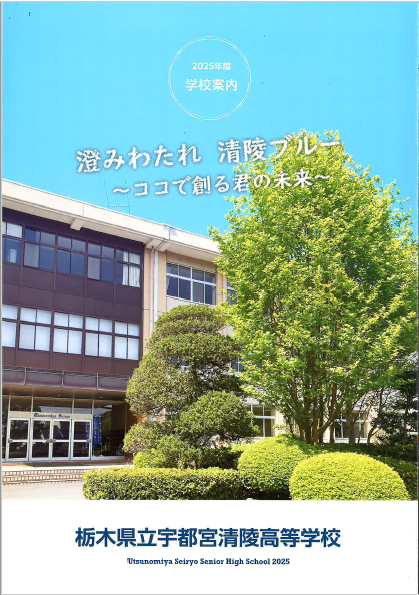
PDFダウンロードは
こちら
⇒2025清陵高学校パンフ.pdf














