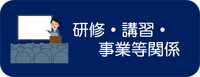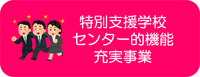令和6(2024)年度 生徒指導部
防災教育研修
7月23日(火)に、栃木県危機管理防災局危機管理課の担当者の方と那須烏山市消防署員の方々をお招きして、教職員の防災教育研修を行いました。
まず、栃木県危機管理防災局危機管理課の担当者の方から講話をいただきました。年明けに起きた能登半島地震について担当者の方は現地に行かれ、現地の写真を交えながら、その経験をお話ししていただきました。また、栃木県の災害対策についても詳しく教えていただきました。今後も十分に気を引き締めて、学校の安全対策に生かしていきたいと思います。

続いて、那須烏山市消防署員の方々から、訓練用の水消火器を使用しての消火訓練の説明を聞き、訓練を行いました。消火器の使い方についてレバーの持ち方やピンの抜き方、ノズルの動かし方など丁寧に教えていただき、実践的な訓練を通して学ぶことができました。その後、学校内の消火器の位置を確認し、研修が終了しました。普段、火災はなかなか身近に感じられるものではありませんが、万が一、起きた時には教職員ひとりひとりが適切に対応できるようにしなければなりません。



今回の研修により、教職員ひとりひとりの防災意識をより一層高めることができました。今回の学びを、今後の児童生徒への防災教育に生かしていきます。
不審者対応避難訓練(児童生徒)
自分の身の安全を守るために
7月8日(月)に不審者対応避難訓練を行いました。講師として那須烏山警察署の方にお越しいただきました。不審者の侵入を知らせる笛の合図を受けた教師の誘導により、児童生徒は避難体制をとることができました。緊迫感の中、児童生徒は緊張しながらも訓練に取り組みました。また、高等部生徒は、登下校中に不審者に声をかけられた時の対処法について訓練を行いました。
不審者は神出鬼没です。学校の中や登下校時、家の周辺で自分の身の安全を守るための対処法を知ることができました。今後とも「いかのおすし」の大切さを日常生活で定着できるよう繰り返し学習していきます。

夏季休業中の過ごし方について
不審者対応避難訓練(教職員)
児童生徒の安全を守るために
6月11日(火)に、職員研修として不審者対応避難訓練を行いました。講師に那須烏山警察署員の方々にお越しいただき、不審者対応や正しいさすまたの使い方を学びました。私たち教職員が、児童生徒の命、そして自身の命を守るため、どのような行動をとるべきなのか、役割、連携を確認し、シミュレーションを行いました。
シミュレーションでは、不審者役の教員、緊急出動班の教員による緊張感をもった訓練となり、教職員間の連携を図ることができました。実際にやってみて課題点・改善点も見つかり、講師の方からも御助言をいただいたので、大変有意義な研修になりました。
〈緊急対応の視点〉
①児童生徒の安全確保を第一に考えて行動する。
②教職員自身の安全確保に努める。
③迅速な連絡、通報を行う。
④報告、連絡、相談を怠らない。
学校行事等において人の出入りが多くなってきている隙を狙い、不審者が学校に入ってくる可能性があるかもしれません。児童生徒が安全に学校生活を送れるように、教職員全員が改めて気を引き締め直す研修になりました。
なお、7月8日(月)には、児童生徒を含めた不審者対応避難訓練を実施する予定です。