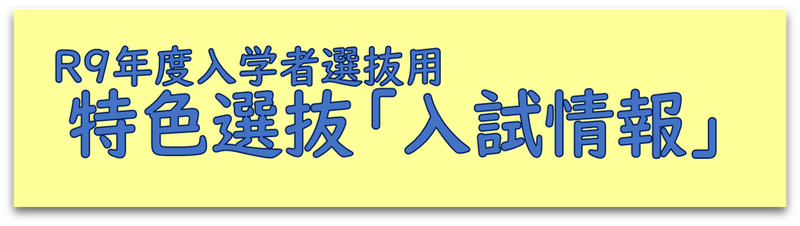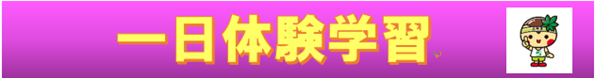文字
背景
行間
日誌
2020年8月の記事一覧
校長室より「山崎正和『劇的なる日本人』
図書紹介の7回目は、浅田次郎氏の『地下鉄(メトロ)に乗って』の予定でしたが、山崎正和氏の『劇的なる日本人』他に変更します。
8月21日、山崎正和氏が亡くなりました。山崎氏は、劇作家、評論家として日本の文化に大きく貢献した方です。
大学2年の時に演劇学の講義を取った時読んだ『世阿弥』や、大学3年の時に森鴎外のゼミに参加していた時読んだ『鴎外 戦う家長』の文筆の鋭さに圧倒されて以来、山崎氏の著作を読むようになりました。
現代文の教科書教材として取り上げられている『劇的なる日本人』は、授業で何度も扱いましたが、何度読んでも飽きることはなく、読むたびに優れた日本人論だと感じています。
優れた日本人論・日本文化論としては他に、『柔らかい個人主義の誕生』や『日本文化と個人主義』などがあります。
「消費社会の美学」という副題が付いた『柔らかい個人主義の誕生』は発表時たいへん話題となり、各界の著名人との対談集『柔らかい個人主義の時代』が発刊されています。
対談集では、丸谷才一氏との都市論『日本の町』が秀逸です。
また、『柔らかい自我の文学』や『近代の擁護』など、文学評論や文明評論も多く出版されています。
先日の外山滋比古氏に続き、巨星墜つの感を否めません。
8月21日、山崎正和氏が亡くなりました。山崎氏は、劇作家、評論家として日本の文化に大きく貢献した方です。
大学2年の時に演劇学の講義を取った時読んだ『世阿弥』や、大学3年の時に森鴎外のゼミに参加していた時読んだ『鴎外 戦う家長』の文筆の鋭さに圧倒されて以来、山崎氏の著作を読むようになりました。
現代文の教科書教材として取り上げられている『劇的なる日本人』は、授業で何度も扱いましたが、何度読んでも飽きることはなく、読むたびに優れた日本人論だと感じています。
優れた日本人論・日本文化論としては他に、『柔らかい個人主義の誕生』や『日本文化と個人主義』などがあります。
「消費社会の美学」という副題が付いた『柔らかい個人主義の誕生』は発表時たいへん話題となり、各界の著名人との対談集『柔らかい個人主義の時代』が発刊されています。
対談集では、丸谷才一氏との都市論『日本の町』が秀逸です。
また、『柔らかい自我の文学』や『近代の擁護』など、文学評論や文明評論も多く出版されています。
先日の外山滋比古氏に続き、巨星墜つの感を否めません。
0
2学期始業式式辞
皆さんおはようございます。
今回も放送による始業式となりました。したがって、また校歌を歌うことができません。皆さんの心の中で歌ってください。
誰もが経験したことのない、非常に短い夏休みが終わり、今日から誰も経験したことのない長い長い2学期が始まります。
1学期の終業式で皆さんに書いてもらった夏休み中にしたいと思うことはできたでしょうか。
あっという間の2週間で、何かしようと思う間もなく過ぎてしまったという人もいるのではないでしょうか。
私は考えていたことの一部しか実行することができず、改めて計画を立てることの大切さと、時間の貴重さに気づかされました。また、不測の事態に備え、早め早めの行動を習慣化しなくてはいけないのだなとも感じました。
おそらくは皆さんも時の経過の早さに驚いていることと思います。今後も何が起こるかわからない状況は続くことと思いますので、先を見越した行動と、代替プランを用意すること、時間を有効に使うことを考えてください。
さて、2学期始業式にあたり、3点ほどお話しししたいことがあります。
今回もプリントを用意しましたので、空欄への記入や余白へのメモをしながら聞いてください。
空欄への記入は日本語ディクテーションのつもりで、耳で聞いた言葉を文字に、漢字仮名交じりで書いてください。漢字が思い浮かばない人は、仮名で書いておいて後で辞書で調べてください。
まず最初に皆さんにお話ししたいことは、長い2学期の過ごし方についてです。
例年になく長い2学期の過ごし方として、生活のあらゆる面で、緊張と弛緩を適宜繰り返してほしいということです。
人間の神経は緊張させたままだと不調を来してしまいます。適宜緩めてしなやかさを保つ必要があります。しなやかさがないと柔軟な発想はできませんし、本来の能力を発揮することができなくなります。
ゴムやバネといったものは、強く引っ張って緊張させたままにしておくと、本来持つ役割を果たせなくなってしまいます。
緊張の限界を超えたゴムは切れてしまいますし、伸ばしたままの状態で長く置くと、縮まなくなってしまいます。
従って、心身の健康を保つうえでも、緊張と弛緩を適宜繰り返しながら長い2学期を乗り越えてほしいと思います。
新型コロナウイルス感染症の感染予防については、なお緊張感を持って取り組んでもらわなくてはなりません。
報道によると、他県では、100名近くの感染者が部活動を中心に出た高校や、20名以上の感染者が出た高校があります。また、大学のサークル内での感染も報じられているところです。
自分たちは大丈夫ということは決してありませんので、緊張感を持った活動をお願いします。
次に、夏休みのある八月という月に関連して思うところです。
北高のホームページ校長室よりに「八月がくるたびに」という記事を掲載し、日本人いや世界中の人たちは、昭和20年(1945年)の8月を忘れてはいけないと訴えましたが、日本人にとっては多くの意味ある日が続きます。
8月6日は広島に原爆が投下され、14万人の命が奪われた日、8月9日は長崎に原爆が投下され7万人の命が奪われた日、8月12日は群馬県上野村に日本航空機が墜落して520名の命が失われた日、8月13日は盂蘭盆会(うらぼんえ)の迎え盆、8月15日は終戦記念の日、8月16日は送り盆と昨日まで意味ある特別な日が続きました。
因みに、日常と異なる非日常の特別な日のことを「晴れ」と言います。「晴れ着」や「晴れの舞台」などと使われる「晴れ」です。「晴れ着」というのは、特別な日、「晴れの日」に着る着物だから「晴れ着」と言うのです。したがって、始業式の今日も、本校生にとっては「晴れの日」となります。たとえ雨が降っていても「晴れの日」なのです。入学式や卒業式、結婚式などで来賓の方が「この晴れの日に」というフレーズを使い、外は土砂降りの雨ということがあっても、「あの人、いくら用意した原稿だからといっても、こんな雨なんだから言い換えればいいのに」などと思わないでください。「雨が降っても晴れの日なのです。」
もし、そのような場に遭遇し、あなたの隣の人が「雨の日に晴れの日なんて言っているよ。」と笑っているようなことがあったら、「晴れの日というのは特別な日ということらしいですよ。」と教えてあげてください。この時大切なのは、「らしいですよ。」の「らしい」という言葉です。決して、「晴れっていうのは、特別な日のことなんだよ。知らないの。」などと言わないこと。「らしい」を使って、「自分もよくは知らないのだけれど」という雰囲気を出すこと。これが円滑な人間関係を構築する秘訣です。
特別な日、非日常を「晴れ」というのに対して、日常をいうことばを「褻(け)」と言います。声だけで説明するのが難しい漢字なので辞書で調べてください。「晴れ」と「褻(け)」、是非知っておいてください。
話を八月の話題に戻します。
一昨日の終戦記念の日、NHKは、原爆の開発に取り組んでいた日本人科学者のドラマを放送しました。京都帝国大学物理学教室において、実際にアトミック・ボム(原子爆弾)をアメリカ・ソ連よりも早く開発しようとしていた若者たちの姿が描かれていました。
ドラマでは、「科学者が兵器を作ることをどう考えるのか」と苦悩する場面や、原爆が投下された広島の町を見て、「自分たちが作ろうとしていたのはこれだったのか。」と嘆息する場面がありました。
私が皆さんに「哲学を持たない科学者ほど恐ろしい者はないから哲学を持ってほしい」といっていることの背景にはこのような事があります。
戦時中に日本の大学で実際におこわなわれていたこととしては、九州帝国大学医学部で行われたアメリカ人捕虜に対する生体解剖事件があります。この事件を題材とする小説が遠藤周作氏の『海と毒薬』です。『海と毒薬』は、今年も新潮文庫の100冊に入っていますので入手しやすいと思います。
新潮文庫の100冊の中には、広島の原爆投下後に降った雨によって被爆した女性を描いた、井伏鱒二氏の『黒い雨』もあります。
『黒い雨』といえば、『黒い雨訴訟』と言われる裁判の一審判決が先月29日に広島地方裁判所であり、国と広島県、広島市が控訴したのは、五日前の12日のことです。
75年前に起こったことは、まだ未解決なままなのです。
また、昨日16日は送り盆の日で、京都では五山の送り火が灯される日でした。今年はコロナウイルス感染症の感染予防のため、大幅に縮小して実施されましたが、これに関して耳を疑うニュースがありました。8月8日の夜に、送り火が行われる山に何者かが登って無断で私有地に入り、大がかりな照明などを用いてライトアップしたそうです。大文字保存会の理事長さんは、「お盆に迎えた先祖の霊を送る大切な儀式を汚す行為だ。」と憤りと嘆きの言葉を発していました。人の思いや、文化を解さない愚かなパフォーマンスといわざるを得ません。
改めて皆さんには、文化を理解し人の気持ちがわかる人間として人々をリードしてほしいと思いました。
最後に、皆さんに是非意識してもらいたいことをお話しします。
私は、本校に赴任するまでに、石橋高校に10年、宇都宮東高校に14年、鹿沼高校に3年と、本校に似通った高校に勤務してきました。
その間、宇都宮北高校を常に他校比較の対象校として、成績の推移や進路状況を見てきました。
その時思っていたことと、本校に勤務して中から皆さんの様子を見て感じたことがあります。
それは、学業面に関しては、もう少し頑張ることで更に進路選択の幅が広がるだろうにということです。
そこで、頭に浮かんだのが、盛唐の詩人、王之渙の「鸛鵲楼(かんじゃくろう)に登る」という五言絶句です。
国語便覧の唐の時代の地図のページに載っていますので、後で見てもらいたいと思いますが、その詩の中に、「千里の目を窮めんと欲し 更に上る一層の楼」という句があります。
「遙か彼方まで見ようと思って、もう一つ上の階に上る」という意味です。
皆さんも知っているように、一つ上の階に行くと見える景色が変わります。
より高みに身を置くことができると、より広くより遠くを見ることができます。
より広い視野を持つことは、より豊かな人生を送ることにつながります。
北高生は、今一歩勉学に励むことで、その成果が実を結び、より広い進路を切り拓き、人生をよりよく変えることができると思いました。
そこで、北高生一人一人が、王之渙の、「更に上る一層の楼」という言葉を意識して、学業に取り組むことを願うものです。
以上3点申し上げ2学期始業式の式辞とします。
今回も放送による始業式となりました。したがって、また校歌を歌うことができません。皆さんの心の中で歌ってください。
誰もが経験したことのない、非常に短い夏休みが終わり、今日から誰も経験したことのない長い長い2学期が始まります。
1学期の終業式で皆さんに書いてもらった夏休み中にしたいと思うことはできたでしょうか。
あっという間の2週間で、何かしようと思う間もなく過ぎてしまったという人もいるのではないでしょうか。
私は考えていたことの一部しか実行することができず、改めて計画を立てることの大切さと、時間の貴重さに気づかされました。また、不測の事態に備え、早め早めの行動を習慣化しなくてはいけないのだなとも感じました。
おそらくは皆さんも時の経過の早さに驚いていることと思います。今後も何が起こるかわからない状況は続くことと思いますので、先を見越した行動と、代替プランを用意すること、時間を有効に使うことを考えてください。
さて、2学期始業式にあたり、3点ほどお話しししたいことがあります。
今回もプリントを用意しましたので、空欄への記入や余白へのメモをしながら聞いてください。
空欄への記入は日本語ディクテーションのつもりで、耳で聞いた言葉を文字に、漢字仮名交じりで書いてください。漢字が思い浮かばない人は、仮名で書いておいて後で辞書で調べてください。
まず最初に皆さんにお話ししたいことは、長い2学期の過ごし方についてです。
例年になく長い2学期の過ごし方として、生活のあらゆる面で、緊張と弛緩を適宜繰り返してほしいということです。
人間の神経は緊張させたままだと不調を来してしまいます。適宜緩めてしなやかさを保つ必要があります。しなやかさがないと柔軟な発想はできませんし、本来の能力を発揮することができなくなります。
ゴムやバネといったものは、強く引っ張って緊張させたままにしておくと、本来持つ役割を果たせなくなってしまいます。
緊張の限界を超えたゴムは切れてしまいますし、伸ばしたままの状態で長く置くと、縮まなくなってしまいます。
従って、心身の健康を保つうえでも、緊張と弛緩を適宜繰り返しながら長い2学期を乗り越えてほしいと思います。
新型コロナウイルス感染症の感染予防については、なお緊張感を持って取り組んでもらわなくてはなりません。
報道によると、他県では、100名近くの感染者が部活動を中心に出た高校や、20名以上の感染者が出た高校があります。また、大学のサークル内での感染も報じられているところです。
自分たちは大丈夫ということは決してありませんので、緊張感を持った活動をお願いします。
次に、夏休みのある八月という月に関連して思うところです。
北高のホームページ校長室よりに「八月がくるたびに」という記事を掲載し、日本人いや世界中の人たちは、昭和20年(1945年)の8月を忘れてはいけないと訴えましたが、日本人にとっては多くの意味ある日が続きます。
8月6日は広島に原爆が投下され、14万人の命が奪われた日、8月9日は長崎に原爆が投下され7万人の命が奪われた日、8月12日は群馬県上野村に日本航空機が墜落して520名の命が失われた日、8月13日は盂蘭盆会(うらぼんえ)の迎え盆、8月15日は終戦記念の日、8月16日は送り盆と昨日まで意味ある特別な日が続きました。
因みに、日常と異なる非日常の特別な日のことを「晴れ」と言います。「晴れ着」や「晴れの舞台」などと使われる「晴れ」です。「晴れ着」というのは、特別な日、「晴れの日」に着る着物だから「晴れ着」と言うのです。したがって、始業式の今日も、本校生にとっては「晴れの日」となります。たとえ雨が降っていても「晴れの日」なのです。入学式や卒業式、結婚式などで来賓の方が「この晴れの日に」というフレーズを使い、外は土砂降りの雨ということがあっても、「あの人、いくら用意した原稿だからといっても、こんな雨なんだから言い換えればいいのに」などと思わないでください。「雨が降っても晴れの日なのです。」
もし、そのような場に遭遇し、あなたの隣の人が「雨の日に晴れの日なんて言っているよ。」と笑っているようなことがあったら、「晴れの日というのは特別な日ということらしいですよ。」と教えてあげてください。この時大切なのは、「らしいですよ。」の「らしい」という言葉です。決して、「晴れっていうのは、特別な日のことなんだよ。知らないの。」などと言わないこと。「らしい」を使って、「自分もよくは知らないのだけれど」という雰囲気を出すこと。これが円滑な人間関係を構築する秘訣です。
特別な日、非日常を「晴れ」というのに対して、日常をいうことばを「褻(け)」と言います。声だけで説明するのが難しい漢字なので辞書で調べてください。「晴れ」と「褻(け)」、是非知っておいてください。
話を八月の話題に戻します。
一昨日の終戦記念の日、NHKは、原爆の開発に取り組んでいた日本人科学者のドラマを放送しました。京都帝国大学物理学教室において、実際にアトミック・ボム(原子爆弾)をアメリカ・ソ連よりも早く開発しようとしていた若者たちの姿が描かれていました。
ドラマでは、「科学者が兵器を作ることをどう考えるのか」と苦悩する場面や、原爆が投下された広島の町を見て、「自分たちが作ろうとしていたのはこれだったのか。」と嘆息する場面がありました。
私が皆さんに「哲学を持たない科学者ほど恐ろしい者はないから哲学を持ってほしい」といっていることの背景にはこのような事があります。
戦時中に日本の大学で実際におこわなわれていたこととしては、九州帝国大学医学部で行われたアメリカ人捕虜に対する生体解剖事件があります。この事件を題材とする小説が遠藤周作氏の『海と毒薬』です。『海と毒薬』は、今年も新潮文庫の100冊に入っていますので入手しやすいと思います。
新潮文庫の100冊の中には、広島の原爆投下後に降った雨によって被爆した女性を描いた、井伏鱒二氏の『黒い雨』もあります。
『黒い雨』といえば、『黒い雨訴訟』と言われる裁判の一審判決が先月29日に広島地方裁判所であり、国と広島県、広島市が控訴したのは、五日前の12日のことです。
75年前に起こったことは、まだ未解決なままなのです。
また、昨日16日は送り盆の日で、京都では五山の送り火が灯される日でした。今年はコロナウイルス感染症の感染予防のため、大幅に縮小して実施されましたが、これに関して耳を疑うニュースがありました。8月8日の夜に、送り火が行われる山に何者かが登って無断で私有地に入り、大がかりな照明などを用いてライトアップしたそうです。大文字保存会の理事長さんは、「お盆に迎えた先祖の霊を送る大切な儀式を汚す行為だ。」と憤りと嘆きの言葉を発していました。人の思いや、文化を解さない愚かなパフォーマンスといわざるを得ません。
改めて皆さんには、文化を理解し人の気持ちがわかる人間として人々をリードしてほしいと思いました。
最後に、皆さんに是非意識してもらいたいことをお話しします。
私は、本校に赴任するまでに、石橋高校に10年、宇都宮東高校に14年、鹿沼高校に3年と、本校に似通った高校に勤務してきました。
その間、宇都宮北高校を常に他校比較の対象校として、成績の推移や進路状況を見てきました。
その時思っていたことと、本校に勤務して中から皆さんの様子を見て感じたことがあります。
それは、学業面に関しては、もう少し頑張ることで更に進路選択の幅が広がるだろうにということです。
そこで、頭に浮かんだのが、盛唐の詩人、王之渙の「鸛鵲楼(かんじゃくろう)に登る」という五言絶句です。
国語便覧の唐の時代の地図のページに載っていますので、後で見てもらいたいと思いますが、その詩の中に、「千里の目を窮めんと欲し 更に上る一層の楼」という句があります。
「遙か彼方まで見ようと思って、もう一つ上の階に上る」という意味です。
皆さんも知っているように、一つ上の階に行くと見える景色が変わります。
より高みに身を置くことができると、より広くより遠くを見ることができます。
より広い視野を持つことは、より豊かな人生を送ることにつながります。
北高生は、今一歩勉学に励むことで、その成果が実を結び、より広い進路を切り拓き、人生をよりよく変えることができると思いました。
そこで、北高生一人一人が、王之渙の、「更に上る一層の楼」という言葉を意識して、学業に取り組むことを願うものです。
以上3点申し上げ2学期始業式の式辞とします。
0
校長室より「八月がくるたびに」
昨日8月6日は、昭和20年(1945年)に広島に原爆が投下され多くの無辜(むこ)の命が奪われた日です。本校では、原爆が投下・爆裂した午前8時15分に、校内にいる者全員でお亡くなりになった方々を悼み黙祷いたしました。
本校では、平和教育の一環として修学旅行で広島を訪れ、平和公園・平和記念資料館にて原爆の恐ろしさを知り、命の尊さ、平和の尊さを実感として学んでいます。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度は、修学旅行での広島訪問を断念せざるを得ませんでした。ただし、貴重な平和学習の機会をなくしてしまいたくはないので、現在広島訪問に代わる平和学習の方法を検討しているところです。
8月9日には、長崎に原爆が投下され、8月15日に終戦となった昭和20年(1945年)の8月を私たち日本人は、いや世界中の人たちは決して忘れてはいけません。
「八月がくるたびに」、毎年8月になると、この言葉が私の脳裡に浮かびます。
「八月がくるたびに」というのは、私が小学校の時に読んだ、おおえひで・作、篠原勝之・絵になる本の題名です。1971年に発刊されたこの本は、現在全く異なる形態で出版されているとのことですが、篠原勝之さんの絵とともに訴えかけるおおえさんの言葉は今も忘れることができません。「だれが… どうして? だれが… どうして?」の言葉は、それこそ8月がくるたびに何度も何度も浮かび上がります。
私がこの本に出会ったのは、この本がその年の読書感想文コンクールの課題図書だったからです。当時本好きではなかった私が、とにかく何か書かなくてはいけない、でも何を読んだらよいかわからないでいる時に母親が買ってきたものだと記憶しています。「8月がくるたびに」という言葉と、「だれが どうして」という言葉は、その後もずっと私の体に張り付いて離れませんでした。
3年前に、栃木県学校図書館協議会長となり、読書感想文コンクールを主催する立場となった時に、1971年の課題図書を調べてみたところ、高校生向けの課題図書には渡辺淳一氏の『花埋み』が選定されていました。
『花埋み』は、日本最初の女性医師となった荻野吟子氏の生涯を描いた作品です。その劇的な人生から演劇やテレビドラマにもなった作品であり、高校生の皆さんに読んでほしい一冊です。
立場上言うのではなく、全国学校図書館協議会では、小中高校生それぞれの年代にふさわしく心に残るであろう作品を課題図書に選定しています。別に紹介しようと思っている重松清氏の『その日の前に』も2006年度の課題図書に選定されています。何を読めばいいかなと思ったら、課題図書を選択肢の一つにしてはいかがでしょうか。今年の高校生の課題図書は、谷津矢車『廉太郎ノオト』、マイケル・モーパーゴ『フラミンゴボーイ』、マーク・アロンソン、マリナ・ブドーズ『キャバとゲルダ:ふたりの戦場カメラマン』の三冊です。
本校では、平和教育の一環として修学旅行で広島を訪れ、平和公園・平和記念資料館にて原爆の恐ろしさを知り、命の尊さ、平和の尊さを実感として学んでいます。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度は、修学旅行での広島訪問を断念せざるを得ませんでした。ただし、貴重な平和学習の機会をなくしてしまいたくはないので、現在広島訪問に代わる平和学習の方法を検討しているところです。
8月9日には、長崎に原爆が投下され、8月15日に終戦となった昭和20年(1945年)の8月を私たち日本人は、いや世界中の人たちは決して忘れてはいけません。
「八月がくるたびに」、毎年8月になると、この言葉が私の脳裡に浮かびます。
「八月がくるたびに」というのは、私が小学校の時に読んだ、おおえひで・作、篠原勝之・絵になる本の題名です。1971年に発刊されたこの本は、現在全く異なる形態で出版されているとのことですが、篠原勝之さんの絵とともに訴えかけるおおえさんの言葉は今も忘れることができません。「だれが… どうして? だれが… どうして?」の言葉は、それこそ8月がくるたびに何度も何度も浮かび上がります。
私がこの本に出会ったのは、この本がその年の読書感想文コンクールの課題図書だったからです。当時本好きではなかった私が、とにかく何か書かなくてはいけない、でも何を読んだらよいかわからないでいる時に母親が買ってきたものだと記憶しています。「8月がくるたびに」という言葉と、「だれが どうして」という言葉は、その後もずっと私の体に張り付いて離れませんでした。
3年前に、栃木県学校図書館協議会長となり、読書感想文コンクールを主催する立場となった時に、1971年の課題図書を調べてみたところ、高校生向けの課題図書には渡辺淳一氏の『花埋み』が選定されていました。
『花埋み』は、日本最初の女性医師となった荻野吟子氏の生涯を描いた作品です。その劇的な人生から演劇やテレビドラマにもなった作品であり、高校生の皆さんに読んでほしい一冊です。
立場上言うのではなく、全国学校図書館協議会では、小中高校生それぞれの年代にふさわしく心に残るであろう作品を課題図書に選定しています。別に紹介しようと思っている重松清氏の『その日の前に』も2006年度の課題図書に選定されています。何を読めばいいかなと思ったら、課題図書を選択肢の一つにしてはいかがでしょうか。今年の高校生の課題図書は、谷津矢車『廉太郎ノオト』、マイケル・モーパーゴ『フラミンゴボーイ』、マーク・アロンソン、マリナ・ブドーズ『キャバとゲルダ:ふたりの戦場カメラマン』の三冊です。
0
1学期終業式 式辞
令和2年度第1学期終業式 式辞
改めて、皆さんこんにちは。
ここからは、1学期の締めくくりとなる終業式の式辞として話しをします。
始業式と同様、放送によるものとなってしまいました。
私が皆さんの前で話をするのは、入学式で1年生の入学を許可し、式辞を述べた時だけであり、未だ2・3年生の前で話をすることができていません。
廊下ですれ違うことがあっても、お互いにマスク越しの顔しか見ることができません。おそらく、私を見て校長だと認識してくれる人は数少ないことでしょう。
いつになったら皆さんのマスクなしの顔を見ることができるのか。皆さんの顔を見ながら話をすることができるのか。その思いは募るばかりです。
しかしながら、連日耳にする過去最多の感染者数という報道には、危機感を覚えずにはいられません。改めてマスクの着用、手洗い、三密を避けた行動に徹することが求められます。
6月から通常登校となりましたが、決して通常の学校生活が送れたわけではありませんでした。登下校の制約、授業内容の制約、休み時間の行動の制約、部活動の制約、学校行事の制約と多種多様な制約を強いられました。
生徒誰もが楽しみにしていた学校祭も中止とせざるをえませんでした。2年生の修学旅行も日程と旅行先が変更されました。今後の状況によっては他の行事等の変更・中止があるかもしれません。
しかし、ここで生徒の皆さんに知っていてもらいたいことがあります。
それは、皆さんの学校生活の思い出がより多く残せるよう、先生方は最大限検討・協議していたということです。
こうすれば出来るのではないか。ああすればできるのではないか。ここまでならやれるのではないかと、何度も何度も計画を練り直し、次の案、更にその次の案と生徒の皆さんからの意見も聞きながら検討し、それでも難しいという結論に達し、実施に向け何度も考えたものが実行不可能となり、変更・中止に至ったということを知っておいてください。今後も何ができるか。どうすればできるかを考えていきたいと思います。
さて、今日は、たった2ヶ月しかなかった1学期の終業式となるわけですが、今日は皆さんに、「令和2年度第1学期終業式校長式辞メモ」というプリントを用意しました。そこに記入しながら話を聞いてください。
ということで、机の上にプリントと筆記具は出ているでしょうか。このメモには、あらかじめ記入を要求されていることだけでなく、話しを聞きながら、書きとどめておきたいこと、疑問に思ったことなどを余白や裏面に書いていってください。使い方は自由です。目的は、ただ聞き流すのではなく、意識を持って聞いてもらうことです。
まず、学年、クラス、出席番号と氏名を記入してください。
では、最初に一学期の振り返りをしてもらいたいと思います。1学期が始まる際に皆さんが立てた目標を記入してください。時間は30秒です。
次に、1学期の間に自分ができたことと、できなかったことを書いてください。時間は1分です。書き終わらない人、思い浮かばない人は、家に帰ってからじっくり1学期の振返りをしてください。
それでは次に、皆さんが夏休みにしたいことを書いてください。
例年に比べて短く、制約の多い夏休みではありますが、その中で皆さんがしたいと思うことを書いてください。時間は30秒です。
終業式は、このように学期中を振り返り、次のスタートのための区切りの行事であり、自己のアイデンティティーを再確認する日です。
そしてまた、自分が北高の生徒であることを再認識し、帰属意識を高める日でもあります。
それを象徴するのが、校歌の斉唱です。しかし、それができません。
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、今年度は未だ校歌を歌うことができていません。1年生は北高の校歌をどれだけ歌えるでしょうか。
在学中は入学式や卒業式、始業式や終業式といった時の慣例だから歌うものと感じている人がいるかもしれませんが、校歌の持つ意味が本当にわかるのは卒業してからです。
卒業後、北高の校歌を耳にし、一緒に歌った時に北高の一員であることの帰属感が実感されます。
それが甲子園のグラウンドであったり、高校生クイズの決勝の場で、テレビから北高の校歌が流れてきたりすると感無量です。
一昨年の夏の甲子園での金足農業の全力校歌が話題となったことは記憶に新しいところですが、肩を組み合い、共に校歌を歌えることの素晴らしさは在校中はなかなか理解できないかもしれませんが、皆さんとともに声高らかに校歌を歌える日を私は心待ちにしています。
北高のホームページには、校歌のアイコンがあり、このアイコンをクリック・タップすると校歌の歌詞が表示されるとともに、吹奏楽の演奏に乗った美しい歌声が流れます。パソコンでも、スマートホンでも聴くことができます。
北高の校歌をうまく歌えないという人は、ホームページにある校歌を使って練習するとうまく歌えるようになるでしょう。
式典で校歌を歌うことができないというのも、制約の一つですが、本当に様々な所で制約を受け続けている今の境遇はとても辛いことです。
明治時代の小説家・ジャーナリストである国木田独歩という人は、その日記『欺かざるの記』の中で、「忍耐と勤勉と希望と満足とは境遇に勝つものなり」と言っています。
このコロナ禍の境遇に勝つものは、一人一人の、「忍耐と勤勉と希望と満足」なのでしょう。
私たちは、今まで十分堪え忍んできたと思いますが、感染の終息には、尚、忍耐が必要なのかもしれません。そして、何事にも勤勉に取り組み、希望と満足をもって歩むことによって、今の境遇に打ち勝ちましょう。
最後に、私が始業式で皆さんに話したことの振り返りで終えたいと思います。
私が始業式で話した、北高生に実践してもらいたいと言ったことを覚えているでしょうか。覚えている人はメモの括弧内に記入してください。
私は、皆さんに「哲学を持つこと」を実践してもらいたいと言ったのですが、その取り組みを皆さんはしてくれたでしょうか。
では、哲学を持つために必要なこととして挙げたことは覚えているでしょうか。覚えている人は二つの括弧内に記入してください。
それは、多くの人と接し、多くの本を読むことです。コロナウイルス感染症の感染拡大予防の点からは多くの人と接することは今は避けなくてはなりませんが、その分、多くの本を読んでください。本の世界でも多くの人に接する事ができます。
北高ホームページには、校長室よりのアイコンがあります。そこには、皆さんに伝えたいことや図書の紹介が載っています。最新の図書紹介では、ブレイディみかこさんの「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」について掲載しましたが、この本を読むことで、遠く離れたイギリスに住む中学生と、彼に関連する多くの人に接する事ができます。また、ブレイディみかこさんの母校、福岡県立修猷館高等学校に関連して紹介した城山三郎氏の作品を読めば、そこに描かれた人々の生き様に接し、自分の生き方に思いをいたすことができます。直接人に接することができない分、読書によって、間接的に多くの人と接してください。
以上で、令和2年度第1学期終業式の校長式辞を終えます。
改めて、皆さんこんにちは。
ここからは、1学期の締めくくりとなる終業式の式辞として話しをします。
始業式と同様、放送によるものとなってしまいました。
私が皆さんの前で話をするのは、入学式で1年生の入学を許可し、式辞を述べた時だけであり、未だ2・3年生の前で話をすることができていません。
廊下ですれ違うことがあっても、お互いにマスク越しの顔しか見ることができません。おそらく、私を見て校長だと認識してくれる人は数少ないことでしょう。
いつになったら皆さんのマスクなしの顔を見ることができるのか。皆さんの顔を見ながら話をすることができるのか。その思いは募るばかりです。
しかしながら、連日耳にする過去最多の感染者数という報道には、危機感を覚えずにはいられません。改めてマスクの着用、手洗い、三密を避けた行動に徹することが求められます。
6月から通常登校となりましたが、決して通常の学校生活が送れたわけではありませんでした。登下校の制約、授業内容の制約、休み時間の行動の制約、部活動の制約、学校行事の制約と多種多様な制約を強いられました。
生徒誰もが楽しみにしていた学校祭も中止とせざるをえませんでした。2年生の修学旅行も日程と旅行先が変更されました。今後の状況によっては他の行事等の変更・中止があるかもしれません。
しかし、ここで生徒の皆さんに知っていてもらいたいことがあります。
それは、皆さんの学校生活の思い出がより多く残せるよう、先生方は最大限検討・協議していたということです。
こうすれば出来るのではないか。ああすればできるのではないか。ここまでならやれるのではないかと、何度も何度も計画を練り直し、次の案、更にその次の案と生徒の皆さんからの意見も聞きながら検討し、それでも難しいという結論に達し、実施に向け何度も考えたものが実行不可能となり、変更・中止に至ったということを知っておいてください。今後も何ができるか。どうすればできるかを考えていきたいと思います。
さて、今日は、たった2ヶ月しかなかった1学期の終業式となるわけですが、今日は皆さんに、「令和2年度第1学期終業式校長式辞メモ」というプリントを用意しました。そこに記入しながら話を聞いてください。
ということで、机の上にプリントと筆記具は出ているでしょうか。このメモには、あらかじめ記入を要求されていることだけでなく、話しを聞きながら、書きとどめておきたいこと、疑問に思ったことなどを余白や裏面に書いていってください。使い方は自由です。目的は、ただ聞き流すのではなく、意識を持って聞いてもらうことです。
まず、学年、クラス、出席番号と氏名を記入してください。
では、最初に一学期の振り返りをしてもらいたいと思います。1学期が始まる際に皆さんが立てた目標を記入してください。時間は30秒です。
次に、1学期の間に自分ができたことと、できなかったことを書いてください。時間は1分です。書き終わらない人、思い浮かばない人は、家に帰ってからじっくり1学期の振返りをしてください。
それでは次に、皆さんが夏休みにしたいことを書いてください。
例年に比べて短く、制約の多い夏休みではありますが、その中で皆さんがしたいと思うことを書いてください。時間は30秒です。
終業式は、このように学期中を振り返り、次のスタートのための区切りの行事であり、自己のアイデンティティーを再確認する日です。
そしてまた、自分が北高の生徒であることを再認識し、帰属意識を高める日でもあります。
それを象徴するのが、校歌の斉唱です。しかし、それができません。
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、今年度は未だ校歌を歌うことができていません。1年生は北高の校歌をどれだけ歌えるでしょうか。
在学中は入学式や卒業式、始業式や終業式といった時の慣例だから歌うものと感じている人がいるかもしれませんが、校歌の持つ意味が本当にわかるのは卒業してからです。
卒業後、北高の校歌を耳にし、一緒に歌った時に北高の一員であることの帰属感が実感されます。
それが甲子園のグラウンドであったり、高校生クイズの決勝の場で、テレビから北高の校歌が流れてきたりすると感無量です。
一昨年の夏の甲子園での金足農業の全力校歌が話題となったことは記憶に新しいところですが、肩を組み合い、共に校歌を歌えることの素晴らしさは在校中はなかなか理解できないかもしれませんが、皆さんとともに声高らかに校歌を歌える日を私は心待ちにしています。
北高のホームページには、校歌のアイコンがあり、このアイコンをクリック・タップすると校歌の歌詞が表示されるとともに、吹奏楽の演奏に乗った美しい歌声が流れます。パソコンでも、スマートホンでも聴くことができます。
北高の校歌をうまく歌えないという人は、ホームページにある校歌を使って練習するとうまく歌えるようになるでしょう。
式典で校歌を歌うことができないというのも、制約の一つですが、本当に様々な所で制約を受け続けている今の境遇はとても辛いことです。
明治時代の小説家・ジャーナリストである国木田独歩という人は、その日記『欺かざるの記』の中で、「忍耐と勤勉と希望と満足とは境遇に勝つものなり」と言っています。
このコロナ禍の境遇に勝つものは、一人一人の、「忍耐と勤勉と希望と満足」なのでしょう。
私たちは、今まで十分堪え忍んできたと思いますが、感染の終息には、尚、忍耐が必要なのかもしれません。そして、何事にも勤勉に取り組み、希望と満足をもって歩むことによって、今の境遇に打ち勝ちましょう。
最後に、私が始業式で皆さんに話したことの振り返りで終えたいと思います。
私が始業式で話した、北高生に実践してもらいたいと言ったことを覚えているでしょうか。覚えている人はメモの括弧内に記入してください。
私は、皆さんに「哲学を持つこと」を実践してもらいたいと言ったのですが、その取り組みを皆さんはしてくれたでしょうか。
では、哲学を持つために必要なこととして挙げたことは覚えているでしょうか。覚えている人は二つの括弧内に記入してください。
それは、多くの人と接し、多くの本を読むことです。コロナウイルス感染症の感染拡大予防の点からは多くの人と接することは今は避けなくてはなりませんが、その分、多くの本を読んでください。本の世界でも多くの人に接する事ができます。
北高ホームページには、校長室よりのアイコンがあります。そこには、皆さんに伝えたいことや図書の紹介が載っています。最新の図書紹介では、ブレイディみかこさんの「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」について掲載しましたが、この本を読むことで、遠く離れたイギリスに住む中学生と、彼に関連する多くの人に接する事ができます。また、ブレイディみかこさんの母校、福岡県立修猷館高等学校に関連して紹介した城山三郎氏の作品を読めば、そこに描かれた人々の生き様に接し、自分の生き方に思いをいたすことができます。直接人に接することができない分、読書によって、間接的に多くの人と接してください。
以上で、令和2年度第1学期終業式の校長式辞を終えます。
0
0
0
5
3
0
6
9
0
0
事務補助員(公仕)募集
本校では現在、事務補助員(公仕)を募集しております。
募集要項はこちら
↓
証明書等の交付申請
卒業生の方で各種証明書等を必要とされる場合は
証明書等の交付申請
のページをご確認ください。
学校情報・入試情報
一日体験学習
特殊詐欺にご注意ください
栃木県警本部より、本校の同窓生に対する特殊詐欺の事案が発生しているとの連絡がありました。同窓生の皆様におかれましては、ご家族・関係者とも連絡を取り、特殊詐欺の電話には十分にご注意いただきますようお願いいたします。また、学校といたしましても個人情報の取り扱いには十分に注意しているところですが、同窓会名簿等の個人情報の取り扱いには十分にご注意いただきますよう、併せてお願いいたします。
主な相談窓口
教育相談の窓口一覧(PDF形式、令和7年5月栃木県教育委員会)です。