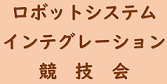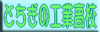文字
背景
行間
電気や機械の基礎的・基本的知識について学ぶとともに、地域社会の先端的技術や高度熟練技能者の技に触れ、ものづくりに真摯に取り組む姿勢と、社会の変化に柔軟に対応する能力を身に付けます。
1年次には電気・機械の基礎を全員が学び、2年次から個々の希望により、電気コースと電子機械コースの2コースに分かれて学習し、地域社会で活躍できる技術者になることを目指します。
【電気コース】
発電から送配電の電気エネルギーについて学習し、電気・電子技術のスペシャリストになることを目指します。
(1)コースの特色
経済産業省の認定を受け、卒業後の実務経験により 第三種 電気主任技術者の国家資格の取得ができます。
発電、送配電、電気機器、電気応用、電子回路など、電気の基礎・基本を学習します。
(2)目指す資格
技能士(電子機器組立)・第二種電気工事士・第一種電気工事士・危険物取扱者
第二級デジタル通信(DD第三種)
【電子機械コース】
機械設計・加工技術からロボット等の制御技術等を学習し、生産技術分野のスペシャリストになることを目指します。
(1)コースの特色
機械、電気・電子及び情報に関する各分野の基礎を学び、メカトロニクス学習の基盤をつくります。
産業界で必要とされる、制御プログラミング技術の基礎・基本を学習します。
(2)目指す資格
技能士(シ-ケンス制御)・第二種電気工事士・危険物取扱者・機械製図検定
産業用ロボット特別教育講習受講
【共通科目】
●工業技術基礎 [履修学年1年 単位数 3]
工業に関する各種の基礎的な技術・技能(電気計測・電気工事・デジタルマルチメータ製作・旋盤・リレーシーケンス等)を体験的に学習します。
●電気回路 [履修学年1、2年 単位数 6]
電気の基礎的なことを学習します。1年生は、直流・交流回路、静電気、磁気回路などについて学習します。2年生では、電圧や電流をベクトルや複素数で表したりします。また三相交流について学びます。
●情報技術基礎 [履修学年1年 単位数 3]
コンピュータの基本構成や2進数の計算、論理回路の基礎、プログラミング(C言語)等について学習します。
●課題研究 [履修学年3年 単位数 3]
作品製作、調査研究、職場実習の各分野において生徒自らがテーマを設定し、研究を行います。本校では、これを1学期に集中して行います。希望により、毎週大学や企業に出向いて研究・調査する生徒もいます。また、年度末に研究成果の発表会を実施しています。
【電気コース】
●電気システム実習 [履修学年2,3年 単位数 7]
アンプの製作、シーケンス制御、模擬送電実習、高電圧実習、直流電動機の速度特性、三相同期発電の並行運転などについて学びます。いずれも少人数のグループに分かれて実習します。
●製図[履修学年2年 単位数 2]
日本産業規格(JIS)に基づく図面の作成方法、図面の見方、CADによる作図方法、屋内配線図の見方について学習します。
●電力技術 [履修学年2、3年 単位数 5]
2年生では電力の発生や輸送に関する技術(発電・送電・配電)、及び電力の制御に関する技術、電力を用途に応じて利用する技術(電力応用)などについて学びます。
●電子回路 [履修学年2年 単位数 2]
身の回りには様々な電気製品がありますが、その多くに電子回路が入っており、その機能や特性を学びます。また電子回路の種類やそれぞれの動作原理について学びます。
●電気機器 [履修学年3年 単位数 2]
電気エネルギーを回転エネルギーに変える直流電動機や様々な運動エネルギーを電気エネルギーに変換する直流発電機の原理や特性について学びます。
また電圧の大きさを変える変圧器や三相交流電動機・三相同期発電機について学びます。
【電子機械コース】
●電気システム実習 [履修学年2年、3年 単位数 7]
電子機械を構成する機械・電気・電子・情報の基礎的な技術、及びそれらの融合技術を実習によって体験的に学習します。
●製図 [履修学年2年 単位数 2]
日本産業規格(JIS)に基づく図面の作成方法、図面の見方、CADによる作図方法、機械図面の見方について学習します。
●電子機械 [履修学年2年 単位数 2]
電子機械を構成する機械要素、センサー、アクチュエータ及びシーケンス制御について学習します。
●機械設計 [履修学年2、3年 単位数 4]
機械を設計するために必要な機械に働く力や仕事、材料の強さ、機械を構成するねじや歯車などの機械要素について学習します。
●生産技術 [履修学年3年 単位数 3]
工業生産のシステム構築をおこなうための、制御技術、ロボット技術、自動化技術について学習します。
| 1年次の共通実習 | |
|
電気工事実習 |
デジタルマルチメーター製作実習 |
|
旋盤実習
|
リレーシーケンス実習
|
| 電気コースの主な実習 | |
|
実践的な電気工事実習 |2年 
1年次に学習する電気工事士の単位作業を基礎として、実践的な電気工事の技術や施工方法の習得を目指します。 |
高電圧実習 |3年 |
|
IoT技術の研究|3年
|
三相同期発電|3年
|
| 電子機械コースの主な実習 | |
|
シーケンス制御実習|2年
|
マイコン実習|3年 |
|
産業用ロボット実習|3年
|
3D CAD実習|3年
|


 第2種電気工事士の取得に向け実技試験(単位作業)および筆記試験の力を身につけます。
第2種電気工事士の取得に向け実技試験(単位作業)および筆記試験の力を身につけます。 正しい半田付け技術、電子部品の取り扱い方法の習得を目標にデジタルマルチメーターを製作します。
正しい半田付け技術、電子部品の取り扱い方法の習得を目標にデジタルマルチメーターを製作します。 旋盤による加工手順や切削条件の決め方などの基礎・基本を学びます。
旋盤による加工手順や切削条件の決め方などの基礎・基本を学びます。 工場の自動化などの基本となるシーケンス制御を理解するために、リレーやタイマなどの配線をしながら学びます。
工場の自動化などの基本となるシーケンス制御を理解するために、リレーやタイマなどの配線をしながら学びます。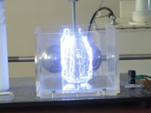 電気を安全に利用するため発電、送電、配電について学びます。放電現象の発生条件について条件を変えながら確認します。
電気を安全に利用するため発電、送電、配電について学びます。放電現象の発生条件について条件を変えながら確認します。 インターネット回線経由で制御をする IoT技術の研究に取り組みます。
インターネット回線経由で制御をする IoT技術の研究に取り組みます。 複数のモータと発電機で同時に発電し、特性を調べます。
複数のモータと発電機で同時に発電し、特性を調べます。 国家資格技能検定3級程度のシーケンス制御プログラムおよび配線技術を学習します。
国家資格技能検定3級程度のシーケンス制御プログラムおよび配線技術を学習します。 C言語やArduinoマイコン言語の実習をとおして、制御実習の基礎を学びトレースロボットを制御します。
C言語やArduinoマイコン言語の実習をとおして、制御実習の基礎を学びトレースロボットを制御します。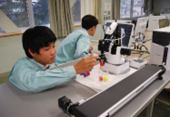 産業用ロボットを使って工場で使われているような生産ラインを設計・制御をします。
産業用ロボットを使って工場で使われているような生産ラインを設計・制御をします。 3D CADでペン立てを設計します。作成した図面を3Dプリンタで出力して製品にします。
3D CADでペン立てを設計します。作成した図面を3Dプリンタで出力して製品にします。