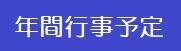文字
背景
行間
新着
11月6日、芸術家の派遣事業の一環として、沢井箏曲院宇都宮研究会より3名の講師の先生方をお迎えし、箏の体験授業を実施しました。限られた時間の中でも丁寧にご指導いただき、中学部、高等部の生徒たちは日本の伝統音楽にじっくりと触れることができました。鑑賞コーナーでは、和楽器のアンサンブルによる「アンパンマンのマーチ」や、教科書にも掲載されている「春の海」「六段」、さらにオリジナル曲「八咫烏(やたがらす)」の演奏が披露され、子どもたちはその音色に魅了されていました。箏に触れるのが初めての小学部の児童も多く、音を出す楽しさや、和楽器ならではの響きに感動する姿が見られました。日本の伝統文化を身近に感じる貴重な機会となりました。
10月9日~10日の1泊2日で小学部5・6年生が東京・埼玉方面へ修学旅行にいってきました。
1日目は新幹線や山手線、地下鉄にも乗って、まずはキッザニア東京に行きました。それぞれが事前に選んでいた仕事の体験をしました。ベーカリーでパン作りをしたり、歯医者さんをしたり、免許を取得してレンタカーに乗ったりしました。お仕事によっては制服も着て、本格的な体験ができました。その後は東京駅一番街でお土産を買ったりレストランで食事をしたりして、ホテルに向かいました。ホテルではユニットバスでの入浴を体験し、ふかふかのベッドでゆっくり休みました。
2日目の朝はホテルのビュッフェ形式の朝食で始まりました。好きなものをおいしくいただき、元気に出発しました。大宮の鉄道博物館では学級ごとに見学をしました。引退した車両に実際に乗り込み、座席に座ったり、網棚やストーブを触察したり、ミニ列車を運転したり、蒸気機関車の汽笛を聞いたりしました。お昼は駅弁を食べ、大満足でした。
二日間、天気にも恵まれ、普段はできない体験を存分に楽しんできました。
10月1日(水)から3日(金)まで、高等部普通科2・3年生が、東北方面へ修学旅行に行きました。
1日目
宇都宮駅新幹線改札前に集合し、出発式の後、東北新幹線に乗って仙台に向かいました。仙台から在来線に乗り換え、松島へ向かいましたが、大雨のため仙台に引き返すことになりました。仙台駅到着後、グループごとに分かれ、それぞれ昼食を取ったり駅周辺を散策してお土産を購入したりするなど、有意義な時間を過ごしました。
2日目
この日は一日グループ別に行動しました。Aグループは、初日はキャンセルとなった松島へ行きました。遊覧船に乗って波の揺れや潮風を感じたり、波の音や海鳥の鳴き声を聞いたりしました。松島のシンボルである五大堂で、緊張しながら透かし橋を歩いたり写真を撮ったりした後、手焼き笹かまや手焼きせんべい、カステラ、焼き牡蠣、ずんだシェイクなどの松島グルメを堪能しました。午後は震災遺構仙台市立荒浜小学校を訪れました。校舎2階にまで来た波の高さ、押し流されてきた瓦礫による床の傷跡などに実際に触れ津波の威力を知るとともに、震災当時の学校や町の様子、地域の復興に尽力してきた人々の思いについて学び...
10月4日(土)宇都宮市のオリオンスクエアにて行われた令和7年度赤い羽根共同募金キックオフイベントおよび13日(月)にベルモールにて行われた街頭募金活動に、本校高等部普通科の生徒3名がボランティアとして参加しました。
キックオフイベントとは、10月1日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動が開始されたことを周知するために行われる、栃木県共同募金会主催のイベントです。生徒1名は昨年度に引き続きセレモニーの司会進行を担当させていただき、心地よい緊張感のもと大役を堂々と務めました。
街頭募金活動では、同年代の高校生や地域の方々と交流を深めながら募金への協力を呼び掛けました。同じ街で暮らす人と人とのつながりをあらためて感じられたのではないかと思います。
9月29日(月)、「寄宿舎うたの王様IN秋祭り」が行われました。午前中のあけぼの会奉仕作業の際に保護者の方々の御協力をいただき、会場をきれいに飾り付けました。寄宿舎生や寄宿舎関係職員に加えて、通学生やその保護者の皆様をお迎えし、熱気に包まれた会場は大盛況でした。今回、寄宿舎生・通学生合わせて総勢11組が、歌や演奏、応援コールなど個性的なパフォーマンスを披露してくれました。加えて、スペシャルゲストでの先生方の楽しい歌や手作りオルゴールを披露されて、最後の最後まで大盛り上がりでした。終了後に寄宿舎生に話を聞くと、「めちゃめちゃ楽しかった。」「まさか自分が王様になるなんて!」「来年は何を歌おうかな」など興奮冷めやらぬ様子でした。
飾りつけに御協力いただいた保護者の皆様、そして当日参加してくださった全ての方々、本当にありがとうございました。
9月21日(日)、2年ぶりに本校が主管校となり、栃木県障害者スポーツセンター(わかくさアリーナ)で第42回関東地区盲学校卓球大会を開催しました。関東地区の盲学校7校から24名、本校からは中学部1名、高等部普通科2名の生徒が出場し、学部と男女に分かれて熱いトーナメント戦が繰り広げられました。
本校の生徒たちは惜しくも1回戦で敗れてしまいました。追いつ追われつの接戦もあり、今後の成長につながるプレーをできたのではないかと思います。大会閉会式における講評では、1対1の緊迫した場面で時折顔を出して試合の流れを変えてしまう「悪魔」の存在、自分自身をコントロールするスキルとその難しさについてのお話があり、みな真剣に耳を傾けていました。STT(サウンドテーブルテニス)という競技を通じて、自分の癖や課題と向き合ったり友達と競い合ったりすることを経験しながら、一層成長していってほしいと思います。
試合の合間には、普段はなかなか会うことのできない他校の生徒たちとお喋りや交流試合を楽しむ姿も見られ、充実した一日になりました。
運営に携わってくださったボランティアの皆様、応援にいらっしゃった保護者の皆様、あ...
9月10日(水)2、3校時に、小学部の井上学級、北山学級、絵面学級の児童と城山西小学校3年生児童との遊び交流が行われました。全体で開会式を行った後、学級ごとに分かれて、自己紹介・ロンドン橋・ボウリング・STT(サウンドテーブルテニス)などを行いました。城山西小児童の中には、アイマスクやアイシェードを付けることにチャレンジして、音を手掛かりに活動を楽しむ児童もいました。本校児童にとっては、大勢の友達の声を聴いたり、触れ合えたりすることのできる貴重な体験になりました。本校児童の中には、「次は城山西小へ行きたい!」という積極的な感想をもつ児童もいるくらい、とても楽しい交流ができたようです。城山西小3年生の皆さん、本当にありがとうございました。
8月23日(土)、今年度も本校を会場にサタデースクールを開催しました。猛暑の中、3組の御家族が参加されました。3組とも地域の弱視特別支援学級に在籍されている小中学生です。 前半は、「触察」をテーマに魚(アジ、ウナギ)の観察を行いました。「たくさん“ひれ”があるんだ!」と発見したり、アジの口から入れた指がエラから出てきて水の流れを理解できたりと実物を触る体験をとおして気づきの機会となったようです。 また、後半は「スポーツ」をテーマに、視覚障害スポーツの一つである「SST(サウンドテーブルテニス)」を行いました。初めて体験した参加者もいましたが、楽しく活動できたようです。 保護者の方々も情報交換を行いました。
12月13日には第2回サタデースクールを予定しています。たくさんの御参加をお待ちしています!
8月21日(木)に第1回ぱんだサークルを実施しました。
当日は3組の親子が参加してくださいました。
子どもたちは担当教員と一緒に、ふれあい遊びをしたり、楽器や手作り教材などの音を聴いたり触れたり、ボールプールのボールで遊んだりして過ごしました。
保護者の皆様は本校理療科教員の体験談を聴いたあと、情報交換会を行いました。
育児が大変なときは各地域の支援センターを活用してリフレッシュしていること、現在困っていることなどなど、様々な情報や悩み、不安などを共有することができました。
第2回ぱんだサークルは12月26日(金)に実施予定です!
視覚に障害を有する乳幼児、そしてその保護者の方々がつながることができる機会ですので、参加を希望される方はお気軽にご連絡ください。
7月10日と14日の2日間にわたり、小学部から高等部普通科までの児童生徒がチェロ教室に参加しました。ボランティアの荒川育子先生によるチェロ演奏の鑑賞と先生との合奏、演奏体験の3部構成で行いました。
「いつか王子様が」や「トップ・オブ・ザ・ワールド」などの鑑賞では、本校職員もコントラバスで演奏に加わり、児童生徒たちは、様々な楽器の響きを楽しみました。合奏では、先生のチェロと一緒に「風になりたい」や「星に願いを」を歌ったり、様々な打楽器で演奏したりしました。ラテン系の軽快な曲や、ゆったりした優しい曲に、児童生徒の演奏する打楽器の音色が合わさってより華やかになり、皆とても喜んでいました。
チェロの演奏体験では、荒川先生が一人一人に合わせて丁寧にご指導くださいました。児童生徒からは、「去年よりも上手に弾くことができて良かった。」という感想があり、技術を積み重ねて成長している様子が見られました。
7月7日(月)の七夕当日、幼小部では七夕集会を行いました。この日までに、短冊に願い事を書いたり七夕飾りを作ったりして準備をしてきました。また、飾り付けする笹竹を組み立ててくれた学級もありました。
当日は、児童生徒会副会長が司会を務め、2年生が始めの言葉や終わりの言葉を担当し、役割分担をして会を進めました。学級ごとに自分の願い事を発表し、笹竹に飾り付けしました。自分の作った飾りについて詳しく説明をする児童もいました。後半は、全員で「たなばたさま」を歌い、「星に願いを」の合唱や合奏をしました。
みんなの素敵な演奏は、きっと天の川まで届いたことでしょう!
飾り付けした笹竹は、幼小玄関に飾りました。みんなの願い事が叶うよう、お地蔵さまが見守っています。
7月3日(水)に外国語指導助手(ALT)のザック先生が来校しました。
<小学部>
〇グループA
「箱の中身は何でしょう?」というゲームを通して、様々な果物の英語の言い方についてザック先生と学習しました。中の果物が何か分かると積極的に英語を使って答えていました。また、ザック先生に「何の果物が好き?」と聞かれたとき、英語での言い方を教えてもらい、好きな果物を伝えることができました。
〇グループB
一日に何をどれくらいするのか、どんな物を食べているかなど、互いの生活について聞いたりたずねたりしました。ザック先生に質問されて自分で答えた後は、「How about Zac?」と英語で聞くことができました。また、好きなスポーツの話題では、盲学校のサウンドテーブルテニスについて説明しました。
<高等部>
〇普通科1年1組 自己紹介と学級のオリジナルゲームを行いました。自己紹介は、予め伝えたいことを考え、自分たちで翻訳サイトを使って英語にしました。当日は、内容についてALTに聞かれて答えることで、より詳しく自分のことを知ってもらうことができました。また、二つのゲームを合わせた学級のオリジナルゲ...
6月27日に、武子希望の家の見学と、鹿沼市文化活動交流館と周辺の散策に行きました。 武子希望の家は広大な敷地に作業棟、園芸施設、入所施設などがあり、敷地内を1時間ほどかけて歩いて見学をしました。
浴槽の発泡材の部品取り付けとビデオテープの解体の見学では、部品を手で触って確認しました。その素材の軽さや大きさに驚きました。また、工場内の接着剤の臭いに驚く生徒もいました。
しいたけの栽培、花卉栽培の見学では、しいたけの原木を持ち上げたり、運搬用の一輪車を動かしたりしました。体力が必要な作業であることを実感しました。
入所施設は、外側から見学しました。カメラを使って建物の外側の様子を見たり、玄関口の外から中の様子を確認したりしました。
これらの様々な作業の見学を通して、自分にできそうな作業かどうか、また、それらの作業をするために身に付けるべき力は何かを考えることができました。
昼食は、鹿沼市文化活動交流館の敷地内にあるベーカリーでパンを食べました。事前にハンバーガーセットを注文した生徒、トレイとトングを持ちその場でパンを選んだ生徒など、それぞれの方法で選び、...
盲学校及び視覚障害教育の理解・啓発を図ることなどを目的として、6月30日(月)に学校公開を実施しました。
本校の教育活動に関心のある外部の方が67名、本校児童生徒の保護者の皆様20名に御参加いただきました。
全体会で学校概要やセンター的役割の説明を行い、2時間目と3時間目の授業を公開しました。
参加された方からは「保育園でも活用できそうな玩具や施設の工夫があり、とても参考になりました。」、「一人一人に応じた支援をされていてとても参考になりました。」、「他の学部も見学して、これからの成長が楽しみになった。」等の感想をいただきました。
アンケートでいただいた御意見も参考にしながら、県内唯一の視覚に障害を有する幼児児童生徒のための拠点を担う学校として、今後も努力して参りたいと考えています。
6月27日(金)、高等部普通科の職場見学が行われました。
2ー1は、宇都宮市にあるとちぎ視聴覚障害者情報センターを見学させていただきました。当施設は、栃木県の点字図書館でもあり、点字図書の製作や貸出、デイジー図書の録音等を行っています。点字プリンターや亜鉛版プレス印刷を用いた点字印刷やページの裁断などの作業の様子を実際に見せていただいたり、視覚障害当事者として勤務されている職員の方のお話を伺ったりしました。工夫をしながら様々な機器を使いこなして働いていることを教えていただきました。
午後は路線バスでJR宇都宮駅へ移動し、自分たちで立てたプランに基づいて活動しました。昼食にラーメンを食べ、近隣の店で買い物をしたり散策したりしました。よくできたこと、達成できたことがあった一方で、今後の成長につながる課題も見つかったようです。今回の職場見学で学んだこと、感じたことを、これからの生活や進路学習等の中で生かしていってほしいと思います。
6月24日(火)、社会福祉法人藹藹会の利用者の皆様と、本校中学部3名、高等部普通科7名の生徒による七夕交流会を開催しました。
はじめに、高等部の作業学習班より藹藹会の皆様へ、回収したプルタブと心を込めて作った作業製品のコースターを贈呈しました。
続いての発表コーナーでは、本校生徒が歌と楽器演奏で「虹」を発表しました。一方、藹藹会の皆様から「365日の紙飛行機」が披露されました。心のこもった歌声と生演奏が響き合い、会場は温かい雰囲気に包まれました。
その後は3つのグループに分かれ、大きな笹に七夕飾りや願い事を書いた短冊を協力して結び付けました。笑顔と会話があふれる、楽しいひとときとなりました。なお、藹藹会の方が本校に運んでくださった笹1本が、中高棟階段を上がった左手のスペースに展示されています。
生徒たちは、年に一度の貴重な交流を心から楽しみ、充実した時間を過ごすことができました。また来年も、皆様とお会いできることを楽しみにしています。
6月2日(月)から6月13日(金)まで実施した第Ⅰ期産業現場等における実習、及び校内実習の実習報告会が6月20日(金)6校時に作業棟で行われました。保護者の方々、校長、進路指導部長はじめ教員が見守る中、5名の生徒が一人ずつ前に出て、実習の成果を発表しました。
1年生は、点字用紙を利用したコースター作りと点字本の解体作業を行いました。各自の目標や今後の課題について写真や動画を提示しながら、初めてとは思えない堂々とした態度で発表することができました。
2・3年生は、それぞれ3か所ずつ事業所で実習を行い、制作したさをり織りの作品や、気に入った教材などを紹介しました。学校で製作した缶つぶしの道具や、事業所で姿勢保持のために使用したクッションを参考に保護者がつくったものも披露されました。高等部2・3年生にとって、卒業後を見据えた事業所との連携がより重要になってくることを感じさせられました。
6月19日(木)、関東地区盲学校生徒会連合(関盲連)代議員会がオンラインにて行われました。この会は、関東地区の盲学校の高等部生徒会の代表生徒(代議員)が本連合の運営について議論したり、情報交換を行ったりするものです。今年度は本校が総務担当の順番となり、普通科2年生の生徒が司会進行を務めました。
午前中の議事は滞りなく進み、その後は参加生徒による自己紹介、学校紹介を順番に行いました。和やかな雰囲気で、個性豊かな発表を聴きました。本校生徒は、本校校庭に生息している「古賀志虫(ブユ)」の恐ろしさや「プールの水に地下水を使っていること」について、漫才のようにボケとツッコミを交えながら楽しく発表しました。
午後の情報交換会では「遊びに行くならどんな場所に行くか」「盲学校あるある」の2つのテーマで自由なディスカッションを行いました。画面越しではありましたが生徒間のやりとりも活発に行われ、にぎやかで充実した会になったことと思います。
6月13日(金)、茨城県水戸市にある「リリーアリーナMITO」で第56回関東地区盲学校フロアバレーボール大会が行われ、本校はオープンリーグに参加しました。オープンリーグは生徒と教職員の混成チームで出場でき、昨年度大会より設けられたものです。本校は実に15、6年もの間 大会出場から遠ざかっていましたが、昨年度より少しずつ練習に取り組んできました。今回は高等部普通科生徒4名、専攻科生徒2名、引率職員7名の計13名で参加しました。
対戦相手である千葉県立盲学校の鋭いスパイクや安定感のあるレシーブ・トスに圧倒されながらも、本校前衛、後衛ともに精一杯声を出し合い、全力でブロックし、できるかぎりの力でスパイクを打って応戦しました。第1セットは千葉盲に取られてしまいましたが、第2セットは本校1点リードのまま、全50分間に渡る試合が終了しました。
総得点による勝敗判定の結果、勝つことはできませんでしたが、チームスポーツの面白さ、試合の緊張感、その中で満足のいくプレーを行う難しさなどなど、生徒たちはたくさんの経験を得ることができたと思います。試合後に観た決勝戦も迫力あるプレイばかりで、生徒たちにとって良い刺激...
5月22日(木)~23日(金)校外宿泊学習に行ってきました。1日目午前中に、那須ロープウェイに乗り那須山頂駅へ向かいました。ロープウェイが揺れるのと窓からの景色に少しどきどきしましたが、山頂駅に着くと壮大な景色を見たり、冷たい山の空気を感じたりすることができました。昼食後、殺生石とつつじ吊り橋を見学しました。殺生石で硫黄の匂いに辟易としたり、つつじ吊り橋で橋の高さや揺れに驚いたりしました。なす高原自然の家に着いてからは、指導員さんに教えてもらいながら木の実クラフト作りをしました。自然の家周辺に落ちていた木の枝に接着剤で木の実をつけて、素敵な作品ができました。夜はベッドメイキングをしたり、談話室に集まってカードゲームなどをしたりして楽しみました。
2日目は、千本松牧場に行き、たくさんの動物と触れ合ったり、広い牧場内を散策したりしました。
2日間、天気にも恵まれ、普段なかなか経験できないことにチャレンジすることができました。今回の校外宿泊学習は、友達同士の関わりの心地よさを知る素敵な経験になったことでしょう。
5月25日(日)、栃木県総合運動公園にて第20回栃木県障害者スポーツ大会が開催されました。高等部2名の生徒が陸上競技に、また中学部1名、高等部1名の生徒がサウンドテーブルテニスに出場しました。
心配していた雨は朝のうちに上がり、時折晴れ間も見え、まずまずのコンディションでの実施となりました。自己記録や入賞などの成績を収めることができた生徒も、悔しい結果に終わってしまった生徒も、持てる力を頑張って出し切る姿が素晴らしかったです。もんな今後につながる良い経験を得られたことと思います。
高1男子 50m【視覚・男子】 第1位 9秒77
高1男子 800m【視覚・男子】 第1位 3分24秒63
中1男子 サウンドテーブルテニス 第2位
高1男子 サウンドテーブルテニス 第3位
保護者様へ
下校対応訓練は無事終了しました。御協力ありがとうございました。
学校では、本日の訓練の反省点を生かし、今後の安全対策を講じていきます。お気づきの点がございましたら、学級担任を通してお知らせください。
6月5日(木)に、宇都宮市立城山西小学校2年生と本校児童による「遊び交流」を実施しました。互いに自己紹介を行った後、全員で大きな輪になってロンドン橋遊びを行いました。ゲームの中で、好きな食べ物や遊び、得意なことについて、全員が発表できました。本校児童にとって、大勢の友達と同じ活動で遊ぶことができる貴重な機会となりました。
その後、城山西小の皆さんは、「盲学校探検」を行いました。校内を見学しながら小学校と盲学校との違いを探したり、本校児童が生活科や算数などの授業で使用している触察教材を触ったり、触る絵本を楽しんだり、拡大読書器を操作したりしました。
また城山西小の皆さんとお会いできることを楽しみにしています。
小・中・高等学校及び特別支援学校において使用している教科書を、下記の期間展示しています。保護者の皆様も自由に見学することができます。
事前展示会:
令和7年6月16日(月)~6月19日(金)
午前9時~午後5時
教科書展示会:
令和7年6月20日(月)~7月11日(金)
午前9時~午後5時 ※土日は除く
会場:栃木県庁河内庁舎本館5階図書展示室
R7 04教科書展示会会場案内図.pdf
4月30日(水)、多くの保護者の御参加をいただき、第1回保護者会が行われました。
全体会では、校長から「目指す学校像」「学校経営方針」やと特別支援教育課より出された「特別支援教育の充実に向けた方針」についての説明がありました。また、担当係より、令和6年度の卒業生の進路等、主体的活動を促す支援、フロアバレーボール、児童生徒会について、それぞれ説明等がありました。保護者の皆様からのアンケートでは、「進路や学校の取組について、実例を挙げて具体的に分かりやすく説明されていてよかったです」「フロアバレーボールという新しいスポーツを知る機会になりました」等の感想をいただきました。
その後学部懇談と授業参観が行われました。授業参観については、「一年の成長がすごく感じられました」「クラスの雰囲気がとてもよかったです」等の感想をいただきました。
今後も保護者の皆様と共通理解を図りながら学校運営を進めてまいりたいと考えておりますので、御協力をお願いいたします。
4月24日(木)、弱視児童生徒を担当されている県内の先生方を対象に『弱視特別支援学級等担当者研修会』を実施いたしました。今回は10校11名の先生方の参加がありました。
まずは、自己紹介を兼ねた情報交換会を行いました。参加された多くの先生が、今年度はじめて弱視の児童生徒を御担当されることとなったとのことでした。午前中は、『教育的視機能評価について』、『ロービジョン疑似体験』、午後は、本校職員による『視覚に障害を有する児童生徒への支援について』、『自立活動について』の講話と、校内の見学をしていただきました。
参加された先生方からは、「弱視と一言で言っても様々な児童・生徒さんがいるのだと知って参考になった」「情報保障の必要性について参考になった。見えていると思ってしまいがちだが、声かけをしていこうと思った」「教材の見やすさや触れて確かめることの重要性、必要性を感じることができた」等の感想をいただきました。
令和7(2025)年度 学校公開のご案内
見えにくさのあるご本人や保護者の方などに、盲学校の施設や盲学校で行われている授業、視覚障害教育のセンターとして盲学校が取り組んでいること等を知っていただくことを目的として、6月30日(月)に学校公開を実施いたします。ぜひお気軽にご参加ください。
R7学校公開案内
4月24日、株式会社キザキ様より白杖が寄贈され、小学部、中学部、高等部の代表が出席し、校長室で贈呈式が行われました。
株式会社キザキ様は長野県でスキーポールなども作っている会社です。金沢大学と使いやすい白杖を開発し、全国の盲学校に直接プレゼントに回る「白杖リレーマラソン」を行っています。
代表の児童生徒は、贈呈された白杖ができた経緯をよく聞き、また、グリップや長さの調節などの改良された特長をよく触って確かめていました。
他県の盲学校の生徒も記入しているメッセージボードには、代表の生徒が「ありがとうございます。自主通学にむけてがんばります。」と書きました。
本校ではいただいた白杖を活用し、多くの幼児児童生徒や相談に来られた方の歩行学習に役立てていきたいと考えています。ありがとうございました。
今年度着任しました校長の平井謙司と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
令和7年度は、中学部に1名、高等部に7名(普通科3名、専攻科保健理療科1名、専攻科理療科3名)の新入生を迎え、幼児児童生徒数25名でのスタートとなりました。
本校の教育目標は、1 明るく健康でたくましい幼児児童生徒の育成2 個性を生かし自らすすんで学べる幼児児童生徒の育成3 社会の一員として活躍できる心豊かな幼児児童生徒の育成です。一人一人の個性や得意なことを更に伸ばし、幼児児童生徒が自立し社会参加していけるよう、教職員全員で取り組んでまいります。併せて、本県唯一の視覚障害特別支援学校として特別支援教育のセンター的機能を発揮し、県内の視覚障害のある幼児児童生徒等への支援の充実にも努めてまいります。
保護者の皆様、地域の皆様、関係機関の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
とちもうeyeサポートセンター
Instagramはじめました
栃木県立盲学校公式Instagramを開設しました
ぜひ、フォローをよろしくお願いいたします
フォト
動画
お知らせ
お知らせ
R4放課後デイ申請書.pdf
お知らせ
「学校施設の使用許可申請書」をダウンロードできるようにしました。
・学校施設の使用は原則として障害者関係団体が対象となります。
・対象外の団体等の使用については、別途御相談ください。
・学校施設の使用を希望される場合は、学校窓口(教頭)に御連絡ください。
学校施設の使用許可申請書(学校長あて).pdf
校歌
相談支援
詳しくは★相談支援★のページをご覧ください。
進路指導部の取り組み
★進路指導部★
(令和元年版に更新されました)
高等部保健理療科・専攻科パンフ
是非、下のリンクをご覧ください。
★保健理療科・専攻科案内.pdf★
お知らせ
お知らせ
※現在は感染症対策のため開催を見合わせております。
進路情報
栃木県立盲学校いじめ防止基本方針
本校では、全ての教職員が「いじめはどの子どもにも、どの学校においても起こり得る」という事実を踏まえ、幼児児童生徒の尊厳を守りながら、いじめのない学校づくりに向けて学校組織をあげて取り組みます。
R6栃木県立盲学校いじめ防止基本方針
R6栃木県立盲学校いじめ防止基本方針実践のための行動計画
図書館
リンク