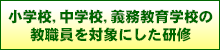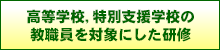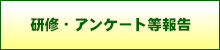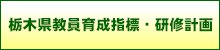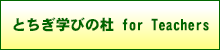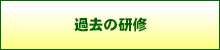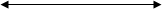研修報告
令和6(2024)年度 数学専門研修(高)
| 目 的 | 数学的活動の理解を深めるとともに、指導力の向上と授業の工夫を図り、魅力ある数学科授業を創造する。 | ||||||||
| 日 時 | 令和 6(2024)年 7月23日(火) 9:30~16:00 | ||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校(高等部)の数学科を担当している教員 | ||||||||
| 研修内容 | 講話「『統計的な推測』をどう教えるのか?~大学入学共通テスト、科学的探究、AI社会の意思決定の観点から~」 研究協議「魅力的な授業の創造」 |
||||||||
| 講 師 | 立正大学データサイエンス学部教授 渡辺美智子 氏 総合教育センター職員 |
||||||||
| 研修の様子 |
|
||||||||
| 受講者の声 |
|
||||||||
| 研修担当者からの メッセージ |
午前の講話では、日本が置かれた状況や産業界の要望などの説明があり、受講者は統計学が求められている経緯や背景を理解することができ、統計教育の重要性を実感できたようです。午後の研究協議では、グループで統計的推測について授業づくりを行いました。受講者のみなさんは、教科書通りの授業展開ではなくデータを活用しながらシミュレーションや確率を根拠として授業を展開するイメージをもつことができたようです。
|
||||||||
令和6(2024)年度 新任校長研修(高等学校、特別支援学校)第2日
| 目 的 | 校長としての職務、今日的な教育課題、学校経営の在り方等について総合的に理解を深め、校長としての資質の向上を図る。 | ||||||||||||||||||
| 日 時 | 令和6(2024)年 7月 9日(火) 9:30~16:00 | ||||||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の新任校長 | ||||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「学校における特別支援教育」 2 講話「学校の財務と事務室との連携」 3 講話・演習「学校におけるICT活用」 4 研究協議「学校経営上の課題とその解決に向けて」 |
||||||||||||||||||
| 講 師 | 県立学校職員 県教委事務局特別支援教育課職員 総合教育センター職員 |
||||||||||||||||||
| 研修の様子 |
|
||||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから |
研修の満足度・活用度
① 本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。
【目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
2 講話「学校の財務と事務室との連携」
【目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
3 講話・演習「学校におけるICT活用」
【目標】
【講話・演習を通しての主な意見・感想】
4 研究協議「学校経営上の課題とその解決に向けて」
【目標】
【研究協議を通しての主な意見・感想】
|
令和6(2024)年度 新任学習指導主任研修(小・中)
| 目 的 | 学習指導主任の職務・役割や学習指導の今日的課題について理解し、校内における実践を通して、学習指導主任としての資質の向上を図る。 | |||||||||||||||||
| 日 時 | 令和 6(2024)年 6月24日(月) 9:30~16:00 | |||||||||||||||||
| 対 象 | 小学校・中学校・義務教育学校の新任学習指導主任 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「新任学習指導主任に期待すること」 2 講話・演習「本県の学習指導の現状と課題」 3 研究協議「学習指導主任の職務と役割」 |
|||||||||||||||||
| 講 師 | 県教委事務局義務教育課学力向上推進担当指導主事 総合教育センター職員 |
|||||||||||||||||
| 研修の様子 |
|
|||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから |
研修の満足度、活用度
① 本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか
【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
2 講話・演習「本県の学習指導の現状と課題」
【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
3 研究協議「学習指導主任の職務と役割
【研修の目標】
【研究協議の主な意見・感想】
|
令和6(2024)年度 教頭2年目研修(小・中学校)第1日
| 目 的 | 管理職としての深い見識と優れたリーダーシップを高めるとともに、学校経営、学校教育管理、人事管理等に関する管理職としての実践的な資質・能力の向上を図る。 | |||||||||||||||||
| 日 時 | 令和6(2024)年 6月 3日(月) 9:30~16:00 | |||||||||||||||||
| 対 象 | 小学校、中学校、義務教育学校の教頭経験2年目に該当する者 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「コーチングを活用した人材育成」 2 講話「学校経営と学校事務」 4 発表・研究協議「学校組織マネジメント校内実践計画」 |
|||||||||||||||||
| 講 師 | 大学等職員 公立小学校事務長 総合教育センター職員 |
|||||||||||||||||
| 研修の様子 |
|
|||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから |
0 研修の満足度、活用度
本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。
【目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
2 講話「学校経営と学校事務」
【目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
3 発表・研究協議「学校組織マネジメント校内実践計画」
【目標】
【発表・研究協議後の主な意見・感想】
|
|||||||||||||||||
令和6(2024)年度 教頭2年目研修(高等学校、特別支援学校)第1日
| 目 的 | 管理職としての深い見識と優れたリーダーシップを高めるとともに、学校経営、学校教育管理、人事管理等に関する管理職としての実践的な資質・能力の向上を図る。 | ||||||||||||||||||
| 日 時 | 令和6(2024)年 6月 3日(月) 9:30~16:00 | ||||||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の教頭経験2年目に該当する者 | ||||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「コーチングを活用した人材育成」 2 講話「特別支援教育の充実に向けて」 3 講話「学校の財務」 4 講話・研究協議「学校運営における危機管理推進のポイント~危機管理体制の確立のために~」 |
||||||||||||||||||
| 講 師 | 大学等職員 総合教育センター職員 |
||||||||||||||||||
| 研修の様子 |
|
||||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから |
0 研修の満足度、活用度
本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。
【目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
2 講話「特別支援教育の充実に向けて」
【目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
3 講話「学校の財務」
【目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
4 講話・研究協議「学校運営における危機管理推進のポイント~危機管理体制の確立のために~」
【目標】
【講話・研究協議を通しての主な意見・感想】
|