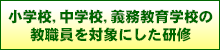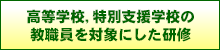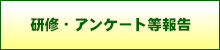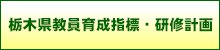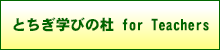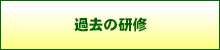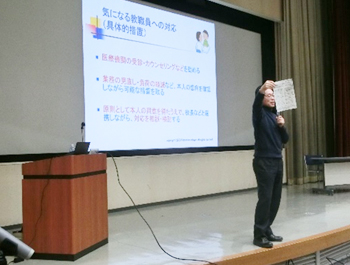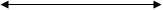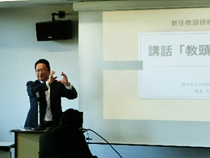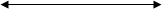研修報告
令和6(2024)年度 教頭2年目研修(高等学校、特別支援学校)第2日
| 目 的 | 管理職としての深い見識と優れたリーダーシップを高めるとともに、学校経営、学校教育管理、人事管理等に関する管理職としての実践的な資質・能力の向上を図る。 | |||||||||||||||||
| 日 時 | 令和 6(2024)年12月 2日(月) 9:30~16:00 | |||||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の教頭経験2年目に該当する者 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 発表・研究協議「学校組織マネジメント校内実践報告」 2 講話「教職員のメンタルヘルス」 3 講話「リーダーシップを生かした組織マネジメント」 |
|||||||||||||||||
| 講 師 | 医療機関等職員 大学等職員 総合教育センター職員 |
|||||||||||||||||
| 研修の様子 |
|
|||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから |
0 研修の満足度、活用度
本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。
【目標】
【発表・研究協議を通しての主な意見・感想】
2 講話「教職員のメンタルヘルス」
【目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
3 講話「リーダーシップを生かした組織マネジメント」
【目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
|
|||||||||||||||||
令和 6(2024)年度 ICT活用研修〔タブレット端末を用いたプログラミング教育〕
| 目 的 | タブレット端末を用いたプログラミング教育を行う方法を学び、指導力の向上を図る。 | ||||||
| 日 時 | 【A組】令和 6(2024)年 8月21日(水) 9:30~16:00 【B組】令和 6(2024)年 9月30日(月) 9:30~16:00 【C組】令和 6(2024)年12月 2日(月) 9:30~16:00 |
||||||
| 対 象 | 授業でのタブレット端末の活用方法を学びたい教職員 | ||||||
| 研修内容 | 講話・演習「タブレット端末を用いたプログラミング教育」 | ||||||
| 講 師 | 総合教育センター職員 | ||||||
| 研修の様子 |
|
||||||
| 受講者の声 |
|
||||||
| 研修担当者からの メッセージ |
タブレット端末を活用したプログラミング教育の研修を実施しました。この研修では、まずプログラミング教育の導入背景や目指すべき学びの姿、育むべき資質・能力について確認しました。その後、クロームミュージックラボやスクラッチ、マイクロビットなどを実際に使いながら、プログラミング演習を行いました。参加者はアプリを体験することで、具体的な指導のイメージを持つことができたようで、「これなら授業で使えそう!」との声が多く聞かれました。さらに、校種ごとに分かれて授業づくりを行い、最後に発表と協議を行うことで、よりよい授業案に仕上げました。
研修を通じて得られるのは、単なる知識ではなく、実際の授業で役立つ具体的なアイデアです。次回の開催でも、多くの先生方にこの研修を体験していただき、生徒の思考力や創造力を育むプログラミング教育を一緒に考えていきたいと思っています。 |
||||||
令和6(2024)年度 教頭2年目研修(小・中学校)第2日
| 目 的 | 管理職としての深い見識と優れたリーダーシップを高めるとともに、学校経営、学校教育管理、人事管理等に関する管理職としての実践的な資質・能力の向上を図る。 | |||||||||||||||||
| 日 時 | 令和 6(2024)年12月 2日(月) 9:30~16:00 | |||||||||||||||||
| 対 象 | 小学校、中学校、義務教育学校の教頭経験2年目に該当する者 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 発表・研究協議「学校組織マネジメント校内実践報告」 2 講話「教職員のメンタルヘルス」 3 講話「リーダーシップを生かした組織マネジメント」 |
|||||||||||||||||
| 講 師 | 医療関係者 大学等職員 総合教育センター職員 |
|||||||||||||||||
| 研修の様子 |
|
|||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから |
0 研修の満足度、活用度
本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。
【目標】
【発表・研究協議を通しての主な意見・感想】
2 講話「教職員のメンタルヘルス」
【目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
3 講話「リーダーシップを生かした組織マネジメント」
【目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
|
|||||||||||||||||
令和6(2024)年度 新任教頭研修(小・中学校)第3日
| 目 的 | 管理職としての見識を深め教育理念を構築するとともに、教頭の職務を理解し、学校経営、学校教育管理、人事管理等に関する管理職としての基本的な資質・能力の向上を図る。 | |||||||||||||||||
| 日 時 | 令和 6(2024)年11月 8日(金) 9:30~16:00 | |||||||||||||||||
| 対 象 | 小・中・義務教育学校の新任教頭 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「教頭に求められる資質・能力」 2 講話・演習「学校組織マネジメント校内実践計画作成に向けて」 3 講話「学校現場とリーガルマインド-2024-スクール・コンプライアンスの視点から-」 |
|||||||||||||||||
| 講 師 | 日本女子大学教職教育開発センター教授 坂田 仰 氏 総合教育センター職員 |
|||||||||||||||||
| 研修の様子 |
|
|||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから |
0 研修の満足度・活用度
本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。
【目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
【目標】
【講話・演習を通しての主な意見・感想】
【目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
|
|||||||||||||||||
令和6(2024)年度 新任教頭研修(高等学校、特別支援学校)第3日
| 目 的 | 管理職としての見識を深め教育理念を構築するとともに、教頭の職務を理解し、学校経営、学校教育管理、人事管理等に関する管理職としての基本的な資質・能力の向上を図る。 | |||||||||||||||||
| 日 時 | 令和 6(2024)年11月 8日(金) 9:30~16:00 | |||||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の新任教頭 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「教頭の役割」 2 研究協議「学校組織マネジメント校内実践計画」 3 講話「学校現場とリーガルマインド-2024-スクール・コンプライアンスの視点から-」 |
|||||||||||||||||
| 講 師 | 日本女子大学教職教育開発センター教授 坂田 仰 氏 県立学校長 総合教育センター職員 |
|||||||||||||||||
| 研修の様子 |
|
|||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから |
0 研修の満足度・活用度
本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。
【目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
【目標】
【研究協議を通しての主な意見・感想】
【目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
|
|||||||||||||||||