文字
背景
行間
進路指導部のページ
中学部A組2・3年生 職業体験
今年度は、9月16日(火)~18日(木)の期間中にそれぞれ3日間、ファッションセンターしまむら 若草店と珈琲館 宇都宮店で職場体験を実施しました。
しまむらでは、店内清掃や検収補助(商品が届いてから店内に陳列するまでの作業補助)を行いました。
困った時には早めに報告すること、仕事をする上で“報告・連絡・相談”のコミュニケーションが大切だということを実感したようです。商品の入っていた段ボールを100個以上潰すことができ、早く潰すコツも身に付けることができました。
珈琲館では、ホールとキッチンの2か所の仕事でした。
ホールは、片付け、注文を受けて品物を運ぶ等の接客業を行いました。キッチンでは、食器の洗い物、飲み物やフード作りをしました。
お客様にくつろいで頂くために、笑顔で挨拶することの大切さを感じることができました。

3日間を通し、今まで経験したことのない貴重な体験をすることができました。“社会”の中で働くということの大変さを直に肌で感じることができたのではないかと思います。この体験を通し、今の自分に必要なこと・身に付けなければならないことに十分に向き合って今後過ごしていってもらいたいと考えます。
【進路】1学期の進路行事を振り返って~中高進路講話~
6月25日(水)5時間目は小学部高学年対象に、6時間目は中高等部及び保護者対象に、『私のキャリア~メーカーで働く研究員として~』という演題で、進路講話を実施しました。
本県出身で聴覚障害があり、花王株式会社 解析科学研究所で従事されている方を講師として、これまでの経歴や現在の仕事内容、今の仕事・会社を選んだ理由などについて、ご講話いただきました。
仕事を選んだ理由として、大学時代の実習を通して、自分の好きなこと・得意なことを生かした仕事を選んだこと、また会社を選んだ理由としては、聴覚障害に理解のある会社という点を重要視したことを知ることができました。
聴覚障害をもつ社会人として伝 えたいこととして、『①聴覚障害だから「できる」こと・「得意」なことを見つけることも大事なこと、②積極的に人とかかわること、③ポジティブな気持ちを大切にすること』の3点をお話くださいました。また、社会人になるまでに身に付けたいこととして、自分が過ごしやすい環境を作るために、『自分の聞こえを理解し正しく伝える力』が大切であることをお話くださいました。
事後学習の生徒の感想の中で、『自分の聞こえについて会社にきちんと伝えられるか心配なので、これから聞こえについて正しく理解しまとめていきたい』や、『自分が理解しやくするための工夫を考えていきたい』などの感想が出ていました。
分かりやすい具体的な話が多く、生徒達の職業観・勤労観及び自分の障害・合理的配慮についての理解がより深められた講話でした。
【進路指導部】1学期の進路行事を振り返って~高等部AB組職場見学~
6月18日(水)全国農業協同組合連合会 栃木県本部(JA全農とちぎ)へ職場見学に行って来ました。自分の将来の仕事や進路についての意識を高めることを目的に、今年度は事務職の仕事の様子を見学しました。貴会の業務概要や生徒からの質問に対するご回答により、給食で扱っている本県の農産物としてお米が一番で、それ以外に主要な品目としてトマト・にら・なす・アスパラガス・ねぎ・きゅうりを扱っていることなど、本県の農業についての理解を深めることができました。また、仕事をするときに心掛けていることとして、「公平性」「客観性」「平等性」「バランス」であることや、目標に対してやっていることがふさわしいのか、無駄はないのかという意識をもつこと、などをお話いただきました。
見学後の生徒から、「自分が立って行う仕事が合っているか、座って行う仕事が合っているのか、どちらが自分に合っているのかを考えたいと思いました。」という感想を聞くことができました。生徒一人一人が自分の進路について真剣に考える、一つの契機となったことと思います。

【進路指導部】1学期進路だより
1学期の進路だよりが完成いたしました。ご覧ください。
【進路指導部】保護者対象進路講話
7月14日(月)中学部保護者会及び高等部授業参観に併せて、保護者対象の進路講話を実施いしました。
宇都宮公共職業安定所の職員の方2名より、『適性に応じた主体的な進路実現のために』というテーマでご講話をいただきました。ご参加いただいた保護者の方からは積極的なご質問もいただき、お子様の進路を考える上で有益な機会となったことと思います。
講話内容を下記の掲載いたしますので、ご一読いただけますようお願いいたします。
中学部A組 校内職業体験
7月8日~9日の2日間、中学部A組で校内職業体験を行いました。
今回も委託業務を受けて製品の袋詰めです。
スポンジと紐を合わせてビニール袋に詰め、テープで留めるという一連の工程を各自で行いました。
自分たちの関わった製品が店頭に並び、お客様の手元に届くのだという実感があり、どの生徒も真剣そのものでした。
出来高にこだわらず、指示通り正確に作業に取り組むということを目標にしてきました。集中し過ぎて目が痛くなったり、今まで感じたことのない疲労を感じたりすることで働くということ・仕事について身近に感じることができました。
中学部 進路の時間Ⅰ
6月17日(火)中学部の進路の時間Ⅰでは、高等部の先生方から各学科について説明をしていただいた後、授業見学を行いました。
〇高等部のA組では、数学の授業や英語の授業の様子を見ました。先輩たちが難しい学習に真剣に取り組む様子にジッと見入っていました。

〇高等部のB組の授業では、生活技術科ではファッション造形基礎の学習・情報機械科で文鎮の制作をしている学習を見学しました。また、機械科実習室では鉄を削る旋盤や着ける溶接の機械についての説明も受けることができました。始めて目にする機械類に興味津々でした。
〇B組は、高等部C 組の先生からパワーポイントで学科の説明をしていただいた後、ワークシートの記入に取り組みました。手帳の種類や卒業後の就労先についての説明、これまでの自分を振り返ってできていること、これから努力が必要なことなどをチェックリストで確認しました。自分の将来について真剣に考える様子が見られました。

中学部A組 職場見学
6月19日(木)にマルハニチロ株式会社宇都宮工場へ職場見学に伺いました。
始めに宇都宮工場の概要について説明を受けました。説明してくださったのは、本校卒業生で就職して3年目の先輩でした。先輩が入室すると生徒たちから「わぁ~」と歓声が上がりました。ハム・ソーセージと鮪のたたきの製造の工程を見学しました。それぞれの担当者の方から説明を受けながら、生徒たちは大きくうなずいたり、メモを取ったり、質問をしたりしていました。


〇鮪のたたきの製造では、特別な包丁と手袋を使用し作業をしていました。魚の皮を剥いだり、内臓や骨を取ったり、決められた大きさに切ったりする工程を見て、生徒は体力や集中力を伴う大変な作業であると感じていたようです。
〇ハム・ソーセージの製造では、使用される魚の種類ごとに袋の色が違うこと、調味料と混ぜて練っていくこと、そしてボールカッターが世界一であることなどなど。初めて聞く言葉や分かったことがたくさんありました。また、『すり身』という言葉が日本独自の言葉であること、すり身があっという間にソーセージになっていく様子など驚くこともたくさんありました。
製造工程を見て、生徒たちは、食品を扱う際の衛生管理や、一つの作業をやり続ける忍耐力の大切さに気付くことができました。
★マルハニチロ宇都宮工場の馬場さんから“コミュニケーションが大切”とのお話がありました。分からないことをそのままにせず、質問すること。体調が悪い、辛い時には訴えること。仕事を進めるうえで大切なことです。今できることを毎日積み重ね、将来の自分につなげて欲しいと思います。

【進】進路だより3学期
3学期進路だよりが完成しました。ご覧ください。
中学部 進路の時間Ⅲ
12月17日(火)の中学部「進路の時間Ⅲ」では、これまでの学習を振り返りつつ、身近な例をもとに「マナー」の大切さや必要性を再確認しました。
★このマナー、○かな?×かな?
実際の友達の態度や行動を写真で見ながら、日常生活におけるマナーをクイズ形式で確認しました。授業中や休み時間、食事中など、いろいろな場面のマナーについて、「どこが、どんなふうに良いのか(悪いのか)」を具体的にチェックし、友達の姿と普段の自分自身の態度や行動とを重ね合わせながら学ぶことで、生徒たちはマナーの大切さや必要性を痛感したようでした。
★こんな時、どうする?
教室・職員室等の入退室時、報告をする時や物を置く時など、いろいろな場面の動画を見て、適切なマナーを確認しました。挨拶やお辞儀の仕方、目上の人への伝え方などのポイントを改めて具体的に学ぶことができ、生徒たちは普段から気を付けて実践しようという思いを強くしたようでした。また、「物を置く時」の動画では、自分たちが給食の食器を片付ける音の大きさに驚き、静かにそっと重ねる必要があることを身に染みて感じたようでした。
今年度の「進路の時間」はこれで最後になりますが、今後の学校生活や進路選択に生かせるよう、正しいマナーの習得に向け、これまで学んだことをもとに積極的に実践を積み重ねていってほしいと思います。



















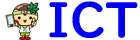
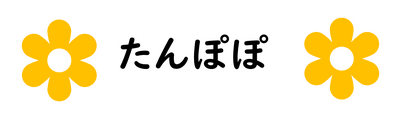

 tochigi-edu.ed.jp
tochigi-edu.ed.jp