文字
背景
行間
進路指導部のページ
中学部A組2・3年生 職業体験
今年度は、9月16日(火)~18日(木)の期間中にそれぞれ3日間、ファッションセンターしまむら 若草店と珈琲館 宇都宮店で職場体験を実施しました。
しまむらでは、店内清掃や検収補助(商品が届いてから店内に陳列するまでの作業補助)を行いました。
困った時には早めに報告すること、仕事をする上で“報告・連絡・相談”のコミュニケーションが大切だということを実感したようです。商品の入っていた段ボールを100個以上潰すことができ、早く潰すコツも身に付けることができました。
珈琲館では、ホールとキッチンの2か所の仕事でした。
ホールは、片付け、注文を受けて品物を運ぶ等の接客業を行いました。キッチンでは、食器の洗い物、飲み物やフード作りをしました。
お客様にくつろいで頂くために、笑顔で挨拶することの大切さを感じることができました。

3日間を通し、今まで経験したことのない貴重な体験をすることができました。“社会”の中で働くということの大変さを直に肌で感じることができたのではないかと思います。この体験を通し、今の自分に必要なこと・身に付けなければならないことに十分に向き合って今後過ごしていってもらいたいと考えます。
【進路】1学期の進路行事を振り返って~中高進路講話~
6月25日(水)5時間目は小学部高学年対象に、6時間目は中高等部及び保護者対象に、『私のキャリア~メーカーで働く研究員として~』という演題で、進路講話を実施しました。
本県出身で聴覚障害があり、花王株式会社 解析科学研究所で従事されている方を講師として、これまでの経歴や現在の仕事内容、今の仕事・会社を選んだ理由などについて、ご講話いただきました。
仕事を選んだ理由として、大学時代の実習を通して、自分の好きなこと・得意なことを生かした仕事を選んだこと、また会社を選んだ理由としては、聴覚障害に理解のある会社という点を重要視したことを知ることができました。
聴覚障害をもつ社会人として伝 えたいこととして、『①聴覚障害だから「できる」こと・「得意」なことを見つけることも大事なこと、②積極的に人とかかわること、③ポジティブな気持ちを大切にすること』の3点をお話くださいました。また、社会人になるまでに身に付けたいこととして、自分が過ごしやすい環境を作るために、『自分の聞こえを理解し正しく伝える力』が大切であることをお話くださいました。
事後学習の生徒の感想の中で、『自分の聞こえについて会社にきちんと伝えられるか心配なので、これから聞こえについて正しく理解しまとめていきたい』や、『自分が理解しやくするための工夫を考えていきたい』などの感想が出ていました。
分かりやすい具体的な話が多く、生徒達の職業観・勤労観及び自分の障害・合理的配慮についての理解がより深められた講話でした。
【進路指導部】1学期の進路行事を振り返って~高等部AB組職場見学~
6月18日(水)全国農業協同組合連合会 栃木県本部(JA全農とちぎ)へ職場見学に行って来ました。自分の将来の仕事や進路についての意識を高めることを目的に、今年度は事務職の仕事の様子を見学しました。貴会の業務概要や生徒からの質問に対するご回答により、給食で扱っている本県の農産物としてお米が一番で、それ以外に主要な品目としてトマト・にら・なす・アスパラガス・ねぎ・きゅうりを扱っていることなど、本県の農業についての理解を深めることができました。また、仕事をするときに心掛けていることとして、「公平性」「客観性」「平等性」「バランス」であることや、目標に対してやっていることがふさわしいのか、無駄はないのかという意識をもつこと、などをお話いただきました。
見学後の生徒から、「自分が立って行う仕事が合っているか、座って行う仕事が合っているのか、どちらが自分に合っているのかを考えたいと思いました。」という感想を聞くことができました。生徒一人一人が自分の進路について真剣に考える、一つの契機となったことと思います。

【進路指導部】1学期進路だより
1学期の進路だよりが完成いたしました。ご覧ください。
【進路指導部】保護者対象進路講話
7月14日(月)中学部保護者会及び高等部授業参観に併せて、保護者対象の進路講話を実施いしました。
宇都宮公共職業安定所の職員の方2名より、『適性に応じた主体的な進路実現のために』というテーマでご講話をいただきました。ご参加いただいた保護者の方からは積極的なご質問もいただき、お子様の進路を考える上で有益な機会となったことと思います。
講話内容を下記の掲載いたしますので、ご一読いただけますようお願いいたします。
中学部A組 校内職業体験
7月8日~9日の2日間、中学部A組で校内職業体験を行いました。
今回も委託業務を受けて製品の袋詰めです。
スポンジと紐を合わせてビニール袋に詰め、テープで留めるという一連の工程を各自で行いました。
自分たちの関わった製品が店頭に並び、お客様の手元に届くのだという実感があり、どの生徒も真剣そのものでした。
出来高にこだわらず、指示通り正確に作業に取り組むということを目標にしてきました。集中し過ぎて目が痛くなったり、今まで感じたことのない疲労を感じたりすることで働くということ・仕事について身近に感じることができました。
中学部 進路の時間Ⅰ
6月17日(火)中学部の進路の時間Ⅰでは、高等部の先生方から各学科について説明をしていただいた後、授業見学を行いました。
〇高等部のA組では、数学の授業や英語の授業の様子を見ました。先輩たちが難しい学習に真剣に取り組む様子にジッと見入っていました。

〇高等部のB組の授業では、生活技術科ではファッション造形基礎の学習・情報機械科で文鎮の制作をしている学習を見学しました。また、機械科実習室では鉄を削る旋盤や着ける溶接の機械についての説明も受けることができました。始めて目にする機械類に興味津々でした。
〇B組は、高等部C 組の先生からパワーポイントで学科の説明をしていただいた後、ワークシートの記入に取り組みました。手帳の種類や卒業後の就労先についての説明、これまでの自分を振り返ってできていること、これから努力が必要なことなどをチェックリストで確認しました。自分の将来について真剣に考える様子が見られました。

中学部A組 職場見学
6月19日(木)にマルハニチロ株式会社宇都宮工場へ職場見学に伺いました。
始めに宇都宮工場の概要について説明を受けました。説明してくださったのは、本校卒業生で就職して3年目の先輩でした。先輩が入室すると生徒たちから「わぁ~」と歓声が上がりました。ハム・ソーセージと鮪のたたきの製造の工程を見学しました。それぞれの担当者の方から説明を受けながら、生徒たちは大きくうなずいたり、メモを取ったり、質問をしたりしていました。


〇鮪のたたきの製造では、特別な包丁と手袋を使用し作業をしていました。魚の皮を剥いだり、内臓や骨を取ったり、決められた大きさに切ったりする工程を見て、生徒は体力や集中力を伴う大変な作業であると感じていたようです。
〇ハム・ソーセージの製造では、使用される魚の種類ごとに袋の色が違うこと、調味料と混ぜて練っていくこと、そしてボールカッターが世界一であることなどなど。初めて聞く言葉や分かったことがたくさんありました。また、『すり身』という言葉が日本独自の言葉であること、すり身があっという間にソーセージになっていく様子など驚くこともたくさんありました。
製造工程を見て、生徒たちは、食品を扱う際の衛生管理や、一つの作業をやり続ける忍耐力の大切さに気付くことができました。
★マルハニチロ宇都宮工場の馬場さんから“コミュニケーションが大切”とのお話がありました。分からないことをそのままにせず、質問すること。体調が悪い、辛い時には訴えること。仕事を進めるうえで大切なことです。今できることを毎日積み重ね、将来の自分につなげて欲しいと思います。

【進】進路だより3学期
3学期進路だよりが完成しました。ご覧ください。
中学部 進路の時間Ⅲ
12月17日(火)の中学部「進路の時間Ⅲ」では、これまでの学習を振り返りつつ、身近な例をもとに「マナー」の大切さや必要性を再確認しました。
★このマナー、○かな?×かな?
実際の友達の態度や行動を写真で見ながら、日常生活におけるマナーをクイズ形式で確認しました。授業中や休み時間、食事中など、いろいろな場面のマナーについて、「どこが、どんなふうに良いのか(悪いのか)」を具体的にチェックし、友達の姿と普段の自分自身の態度や行動とを重ね合わせながら学ぶことで、生徒たちはマナーの大切さや必要性を痛感したようでした。
★こんな時、どうする?
教室・職員室等の入退室時、報告をする時や物を置く時など、いろいろな場面の動画を見て、適切なマナーを確認しました。挨拶やお辞儀の仕方、目上の人への伝え方などのポイントを改めて具体的に学ぶことができ、生徒たちは普段から気を付けて実践しようという思いを強くしたようでした。また、「物を置く時」の動画では、自分たちが給食の食器を片付ける音の大きさに驚き、静かにそっと重ねる必要があることを身に染みて感じたようでした。
今年度の「進路の時間」はこれで最後になりますが、今後の学校生活や進路選択に生かせるよう、正しいマナーの習得に向け、これまで学んだことをもとに積極的に実践を積み重ねていってほしいと思います。
中学部 進路の時間Ⅱ
11月5日(火)の中学部「進路の時間Ⅱ」では、受験の面接場面を想定し、丁寧な言葉遣いやマナーについて学習しました。 「マナー」という言葉の意味や正しい言葉の使い方など、基本的な内容について確認した後、「マナークイズ」に挑戦しました。
★服装の間違いを探そう!
2チームに分かれて、各チームの3年生が出題者となりました。1~2年生は、先輩たちの服装を見て、どこを直せば正しい服装になるかを考えました。正しい服装とそうでない服装の先輩の姿を間近で目にすることで、服装の印象が周囲の人にどのような影響を与えるかということに気付き、身だしなみを整える大切さを改めて実感したようでした。
★面接時のマナー、正しいのはどちら?
2パターンの動画を見て、どちらの生徒の言動が面接時のマナーとして適切かを考えました。全員、正しいマナーの動画を選ぶことができました。また、もう一方の動画の中で不適切だと感じた場面について、どの言動がどんなふうに良くなかったのか、どうすれば良かったのかを考え、みんなで意見を出し合いました。「返事や挨拶の仕方」「入室時のノックの仕方」「椅子の座り方」「声の大きさ」「言葉遣い」など、様々なポイントが指摘され、特に「椅子の座り方」については、生徒二名に前に出てもらい、座るときの正しい姿勢や手足の位置を実際に見て確認しました。
【進路指導部】高等部講演会
9月25日(水)に「人の付き合い方」という演題で、高等部講演会を実施しました。本校幼稚部に在籍され、その後は地元の学校を卒業された方から、ご自身の経験をもとにしたご講話をいただきました。
講演を聞いて、「趣味をもつことで交友関係が広がること」や「周囲への自分の障害についての開示の方法」などについて、分かりやすく学ぶことができました。生徒達も興味深く聞くことができ、質疑応答も活発に行われました。
中学部A組 職業体験学習
7月9日(火)、10日(水)の二日間、職業体験学習を行いました。内容は、校内実習等でお世話になっている企業から受注させていただいた「スポンジの袋詰め作業」です。
「スポンジの穴抜き」「紐とスポンジの袋詰め」「テープ貼り」「検品」「梱包」の五つの工程を、それぞれ毎日の目標を立てながら、意欲的に取り組みました。
初めて仕事に触れた生徒たちからは「仕事は厳しい・難しいイメージだったけど、製品が一つ一つ完成していくのは楽しかった。」「最初は上手くできなかったけど、少しずつできるようになって、上手にできたときに褒めてもらえてうれしかった」と感想がありました。また、反省会では、3年生から「長時間、集中を続けることが難しかったが、今後の進路のためにも中学部卒業までに集中力を高めたい。」「プラス思考で物事を考えられるようになりたいと思う。」など、中学部卒業後の進路を見据え、今後取り組みたいことについての発表があり、中学部全体で将来に向けた職業観の育成につなげることができました。
今回の職業体験で学んだことや感じたことを忘れずに、目指す進路に向けて理解を深めていってほしいと思います。
中学部A組 職場見学
6月20日(木)に、平石化成品工業株式会社みずほの第二工場へ職場見学に伺いました。
今回の見学では三つの体験を準備してくださり、グループごとに従業員の方の指示を受けながらそれぞれの活動に取り組みました。
シュリンク作業では、フィルムの中心を意識しながらテープに巻き付ける作業に苦戦していましたが、熱を利用してフィルムを縮ませる様子やその機械の中からきれいに包装されて出てくる様子を見て面白さを感じていました。

自動車部品の梱包箱作成では、緩衝材となる部品の組み立てやインパクトドライバーを使用したビス留めを行いました。初めて扱う機械に戸惑いながら、補助を受け恐る恐るスイッチに指をかけている様子が印象的でした。
ロット番号押しと梱包作業では、スポンジ製品を扱いました。ロット番号押しは見た目以上に力が必要なことや、長時間同様の作業を続けることへの集中力が必要なことに驚いていました。
今回の職場見学を通じて、人の手で一つ一つ作ることを大切にしていることや、「できない」と最初から諦めずに何事にも挑戦する気持ちが大切なことを学ぶことができました。これからの学校生活に生かしてほしいと思います。
【進路】令和6年度特別支援連携協議会
5月20日(月)に連携協議会を開催しました。本校生徒の進路先や実習先でお世話になっている福祉事業所や企業及び行政機関の方々をお招きして、聴覚障害教育についての講話、授業参観、そして情報交換・協議を行いました。午前中は、15の福祉事業所から16名の方にご参加いただき、「円滑な移行支援について」というテーマで協議を行いました。午後は、15の企業から20名、7の行政機関から13名の方にご参加いただき、「聴覚障害者の雇用について」の情報交換及び協議を行いました。協議会は3グループに分かれ、職場における現状・課題と、「本校OB・OGのキャリアモデルの好事例」について、協議することができました。職場における障害者の「キャリア」について、どのように進めていくと良いのか、といった話題に対して、企業の取組についてお話いただいたり、また行政機関から支援事例についてお話いただいたりするなどして、活発な情報共有が行われました。
【進路】2学期 進路だより
2学期進路だよりが完成しました。ご覧ください。
【進路】進路だより
1学期 進路だよりが出来上がりました。ご覧ください。
【進路】令和5年度 特別支援連携協議会
5月23日(火)に連携協議会を実施しました。関係諸機関の方々をお招きして、聴覚障害教育についての講話、授業参観、そして情報交換及び協議を行いました。
午前中は、福祉事業所関係の16名の方が参加し、「コミュニケーション支援について」というテーマで、午後は、企業や行政関係の29名の方が参加し、「関係機関との関係について」というテーマで協議しました。午後は、各機関の役割について、ハローワーク・宇都宮圏域障害者就業・生活支援センター・栃木障害者職業センターからご説明を受け、それぞれの役割を再確認することができました。また、協議会は2グループに分かれて実施し、職場における関係機関との関わりの事例や課題などについて、活発な意見交換を行うことができました。
協議会テーマ以外にも、各事業所や行政機関それぞれにおける、聴覚障害者への支援の現状や課題を伺うことができ、大変有意義な機会となりました。久しぶりに授業参観も実施し、生徒の様子を多くの方に知っていただくことができました。

【進路】2学期 進路だより
【進路】1学期 進路だより
【進路】令和4年度 特別支援連携協議会
関係諸機関の方々をお招きして、本校及び聴覚障害教育のご説明をしたり、情報交換及び協議を行ったりしました。
午前中は福祉関係の方々をお招きして聴覚障害についての説明をした後、
「移行に伴う様々な課題について」というテーマで協議会等を実施しました。
午後は企業や行政関係等の方々をお招きして本校の概要や聴覚障害についての説明をした後、行政の方より障害者雇用状況についてのお話をいただき、
さらに、「職場定着に向けた取り組み〜それぞれの立場から」というテーマで協議会等を実施しました。
〜連携協議会のアンケートより(一部抜粋)〜
・一生懸命な姿は見ていて気持ちが良く、温かい気持ちになりました(授業見学の感想)。
・第一言語に手話や指文字があると思いますが、第2第3言語と表現できる方法や手段を多く身に付けると、社会でも生活しやすくなると思われます。
・他社の取り組みや、行政機関の方のお話など大変参考になりました。
・各企業の職場定着に向けた取り組みを会社で情報共有したいです。
その他、有意義な協議会だったとの感想を多数いただきました。
当日はご多忙の中ご参加いただきありがとうございました。今後の指導に反映させていただきます。


進路だより3学期
進路だより 2学期
令和3年度1学期進路だより
令和3年度 栃木県立聾学校特別支援連携協議会の実施について
新型コロナウイルスの影響により5月20日(木)に2年ぶりの開催となりました。午前中は、福祉施設関係などの方々をお招きし、聴覚管理、手話講習会などの実施後、「コロナ禍の中での移行に伴う様々な課題」という協議題で施設や本校卒業生の取り組みや課題についてご意見をいただきました。午後は、企業や行政関係などの方々をお招きし、「コロナ禍での職場定着に向けて」という協議題で始めにハローワークの方から情報提供をいただき、話し合いをもちました。各企業や県内の生活支援センターの方々からは、相談内容としてコロナ禍の中で全員がマスクを着用しているためグループトークに参加できないことやメンタル面の相談の増加に伴う対処の仕方が変わってきていることなどが話題に出ました。
アンケートから
・幼稚部から慣れた場所で相談や教育を受けられるのは、親も子も安心できると思いました。
・生徒が少人数で、子ども達への配慮が行き届いており、しっかり顔が見え変化にも気づける関係性が保たれていると感じました。
・掲示板やUDトークの紹介があり良かったことや聴こえを補うために見える化されていることへの気付きやトイレをきれいにされている印象を受けました。
・新しいツールの話やwithコロナに関する話、他社の取り組み、行政の対応方針などを知ることができ有意義でした。
・ロジャー等知らないものなどの知識を得られて勉強になりました。
・企業の生の声を聞くことができて良かったです。企業間でも学び合っている様子が見られ、印象的でした。
など
当日は、コロナ禍の中で多くの方々に参加していただき大変、ありがとうございました。在学中に必要なことへのアドバイスや具体的な状況に応じた多くのご意見をいただき今後の指導に生かしていきたいと考えております。
【進路指導部】令和2年度進路だより①
【進路】令和2年 特別支援連絡協議会の中止の件について
3学期進路だより
進路だより
【進路講話】高等部、中学部、小学部高学年1組
6月26日(水)に、鹿沼相互信用金庫から、本校卒業生を招いて、講話をしていただきました。前半は、会社の業務を中心に、仕事で必要な心構えなどを話していただきました。後半は、本校生徒からの質問に対して、1つ1つ丁寧に答えていただきました。参加した、高等部17名、中学部14名、小学部高学年1組8名、保護者3名は、熱心に話に聞き入り、有意義な時間を過ごすことができました。


【職場見学】高等部AB組

【職場見学】中学部B、C組・高等部C組
7月5日(金)に鹿沼市方面に職場見学に行ってきました。
武子希望の家では、部品組立やしいたけ栽培等の作業を見学した後、平成19年度卒業生のA・Kさんと話をする機会をいただきました。先輩からは、「仕事中は筆談で周りの方とやりとりをします。仕事は大変だけど好きです。」というお話がありました。
CCVウェルフェアでは、併設のカフェ(デリカフェココボ)にて施設内で作ったパンや野菜を使った昼食を食べました。その後、軽作業やパソコン作業の様子を見学しました。
先輩方の姿を見習い、今後の学習を頑張っていきたいと思います。
令和元年度 栃木県立聾学校特別支援連携協議会の実施について
【アンケートから】
①1対1、1対2等とても手厚い指導を感じました。就職してからは、同じ対応は難しいと思うのでそのギャップを埋めるような支援の必要性を考えていきたいと思いました。
②授業時に生徒の発言が少ないと感じました。間違っていても良いので積極的に発言する習慣があると良いと思います。
③グループトークがとても良かったです。企業の方々は、たくさん話せて良かったと思います。特に障害を持つ方が、自分の居場所を職場で見つけられることが定着につながることを改めて感じました。
当日は、お忙しい中、参加していただいた方々、大変ありがとうございました。今年度の午後の協議会につきましては2つのグループに分かれての話し合いとなりました。具体的な状況に応じた多くのご意見をいただき今後の指導に生かしていきたいと考えております。
2009年度卒業生より
私は、『鹿沼相互信用金庫』という金融機関に勤めています。勤務歴は早9年が経ちました。「かぬましんきん」は、地元の信用金庫として、本店が所在する鹿沼市をはじめ、宇都宮市、日光市、栃木市に支店があり、合計12店舗で営業しています。業務内容は、預金・融資(貸付)・為替(振込等)といった金融機関の基本業務をはじめとして、各種金融商品の取扱い、お客様のサポート・相談業務等々幅広く活動しています。
その中で、私は本部の事務管理部・事務集中グループという部署に所属しており、当グループは全店の事務を効率化するため、本部に事務処理を集約し様々な業務を行っています。主な仕事には、自動振替・決済業務(口座振替等)、為替業務(振込、手形・小切手等)出納業務(現金管理等)、各種登録業務(ファイリング)等があり、その中で私は、自動振替・決済業務、登録業務をメインとして仕事をしています。正確な事務処理を行うことが当然の部署であり、取扱う書類は個人情報等が満載で、日々神経を使い、ミスをしないよう気を付けています。
後輩の皆さんに伝えたいことは、歴代の諸先輩も話されているとおり、何事にも積極的に行動すること、取り組むことが大切かと思います。分からないことがあれば、自分から進んで確認したり、何か新しいことにも失敗を恐れずチャレンジしたりする意気込みが大切であると思います。また、社会・職場では協調性が重要であり、何か困ったことがあれば、お互いに助け合うことが大切です。
それらの積極性、協調性が重要というのは、皆さんの学生生活でも共通する点があると思いますので、社会に出るまでに自分なりに心掛け、学生生活を有意義に過ごしてください。
平成30年度 栃木県立聾学校特別支援連携協議会の実施について
5月22日(火)の午前中は、福祉施設関係などの方々をお招きし、手話講習会、その後、「移行に伴う様々な課題について」という協議題で一人ずつ課題点や改善方法などを出し合い、意見交換を行いました。午後は、企業、行政関係などの方々を招き、「職場定着に向けた取り組みについて」という協議題で話し合いを持ち、最後にハローワークの方から情報提供をいただき、具体的には「職場での孤独感」と言うことに絞り、各企業から様々な意見が出ました。
アンケートから
① 聴覚障害者の利用者に対してすぐに使える内容を講義して頂き勉強になりました。
② 他作業所での取り組みや支援方法の話が聞けて有意義な協議会でした。
③ 「聴覚障害について」の話がとてもわかりやすかったので、ぜひ会社に来て頂き、理解度の促進を手助けしてほしいと感じました。
④ 聴覚障害の方とのコミュニケーションを取る話のきっかけとして何か一つでも自信が持てることを身に付けることも大切であるということを知ることができました。
など他にも多くの参考になるご意見をいただきました。
当日は、お忙しい中、参加していただいた方々、大変ありがとうございました。多くのご意見をいただき今後の指導に生かしていきたいと考えております。
進路だより
卒業生より
1996年3月に栃木県立聾学校を卒業した「T.T」です。
現在「富士通テレコムネットワークス株式会社」に勤務しております。
製造部のSMTという職場で働いており、現状の仕事内容は下記のとおりです。
【仕事の内容】
1.自動機の機械についてるカ-トリッジのメンテナンス(綺麗にすること)
2.部品を包んだ丸い物(リール)をアルミ袋に包装する作業
そしてパソコン作業で確認の上、棚へ入庫処理
3.他の会社(外注)への基板払い出し
4.改善作業(作業をやりやすくする為の改善)
【働く上でのアドバイス】
・一般常識のマナ-
・何をすべきか自分で先を考え、行動にうつすこと。(積極性)
私は、学生時代にスポ-ツが大好きで、色々積極的にやってきました。
野球部のキャプテン、陸上、剣詩舞クラブ、生徒会副会長等を行い、学生のときに学んだ事が今仕事をする上でも活かされていると思います。
昨年、一昨年とアビリンピックに出場した時も「強い気持ち(積極性)」と周りの人たちとのコミュニケーションの大切さを実感しました。
まずは自分が得意な分野を見つけて、それを伸ばして積極的に活動して欲しいと思います。頑張って下さい。先輩として応援しています。
進路講話を実施しました
7月7日(金)に中学部・高等部生、小学部高学年児童や保護者の参加など多くの人が集まり、本校卒業生で現在、宇都宮市役所にお勤めしている先輩を招いて進路講話を行いました。多くの参考になる言葉をいただきましたが、その中でも特に大切と思われることをいくつか挙げてみました。
1 職場でのコミュニケーションと信頼関係について
・自分から積極的に周囲の人たちに声をかけ、困り感を知ってもらう。
・会話には敬語を使うと信頼関係がアップし、会話がスムーズにいく。
・挨拶の必要性(会話したことない人や部署が違う人にも会釈を忘れない)
2 手話を覚えて仲間を増やす
・自分の近くにいる人に積極的に簡単な手話を教えることで手話に興味を持っても
らい、手話を使ってくれる職員が増えてくる。
3 働く意味を理解する
・進路決定は早くから動き出すことが必要。どんな仕事をしたいのかをよく考えて目
標を持って計画的に進めていってほしい。
・生きていくために仕事は必要である。
4 働く上で必要なこと
・健康であること
・一度仕事に就いたら辞めないで自分に責任を持って最後まで頑張る。
・困った時は、一人で悩まず周りの人に相談して支えてもらう。
・辞めて違う職に就いても、くせになって何回も辞めることになってしまう。
最後は、生徒からの質問内容にも答えていただくなど有意義な時間を過ごすことができました。今後は、これらの内容を進路を考える上で生かしていきたいと考えています。
平成29年度 栃木県立聾学校特別支援連携協議会の実施について
5月23日(月)、栃木県障害福祉課や福祉施設関係などの方々をお招きし、「現場でのコミュニケーション方法等の課題について」、午後は、企業、行政関係などの方々をお招きし、ハローワークの方から「支援体制の構築について」の話題提供のあと、それぞれ話し合いを持ちました。
午前中には、栃木県障害福祉課の方から、国が進めているユニバーサル農業を栃木県でも工賃向上のために農業と福祉の連携を具体化して拡大する動きがあることの話をいただきました。
福祉施設関係の方からの問題点として次の点が挙げられました。
① 手話のできる職員の不足による聴覚障害者とのコミュニケーションの難しさ
② 聴覚障害者の気持ちの伝わらなさや友人関係での思い悩んでいたりする事例
③ 気をひきたい行動など
これらに対し、本校からは、次のようなアドバイスを行いました。
① 見通しの大切さ、特に視覚的支援を使っての生活の見通しの必要性
② 行動の無視、プラス行動の時にほめる
午後は、ハローワークの方からの話題提供のあと、企業の方より次の質問がありました。
① コミュニケーション面でマスク使用が必要な職場では口元が見えないといった問題
② 安全関係や地震対策など
これに対し、話し合いでは、他の企業から次のような回答が寄せられました。
① マスク使用の職場では、周囲の職員の手話の向上が必須であるが、現時点では携帯
できるホワイトボードを使っての筆談が多いこと
② 安全関係の問題では、閉じ込め対策として防犯ブザーの使用や携帯電話の使用許
可、ホイッスルの使用
当日は、お忙しい中、参加していただいた方々、大変ありがとうございました。多くのご意見をいただき今後の指導に活かしていきたいと考えております。
第1学期高等部産業現場等における実習
第1学期 高等部産業現場等における実習を行いました!
高等部では、社会に出て働くということの意義を知り、仕事をするときの態度等を学ぶために、校外の企業や福祉施設での実習を各学期1~2週間行っています。
今回は、3年生1名について、2週間、企業での実習を行いました。初めは緊張した様子が見られましたが、少しずつ、作業にも習熟し、しっかり取り組むことができました。また、仕事をする上では、作業の能力だけではなく、態度や周囲の方とのコミュニケーションも大切です。「挨拶、返事、報告、相談」について実践したり、休憩時間にも、社員の皆様とお話をしたりと、学校での授業時に学んだことを生かせるように、努力することができました。
会社でいただいた課題を学校に持ち帰り、改善やさらなる向上を目指して、日々の生活に取り組んでいきます。
1年生についても、2学期から実習が始まります。それに向けて、学習を頑張っていきましょう。
進路だより
卒業生の近況報告
私は、いすゞ自動車(株)栃木工場 パワートレイン製造第一部検査課に所属しております。
主な仕事内容は、製品検査に使用する測定具の校正業務です。0.1ミクロン単位の測定具の精度を測定・判定します。不良品を作らない・流さないための重要な仕事であり、大変なことが多いのですがその分やりがいを感じられます。
作業を行っているのが、恒温室とよばれる、常に室温が20°で管理された部屋です。そこには私を含め聾者が3人作業にあたっています。職場のその他の方々とは、筆談や簡単な口話でコミュ二ケーションを図っています。そのため、仕事をする際に私はいつもメモ帳を持ち歩いています。
耳が聞こえないと、できる仕事が限られると思われがちです。しかし、いざ働いてみると、耳が聞こえなくてはできない仕事はそれほど多くありません。逆に言えば、自分から積極的に動いていくことで、チャレンジの幅は広がっていくと思っています。
皆さんも将来のことで悩まれるかと思いますが、自分から動けば、きっと会社や周りの方々から、理解と協力をしていただけます。皆さん、頑張ってください。

卒業生より
聴覚障がいでも常にポジティブで!!
昭和60年度高等部卒 F.T
宇都宮市役所勤務
私は,宇都宮市役所に所属して,福祉関係の多種多様な事業に取り組んでいます。
仕事柄,外部と連絡をとることが多いですが,私は電話応対ができないので,代わりにFAXやメールを利用して対応しています。
職場では,同僚が指文字や簡単な手話を覚えてくれて,ほとんど指文字で会話しています。やっぱり,同僚と仕事をする上でコミュニケーションは大事なので,自分から進んで筆談,指文字や手話を教えるなど,積極的に行動することが必要だと思います。
在学生の皆さんには,社会人になると障がいに関係なく一人前の大人として仕事することを求められますので,おどおどしないで,常にポジティブに頑張ってほしいと思います。
卒業生より
H7年度卒業 M.T
㈱本田技術研究所 四輪R&D センター
Hondaの四輪研究開発を担う会社に10年以上勤めています。
現在は中堅社員として世界中のHonda事業所に導入しているコンピューターシステムのグローバルサポート業務や新しいITシステム開発といったクリエイティブ思考を伴う業務に従事しています。
また、プログラム作成や英語メールでやり取りする機会もありますので、いつも自習を積み重ねながら取り組んでいます。
会社でのコミュニケーション方法を紹介したいと思います。
会社で標準導入されているソフトで、事前の準備がなくても誰とでもグループチャットができるメリットがあります。会議等に積極的に活用しています。
(2)タブレットや紙ベースでの筆談
マンツーマン(一対一)のコミュニケーションやパソコンが使えない場面では、タブレットの筆談系アプリや紙を使った従来ながらのアナログライクな筆談を活用することもあります。また、記録に残す必要があるかどうか内容に応じてツールや手段を使い分けることもあります。職場の飲み会や出張移動中は破損リスクが少ない軽量の電子メモパッドを活用する工夫もしています。
(3)会社支給携帯電話によるSNS/SMS(ショートメール)の活用
出張や外出先の職場から離れているところからの社内情報共有や連絡手段として
SNS/SMS(ショートメール)を活用しています。緊急時の電話(発着信)が必要な場面がある時は、周囲にいる同僚に代理電話をお願いできるようにしています。
職場の方の協力を得ながら、場面に応じてパソコンソフトや手段を柔軟に使い分けていますが、パソコンを使った仕事がほとんどの職場ですので、基本的にPC ノートテイクを中心に活用しています 。
このようにコミュニケーションツールや手段の特徴を上手に使い分けることで、コミュニケーションスタイルや情報共有の違いを乗り越え、職場の信頼やサポートを得ながら、自分のスキルアップやチャレンジ精神を持って取り組んでいます。また、自分ひとりではなくチームの一員として仕事に取り組むことや自らコミュニケーションツールの使い方を覚えて周りに伝授することで聴覚障害に対する認識を深めてもらうことも大切だと思います。
学ぶことは在学時だけではなく、社会に出てからはさらに重要になります。
自分の人生をどう生きていくかを考えていくことも大切です。世の中のあらゆる出来事、物事や思想に対しても客観的思考を自ら健全に育んで認識・形成していくことを前提に、各自が自助努力で出来ること、出来ないことを自ら気付き、そして、きちんと認識し整理できるようになって欲しいと思います。
それから、障害の有無に関わらず、同じ人間としてお互いの多様性を認め合える人間尊重はもちろんのこと、聴力の程度や失聴のタイミングの違いによって、多種多様な能力を持つろう者同士でもお互いを健全に受け入れ、受容性を高めることができる人になって欲しいと思います。
その上で、みなさん一人ひとりに合ったポジティブな方法で日本語やコミュニケーションの壁を上手に乗り越えて、人間関係や信頼関係を築いていくアクションを積み重ねていくのは、在学時も社会に出てからもとても重要だと心がけてください。
具体的な方法は人それぞれですが、多くの先輩が持っている技術・経験・知識、そして学校の先生方や地域・家族の身近な方のたくさんの教養にも自ら積極的に触れてください。そして客観的に耳(眼)を傾けて認識し、それを糧にし、自分自身の生き方を磨くことにつなげて欲しいと思います。
また、明日(未来)は自分の力で掴みとることにつなげられるよう、在学時からたくさんの知識や体験による習得、見聞や教養を積極的に広めて、分からないことがあっても分からないなりに一歩ずつ積み重ねていく努力や前向きな意欲・向上心を社会人になっても持ち続けてください。
そういった意欲や姿勢に対し、在学時は聾学校の先生方や家族の方が、社会人になってからは社会(地域)や職場の方が支援・協力を惜しまずに支えてくれるはずです。










































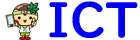
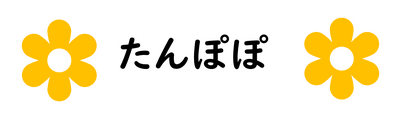

 tochigi-edu.ed.jp
tochigi-edu.ed.jp