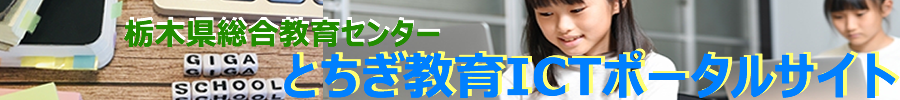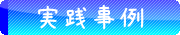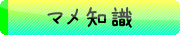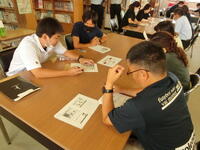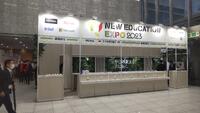「お知らせ」バックナンバー
佐野市立南中学校講話
「佐野市立南中学校で講話をしてきました」
6月21日(水)に情報室職員が佐野市立南中学校の校内研修に伺って、
情報モラル教育についての講話を行いました。
「ネットトラブルから子どもたちを守るための指導支援について」と題して、
「情報モラル教育とは何か」「情報モラル教育の指導法について」などを伝えてきました。
情報モラルの指導力を含むICT活用指導力は、
すべての教員に求められる基本的な資質・能力です。
本研修が、生徒を指導する上で参考となりましたら幸いです。
義務教育に関する調査研究の学習会
「義務教育に関する調査研究の学習会が行われました」
6月20日(火)にセンターを会場として、
「小・中学校における教科指導充実に関する調査研究」学習会が行われました。
午前中は指導助言者の玉川大学大学院教育学研究科教授の、久保田善彦様に
「各教科の資質・能力の育成に資するICTの活用について」と題して講話をいただきました。
お話の中で特に印象的だったのが、「ねらいが明確であれば、単純な機能でも効果的である」
ということでした。ICTを使った授業を行うことに意識がいきがちですが、
ICTはツールであって、やはり授業をどうデザインするかが大切なんだと感じました。
今年度も研究協力委員の先生方と調査研究を進めていきます。
昨年度の成果等については、「こちら」を参照して下さい。
NEW EDUCATION EXPO 2023 TOKYO
「NEW EDUCATION EXPO 2023 TOKYOに行ってきました」
6月1日(木)~3日(土)に東京ファッションタウンビルで行われた
NEW EDUCATION EXPO 2023 TOKYOに情報室職員が出席してきました。
ICT関連の最先端のものに触れたり、未来の学習空間を体験したり、
セミナーに参加して、貴重なお話を聞くことができました。
「ICTを使った対話的な学び」の講話から、『どんなICTを使うか』ではなく、
『何を子どもたちに問いかけるか』の方が大切であり、
ICTは深い学びのための効果的なツールであるということを改めて感じることができました。
「問いは意図」実践しましょう!
教育CDO来所
「教育CDOが来所しました」
5月26日(金)に県教委事務局の教育CDO(チーフデジタルオフィサー)の
及川葉月氏が当センターを視察されました。
研究調査部の情報室職員が、センターのICT環境の現状と課題及び今後の
在り方を説明しました。
先生方のよりよい研修につながっていくよう、当センターでは、更なるICT環境の
向上を目指していきます。
EDIX(総合教育展)東京
「EDIX(総合教育展)東京に行ってきました」
5月10日(水)~12日(金)に東京ビックサイトで行われたEDIX(総合教育展)東京に
情報室職員が出席してきました。
ニュースでも取り上げられていましたが、会場は活況を呈し、
ICT関連の最先端のものに触れることができる有意義な機会となりました。
自動採点システムや授業支援ツールなどの展示が多くあったことが印象的です。
教育界にもDXの波が押しよせてきていますね。
新規採用学校栄養職員研修 第3日
「センターで講話を行いました」
「学校における個人情報保護」と題して、
セキュリティに関する内容について情報室が講話を行いました。
パスワードの使い回しは危険ですので、みなさんも気をつけましょう。
「リーフレット」のデータです
「リーフレットのデータ」
1人1枚お手元に届くように発送させていただきましたが、
「非常勤講師や事務職員にも見てほしい」「もう1枚欲しい」という方のために、
リーフレットのデータをダウンロードできるようにしました。
ぜひ御活用ください! → こちらをクリック!
「リーフレット」を発送しました
「リーフレット 発送」
4月19日(水)にポータルサイト開設にあたり、リーフレットを各学校に発送しました。
裏面は情報室が厳選したショートカットキーと、求められる情報リテラシーをまとめました。
ぜひ御活用ください。
「とちぎ教育ICTポータルサイト」を公開しました
「とちぎ教育ICTポータルサイト オープン」
先生方の授業や校務等における積極的なICT活用をサポートするため、総合教育センターのWebサイトにポータルサイトを作成しました! ぜひご活用ください!
リーフレットの解説
【リーフレットの解説】
「著作権や情報モラルについて、正しく理解していますか?」編
| 番号 | 正解 | 解 説 |
| 1 | ○ | 児童生徒が授業中に書いた作文にも著作権は発生します。例えば学級通信などに作文を掲載する場合にも、著作者としての児童生徒(本人と保護者)に同意を取らなければなりません。 |
| 2 | ○ | 著作者が実名(または周知の変名)で公表したものについては、「著作者の死後70年まで」が著作権の期限となります。その他にも「著作物の公表後70年まで」が期限となる場合もあります。 |
| 3 | × | インターネット上で利用するには、自分が著作権を持っているものか、著作者から許可を得たものである必要があります。CDを購入したからといっても著作権は自分にはありません。 |
| 4 | × | 著作権法第三十五条では、授業で必要と認められる限度において、複製することが認められています。しかし、教師が購入したものを児童生徒に配布する行為は、「著作者の利益を不当に害することとなる場合」に該当するため認められません。 |
| 5 | × | フリー画像であっても、著作者の意図により様々な制限がある場合があります。著作者が示す利用規程(利用の範囲)について必ず確認の上、利用しましょう。 |
| 6 | × | 「肖像権のプライバシー権」があるため、撮影と公開にあたっては、児童生徒(本人と保護者)から承諾を得る必要があります。なお、個人が特定されない写真については肖像権が発生しません。 |
| 7 | ○ | 2019年5月、世界保健機関(WHO)が「ゲーム障害」を国際疾病分類として認定しました。この疾病は利用時間をコントロールできない、日常生活よりゲームを優先するなどの状態が1年以上(症状が重い場合は1年未満)続くことを指します。 |
| 8 | × | インターネット上に公開されている情報は、必ずしも正しいものではありません。二つのサイトだけでは信頼できる情報になり得ない場合があります。「情報元が異なる複数のサイトまたは、別の方法(新聞やニュース)」による確認が必要です。その他に、情報の発信元、時期などについても確認しましょう。 |
「セキュリティ診断」編
| 番号 | 解 説 |
| 1 | 職員室や準備室などは児童生徒も入室します。多数の人の目に触れる場所には、成績や個人情報を掲載した印刷物等を置かないようにしましょう。また、プリンタに出力した用紙も取り忘れないようにしましょう。 |
| 2 | 原則として、児童生徒の情報を校外へ持ち出すことは禁止です。ただし、管理職の許可のもと、持ち出し可能な場合もあります。セキュリティポリシーや実施手順にしたがって情報漏洩の防止に努めましょう。 |
| 3 | 悪意のあるWebサイトを閲覧しただけで、マルウェア等に感染する可能性があります。組織で設定されているフィルタリングや、ウイルス対策ソフトでも完全に防御できるわけではないので注意が必要です。 |
| 4 | 確認の取れない宛先からのメールや、URLが貼り付けられたメールには十分注意しましょう。URLを安易にクリックしないことが大切です。 |
| 5 | 許可されていないソフトウェアをインストールしたことでマルウェアに感染することもあります。機密情報を扱う校務用のパソコンには、不要なソフトウェアをインストールしないようにしましょう。また、定期的にアップデートをすることも大切です。 |
| 6 | 画面をのぞき見られたり、勝手にコンピュータを操作されたりしないようにするために、たとえ短時間であっても離席時には画面ロック等をしましょう。 |
| 7 | 初期パスワードは組織内の全ての人が知ることができ、「なりすまし」にも繋がるため危険です。必ず変更してから利用しましょう。 |
| 8 | 同じパスワードを使い回すと、パスワードが流出した際に危険です。利用するWebサイトに応じてパスワードは異なるものを利用するようにしましょう。管理が煩雑だと感じるときは、パスワード管理ツールなどを用いる方法もあります。 |