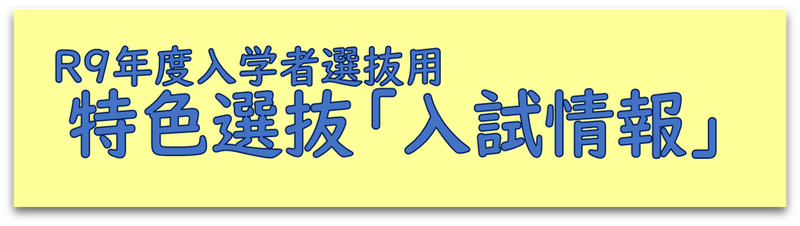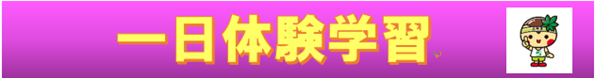文字
背景
行間
校長室だより
入学式を彩った花々



高校入試期間中の過ごし方について
この期間の過ごし方については、各クラスで担任の先生から話しがあったかと思いますが、このような自分で律する時間をどう使うかが高校生にとって重要です。
先月は、特色選抜のための学校休業日がありましたが、どう過ごしましたか。
校長室掃除の一年生が、「高校は、こんなに休みが多いんですね。」と驚いていましたが、このような期間を場当たり的にではなく計画的に実りあるものとするのが高校生です。
大学生になると、この時間が更に増えます。というより、毎日が自分で自分を律していくことになります。今からそのトレーニングをしておいてください。
さて、この一週間、各教科、各学年から課題が出されていることと思います。まずはそれを仕上げてください。そのうえで本を読む時間を作ってください。くれぐれもゲームだけで一週間が過ぎ去るなどということがないように。高校生なのですから。
では、何を読むか。今日は、「MIYATEEN VOL.12」で紹介されている本を紹介します。
「MIYATEEN」は、「宇都宮の高校生のための読書情報誌」として、宇都宮市立中央図書館から発行されています。
編集委員はすべて、宇都宮市内の高校に通う生徒です。したがって紹介される本は高校生が高校生に勧めるものとなりますので、きっと気になる本があると思います。そして、気になったら是非読んでください。
「MIYATEEN VOL.12」は、昨年末に各クラスに2部ずつ配布してありますが、見ていない人がいると思い、作者名・作品名のみここで紹介します。「MIYATEEN」は、とてもよくできた冊子ですので、登校後手にとってください。市立図書館にも配備されているので、この休業中に図書館で手にとることもできます。
今回の「MIYATEEN」は、「-WELCOME TO OUR THEATER-」という副題がついており、シネコン風の作りになっています。とても魅力的な作りになっているので、文字だけで紹介するのはとても味気ないのですが、紹介されている本は下記のとおりです。
「傘ももたない蟻たちは」加藤シゲアキ
「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」岩崎夏海
「人間失格」太宰治
「カラスの教科書」松原始
「ののはな通信」三浦しをん
「午後の恐竜」星新一
「三匹のおっさん」有川浩
「Another エピソードS」綾辻行人
「蜜蜂と遠雷」恩田陸
「フリーター、家を買う」有川浩
「本屋さんのダイアナ」柚木麻子
「悩み部の結成と、その結末。」麻木一樹
「永遠(とわ)をさがしに」原田マハ
「桜風堂ものがたり」村山早紀
「15歳のテロリスト」松村涼哉
「氷菓」米澤穂信
「今だけあの子」芦沢央
「フーガはユーガ」伊坂幸太郎
「吉祥寺の朝日奈くん」中田永一
「生のみ生のまま」 上・下」綿矢りさ
「ロマンシエ」原田マハ
「100日間、あふれるほどの「好き」を教えてくれたきみへ」永良サチ
「パラレルワールド・ラブストーリー」東野圭吾
「夜が明けたら、いちばんに君に会いに行く」汐見夏衛
「文房具の解剖図館」ヨシムラマリ、トヨオカアキヒコ
「老人と海」アーネスト・ヘミングウエイ
「神隠しの森 とある男子高校生、夏の記憶」梨沙
「嫌われる勇気」岸見一郎、古賀史健
「ほくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」ブレイディみかこ
「思い出のマーニー 上・下」ジョーン・ロビンソン
「MIYATEEN」には、本の概略と感想が編集した高校生によって記されていますので、登校後はそちらを参考にしてください。
卒業式 式辞
式 辞
朝夕の厳しい冷え込みはまだ残るものの、日増しに強まる春の陽射しに万物が胎動する季節となりました。
この佳き日に、PTA会長小野浩一様、同窓会長四十物英晴様の御臨席を賜り、保護者の皆様のご列席の下、栃木県立宇都宮北高等学校第三十九回卒業式を挙行できますことは、本校にとりましてこの上ない喜びであり、厚くお礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、多くの御来賓の方々をお招きすることができず、在校生がこの会場で卒業生の姿を見ることはできませんが、二年生は西体育館にて、一年生は配信された映像にて気持ちを一つに先輩方の卒業を祝福しています。
卒業生の皆さん、御卒業おめでとうございます。
また、保護者の皆様には、今日まで陰に陽に、慈しみ育ててこられた御苦労が実を結び、ここに無事お子さまが卒業を迎えられましたことを、心からお祝い申し上げます。
ただいま卒業証書を授与した三一五名の卒業生の皆さんは、本校に入学以来、「励み 結び 拓く」の校訓のもと、「高い志をもつ生徒」「全力を尽くす生徒」「リーダーとなる生徒」「国際人の資質をもつ生徒」を目指し、勉学はもちろん、部活動に、学校行事などに、常に真摯に取り組み、在校生にも良い手本を示してくれました。皆さんの歩みは、本校の歴史に新たなる一ページを記すとともに、一人一人が精神的にも肉体的にも見違えるような成長を遂げました。
今この席にある皆さんの姿を、指導に携わった我々も後ろの席の保護者の皆様と同様、様々な感慨を込めて見守っています。
皆さんほど多くの試練を強いられた学年はないと思われます。
第一に、大学入試改革のもと、多くの変更が皆さんの前に示されました。
大学入試センター試験を大学入学共通テストと名称を変更し、出題内容は思考力、判断力、表現力を問うものとすることが発表されました。
解答方法も、本校開校の前の年に始まった共通一次試験から四〇年続く、マークシート方式のみの解答であったものが、国語と数学では、記述式の解答が加わることとなり、英語では、四技能の力を見る試験となることが示されました。
これほど大きな変更が、一度に課され、未知なるものに取り組む不安を皆さんは強いられました。
ところが、一昨年末になって、記述解答も英語四技能試験も実施されないこととなり、それまでの取り組みは何だったのかと思わされることとなりました。
しかし、記述式解答試験の撤回には、一つの希望がありました。それは、撤回の決め手となったのが、皆さんと同年齢の高校生の声であったことです。直前での変更で混乱は生じたものの、私たち教員が何度訴えても止められなかった未熟な制度変更を、高校生の声によって止めることができたということに、私は感動を覚えました。
第二の試練は、昨年一月から世界中に猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症による様々な影響です。
突然の三ヶ月にも及ぶ臨時学校休業、学校再開後もあらゆる活動が制限されることとなり、高校生活にも進路選択にも大きな影響を及ぼしました。
運動部、文化部の各種大会やコンクールはことごとく中止され、これまでの成果を発揮することができずに、部活動を引退することとなりました。
本校においても、スポーツ大会や学校祭といった、皆さんが楽しみにしていた行事が中止となり、生き生きと活躍できる場を失いました。
どんなに辛く悲しかったことでしょう。
誰もが、言いしれぬ不安と寂しさを抱えながら過ごしたことでしょう。
できることなら皆さんに、もう一度、三年生として高校生活を全うしてもらいたいと考えるのは私一人ではないでしょう。
私が皆さんと時間を共有できたのは、わずか九ヶ月でした。あまりにも短い。
私が皆さんのはち切れんばかりの笑顔を、マスクなしに見ることができたのは、学年別ドッジボール大会の一日と、体育の授業を見に行った時だけでした。あまりにも少ない。
実は、皆さんにもう一度、三年生として高校生活を送ってほしいという私の願いは、私が皆さんともっと触れあいたかったという個人的な思いでもあります。
皆さんが北高への入学を強く望み、その願いを果たしたのに、思い描いた高校生活を送ることができなかったことを残念に思うように、私にとっても長年希望していた北高に勤務することができたのに、北高生と手を携え、よりよい北高作りに取り組むという目的を十分にできなかったことが残念でなりません。
北高生は、皆優れた資質を持ち、可能性に満ちたすばらしい人たちです。その人たちの教育に携わりたいというのが、私のかねてからの望みでしたから、それが十分にできないことの悔しさはなかなかぬぐい去れません。
しかし皆さんは立派でした。
置かれた境遇をしっかりと受け止め、前を向いて次なるステージに思いを致し、歩んできました。その姿はとても頼もしく、「さすが北高生」と思いました。
だからこそ皆さんには大きな期待が寄せられるのです。
本校の目指す生徒像の一つ「リーダーとなる生徒」について、皆さんは、自らが望むと望まざるとに関わらず、地域で職場で様々な組織の中で、リーダーとして活躍することを期待されています。
本校の教育目標が「人間性豊かで、我が国の伝統・文化を理解し、国際感覚をもって社会で活躍する人材を育成する。」とあるのも、リーダーとして活躍することを求められる、宇都宮北高校だからだと言えます。
数年前、ある生徒から「リーダーに必要なものは何ですか。」と尋ねられたことがありました。その時、私は、「何よりもまず熱さだ。」と答えました。「熱意がなくてはリーダーにはなれない。熱意のない者に人はついてこない。」と。「しかし、熱意だけでは組織は動かせない。リーダーに冷静な判断力がなくては組織は崩壊してしまう。」「熱さと冷静さの相反する要素を兼ね備えていることが必要だと思う。」と答えました。
世の中には様々なリーダー論がありますが、その一つに「リーダーは、ぶれてはいけない。」というものがあります。多くの人がイメージする理想のリーダー像と言えるでしょう。
一方で、アル・ビタンバリという人の「すごいヤツほど上手にブレる」という本の中には、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏をはじめ優れたトップリーダーの多くは、「一度決めたことにこだわることはせず、説得を受け入れ、ブレることで成功をおさめている。」と書かれていました。
イトーヨーカドーの創業者である鈴木敏文氏は、その著書「朝令暮改の発想」の中で、「朝令暮改となることを恐れてはいけない。」と説いています。「朝令暮改」という言葉は、「命令や法令がたびたび変更されてあてにならない。」という意味で、戒めの言葉として使われるものですから、一般的な考え方に反するものです。
一方でぶれてはいけないというリーダー論があり、一方で一度言ったことに固執せずにブレることを勧めるリーダー論がある。
どちらが正しいということはなく、いずれもそれぞれの場にあっては正しい在り方だと言えるでしょう。
このように、これから皆さんが進む社会では、一つの正解があって、それに向かって進めば良いということはありません。
一つの事象を多面的に見て、その時、その場での最善は何かを主体的に判断し、実行していくことが求められます。
その際、判断の基となるのが「哲学」です。
私はこの九ヶ月、皆さんに哲学を持つようにと繰り返し言ってきました。自分がいかに生きようとするか、どうありたいと考えるか。
これらの「生き方」「信念」といったものが、主体的判断の基となるのです。
本校の校訓である「励み 結び 拓く」の精神こそは、自らの哲学を考えるうえでの基盤となり、リーダーの資質として欠くことのできないものであります。
どんなに熱意があろうとも、どんなに冷静さがあろうとも、励む姿の見られない人、何事も中途半端で結果を示さない人、新たな世界を切り拓こうしない人のもとには人は集まりません。
人間性豊かで、我が国の伝統・文化を理解し、国際感覚をもって社会で活躍する人物として生きていくために、この三つを卒業後も人生の指針としてほしいと切に願います。
自らの励む姿、結ぶ姿、拓く姿を念頭において日々を送ってください。きっと皆さんの人生を豊かなものにしてくれるはずです。
保護者の皆様、改めましてお子様の御卒業おめでとうございます。皆様からお預かりしました大切なお子様方を、本日お返しいたします。三年間でかくも成長しました。
お子様方が卒業後も宇都宮北高校の同窓生として本校とつながっていくように、保護者の皆様におかれましても、保護者の皆様同士で築いた御縁、保護者の皆様と我々教職員との間で育んだこの御縁をこれからも大切にしていただき、いつまでも本校を愛し続けてくださいますようお願い申し上げます。
最後に、卒業生の皆さん。
未来を切り拓くのは君たちです。この国の、この世界の未来を君たちに託します。
君たちにはその力があります。
これほどの試練を乗り越えてきた皆さん。
逆境を知る者は強く、それを乗り越えた者は更に強い。
君たちの未来に幸多からんことを祈り式辞といたします。
令和三年三月一日
栃木県立宇都宮北高等学校長 笠原紀昭
卒業式を飾った花々



「伝えよう!本の魅力コンテスト」最優秀賞、優秀賞受賞
応募総数741名の中から最優秀賞1名、優秀賞5名ということですので、快挙と言えます。
最優秀賞:林之子さん 『でも女』(群ようこ/著 集英社)
仲良し3人組の新しい仲間はとっても鈍くさい女の子。私たちとは少しリズムが合わないみたいだけど、かっこいいお兄さんがいるらしいから…。女性の少~し嫌なところが、作者らしくズバズバ描かれている。あーいるこんな人とくすっとしたり、私だ…とドキッとしたり、飽きのこない短編集です。
優秀賞:中村七海さん 『15歳のテロリスト』(松村涼哉/著 KADOKAWA)
15歳の少年が真実を知るために事件を起こす。それは、復讐であり、少年の真の目的のためであった。登場人物一人一人の過去を知り、真実がわかったとき、あなたはこの少年を犯罪者といえますか?誰もが少年法について考え、希望ある未来を望む。心が震え、息をのむ世界からあなたは抜け出せなくなる。
優秀賞:森田楓彩さん『アウシュヴィッツの図書館』(アントニオ・G.イトゥルベ/著 集英社)
舞台は第2次世界大戦中のアウシュヴィッツ強制収容所。そこには命を懸けて8冊だけの秘密の本を守る少女ディタがいた。死と常に隣り合わせで生きていくディタからは、生きるということがどういうことか、勇気を持つのはいかに大切かを学ぶことができる。実際に著者が取材して得た感動の実話を、ぜひ。
このコンテストは、高校生同士の本のすすめ合いを一層促進するために、ポップやツイッターを想定した短文により、おすすめの本を紹介するもので、コンテストの審査を高校生である読書コンシェルジュ経験者が行うことで、同世代の感性を生かした読書推進につなげることを趣旨として、栃木県教育委員会が主催したものです。
入賞作品は栃木県のホームページと公式ツイッターで発信されています。
卒業生の方で各種証明書等を必要とされる場合は
証明書等の交付申請
のページをご確認ください。
栃木県警本部より、本校の同窓生に対する特殊詐欺の事案が発生しているとの連絡がありました。同窓生の皆様におかれましては、ご家族・関係者とも連絡を取り、特殊詐欺の電話には十分にご注意いただきますようお願いいたします。また、学校といたしましても個人情報の取り扱いには十分に注意しているところですが、同窓会名簿等の個人情報の取り扱いには十分にご注意いただきますよう、併せてお願いいたします。
教育相談の窓口一覧(PDF形式、令和7年5月栃木県教育委員会)です。