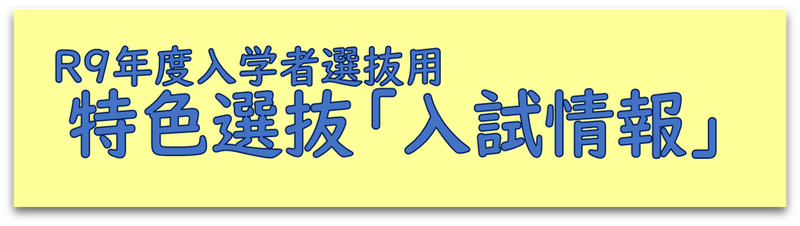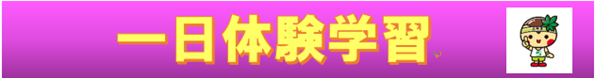文字
背景
行間
校長室だより
入学式を彩った花々



高校入試期間中の過ごし方について
この期間の過ごし方については、各クラスで担任の先生から話しがあったかと思いますが、このような自分で律する時間をどう使うかが高校生にとって重要です。
先月は、特色選抜のための学校休業日がありましたが、どう過ごしましたか。
校長室掃除の一年生が、「高校は、こんなに休みが多いんですね。」と驚いていましたが、このような期間を場当たり的にではなく計画的に実りあるものとするのが高校生です。
大学生になると、この時間が更に増えます。というより、毎日が自分で自分を律していくことになります。今からそのトレーニングをしておいてください。
さて、この一週間、各教科、各学年から課題が出されていることと思います。まずはそれを仕上げてください。そのうえで本を読む時間を作ってください。くれぐれもゲームだけで一週間が過ぎ去るなどということがないように。高校生なのですから。
では、何を読むか。今日は、「MIYATEEN VOL.12」で紹介されている本を紹介します。
「MIYATEEN」は、「宇都宮の高校生のための読書情報誌」として、宇都宮市立中央図書館から発行されています。
編集委員はすべて、宇都宮市内の高校に通う生徒です。したがって紹介される本は高校生が高校生に勧めるものとなりますので、きっと気になる本があると思います。そして、気になったら是非読んでください。
「MIYATEEN VOL.12」は、昨年末に各クラスに2部ずつ配布してありますが、見ていない人がいると思い、作者名・作品名のみここで紹介します。「MIYATEEN」は、とてもよくできた冊子ですので、登校後手にとってください。市立図書館にも配備されているので、この休業中に図書館で手にとることもできます。
今回の「MIYATEEN」は、「-WELCOME TO OUR THEATER-」という副題がついており、シネコン風の作りになっています。とても魅力的な作りになっているので、文字だけで紹介するのはとても味気ないのですが、紹介されている本は下記のとおりです。
「傘ももたない蟻たちは」加藤シゲアキ
「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」岩崎夏海
「人間失格」太宰治
「カラスの教科書」松原始
「ののはな通信」三浦しをん
「午後の恐竜」星新一
「三匹のおっさん」有川浩
「Another エピソードS」綾辻行人
「蜜蜂と遠雷」恩田陸
「フリーター、家を買う」有川浩
「本屋さんのダイアナ」柚木麻子
「悩み部の結成と、その結末。」麻木一樹
「永遠(とわ)をさがしに」原田マハ
「桜風堂ものがたり」村山早紀
「15歳のテロリスト」松村涼哉
「氷菓」米澤穂信
「今だけあの子」芦沢央
「フーガはユーガ」伊坂幸太郎
「吉祥寺の朝日奈くん」中田永一
「生のみ生のまま」 上・下」綿矢りさ
「ロマンシエ」原田マハ
「100日間、あふれるほどの「好き」を教えてくれたきみへ」永良サチ
「パラレルワールド・ラブストーリー」東野圭吾
「夜が明けたら、いちばんに君に会いに行く」汐見夏衛
「文房具の解剖図館」ヨシムラマリ、トヨオカアキヒコ
「老人と海」アーネスト・ヘミングウエイ
「神隠しの森 とある男子高校生、夏の記憶」梨沙
「嫌われる勇気」岸見一郎、古賀史健
「ほくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」ブレイディみかこ
「思い出のマーニー 上・下」ジョーン・ロビンソン
「MIYATEEN」には、本の概略と感想が編集した高校生によって記されていますので、登校後はそちらを参考にしてください。
卒業式 式辞
式 辞
朝夕の厳しい冷え込みはまだ残るものの、日増しに強まる春の陽射しに万物が胎動する季節となりました。
この佳き日に、PTA会長小野浩一様、同窓会長四十物英晴様の御臨席を賜り、保護者の皆様のご列席の下、栃木県立宇都宮北高等学校第三十九回卒業式を挙行できますことは、本校にとりましてこの上ない喜びであり、厚くお礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、多くの御来賓の方々をお招きすることができず、在校生がこの会場で卒業生の姿を見ることはできませんが、二年生は西体育館にて、一年生は配信された映像にて気持ちを一つに先輩方の卒業を祝福しています。
卒業生の皆さん、御卒業おめでとうございます。
また、保護者の皆様には、今日まで陰に陽に、慈しみ育ててこられた御苦労が実を結び、ここに無事お子さまが卒業を迎えられましたことを、心からお祝い申し上げます。
ただいま卒業証書を授与した三一五名の卒業生の皆さんは、本校に入学以来、「励み 結び 拓く」の校訓のもと、「高い志をもつ生徒」「全力を尽くす生徒」「リーダーとなる生徒」「国際人の資質をもつ生徒」を目指し、勉学はもちろん、部活動に、学校行事などに、常に真摯に取り組み、在校生にも良い手本を示してくれました。皆さんの歩みは、本校の歴史に新たなる一ページを記すとともに、一人一人が精神的にも肉体的にも見違えるような成長を遂げました。
今この席にある皆さんの姿を、指導に携わった我々も後ろの席の保護者の皆様と同様、様々な感慨を込めて見守っています。
皆さんほど多くの試練を強いられた学年はないと思われます。
第一に、大学入試改革のもと、多くの変更が皆さんの前に示されました。
大学入試センター試験を大学入学共通テストと名称を変更し、出題内容は思考力、判断力、表現力を問うものとすることが発表されました。
解答方法も、本校開校の前の年に始まった共通一次試験から四〇年続く、マークシート方式のみの解答であったものが、国語と数学では、記述式の解答が加わることとなり、英語では、四技能の力を見る試験となることが示されました。
これほど大きな変更が、一度に課され、未知なるものに取り組む不安を皆さんは強いられました。
ところが、一昨年末になって、記述解答も英語四技能試験も実施されないこととなり、それまでの取り組みは何だったのかと思わされることとなりました。
しかし、記述式解答試験の撤回には、一つの希望がありました。それは、撤回の決め手となったのが、皆さんと同年齢の高校生の声であったことです。直前での変更で混乱は生じたものの、私たち教員が何度訴えても止められなかった未熟な制度変更を、高校生の声によって止めることができたということに、私は感動を覚えました。
第二の試練は、昨年一月から世界中に猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症による様々な影響です。
突然の三ヶ月にも及ぶ臨時学校休業、学校再開後もあらゆる活動が制限されることとなり、高校生活にも進路選択にも大きな影響を及ぼしました。
運動部、文化部の各種大会やコンクールはことごとく中止され、これまでの成果を発揮することができずに、部活動を引退することとなりました。
本校においても、スポーツ大会や学校祭といった、皆さんが楽しみにしていた行事が中止となり、生き生きと活躍できる場を失いました。
どんなに辛く悲しかったことでしょう。
誰もが、言いしれぬ不安と寂しさを抱えながら過ごしたことでしょう。
できることなら皆さんに、もう一度、三年生として高校生活を全うしてもらいたいと考えるのは私一人ではないでしょう。
私が皆さんと時間を共有できたのは、わずか九ヶ月でした。あまりにも短い。
私が皆さんのはち切れんばかりの笑顔を、マスクなしに見ることができたのは、学年別ドッジボール大会の一日と、体育の授業を見に行った時だけでした。あまりにも少ない。
実は、皆さんにもう一度、三年生として高校生活を送ってほしいという私の願いは、私が皆さんともっと触れあいたかったという個人的な思いでもあります。
皆さんが北高への入学を強く望み、その願いを果たしたのに、思い描いた高校生活を送ることができなかったことを残念に思うように、私にとっても長年希望していた北高に勤務することができたのに、北高生と手を携え、よりよい北高作りに取り組むという目的を十分にできなかったことが残念でなりません。
北高生は、皆優れた資質を持ち、可能性に満ちたすばらしい人たちです。その人たちの教育に携わりたいというのが、私のかねてからの望みでしたから、それが十分にできないことの悔しさはなかなかぬぐい去れません。
しかし皆さんは立派でした。
置かれた境遇をしっかりと受け止め、前を向いて次なるステージに思いを致し、歩んできました。その姿はとても頼もしく、「さすが北高生」と思いました。
だからこそ皆さんには大きな期待が寄せられるのです。
本校の目指す生徒像の一つ「リーダーとなる生徒」について、皆さんは、自らが望むと望まざるとに関わらず、地域で職場で様々な組織の中で、リーダーとして活躍することを期待されています。
本校の教育目標が「人間性豊かで、我が国の伝統・文化を理解し、国際感覚をもって社会で活躍する人材を育成する。」とあるのも、リーダーとして活躍することを求められる、宇都宮北高校だからだと言えます。
数年前、ある生徒から「リーダーに必要なものは何ですか。」と尋ねられたことがありました。その時、私は、「何よりもまず熱さだ。」と答えました。「熱意がなくてはリーダーにはなれない。熱意のない者に人はついてこない。」と。「しかし、熱意だけでは組織は動かせない。リーダーに冷静な判断力がなくては組織は崩壊してしまう。」「熱さと冷静さの相反する要素を兼ね備えていることが必要だと思う。」と答えました。
世の中には様々なリーダー論がありますが、その一つに「リーダーは、ぶれてはいけない。」というものがあります。多くの人がイメージする理想のリーダー像と言えるでしょう。
一方で、アル・ビタンバリという人の「すごいヤツほど上手にブレる」という本の中には、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏をはじめ優れたトップリーダーの多くは、「一度決めたことにこだわることはせず、説得を受け入れ、ブレることで成功をおさめている。」と書かれていました。
イトーヨーカドーの創業者である鈴木敏文氏は、その著書「朝令暮改の発想」の中で、「朝令暮改となることを恐れてはいけない。」と説いています。「朝令暮改」という言葉は、「命令や法令がたびたび変更されてあてにならない。」という意味で、戒めの言葉として使われるものですから、一般的な考え方に反するものです。
一方でぶれてはいけないというリーダー論があり、一方で一度言ったことに固執せずにブレることを勧めるリーダー論がある。
どちらが正しいということはなく、いずれもそれぞれの場にあっては正しい在り方だと言えるでしょう。
このように、これから皆さんが進む社会では、一つの正解があって、それに向かって進めば良いということはありません。
一つの事象を多面的に見て、その時、その場での最善は何かを主体的に判断し、実行していくことが求められます。
その際、判断の基となるのが「哲学」です。
私はこの九ヶ月、皆さんに哲学を持つようにと繰り返し言ってきました。自分がいかに生きようとするか、どうありたいと考えるか。
これらの「生き方」「信念」といったものが、主体的判断の基となるのです。
本校の校訓である「励み 結び 拓く」の精神こそは、自らの哲学を考えるうえでの基盤となり、リーダーの資質として欠くことのできないものであります。
どんなに熱意があろうとも、どんなに冷静さがあろうとも、励む姿の見られない人、何事も中途半端で結果を示さない人、新たな世界を切り拓こうしない人のもとには人は集まりません。
人間性豊かで、我が国の伝統・文化を理解し、国際感覚をもって社会で活躍する人物として生きていくために、この三つを卒業後も人生の指針としてほしいと切に願います。
自らの励む姿、結ぶ姿、拓く姿を念頭において日々を送ってください。きっと皆さんの人生を豊かなものにしてくれるはずです。
保護者の皆様、改めましてお子様の御卒業おめでとうございます。皆様からお預かりしました大切なお子様方を、本日お返しいたします。三年間でかくも成長しました。
お子様方が卒業後も宇都宮北高校の同窓生として本校とつながっていくように、保護者の皆様におかれましても、保護者の皆様同士で築いた御縁、保護者の皆様と我々教職員との間で育んだこの御縁をこれからも大切にしていただき、いつまでも本校を愛し続けてくださいますようお願い申し上げます。
最後に、卒業生の皆さん。
未来を切り拓くのは君たちです。この国の、この世界の未来を君たちに託します。
君たちにはその力があります。
これほどの試練を乗り越えてきた皆さん。
逆境を知る者は強く、それを乗り越えた者は更に強い。
君たちの未来に幸多からんことを祈り式辞といたします。
令和三年三月一日
栃木県立宇都宮北高等学校長 笠原紀昭
卒業式を飾った花々



「伝えよう!本の魅力コンテスト」最優秀賞、優秀賞受賞
応募総数741名の中から最優秀賞1名、優秀賞5名ということですので、快挙と言えます。
最優秀賞:林之子さん 『でも女』(群ようこ/著 集英社)
仲良し3人組の新しい仲間はとっても鈍くさい女の子。私たちとは少しリズムが合わないみたいだけど、かっこいいお兄さんがいるらしいから…。女性の少~し嫌なところが、作者らしくズバズバ描かれている。あーいるこんな人とくすっとしたり、私だ…とドキッとしたり、飽きのこない短編集です。
優秀賞:中村七海さん 『15歳のテロリスト』(松村涼哉/著 KADOKAWA)
15歳の少年が真実を知るために事件を起こす。それは、復讐であり、少年の真の目的のためであった。登場人物一人一人の過去を知り、真実がわかったとき、あなたはこの少年を犯罪者といえますか?誰もが少年法について考え、希望ある未来を望む。心が震え、息をのむ世界からあなたは抜け出せなくなる。
優秀賞:森田楓彩さん『アウシュヴィッツの図書館』(アントニオ・G.イトゥルベ/著 集英社)
舞台は第2次世界大戦中のアウシュヴィッツ強制収容所。そこには命を懸けて8冊だけの秘密の本を守る少女ディタがいた。死と常に隣り合わせで生きていくディタからは、生きるということがどういうことか、勇気を持つのはいかに大切かを学ぶことができる。実際に著者が取材して得た感動の実話を、ぜひ。
このコンテストは、高校生同士の本のすすめ合いを一層促進するために、ポップやツイッターを想定した短文により、おすすめの本を紹介するもので、コンテストの審査を高校生である読書コンシェルジュ経験者が行うことで、同世代の感性を生かした読書推進につなげることを趣旨として、栃木県教育委員会が主催したものです。
入賞作品は栃木県のホームページと公式ツイッターで発信されています。
校長室より『ビブリオバトル』
1,発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる。
2,順番に一人5分間で本を紹介する。
3,それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを2~3分行う。
4,全ての発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加者全員一票で行い、最多票を集めたものを『チャンプ本』とする。
令和2年12月6日(日)に「高等学校ビブリオバトル2020栃木県大会」が、栃木県庁にて開催されました。
コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、例年よりも規模を大幅に縮小し、県の関係者以外は生徒のみというものでした。
既に全国大会の中止が決まっておりましたが、予選から各会場とも熱い戦いが繰り広げられました。
本校からバトラーとして参加する者はいませんでしたが、読書コンシェルジュの4名が運営に携わりながら参加しました。決勝戦のディスカッションでは、本校生の質問が最も多く活躍していました。
チャンプ本には、小山工業高等専門学校の塚田蓮大さんが紹介した『屋上のテロリスト』(知念実希人/光文社文庫)が選ばれました。
決勝には、以下の5作品が残りました。(発表順)
1,『答えより問いを探して』(高橋源一郎/講談社)
2,『いのちの車窓から』(星野源/KADOKAWA)
3,『夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく』(汐見夏衛/スターツ出版文庫)
4,『キケン』(有川浩/新潮社)
5,『東大の先生!文系の私に超わかりやすく数学を教えてください!』(西成活裕/かんき出版)
予選各グループで紹介された作品は以下のとおりです。
1,『コンビニ人間』(村田紗耶香/文春文庫)
2,『人間椅子』(江戸川乱歩/角川ホラー文庫)
3,『小公女』(フランシス・ホジソン・バーネット/新潮文庫)
4,『希望の糸』(東野圭吾/講談社)
5,『多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。』(Jam/サンクチュアリ出版)
6,『アーモンド』(ソン・ウォンピョン/祥伝社)
7,『桜のような僕の恋人』(宇山佳祐/集英社文庫)
8,『たとえ明日、世界が滅びても今日、僕はリンゴの木を植える』(瀧森古都/SBクリエイティブ)
9,『コーヒーが冷めないうちに』(川口俊和/サンマーク出版)
10,『僕は、字が読めない。ー識字障害と戦いつづけた南雲明彦の24年』(小菅宏/集英社インターナショナル)
11,『彩雲国秘抄 骸骨を乞う』(雪乃紗衣/角川文庫)
12,『世界から戦争がなくならない本当の理由』(池上彰/祥伝社新書)
来年は、バトラーとしての参加、読書コンシェルジュとしての参加、一般観戦者としての参加と多くの生徒が参加することを期待します。
全国高等学校文化連盟賞受賞
大川さんの弁論は10月31日までネット上で公開されていますので、「WEB SOUBUN」で検索し、御覧ください。
校長室より「山崎正和『劇的なる日本人』
8月21日、山崎正和氏が亡くなりました。山崎氏は、劇作家、評論家として日本の文化に大きく貢献した方です。
大学2年の時に演劇学の講義を取った時読んだ『世阿弥』や、大学3年の時に森鴎外のゼミに参加していた時読んだ『鴎外 戦う家長』の文筆の鋭さに圧倒されて以来、山崎氏の著作を読むようになりました。
現代文の教科書教材として取り上げられている『劇的なる日本人』は、授業で何度も扱いましたが、何度読んでも飽きることはなく、読むたびに優れた日本人論だと感じています。
優れた日本人論・日本文化論としては他に、『柔らかい個人主義の誕生』や『日本文化と個人主義』などがあります。
「消費社会の美学」という副題が付いた『柔らかい個人主義の誕生』は発表時たいへん話題となり、各界の著名人との対談集『柔らかい個人主義の時代』が発刊されています。
対談集では、丸谷才一氏との都市論『日本の町』が秀逸です。
また、『柔らかい自我の文学』や『近代の擁護』など、文学評論や文明評論も多く出版されています。
先日の外山滋比古氏に続き、巨星墜つの感を否めません。
2学期始業式式辞
今回も放送による始業式となりました。したがって、また校歌を歌うことができません。皆さんの心の中で歌ってください。
誰もが経験したことのない、非常に短い夏休みが終わり、今日から誰も経験したことのない長い長い2学期が始まります。
1学期の終業式で皆さんに書いてもらった夏休み中にしたいと思うことはできたでしょうか。
あっという間の2週間で、何かしようと思う間もなく過ぎてしまったという人もいるのではないでしょうか。
私は考えていたことの一部しか実行することができず、改めて計画を立てることの大切さと、時間の貴重さに気づかされました。また、不測の事態に備え、早め早めの行動を習慣化しなくてはいけないのだなとも感じました。
おそらくは皆さんも時の経過の早さに驚いていることと思います。今後も何が起こるかわからない状況は続くことと思いますので、先を見越した行動と、代替プランを用意すること、時間を有効に使うことを考えてください。
さて、2学期始業式にあたり、3点ほどお話しししたいことがあります。
今回もプリントを用意しましたので、空欄への記入や余白へのメモをしながら聞いてください。
空欄への記入は日本語ディクテーションのつもりで、耳で聞いた言葉を文字に、漢字仮名交じりで書いてください。漢字が思い浮かばない人は、仮名で書いておいて後で辞書で調べてください。
まず最初に皆さんにお話ししたいことは、長い2学期の過ごし方についてです。
例年になく長い2学期の過ごし方として、生活のあらゆる面で、緊張と弛緩を適宜繰り返してほしいということです。
人間の神経は緊張させたままだと不調を来してしまいます。適宜緩めてしなやかさを保つ必要があります。しなやかさがないと柔軟な発想はできませんし、本来の能力を発揮することができなくなります。
ゴムやバネといったものは、強く引っ張って緊張させたままにしておくと、本来持つ役割を果たせなくなってしまいます。
緊張の限界を超えたゴムは切れてしまいますし、伸ばしたままの状態で長く置くと、縮まなくなってしまいます。
従って、心身の健康を保つうえでも、緊張と弛緩を適宜繰り返しながら長い2学期を乗り越えてほしいと思います。
新型コロナウイルス感染症の感染予防については、なお緊張感を持って取り組んでもらわなくてはなりません。
報道によると、他県では、100名近くの感染者が部活動を中心に出た高校や、20名以上の感染者が出た高校があります。また、大学のサークル内での感染も報じられているところです。
自分たちは大丈夫ということは決してありませんので、緊張感を持った活動をお願いします。
次に、夏休みのある八月という月に関連して思うところです。
北高のホームページ校長室よりに「八月がくるたびに」という記事を掲載し、日本人いや世界中の人たちは、昭和20年(1945年)の8月を忘れてはいけないと訴えましたが、日本人にとっては多くの意味ある日が続きます。
8月6日は広島に原爆が投下され、14万人の命が奪われた日、8月9日は長崎に原爆が投下され7万人の命が奪われた日、8月12日は群馬県上野村に日本航空機が墜落して520名の命が失われた日、8月13日は盂蘭盆会(うらぼんえ)の迎え盆、8月15日は終戦記念の日、8月16日は送り盆と昨日まで意味ある特別な日が続きました。
因みに、日常と異なる非日常の特別な日のことを「晴れ」と言います。「晴れ着」や「晴れの舞台」などと使われる「晴れ」です。「晴れ着」というのは、特別な日、「晴れの日」に着る着物だから「晴れ着」と言うのです。したがって、始業式の今日も、本校生にとっては「晴れの日」となります。たとえ雨が降っていても「晴れの日」なのです。入学式や卒業式、結婚式などで来賓の方が「この晴れの日に」というフレーズを使い、外は土砂降りの雨ということがあっても、「あの人、いくら用意した原稿だからといっても、こんな雨なんだから言い換えればいいのに」などと思わないでください。「雨が降っても晴れの日なのです。」
もし、そのような場に遭遇し、あなたの隣の人が「雨の日に晴れの日なんて言っているよ。」と笑っているようなことがあったら、「晴れの日というのは特別な日ということらしいですよ。」と教えてあげてください。この時大切なのは、「らしいですよ。」の「らしい」という言葉です。決して、「晴れっていうのは、特別な日のことなんだよ。知らないの。」などと言わないこと。「らしい」を使って、「自分もよくは知らないのだけれど」という雰囲気を出すこと。これが円滑な人間関係を構築する秘訣です。
特別な日、非日常を「晴れ」というのに対して、日常をいうことばを「褻(け)」と言います。声だけで説明するのが難しい漢字なので辞書で調べてください。「晴れ」と「褻(け)」、是非知っておいてください。
話を八月の話題に戻します。
一昨日の終戦記念の日、NHKは、原爆の開発に取り組んでいた日本人科学者のドラマを放送しました。京都帝国大学物理学教室において、実際にアトミック・ボム(原子爆弾)をアメリカ・ソ連よりも早く開発しようとしていた若者たちの姿が描かれていました。
ドラマでは、「科学者が兵器を作ることをどう考えるのか」と苦悩する場面や、原爆が投下された広島の町を見て、「自分たちが作ろうとしていたのはこれだったのか。」と嘆息する場面がありました。
私が皆さんに「哲学を持たない科学者ほど恐ろしい者はないから哲学を持ってほしい」といっていることの背景にはこのような事があります。
戦時中に日本の大学で実際におこわなわれていたこととしては、九州帝国大学医学部で行われたアメリカ人捕虜に対する生体解剖事件があります。この事件を題材とする小説が遠藤周作氏の『海と毒薬』です。『海と毒薬』は、今年も新潮文庫の100冊に入っていますので入手しやすいと思います。
新潮文庫の100冊の中には、広島の原爆投下後に降った雨によって被爆した女性を描いた、井伏鱒二氏の『黒い雨』もあります。
『黒い雨』といえば、『黒い雨訴訟』と言われる裁判の一審判決が先月29日に広島地方裁判所であり、国と広島県、広島市が控訴したのは、五日前の12日のことです。
75年前に起こったことは、まだ未解決なままなのです。
また、昨日16日は送り盆の日で、京都では五山の送り火が灯される日でした。今年はコロナウイルス感染症の感染予防のため、大幅に縮小して実施されましたが、これに関して耳を疑うニュースがありました。8月8日の夜に、送り火が行われる山に何者かが登って無断で私有地に入り、大がかりな照明などを用いてライトアップしたそうです。大文字保存会の理事長さんは、「お盆に迎えた先祖の霊を送る大切な儀式を汚す行為だ。」と憤りと嘆きの言葉を発していました。人の思いや、文化を解さない愚かなパフォーマンスといわざるを得ません。
改めて皆さんには、文化を理解し人の気持ちがわかる人間として人々をリードしてほしいと思いました。
最後に、皆さんに是非意識してもらいたいことをお話しします。
私は、本校に赴任するまでに、石橋高校に10年、宇都宮東高校に14年、鹿沼高校に3年と、本校に似通った高校に勤務してきました。
その間、宇都宮北高校を常に他校比較の対象校として、成績の推移や進路状況を見てきました。
その時思っていたことと、本校に勤務して中から皆さんの様子を見て感じたことがあります。
それは、学業面に関しては、もう少し頑張ることで更に進路選択の幅が広がるだろうにということです。
そこで、頭に浮かんだのが、盛唐の詩人、王之渙の「鸛鵲楼(かんじゃくろう)に登る」という五言絶句です。
国語便覧の唐の時代の地図のページに載っていますので、後で見てもらいたいと思いますが、その詩の中に、「千里の目を窮めんと欲し 更に上る一層の楼」という句があります。
「遙か彼方まで見ようと思って、もう一つ上の階に上る」という意味です。
皆さんも知っているように、一つ上の階に行くと見える景色が変わります。
より高みに身を置くことができると、より広くより遠くを見ることができます。
より広い視野を持つことは、より豊かな人生を送ることにつながります。
北高生は、今一歩勉学に励むことで、その成果が実を結び、より広い進路を切り拓き、人生をよりよく変えることができると思いました。
そこで、北高生一人一人が、王之渙の、「更に上る一層の楼」という言葉を意識して、学業に取り組むことを願うものです。
以上3点申し上げ2学期始業式の式辞とします。
校長室より「八月がくるたびに」
本校では、平和教育の一環として修学旅行で広島を訪れ、平和公園・平和記念資料館にて原爆の恐ろしさを知り、命の尊さ、平和の尊さを実感として学んでいます。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度は、修学旅行での広島訪問を断念せざるを得ませんでした。ただし、貴重な平和学習の機会をなくしてしまいたくはないので、現在広島訪問に代わる平和学習の方法を検討しているところです。
8月9日には、長崎に原爆が投下され、8月15日に終戦となった昭和20年(1945年)の8月を私たち日本人は、いや世界中の人たちは決して忘れてはいけません。
「八月がくるたびに」、毎年8月になると、この言葉が私の脳裡に浮かびます。
「八月がくるたびに」というのは、私が小学校の時に読んだ、おおえひで・作、篠原勝之・絵になる本の題名です。1971年に発刊されたこの本は、現在全く異なる形態で出版されているとのことですが、篠原勝之さんの絵とともに訴えかけるおおえさんの言葉は今も忘れることができません。「だれが… どうして? だれが… どうして?」の言葉は、それこそ8月がくるたびに何度も何度も浮かび上がります。
私がこの本に出会ったのは、この本がその年の読書感想文コンクールの課題図書だったからです。当時本好きではなかった私が、とにかく何か書かなくてはいけない、でも何を読んだらよいかわからないでいる時に母親が買ってきたものだと記憶しています。「8月がくるたびに」という言葉と、「だれが どうして」という言葉は、その後もずっと私の体に張り付いて離れませんでした。
3年前に、栃木県学校図書館協議会長となり、読書感想文コンクールを主催する立場となった時に、1971年の課題図書を調べてみたところ、高校生向けの課題図書には渡辺淳一氏の『花埋み』が選定されていました。
『花埋み』は、日本最初の女性医師となった荻野吟子氏の生涯を描いた作品です。その劇的な人生から演劇やテレビドラマにもなった作品であり、高校生の皆さんに読んでほしい一冊です。
立場上言うのではなく、全国学校図書館協議会では、小中高校生それぞれの年代にふさわしく心に残るであろう作品を課題図書に選定しています。別に紹介しようと思っている重松清氏の『その日の前に』も2006年度の課題図書に選定されています。何を読めばいいかなと思ったら、課題図書を選択肢の一つにしてはいかがでしょうか。今年の高校生の課題図書は、谷津矢車『廉太郎ノオト』、マイケル・モーパーゴ『フラミンゴボーイ』、マーク・アロンソン、マリナ・ブドーズ『キャバとゲルダ:ふたりの戦場カメラマン』の三冊です。
1学期終業式 式辞
改めて、皆さんこんにちは。
ここからは、1学期の締めくくりとなる終業式の式辞として話しをします。
始業式と同様、放送によるものとなってしまいました。
私が皆さんの前で話をするのは、入学式で1年生の入学を許可し、式辞を述べた時だけであり、未だ2・3年生の前で話をすることができていません。
廊下ですれ違うことがあっても、お互いにマスク越しの顔しか見ることができません。おそらく、私を見て校長だと認識してくれる人は数少ないことでしょう。
いつになったら皆さんのマスクなしの顔を見ることができるのか。皆さんの顔を見ながら話をすることができるのか。その思いは募るばかりです。
しかしながら、連日耳にする過去最多の感染者数という報道には、危機感を覚えずにはいられません。改めてマスクの着用、手洗い、三密を避けた行動に徹することが求められます。
6月から通常登校となりましたが、決して通常の学校生活が送れたわけではありませんでした。登下校の制約、授業内容の制約、休み時間の行動の制約、部活動の制約、学校行事の制約と多種多様な制約を強いられました。
生徒誰もが楽しみにしていた学校祭も中止とせざるをえませんでした。2年生の修学旅行も日程と旅行先が変更されました。今後の状況によっては他の行事等の変更・中止があるかもしれません。
しかし、ここで生徒の皆さんに知っていてもらいたいことがあります。
それは、皆さんの学校生活の思い出がより多く残せるよう、先生方は最大限検討・協議していたということです。
こうすれば出来るのではないか。ああすればできるのではないか。ここまでならやれるのではないかと、何度も何度も計画を練り直し、次の案、更にその次の案と生徒の皆さんからの意見も聞きながら検討し、それでも難しいという結論に達し、実施に向け何度も考えたものが実行不可能となり、変更・中止に至ったということを知っておいてください。今後も何ができるか。どうすればできるかを考えていきたいと思います。
さて、今日は、たった2ヶ月しかなかった1学期の終業式となるわけですが、今日は皆さんに、「令和2年度第1学期終業式校長式辞メモ」というプリントを用意しました。そこに記入しながら話を聞いてください。
ということで、机の上にプリントと筆記具は出ているでしょうか。このメモには、あらかじめ記入を要求されていることだけでなく、話しを聞きながら、書きとどめておきたいこと、疑問に思ったことなどを余白や裏面に書いていってください。使い方は自由です。目的は、ただ聞き流すのではなく、意識を持って聞いてもらうことです。
まず、学年、クラス、出席番号と氏名を記入してください。
では、最初に一学期の振り返りをしてもらいたいと思います。1学期が始まる際に皆さんが立てた目標を記入してください。時間は30秒です。
次に、1学期の間に自分ができたことと、できなかったことを書いてください。時間は1分です。書き終わらない人、思い浮かばない人は、家に帰ってからじっくり1学期の振返りをしてください。
それでは次に、皆さんが夏休みにしたいことを書いてください。
例年に比べて短く、制約の多い夏休みではありますが、その中で皆さんがしたいと思うことを書いてください。時間は30秒です。
終業式は、このように学期中を振り返り、次のスタートのための区切りの行事であり、自己のアイデンティティーを再確認する日です。
そしてまた、自分が北高の生徒であることを再認識し、帰属意識を高める日でもあります。
それを象徴するのが、校歌の斉唱です。しかし、それができません。
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、今年度は未だ校歌を歌うことができていません。1年生は北高の校歌をどれだけ歌えるでしょうか。
在学中は入学式や卒業式、始業式や終業式といった時の慣例だから歌うものと感じている人がいるかもしれませんが、校歌の持つ意味が本当にわかるのは卒業してからです。
卒業後、北高の校歌を耳にし、一緒に歌った時に北高の一員であることの帰属感が実感されます。
それが甲子園のグラウンドであったり、高校生クイズの決勝の場で、テレビから北高の校歌が流れてきたりすると感無量です。
一昨年の夏の甲子園での金足農業の全力校歌が話題となったことは記憶に新しいところですが、肩を組み合い、共に校歌を歌えることの素晴らしさは在校中はなかなか理解できないかもしれませんが、皆さんとともに声高らかに校歌を歌える日を私は心待ちにしています。
北高のホームページには、校歌のアイコンがあり、このアイコンをクリック・タップすると校歌の歌詞が表示されるとともに、吹奏楽の演奏に乗った美しい歌声が流れます。パソコンでも、スマートホンでも聴くことができます。
北高の校歌をうまく歌えないという人は、ホームページにある校歌を使って練習するとうまく歌えるようになるでしょう。
式典で校歌を歌うことができないというのも、制約の一つですが、本当に様々な所で制約を受け続けている今の境遇はとても辛いことです。
明治時代の小説家・ジャーナリストである国木田独歩という人は、その日記『欺かざるの記』の中で、「忍耐と勤勉と希望と満足とは境遇に勝つものなり」と言っています。
このコロナ禍の境遇に勝つものは、一人一人の、「忍耐と勤勉と希望と満足」なのでしょう。
私たちは、今まで十分堪え忍んできたと思いますが、感染の終息には、尚、忍耐が必要なのかもしれません。そして、何事にも勤勉に取り組み、希望と満足をもって歩むことによって、今の境遇に打ち勝ちましょう。
最後に、私が始業式で皆さんに話したことの振り返りで終えたいと思います。
私が始業式で話した、北高生に実践してもらいたいと言ったことを覚えているでしょうか。覚えている人はメモの括弧内に記入してください。
私は、皆さんに「哲学を持つこと」を実践してもらいたいと言ったのですが、その取り組みを皆さんはしてくれたでしょうか。
では、哲学を持つために必要なこととして挙げたことは覚えているでしょうか。覚えている人は二つの括弧内に記入してください。
それは、多くの人と接し、多くの本を読むことです。コロナウイルス感染症の感染拡大予防の点からは多くの人と接することは今は避けなくてはなりませんが、その分、多くの本を読んでください。本の世界でも多くの人に接する事ができます。
北高ホームページには、校長室よりのアイコンがあります。そこには、皆さんに伝えたいことや図書の紹介が載っています。最新の図書紹介では、ブレイディみかこさんの「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」について掲載しましたが、この本を読むことで、遠く離れたイギリスに住む中学生と、彼に関連する多くの人に接する事ができます。また、ブレイディみかこさんの母校、福岡県立修猷館高等学校に関連して紹介した城山三郎氏の作品を読めば、そこに描かれた人々の生き様に接し、自分の生き方に思いをいたすことができます。直接人に接することができない分、読書によって、間接的に多くの人と接してください。
以上で、令和2年度第1学期終業式の校長式辞を終えます。
校長室より「読書感想文について」
また、読書感想文は、過去の自分との出会いをもたらしてくれます。数年後、数十年後、過去に自分が書いた読書感想文を読み返した時に、当時の自分の考えや感動を思い起こし、ああ、私はこういう子どもだったんだな、こういう人間だったんだなと振り返って、その時の感動や考えを基に新たな歩みを始めるきっかけとなります。
私は、1学期の始業式で生徒の皆さんに「哲学を持ちなさい」と言いました。
哲学というのは、「人間が生きるということはどういうことか」「自分はいかに生きるか」ということを考えることです。
何かするにあたって、これは良いことなのか悪いことなのか、自分はどう行動したら良いのかの基準を持つことです。
哲学を持つためには、自分自身の体験だけでは十分ではありません。本を読み、自分が直接体験することのできない世界にも、本の世界に自分を置いて間接的に体験し、考えることが大切です。
読書感想文は、その本を読んで感じたことの記録だけでなく、書くことによって考えを深め、それによって自分自身を見つめ、書くことを通して思考の世界へ導いてくれます。
皆さんが、多くの本を読み、書くことによって、皆さんの哲学を持ってくれることを期待しています。
全国高等学校総合文化祭出場(弁論部門)
本校からは、3年生の大川英莉さんが弁論部門に出場します。
大川さんは、第56回栃木県高等学校国際理解弁論大会において、優秀賞・栃木県教育委員会教育長賞を受賞し、栃木県代表として参加します。
本来であれば、高知県室戸市で発表する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により一堂に集まっての開催ができず、WEB上での発表となりました。
「WEB SOUBUN」で検索していただければ入ることができますので、ぜひ御覧ください。
学校では、1学期終業式の前に壮行会を開き、大川さんの栄誉を讃え、生徒教職員一同で喜びを共有したいと考えております。
本来であれば、壮行会の場でもっと大勢の生徒が紹介され、全国高校総体等での活躍が期待されたであろうことを思うと、返す返す残念でなりませんが、次のステージで頑張ってくれることを祈っております。
校長室より「ブレイディみかこ『ほくはイエローでホワイトで、……』」
次回は映画を離れて、ブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』ですと予告してから、ちょうど2ヶ月が経ってしまいました。申し訳ありません。
この本は、私が2019年に読んだノンフィクション、エッセイの中で、最も面白く、最も生徒に読んでほしいと思ったものです。
新潮社が発行する文芸雑誌『波』の2018年1月号から2019年4月号に連載されたものを、2019年6月に単行本として出版し、現在もなお書店に平置きされ、売り上げ上位に位置しています。
日本人の母親(著者)と白人英国人の父を持つ息子の中学校生活によって、イギリスの今が描き出されています。レイシズム、LGBTQ、貧困、差別といった様々な問題について考えることができるもので、是非とも読んでほしい一冊です。
赤坂ACTシアターに2度見に行ったミュージカル「リトル・ダンサー(原題ビリー・エリオット)」の背景にも触れられていて、そうだったのかと理解が深まったことも私としては面白く読めました。
著者のブレイディみかこさんは、マスコミにも頻繁に出るようになりましたので、知っている人もいるかと思いますが、本に書かれている著者紹介には、「保育士・ライター・コラムニスト。1965年福岡市生まれ。県立修猷館高校卒。音楽好きが高じてアルバイトと渡英を繰り返し、1996年から英国ブライトン在住。ロンドンの日系企業で数年間勤務したのち英国で保育士資格を取得、「最低保育所」で働きながらライター活動を開始。2017年に新潮ドキュメント賞を受賞し、大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション大賞候補となった『子どもたちの階級闘争-ブロークン・ブリテンの無料託児所から』(みすず書房)をはじめ、著書多数。」とあります。
ブレイディみかこさんの卒業した修猷館高校というのは、福岡県内屈指の進学校で、今年度の国公立大学合格者は299名、東大に16名、京大に11名、九州大に131名が合格しています。私の大学時代の剣道部の同期にも修猷館高校の卒業生がいますが、母校に対する誇りを持っていました。卒業生は著名人も多く、元総理大臣の広田弘毅もその一人です。第二次世界大戦後の極東国際軍事裁判で文官としては唯一のA級戦犯として有罪判決を受け死刑となった人ですが、その生涯を描いた、城山三郎の『落日燃ゆ』を読むと、彼の生き様に感慨を覚えることと思います。
因みに、私は高校時代、城山三郎の小説を貪るように読んだ時期がありました。きっかけは、総理大臣として金解禁を断行し、東京駅で凶弾に倒れた浜口雄幸を描いた『男子の本懐』を読んだこと。そこから、『落日燃ゆ』、来年のNHK大河ドラマの主人公となる新一万円札の顔、日本資本主義の父である渋沢栄一を描いた『雄気堂々』、三井物産社長から国鉄総裁となった石田禮助を描いた『祖にして野だが卑ではない』、『官僚たちの夏』、直木賞を受賞した『総会屋錦城』と続きました。
さて、話しを『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』に戻します。とにかく引き込まれます。優れた文章力です。出会うべき一冊と言えるでしょう。
次回は、映画に戻って、浅田次郎さんの『地下鉄(メトロ)に乗って』です。
県の警戒度が引き上げられました。
生徒の皆さんは、学校再開前後の緊張感を思い出し、3密の回避、マスクの着用、手洗い、換気、消毒の徹底などの基本的な感染症対策に心がけて通常登校が続けられるよう協力してください。
テスト週間
先々週から職員室廊下では、先生に質問したり学習したりする生徒の姿が多くみられるようになりましたが、一昨日の土曜日には100名弱の生徒が登校して学習していました。
高校入学後初めての定期テストに備えようという気持ちからなのでしょう。1年生の姿が一番多く見られました。
しかし、学習への集中度は1年生よりも2年生、2年生よりも3年生の方が高いと感じられました。
梅雨寒の中、体調を崩すことなく万全の体制で期末試験に臨んでください。
また、雨で見通しが悪くなっています。登下校には十分注意してください。
6月一ヶ月間で、本校生の交通事故が6件に及びました。危険な自転車の走行に対する苦情や心配の声も多く寄せられています。SHRで担任の先生を通して繰り返し注意しているところですが、改めて注意を促したいと思います。被害者となることも加害者となることもないよう十分注意してください。
校長室より「進路資料発刊に寄せて」
まずは、過日発刊されました「進路資料」について。
配布された令和2年度進路資料を生徒の皆さんはもちろん、保護者の皆様も御覧いただき、進路選択にお役立てください。
先輩方の合格体験記や後輩へのアドバイスのページはたいへん参考になりますので、是非お読みください。
以下は、巻頭言として掲載した私の文章です。
令和2年度進路資料が完成しましたので皆さんの許にお届けします。
3年生にとっては3冊目となる進路資料ですが、過去2冊の進路資料を今までに何度読み返しましたか。
受験産業を中心に様々な進路に関する書籍が出版されていますが、皆さんにとって本誌に勝る進路情報誌はありません。なぜなら、本誌は宇都宮北高の生徒を読み手として作成されたものだからです。
本校の職員が、本校生の進路研究に役立つようデータを分析し検討した成果であり、何よりも、皆さんの先輩方が、宇都宮北高校生として進路決定に至った足跡が掲載されています。
つまり、宇都宮北高校の生徒である君たちが、今後どうすればよいかの指針がここにはあります。
是非熟読し読み返して、自分の進路を切り拓く手立てとしてください。
進路とは正に自ら切り拓くものです。しかし、決して孤独な営みではありません。友人や保護者、先生といった協力者がいて成り立つものであり、あなたも同級生や後輩達の協力者なのです。
「受験は団体戦」という言葉がありますが、この言葉に疑問を感じる人がいるかもしれません。
なるほど、試験を受けるのは自分ですし、試験中、他の人の力を借りて解答を書けばカンニング(不正行為)となり、受験資格を剥奪されるだけでなく、成人であれば名前まで報道されることもあります。
しかし、試験そのものは孤独に問題と取り組むものであっても、試験に至るまでの苦しい時期を乗り越えるためには、友人や保護者、先生といった人たちの支えが必要なのです。
一方で、受験生が試験の合否を自分の実力以外に転嫁し、努力が十分でないにも関わらず、他者の協力が足りなかったから自分は不合格になったのだと考えたり、自分の実力が上がらないのは他者の協力が足りないからだと思う気持ちを持ってはいけません。進路の決定は、最終的に自分が責任を負うものです。
良い結果も、悪い結果も自分が受け止めなくてはいけません。自分の実力と努力に負う所は大きいのです。
人生の岐路はいたるところに現れてきます。
その都度、どちらに進むか決断しながら歩んでいかなくてはなりません。後でこうしておけばよかったという思いはあっても、あのときの自分にとってはあれが精一杯だったと思えること、自分が決断して決めた事だからと思えることで前に進むことができます。ところが、自分以外の力によって決まってしまったという思いがあると、過去にこだわり、現状に満足せず、未来に向かって進むことができなくなってしまいます。
皆さんにとって目の前にある岐路は、高校卒業後どうするかといったことでしょう。進学するのか就職するのか。進学するならどういう学問を選ぶのか。どこで研究するのかといったことを選ばなくてはいけません。将来設計がしっかりできていて、この大学のこの学部でこの教授のもとにこの研究をしたいという明確な目標を持って進路を決定することができれば理想的ですが、自分の実力が伴わなければそれも叶うものではありません。ですから、既に目標設定ができている人は、その実現に向けて実力をつけてください。目標設定が十分でない人は、多くの本を読み考えてください。自分が取り組みたいと思うものがあれば、図書館に行って関連する本を読み、これだと思えば、執筆者が誰か確認し、学者であれば、どこの大学の教員なのか調べ、そこに入る力が自分にあるのか、学力はあってもその大学に進んでよいのかということを保護者や先生と相談して進路の明確化を図ってください。まずは、この「進路資料」を手がかりにしてください。
結びに、本資料の作成に御尽力いただいた先生方と貴重な体験談を提供していただいた卒業生の皆さんにに感謝の意を表します。ありがとうございました。
校長室より「新たなステージへ」
しかし、日本国内や世界の感染状況に目を向けると、決して安閑としていられないことが見て取れます。
また、県内公立校最大規模の本校にあっては、他校で可能なことも本校では実施困難なことが多々あります。
生徒の皆さんは、今後も感染予防に向けた行動に心がけ、日々の生活を充実したものにしてください。
校長室より「横山秀夫『影踏み』」
通常登校後も、図書紹介を継続していきたいと思います。ただ、今までの映画原作を中心としたものだけでないものも随時とりあげていきたいと考えております。
さて、横山秀夫さんは、最新作『ノースライト』が、2020年本屋大賞第4位(大賞は、凪良ゆうさんの『流浪の月』でした。)となり、『クライマーズハイ』『半落ち』『64』など有名作品を多く持つ作家です。『ノースライト』は、横山ミステリー史上最も美しい謎と謳われる作品ですので、長編ですがミステリー好きに限らず挑戦してはいかがでしょうか。
『影踏み』は、横山氏と、篠原監督、主演の山崎まさよしさんが意気投合し映画化となったという裏話があります。主人公の意識の中に、亡くなった双子の弟が存在するという設定で、のび師という犯罪者が主人公となるため、篠原監督からは「高校生にすすめるのはどうなのかわからない。笠原が見て大丈夫と思ったら紹介してくれ。」と封切り前に言われました。映画では小説に比べ明るい結び方となっていました。
因みに、山崎まさよし主演の篠原作品は、『月とキャベツ』『けん玉(『Jam Films』内の一編)』に続く三作目。『月とキャベツ』が山崎さんの映画デビュー作となってから篠原監督と親交が深まり、篠原の結婚披露宴では、ギターを弾きながらセロリを歌ってくれました。演奏前、披露宴会場の中にあるバーカウンターで私がウイスキーを飲んでいる隣に山崎さんが来て5分ほど一緒に飲みました。といっても、お互いに何を語るということもなくただグラスを傾けるという貴重な経験に内心緊張していた自分がいたことを覚えています。
次回は映画を離れて、ブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』です。
校長室より「通常登校に向けて、生徒・保護者の皆さんへ」
6月1日(月)より、いよいよ通常登校となります。
先週5月18日(月)より分散登校を開始し、通常登校に向けた準備を2週間行ってまいりましたが、別途掲載してあります感染予防のための対策を一層充実させ、安全安心な学校生活とともに、学びの保障に努めてまいります。
しかしながら、登校への不安もぬぐいきれないことと思います。
私の二人の子供は、いずれも医療従事者のため、3月以降、病院(外来)が休みの日以外一日も休むことなく公共交通機関を用いて出勤しています。一人は東京在住のため、1月以降LINEのテレビ電話で話すことしかできていません。もう一人は同居しているため毎日顔を合わすことができますが、二人とも感染のリスクが高い環境のため、不安を抱えながら出勤しております。その分、感染予防の意識も高く、通勤時や買い出しのための外出時の行動にも気を配っています。帰宅後は、マスクを所定の場所に捨て、手洗いとうがいをしっかり行い、すぐにシャワーを浴びて着替えるなど、できうる対策をとって感染の予防に努めています。既に退職しましたが、妻も医療従事者であったため感染予防の意識は高いですし、私も子供に倣って手洗い、うがい、帰宅後のシャワー、感染リスクの高い場所を訪れない等によって家族全員が不安の低減をはかっています。
第二波・第三波の発生予想や、どこに潜んでいるかわからないウイルスの存在は、誰にとっても脅威です。だからこそ、一人一人が適切な行動をとることによって不安を和らげ、日常を取り戻していくことが大切なのだと思います。
先週来、校内で見られた生徒の笑顔、生徒の存在に私は希望を感じました。
間違いなく光が射し始めたと感じております。
どうか通常登校後も、他者を思い、自分を大切に思う行動によって、光に満ちあふれた宇都宮北高校にしていきましょう。
校長室より「いくえみ綾『プリンシパル』」
愛好家の方はおわかりでしょうが、今回の作品は『Cookie』(集英社)に2010年11月号から2013年9月号まで連載され、マーガレットコミックス全7巻 からなる漫画です。
『プリンシパル〜恋する私はヒロインですか?〜』のタイトルで実写映画化され、ジャニーズWESTの小瀧望君と黒島結菜さんのW主演でした。
高校生の主人公住友糸真が、母親の4度目の結婚相手と上手くいかず、入学した女子高でハブられ、実父を頼って北海道へ引っ越すところから話は始まります。
現実的な問題、現実離れした展開等、それあり?、確かに!といったストーリーに全7巻一気に読み切ってしまいました。
日本の漫画には、文化として世界に誇れるものがたくさんあります。
それは、優れたストーリーテラーが、小説の世界ではなく漫画の世界でその才能を発揮しているからであり、それはロールプレイングゲームの世界でも言えます。
『プリンシパル』は、文化云(うん)々(ぬん)というようなだいそれた内容ではありませんが、いじめという問題も含まれています。
いじめや人間関係の問題について考える一冊としては、菅野仁さんの『友だち幻想』(ちくまプリマ-新書)をお薦めします。心が少し軽くなるかもしれません。
次回は、横山秀夫さんの『影踏み』です。
校長室より「今日は創立記念日です。」
1年生にとっては、高校に入って初めての授業、緊張の面持ちが見られました。
2・3年生は、久々にクラスメートと会えた喜びからか、随所で笑顔が見られました。
さて、今日5月20日は、宇都宮北高等学校の創立記念日です。
創立10周年記念誌には、本校創立記念日の由来が次のように記されています。
『本校の創立記念日は5月20日であるが、それは昭和55年が開校であるので5月とし、工事の鍬入れが6月20日であったことから20日を選び、5月20日とした。』
また、創立10周年記念誌には、昭和57年5月20日に、校舎落成・校旗樹立記念式典が盛大に執り行われ、本校第2代校長花村冨士男先生が式辞で「今日、学校がこのように立派に完成したのは、地域の人々をはじめとする県民の協力の賜である。人間は一人では生きられない。両親をはじめとして社会の人々や大自然の恵みに報いるために真剣に学んでほしい。………本校は国際理解教育を特色とし、成果を挙げているが単なるコスモポリタンになることなく、自国認識を深め自ら郷土を愛し、国を愛する、すばらしい誇り高き日本人になってほしい。」と生徒を励ましたとあり、現同窓会長である四十物英晴先輩が生徒代表として「開校時の不自由さが、かえって宇北高の基礎づくりの意欲をかきたてた。あとに続く後輩のためにも、独自の校風と伝統を持ち、存在感ある学校になるよう一同努力する」と力強い誓いの挨拶を行ったと記されています。
コロナウイルス感染症によって世界が劇的に変化している今、創立当時に思いを致し、宇都宮北高校のアイデンティティーを考える日としてください。
校長室より「臨時休業中の学校運営に関する県立学校の指針」について
本校では、この指針をもとに学校再開に向けた準備を進めてまいります。
しかしながら、本校は県内最大規模の学校であるため、指針に示された目安通りにはゆかない面がございます。その点、生徒・保護者の皆様には御理解と御協力を賜りますようお願いします。具体的な方法については追って御連絡いたしますのでお待ちください。
以下に、指針に掲載された栃木県教育長の言葉を掲載いたします。
はじめに
令和2年2月に本県で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されてから、これまで県内55 件の発生が確認されています(5月8日現在)。
この間、県立学校では、国の要請を受け、令和2年3月2日から春休みまでの期間、学校保健安全法に基づく臨時休業の措置をとりました。その後、東京都をはじめとする7都県(本県を除く)に対する緊急事態宣言(4月7日~5月6日)の発令に伴い、県立学校を始業式の翌日から4月22 日まで臨時休業としました。さらに4月17 日には、緊急事態宣言が全都道府県に拡大され、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく知事の要請を受け、県立学校の臨時休業を5月6日まで延長することとしました。
そして4月30 日、依然として県内に感染拡大の危機感が広がっていることから、児童生徒の安全・安心に最大限配慮するため、臨時休業を5月31 日まで再延長することを決め、現在に至っています。また、国では、5月4日に緊急事態宣言を5月31日まで延長することを決めました。
このように私たちは、3月から約3ヶ月にわたって、県立学校における教育活動が行われていないという未曽有の事態に直面しています。児童生徒の皆さんは、学校生活という日常から離れるとともに、外出の自粛など行動の制約が求められる中、辛い毎日を過ごされていることと思います。
学校は本来、友人らとともに学び、人とのふれあいの素晴らしさを実感して日々成長していく場所であります。残念ながら現状では、こうした学校教育を受ける機会が長期にわたって失われております。一方で、児童生徒の安全を確保し、保護者の皆様が安心して子どもたちを学校に預けられるようにすることも大切なことです。教育を受ける機会の確保と児童生徒の安全の確保という2つを、可能な限り両立させながら、学校運営の舵取りをしていくことが各学校には求められていると言えます。
そこで県教育委員会では、臨時休業中の学校運営に関する県立学校の指針を作成し、これを公表することといたしました。保護者及び県民の皆様におかれましては、何卒御理解、御協力をいただきますようお願い申し上げます。
また、各県立学校では、この指針を踏まえ、校長のリーダーシップの下、臨時休業中の分散登校日の設定をはじめ、家庭学習の充実に向けた工夫、児童生徒に対する学習支援の工夫、さらには学校における感染防止対策の工夫等、万全の態勢を整えていただきますよう、お願いいたします。
令和2年5月8日
栃木県教育委員会 教育長 荒川 政利
校長室より「今日(5/8)の北高」

今朝正門を入る時にとても美しかったので見てもらいたくなりました。
人間の営みはコロナウイルスによって混迷を極めていますが、自然は営々としてその生を全うしています。
校長室より「藤沢周平『山桜』『小川の辺』」
第3回は、藤沢周平さんの『山桜』と『小川の辺』です。
映画の主演は、どちらも少年隊の東山紀之。凜々しい武士の姿が印象的でした。殺陣は・・・。もちろん『小川の辺』に出演したKis-My-Ft2の二階堂君とは比べようもない見事な殺陣でしたが。
妻役は、『山桜』は田中麗奈、『小川の辺』は尾野真千子。田中麗奈さんと私は、NHK-BSで放送された『旦那様はFBI』というノンフィクションドラマで共演しています。と言ってもほんの一瞬エキストラで出ただけなので、クレジット(エンドロール)に名前も出ず、一緒に見ていた家族にも気づいてもらえませんでした。
『小川の辺』は、『山桜』を見た藤沢周平氏の奥様がたいへん気に入り、映画化につながったということです。
どちらも、江戸時代の架空の藩「海坂藩(うなさかはん)」を舞台にした時代小説です。
映像では、とにかく草木の「緑」がとても美しく感じました。そういえば、篠原監督初の16mm作品は『草の上の仕事』という、二人の青年(一人は爆笑問題の太田光)がただただ草を刈るもの。その時から草の緑をきれいに撮ると感じていました。
北高の校内も今は新緑がとても美しいです。この清々しい緑を旬の時期に皆さんに見てもらえないのが残念です。
「山桜」というと、私は江戸時代の国学者、本居宣長の詠んだ「敷島の 大和心(やまとごころ)を 人問はば 朝日ににほふ 山桜花(やまざくらばな)」という和歌を思い出します。日本人の精神とは何だろうと思う時に、必ずこの和歌が口を衝いて出てきます。皆さんにとって日本人の精神とは何でしょう。
因みに、「敷島の」は、『大和(やまと)』にかかる枕詞。他にどんな枕詞があるか国語便覧で確認しましょう。
さて、藤沢周平作品では、『たそがれ清兵衛』や『武士の一分』なども映画化されていますが、高校生の皆さんには『蝉しぐれ』がおすすめです。
長編ですが、主人公牧文四郎に共感し、作品の世界に引きずり込まれることでしょう。時代小説の名手、藤沢周平の世界を堪能できます。
次回は、いくえみ綾さんの『プリンシパル』です。
校長室より「インターハイ中止を受けて」
この報に接し、どれほどの生徒・保護者・先生方が涙したことでしょうか。私自身も受け止めきれません。
選抜がなくなり、関東大会がなくなり、集大成の全国大会に挑戦することもできずに高校部活動が終わってしまう。さぞかし無念でしょう。
私は高校3年のインターハイ予選まで部活動中心の高校生活でした。結局全国大会にも関東大会にも出場することはできませんでした。強かったわけでもなく、実績も残していませんが、最後までやりきったことが今も私の支えになっています。ですから、3年生には結果はどうあれ、最後までやりきったという思いを持ってもらいたかったのです。
一昨日、学校の敷地をくまなく歩きました。グランドも体育館も誰一人いない虚しい空間ではありましたが、一方で皆さんの帰りを待ち焦がれる場でもありました。
野球部についてはまだ希望が残るものの、他の運動部では、ここに3年生が現役部員として大会に向けた姿を見せることはないのかと思うと残念でなりません。
3年生に限らず、誰もが「なんで。」と思っていることでしょう。一刻も早い学校再開のために、外出を控え窮屈な生活を我慢しているのに報われることがないのかと。
でも改めて考えてください。今私たちが直面している現実はそれほど厳しいものなのだと。ここで心折れることなく気持ちを強く持つことが必要なのだと。
コロナ終息までの期間もそうですが、コロナ終息後の世界は、今まで私たちが経験してきた世界とは全く異なることでしょう。その世界に適応し、新たなステージで活躍できるよう力を蓄えておきましょう。
校長室より「恩田陸『木曜組曲』ほか」
『蜜蜂と遠雷』は、史上初の快挙となる直木賞(第156回)、本屋大賞(2017年)のW受賞を果たした傑作。恩田さんにとっては『夜のピクニック』以来の二度目の本屋大賞受賞作となります。
風間塵16歳、栄伝亜夜20歳、高島明石28歳、マサル・C・レヴィ=アナトール19歳の4人の若きピアニストの姿が国際ピアノコンクールを舞台に描かれています。
音楽の知識がない私でも作品の世界に引き込まれ、わくわくしながら一気に読み切ってしまいました。1次予選から3次予選、本選で演奏される曲を知る人にとっては、演奏を頭に浮かべながら、いや4人の演奏をあたかも実際に耳にしているように感じながら読み進めることができるのだろうなと羨ましく思いながら読みました。
ピアノを題材とした映画で小説を原作としたものには、一昨年公開された宮下奈都さん原作で橋本光次郎さんが監督した『羊と鋼の森』があります。
『羊と鋼の森』は、2016年・第13回本屋大賞を受賞した作品。
将来の夢もなく生きていた主人公が、高校でピアノ調律師と出会い、その音色に魅せられ専門学校を出て調律師として働くなかで人間として成長していく姿が描かれています。特に、高校生の姉妹との交流の場面は胸に熱く迫るものがあります。
さて、恩田陸さんの『木曜組曲』ですが、この小説は、恩田さんが作家を専業とした後、1999年に単行本が刊行され、2002年2002年に映画化さた作品です。
謎の死を遂げた耽美派女流作家を偲んで集まった5人の女性たちが、その死の謎を解明していく密室ミステリーと言われるものです。登場人物一人ひとりが個性的で、重層的な深みのある作品で面白く読めました。
因みに、耽美派の作家といえば誰がいますか?国語便覧を開くとわかりますよ。
次回は、藤沢周平さんの『山桜』『小川の辺』を紹介します。
校長室より「夢枕獏『陰陽師』」
私の好みだけで選んでいくと偏りが出てしまうので、映画監督をしている友人、大学の剣道部(体育会ではありません)の同期、篠原哲雄君が監督したものから紹介したいと思います。彼はオリジナル作品も多くありますが、文学作品の映画化を頼まれることが多く多岐にわたるので、偏りなく紹介できるかと思います。
第1回は、3月29日(日)午後9時からテレビ朝日で放送された『陰陽師』。
夢枕獏さんの代表作『陰陽師』は、野村萬斎主演の映画もありますが、テレビ版は佐々木蔵之介主演でした。余談ですが、篠原君が監督した映画『花戦さ』は野村萬斎主演でした。こちらは後ほど紹介します。
さて、『陰陽師』は、平安時代に実在した安倍晴明(あべのせいめい)を主役とした作品。シリーズ化されていて、はまるとたいへん。
陰陽師について気になったら、皆さんの持っている国語便覧を開いてください。
12ページか44ページ(平安京のページ)に安倍晴明の屋敷が都のどこにあったかが載っています。
35ページか56ページ(信仰のページ)には、陰陽道の解説(物忌や方違など)があります。
134ページか144ページ(『大鏡』の描く人物像のページ)には、平安時代の歴史物語『大鏡』の中の「花山天皇の出家」に安倍晴明が出てくるシーンが記されています。因みに、『大鏡』は私の大学の卒業論文のテーマ(「大鏡研究-主として東松本と流布本の相違について-」)です。
次回は、恩田陸さんの『木曜組曲』を紹介します。
校長室より「命を守り、力を蓄えよう。」
外出もままならず、部活もできず友達とも会えず、窮屈な寂しい日々と感じている人がほとんどではないでしょうか。
そんななか、昨日、国の緊急事態宣言が全国に拡大されました。
22日までとされた本県の臨時休業も延長されるだろうことが報道されました。
更に窮屈で寂しい日が続くのかと思うことでしょうが、改めて、皆さん一人ひとりが自分の命、家族の命、友人の命、社会を守る行動をとることに努めてください。
先行きの見えない不安を誰もが抱くことでしょう。
でも、明けない夜はありません。
希望の光は必ず訪れます。
今は地中でじっと耐え、地上に出て光を浴びた時に勢いよく成長できるよう、たっぷりと栄養を蓄えておいてください。
今、どれだけ栄養を蓄えておくことができるかによって、皆さんの飛躍の度合いが決まってきます。
皆さんにとっての栄養とは、学力と体力、そして人間力です。
学力については、先生方が皆さんにあてて様々なメッセージを発しています。まずは、与えられた課題に取り組み、さらに発展的な学習に取り組んでください。
体力については、自宅でできる体力作りの方法がネット等で紹介されています。私は、全日本剣道連盟のHPで公開されている筋力トレーニングをしています。
人間力については、読書によって高めてください。図書館も閉まっていて新たな本の入手は難しい時ですが、青空文庫などのようにネット上で無料で読める本がたくさんあります。この機会に、今まで接することのなかった世界に触れてください。
読書については、今後、できるだけ紹介していこうと思います。
ピンチをチャンスに変えましょう。
校長室より(4/9)
北高の先生方は、皆さんのことを考えて一日中大忙しでした。
その一端がこのHPに表れています。皆さんへ向けたメッセージが発信されています。それぞれに目を通してください。
私からは昨日の始業式で話したことに関連して一点だけ。
正しい情報の入手に努めてください。多くの皆さんはスマホやパソコンによってネット上のニュースを見るていると思いますが、ネット上に挙げられている情報には、出所のはっきりしない不確かなものや誤ったもの、作為的に嘘の情報を流したものなどがありますので注意が必要です。必ず信頼できるものか確認してください。やはり安心なのは全国紙や地方紙と言われる新聞社の出しているものでしょう。全国紙の中には、ネットで無料で見られるものもありますので利用してください。できればこの機会に、各家庭に届けられる新聞を読む習慣をつけてください。
始業式 式辞
令和2年度1学期始業式式辞(校長着任式挨拶を含む)
皆さん、おはようございます。
四月より宇都宮北高校校長となりました笠原です。どうぞよろしくお願いします。
三月まで、三年間、鹿沼高校の校長を務めていました。その前3年間は宇都宮東高校と宇都宮東高校附属中学校の教頭を務めておりました。
このたび、宇都宮北高校という県内で最も人気のあるすばらしい学校の校長を拝命し、とても嬉しく思うと同時に、責任の重さを感じております。
一年生とは昨日の入学式で会いましたが、2・3年生の顔を見ることができず、放送での始業式となってしまい、残念でなりませんが、皆さんの命と健康を守ることが第一ですので、今回は放送にて行い、皆さんの顔を見て話が出来る日を待ちたいと思います。
さて、昨日、国の緊急事態宣言が発令されたのを受けて、栃木県の緊急対策会議が開かれ、明日から2週間の臨時休業が発表されました。
学校が再開されることを待ち望んでいた者にとっては、残念に感じる面もありますが、現状を見たとき、ほっとした気持ちの方が勝っているかもしれません。
生徒の皆さんだけでなく、御家族を含め、社会全体を守るための措置ですので、休校のの趣旨をよく理解し、宇都宮北高生の自覚を持って責任ある行動をとってほしいと思います。宇都宮北高校のイメージとして自由な雰囲気が挙げられますが、自由には責任が伴うことを忘れてはいけません。
そこで、皆さんに一冊の本を紹介します。
岩波新書で池田潔という方の「自由と規律」という本です。
この本は著者がイギリスのパブリックスクールで学んでいた時のことを記したものです。今から60年も前に書かれたものですが、新学期になると今でも書店に平積みとなる歴史的名著です。
この本は私が高校入学の時に入学式で校長先生が紹介されたもので、自分の中で自由とはということを考える基盤となった本です。是非読んでみてください。
昨日の記者会見での栃木県教育長の話では、休校の期間を更に延長するかどうかは、二週間後、休校の効果があったかどうかの状況により判断するとのことでしたので、学校が一刻も早く、安全な場所として再開できるよう、自分・家族・社会を守る行動を皆さんは実践してください。
まずは、緊急事態宣言地域である、東京・埼玉・千葉・神奈川へは、よほどの理由がなければ行かないということを徹底してください。
そして、誤った情報やデマに踊らされることなく、冷静な行動をとってください。
昨日の入学式の式辞で1年生に話したことですが、コロナウイルス感染症拡大の混乱の中で改めて感じたのが、科学教育の充実と情報教育の充実です。あまりにも多くの非科学的なデマや情報に踊らされ、混乱を自ら深刻化している姿は嘆かわしくも悲しくもあります。そこで皆さんには、本校で科学的な考え方と正しい情報の活用をしっかりと身につけてもらい、社会の中で率先した行動をとってもらいたいと思います。
もう一点、昨日述べたことで、2・3年生にも実践してほしいことがあります。
それは、「哲学を持つ」ということです。
哲学を持つことは、「命を大切にする」「人を大切にする」ことにつながります。
皆さん一人ひとりの命はかけがえのないものであり、今ここに存在することには大きな意味があります。その意味はまだ見えないかもしれませんが、それを探していく行為こそ、「哲学を持つ」ということにつながります。
1年生には繰り返しとなってしまいますが、それだけ重要だと思って聞いてください。
なぜ哲学を持ってほしいかというと、哲学を持たぬ科学者ほど恐ろしいものはないと考えるからです。この場合の科学とは、物理学や数学といった自然科学だけではなく、文学や歴史学といった人文科学、法律や経済といった社会科学も含みます。
つまり、皆さん誰もが、何かしらの科学を専門とすることとなるわけですが、哲学を持たずに取り組むことは恐ろしいことだと考えるからです。
しかし、哲学を持つということは容易なことではありません。哲学を持つためには、自分自身の体験だけでは十分ではありません。多くの人と接して様々な生き方・考え方に触れること。本を読み、先哲の優れた思想を学ぶこと、直接体験できないことも、本の世界に自分を置いて間接的に体験し、考えることが必要です。
したがって、皆さんには多くの人と接し、多くの本を読んでもらい哲学の世界、学問の世界に羽ばたいてもらいたいと思います。
私が石橋高校に勤務していた時の生徒で、現在明治大学の准教授をしている人物は、高校在学中に石橋高校の図書館にある哲学書をすべて読んだと言っていました。皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
宇都宮北高校の校章の由来の一つである「知・徳・体・情・意」という言葉も哲学と大きな関係があります。この点については自分で調べてみてください。
まだまだ話したいことはたくさんあるのですが、時間短縮のため、今日はここまでとし、これから様々な場面でいろいろな話をしていきたいと思います。
以上、令和2年度第一学期始業式にあたっての校長式辞と致します。
2週間後、皆さんの元気な姿を見せてください。
入学式 式辞
令和二年度 栃木県立宇都宮北高等学校 入学式 式辞
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、保護者・来賓の方々に御臨席いただけなかったことは誠に残念ではありますが、ここに、令和二年度、栃木県立宇都宮北高等学校入学式を挙行できますことは、新入生はもとより私ども教職員にとりましても大きな喜びでございます。
ただいま入学を許可いたしました三百二十一名の新入生の皆さん、入学おめでとう。
私たち教職員一同は、心より皆さんを歓迎し、祝福いたします。
また、この場に御同席いただくことはかないませんでしたが、保護者の皆様におかれましても、今日の日を迎えお喜びのことと存じます。心よりお祝い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の報道に触れて、新入生の皆さんも、保護者の皆様も、不安を抱えて今日の日を迎えたことと思いますが、一方で本校への入学を心待ちにしていたことと思います。
その思いは、私ども教職員も同じでございます。
本校は今年秋に、創立40周年記念式典を挙行致します。その節目の年に入学する皆さんと一緒に宇都宮北高校の新たな歴史を作っていきたいと考えております。
皆さんは、特色選抜を経て入学した人も、一般選抜を経て入学してきた人も、ともに宇都宮北高校への進学を希望して、今日この場にいます。保護者の薦め、先生の薦めがあったにしても、最終的には自らの意志によって本校を志願し受検したことには変わりありません。
では、皆さんが本校を志望した理由は何だったのでしょうか。
人それぞれではあるかと思いますが、本校に魅力を感じ、本校で学びたいと思ったからでしょう。
そのように本校を希望し、高校生となった皆さんに、私から是非ともしてもらいたいことが三つあります。
まず第一に、「哲学を持つ」ということです。それは、哲学を持たぬ科学者ほど恐ろしいものはないと考えるからです。この場合の科学とは、物理学や数学といった自然科学だけではなく、文学や歴史学といった人文科学、法律や経済といった社会科学も含みます。
つまり、皆さん誰もが、将来的に何かしらの科学、即ち学問を専門とすることとなるわけですが、どの学問にとっても、哲学を持たずに取り組むことは恐ろしいことだと考えるからです。
哲学というのは、「人間が生きるということはどういうことか」「自分はいかに生きるか」ということを考えることです。
何かするにあたって、これは良いことなのか悪いことなのか、自分はどう行動したら良いのかの基準を持つことです。
ですから哲学を持つということは容易なことではありません。
哲学を持つためには、自分自身の体験だけでは十分ではありません。多くの人と接して様々な生き方・考え方に触れること。本を読み、先哲の優れた思想を学ぶこと、自分が直接体験することのできない世界にも、本の世界に自分を置いて間接的に体験し、考えることが必要です。
したがって、皆さんには多くの人と接し、多くの本を読んでもらいたいと考えます。そして、哲学の世界、学問の世界に羽ばたいてほしいと願います。
二つ目は、「学び」の質を変えるということです。即ち、「学習」から「学問」へと転換し、「知識」を「智恵」へと昇華してほしいということです。
学習は、「学び習う」と書き、学んだことを繰り返し繰り返し練習・復習して身につけることで、知識の集積にあたります。
これに対し、学問は、「学び問う」と書き、学んだことから疑問を持ち、探求して真理へ向かい、智恵へと高めることです。
コロナウイルス感染拡大の混乱の中で改めて感じたのが、科学教育の充実と情報教育の充実です。日本ほど国民全体に教育が施されている国はないと言われていますが、報道される一連の騒動を見るかぎり、日本は決して教育先進国とは言えません。
あまりにも多くの非科学的なデマや情報に踊らされ、混乱を自ら深刻化している姿は嘆かわしくも悲しくもあります。
そこで皆さんには、本校で科学的な考え方と正しい情報の活用をしっかりと身につけてもらい、社会の中で率先した行動をとってもらいたいと思います。
三つ目は、「友情を育む」ということです。私は、人は最終的には、「知によって動くものではなく、情によって動くものだ」と考えています。「知」とは「知識の知」です。この人について行った方が得だろうという状況判断によって動くことはもちろんあるでしょう。しかし、何か重大なことにあたって最後の最後に自分がどう動くかは、それまでに育まれた愛情や友情といったものだと思っています。高校時代に育んだ友情は一生ものであり、困難にぶつかった時の支えとなります。どうか、一生ものの友情を宇都宮北高校の三年間で育んでください。
結びに、新入生の皆さんが、今日の感動を忘れることなく、自分たちの力で学校を一層活気あるものにしていくという意気込みをもって、勉学に部活動や各種特別活動に取り組み、学校生活が実り多く、輝くものとなることを心から期待して、式辞と致します。
令和二年四月七日
栃木県立宇都宮北高等学校長 笠原 紀昭
卒業生の方で各種証明書等を必要とされる場合は
証明書等の交付申請
のページをご確認ください。
栃木県警本部より、本校の同窓生に対する特殊詐欺の事案が発生しているとの連絡がありました。同窓生の皆様におかれましては、ご家族・関係者とも連絡を取り、特殊詐欺の電話には十分にご注意いただきますようお願いいたします。また、学校といたしましても個人情報の取り扱いには十分に注意しているところですが、同窓会名簿等の個人情報の取り扱いには十分にご注意いただきますよう、併せてお願いいたします。
教育相談の窓口一覧(PDF形式、令和7年5月栃木県教育委員会)です。