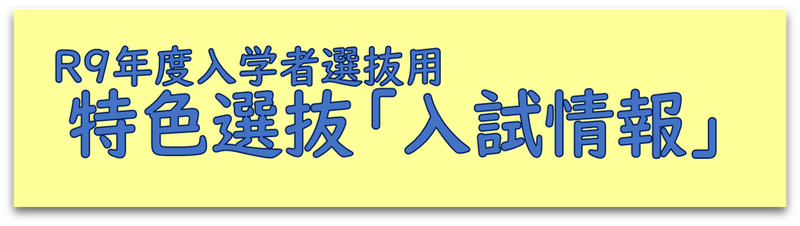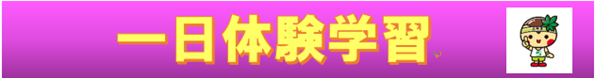文字
背景
行間
日誌
校長室だより
1学期終業式 式辞
令和2年度第1学期終業式 式辞
改めて、皆さんこんにちは。
ここからは、1学期の締めくくりとなる終業式の式辞として話しをします。
始業式と同様、放送によるものとなってしまいました。
私が皆さんの前で話をするのは、入学式で1年生の入学を許可し、式辞を述べた時だけであり、未だ2・3年生の前で話をすることができていません。
廊下ですれ違うことがあっても、お互いにマスク越しの顔しか見ることができません。おそらく、私を見て校長だと認識してくれる人は数少ないことでしょう。
いつになったら皆さんのマスクなしの顔を見ることができるのか。皆さんの顔を見ながら話をすることができるのか。その思いは募るばかりです。
しかしながら、連日耳にする過去最多の感染者数という報道には、危機感を覚えずにはいられません。改めてマスクの着用、手洗い、三密を避けた行動に徹することが求められます。
6月から通常登校となりましたが、決して通常の学校生活が送れたわけではありませんでした。登下校の制約、授業内容の制約、休み時間の行動の制約、部活動の制約、学校行事の制約と多種多様な制約を強いられました。
生徒誰もが楽しみにしていた学校祭も中止とせざるをえませんでした。2年生の修学旅行も日程と旅行先が変更されました。今後の状況によっては他の行事等の変更・中止があるかもしれません。
しかし、ここで生徒の皆さんに知っていてもらいたいことがあります。
それは、皆さんの学校生活の思い出がより多く残せるよう、先生方は最大限検討・協議していたということです。
こうすれば出来るのではないか。ああすればできるのではないか。ここまでならやれるのではないかと、何度も何度も計画を練り直し、次の案、更にその次の案と生徒の皆さんからの意見も聞きながら検討し、それでも難しいという結論に達し、実施に向け何度も考えたものが実行不可能となり、変更・中止に至ったということを知っておいてください。今後も何ができるか。どうすればできるかを考えていきたいと思います。
さて、今日は、たった2ヶ月しかなかった1学期の終業式となるわけですが、今日は皆さんに、「令和2年度第1学期終業式校長式辞メモ」というプリントを用意しました。そこに記入しながら話を聞いてください。
ということで、机の上にプリントと筆記具は出ているでしょうか。このメモには、あらかじめ記入を要求されていることだけでなく、話しを聞きながら、書きとどめておきたいこと、疑問に思ったことなどを余白や裏面に書いていってください。使い方は自由です。目的は、ただ聞き流すのではなく、意識を持って聞いてもらうことです。
まず、学年、クラス、出席番号と氏名を記入してください。
では、最初に一学期の振り返りをしてもらいたいと思います。1学期が始まる際に皆さんが立てた目標を記入してください。時間は30秒です。
次に、1学期の間に自分ができたことと、できなかったことを書いてください。時間は1分です。書き終わらない人、思い浮かばない人は、家に帰ってからじっくり1学期の振返りをしてください。
それでは次に、皆さんが夏休みにしたいことを書いてください。
例年に比べて短く、制約の多い夏休みではありますが、その中で皆さんがしたいと思うことを書いてください。時間は30秒です。
終業式は、このように学期中を振り返り、次のスタートのための区切りの行事であり、自己のアイデンティティーを再確認する日です。
そしてまた、自分が北高の生徒であることを再認識し、帰属意識を高める日でもあります。
それを象徴するのが、校歌の斉唱です。しかし、それができません。
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、今年度は未だ校歌を歌うことができていません。1年生は北高の校歌をどれだけ歌えるでしょうか。
在学中は入学式や卒業式、始業式や終業式といった時の慣例だから歌うものと感じている人がいるかもしれませんが、校歌の持つ意味が本当にわかるのは卒業してからです。
卒業後、北高の校歌を耳にし、一緒に歌った時に北高の一員であることの帰属感が実感されます。
それが甲子園のグラウンドであったり、高校生クイズの決勝の場で、テレビから北高の校歌が流れてきたりすると感無量です。
一昨年の夏の甲子園での金足農業の全力校歌が話題となったことは記憶に新しいところですが、肩を組み合い、共に校歌を歌えることの素晴らしさは在校中はなかなか理解できないかもしれませんが、皆さんとともに声高らかに校歌を歌える日を私は心待ちにしています。
北高のホームページには、校歌のアイコンがあり、このアイコンをクリック・タップすると校歌の歌詞が表示されるとともに、吹奏楽の演奏に乗った美しい歌声が流れます。パソコンでも、スマートホンでも聴くことができます。
北高の校歌をうまく歌えないという人は、ホームページにある校歌を使って練習するとうまく歌えるようになるでしょう。
式典で校歌を歌うことができないというのも、制約の一つですが、本当に様々な所で制約を受け続けている今の境遇はとても辛いことです。
明治時代の小説家・ジャーナリストである国木田独歩という人は、その日記『欺かざるの記』の中で、「忍耐と勤勉と希望と満足とは境遇に勝つものなり」と言っています。
このコロナ禍の境遇に勝つものは、一人一人の、「忍耐と勤勉と希望と満足」なのでしょう。
私たちは、今まで十分堪え忍んできたと思いますが、感染の終息には、尚、忍耐が必要なのかもしれません。そして、何事にも勤勉に取り組み、希望と満足をもって歩むことによって、今の境遇に打ち勝ちましょう。
最後に、私が始業式で皆さんに話したことの振り返りで終えたいと思います。
私が始業式で話した、北高生に実践してもらいたいと言ったことを覚えているでしょうか。覚えている人はメモの括弧内に記入してください。
私は、皆さんに「哲学を持つこと」を実践してもらいたいと言ったのですが、その取り組みを皆さんはしてくれたでしょうか。
では、哲学を持つために必要なこととして挙げたことは覚えているでしょうか。覚えている人は二つの括弧内に記入してください。
それは、多くの人と接し、多くの本を読むことです。コロナウイルス感染症の感染拡大予防の点からは多くの人と接することは今は避けなくてはなりませんが、その分、多くの本を読んでください。本の世界でも多くの人に接する事ができます。
北高ホームページには、校長室よりのアイコンがあります。そこには、皆さんに伝えたいことや図書の紹介が載っています。最新の図書紹介では、ブレイディみかこさんの「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」について掲載しましたが、この本を読むことで、遠く離れたイギリスに住む中学生と、彼に関連する多くの人に接する事ができます。また、ブレイディみかこさんの母校、福岡県立修猷館高等学校に関連して紹介した城山三郎氏の作品を読めば、そこに描かれた人々の生き様に接し、自分の生き方に思いをいたすことができます。直接人に接することができない分、読書によって、間接的に多くの人と接してください。
以上で、令和2年度第1学期終業式の校長式辞を終えます。
改めて、皆さんこんにちは。
ここからは、1学期の締めくくりとなる終業式の式辞として話しをします。
始業式と同様、放送によるものとなってしまいました。
私が皆さんの前で話をするのは、入学式で1年生の入学を許可し、式辞を述べた時だけであり、未だ2・3年生の前で話をすることができていません。
廊下ですれ違うことがあっても、お互いにマスク越しの顔しか見ることができません。おそらく、私を見て校長だと認識してくれる人は数少ないことでしょう。
いつになったら皆さんのマスクなしの顔を見ることができるのか。皆さんの顔を見ながら話をすることができるのか。その思いは募るばかりです。
しかしながら、連日耳にする過去最多の感染者数という報道には、危機感を覚えずにはいられません。改めてマスクの着用、手洗い、三密を避けた行動に徹することが求められます。
6月から通常登校となりましたが、決して通常の学校生活が送れたわけではありませんでした。登下校の制約、授業内容の制約、休み時間の行動の制約、部活動の制約、学校行事の制約と多種多様な制約を強いられました。
生徒誰もが楽しみにしていた学校祭も中止とせざるをえませんでした。2年生の修学旅行も日程と旅行先が変更されました。今後の状況によっては他の行事等の変更・中止があるかもしれません。
しかし、ここで生徒の皆さんに知っていてもらいたいことがあります。
それは、皆さんの学校生活の思い出がより多く残せるよう、先生方は最大限検討・協議していたということです。
こうすれば出来るのではないか。ああすればできるのではないか。ここまでならやれるのではないかと、何度も何度も計画を練り直し、次の案、更にその次の案と生徒の皆さんからの意見も聞きながら検討し、それでも難しいという結論に達し、実施に向け何度も考えたものが実行不可能となり、変更・中止に至ったということを知っておいてください。今後も何ができるか。どうすればできるかを考えていきたいと思います。
さて、今日は、たった2ヶ月しかなかった1学期の終業式となるわけですが、今日は皆さんに、「令和2年度第1学期終業式校長式辞メモ」というプリントを用意しました。そこに記入しながら話を聞いてください。
ということで、机の上にプリントと筆記具は出ているでしょうか。このメモには、あらかじめ記入を要求されていることだけでなく、話しを聞きながら、書きとどめておきたいこと、疑問に思ったことなどを余白や裏面に書いていってください。使い方は自由です。目的は、ただ聞き流すのではなく、意識を持って聞いてもらうことです。
まず、学年、クラス、出席番号と氏名を記入してください。
では、最初に一学期の振り返りをしてもらいたいと思います。1学期が始まる際に皆さんが立てた目標を記入してください。時間は30秒です。
次に、1学期の間に自分ができたことと、できなかったことを書いてください。時間は1分です。書き終わらない人、思い浮かばない人は、家に帰ってからじっくり1学期の振返りをしてください。
それでは次に、皆さんが夏休みにしたいことを書いてください。
例年に比べて短く、制約の多い夏休みではありますが、その中で皆さんがしたいと思うことを書いてください。時間は30秒です。
終業式は、このように学期中を振り返り、次のスタートのための区切りの行事であり、自己のアイデンティティーを再確認する日です。
そしてまた、自分が北高の生徒であることを再認識し、帰属意識を高める日でもあります。
それを象徴するのが、校歌の斉唱です。しかし、それができません。
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、今年度は未だ校歌を歌うことができていません。1年生は北高の校歌をどれだけ歌えるでしょうか。
在学中は入学式や卒業式、始業式や終業式といった時の慣例だから歌うものと感じている人がいるかもしれませんが、校歌の持つ意味が本当にわかるのは卒業してからです。
卒業後、北高の校歌を耳にし、一緒に歌った時に北高の一員であることの帰属感が実感されます。
それが甲子園のグラウンドであったり、高校生クイズの決勝の場で、テレビから北高の校歌が流れてきたりすると感無量です。
一昨年の夏の甲子園での金足農業の全力校歌が話題となったことは記憶に新しいところですが、肩を組み合い、共に校歌を歌えることの素晴らしさは在校中はなかなか理解できないかもしれませんが、皆さんとともに声高らかに校歌を歌える日を私は心待ちにしています。
北高のホームページには、校歌のアイコンがあり、このアイコンをクリック・タップすると校歌の歌詞が表示されるとともに、吹奏楽の演奏に乗った美しい歌声が流れます。パソコンでも、スマートホンでも聴くことができます。
北高の校歌をうまく歌えないという人は、ホームページにある校歌を使って練習するとうまく歌えるようになるでしょう。
式典で校歌を歌うことができないというのも、制約の一つですが、本当に様々な所で制約を受け続けている今の境遇はとても辛いことです。
明治時代の小説家・ジャーナリストである国木田独歩という人は、その日記『欺かざるの記』の中で、「忍耐と勤勉と希望と満足とは境遇に勝つものなり」と言っています。
このコロナ禍の境遇に勝つものは、一人一人の、「忍耐と勤勉と希望と満足」なのでしょう。
私たちは、今まで十分堪え忍んできたと思いますが、感染の終息には、尚、忍耐が必要なのかもしれません。そして、何事にも勤勉に取り組み、希望と満足をもって歩むことによって、今の境遇に打ち勝ちましょう。
最後に、私が始業式で皆さんに話したことの振り返りで終えたいと思います。
私が始業式で話した、北高生に実践してもらいたいと言ったことを覚えているでしょうか。覚えている人はメモの括弧内に記入してください。
私は、皆さんに「哲学を持つこと」を実践してもらいたいと言ったのですが、その取り組みを皆さんはしてくれたでしょうか。
では、哲学を持つために必要なこととして挙げたことは覚えているでしょうか。覚えている人は二つの括弧内に記入してください。
それは、多くの人と接し、多くの本を読むことです。コロナウイルス感染症の感染拡大予防の点からは多くの人と接することは今は避けなくてはなりませんが、その分、多くの本を読んでください。本の世界でも多くの人に接する事ができます。
北高ホームページには、校長室よりのアイコンがあります。そこには、皆さんに伝えたいことや図書の紹介が載っています。最新の図書紹介では、ブレイディみかこさんの「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」について掲載しましたが、この本を読むことで、遠く離れたイギリスに住む中学生と、彼に関連する多くの人に接する事ができます。また、ブレイディみかこさんの母校、福岡県立修猷館高等学校に関連して紹介した城山三郎氏の作品を読めば、そこに描かれた人々の生き様に接し、自分の生き方に思いをいたすことができます。直接人に接することができない分、読書によって、間接的に多くの人と接してください。
以上で、令和2年度第1学期終業式の校長式辞を終えます。
0
校長室より「読書感想文について」
読書は、基本的に自分ひとりの孤独な営みです。しかし、読書感想文として言葉で表現したものは、自分ひとりのものではなくなります。それを読む人とともに共有することとなり、直接会うことはなくても、読んだ人との出会いを生んでくれます。
また、読書感想文は、過去の自分との出会いをもたらしてくれます。数年後、数十年後、過去に自分が書いた読書感想文を読み返した時に、当時の自分の考えや感動を思い起こし、ああ、私はこういう子どもだったんだな、こういう人間だったんだなと振り返って、その時の感動や考えを基に新たな歩みを始めるきっかけとなります。
私は、1学期の始業式で生徒の皆さんに「哲学を持ちなさい」と言いました。
哲学というのは、「人間が生きるということはどういうことか」「自分はいかに生きるか」ということを考えることです。
何かするにあたって、これは良いことなのか悪いことなのか、自分はどう行動したら良いのかの基準を持つことです。
哲学を持つためには、自分自身の体験だけでは十分ではありません。本を読み、自分が直接体験することのできない世界にも、本の世界に自分を置いて間接的に体験し、考えることが大切です。
読書感想文は、その本を読んで感じたことの記録だけでなく、書くことによって考えを深め、それによって自分自身を見つめ、書くことを通して思考の世界へ導いてくれます。
皆さんが、多くの本を読み、書くことによって、皆さんの哲学を持ってくれることを期待しています。
また、読書感想文は、過去の自分との出会いをもたらしてくれます。数年後、数十年後、過去に自分が書いた読書感想文を読み返した時に、当時の自分の考えや感動を思い起こし、ああ、私はこういう子どもだったんだな、こういう人間だったんだなと振り返って、その時の感動や考えを基に新たな歩みを始めるきっかけとなります。
私は、1学期の始業式で生徒の皆さんに「哲学を持ちなさい」と言いました。
哲学というのは、「人間が生きるということはどういうことか」「自分はいかに生きるか」ということを考えることです。
何かするにあたって、これは良いことなのか悪いことなのか、自分はどう行動したら良いのかの基準を持つことです。
哲学を持つためには、自分自身の体験だけでは十分ではありません。本を読み、自分が直接体験することのできない世界にも、本の世界に自分を置いて間接的に体験し、考えることが大切です。
読書感想文は、その本を読んで感じたことの記録だけでなく、書くことによって考えを深め、それによって自分自身を見つめ、書くことを通して思考の世界へ導いてくれます。
皆さんが、多くの本を読み、書くことによって、皆さんの哲学を持ってくれることを期待しています。
0
全国高等学校総合文化祭出場(弁論部門)
第44回全国高等学校総合文化祭2020こうち総文が、「webSOUBUN」として7月31日(金)~10月31日(土)、ネット上にて開催されます。
本校からは、3年生の大川英莉さんが弁論部門に出場します。
大川さんは、第56回栃木県高等学校国際理解弁論大会において、優秀賞・栃木県教育委員会教育長賞を受賞し、栃木県代表として参加します。
本来であれば、高知県室戸市で発表する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により一堂に集まっての開催ができず、WEB上での発表となりました。
「WEB SOUBUN」で検索していただければ入ることができますので、ぜひ御覧ください。
学校では、1学期終業式の前に壮行会を開き、大川さんの栄誉を讃え、生徒教職員一同で喜びを共有したいと考えております。
本来であれば、壮行会の場でもっと大勢の生徒が紹介され、全国高校総体等での活躍が期待されたであろうことを思うと、返す返す残念でなりませんが、次のステージで頑張ってくれることを祈っております。
本校からは、3年生の大川英莉さんが弁論部門に出場します。
大川さんは、第56回栃木県高等学校国際理解弁論大会において、優秀賞・栃木県教育委員会教育長賞を受賞し、栃木県代表として参加します。
本来であれば、高知県室戸市で発表する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により一堂に集まっての開催ができず、WEB上での発表となりました。
「WEB SOUBUN」で検索していただければ入ることができますので、ぜひ御覧ください。
学校では、1学期終業式の前に壮行会を開き、大川さんの栄誉を讃え、生徒教職員一同で喜びを共有したいと考えております。
本来であれば、壮行会の場でもっと大勢の生徒が紹介され、全国高校総体等での活躍が期待されたであろうことを思うと、返す返す残念でなりませんが、次のステージで頑張ってくれることを祈っております。
0
校長室より「ブレイディみかこ『ほくはイエローでホワイトで、……』」
図書紹介第6回は、ブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』です。
次回は映画を離れて、ブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』ですと予告してから、ちょうど2ヶ月が経ってしまいました。申し訳ありません。
この本は、私が2019年に読んだノンフィクション、エッセイの中で、最も面白く、最も生徒に読んでほしいと思ったものです。
新潮社が発行する文芸雑誌『波』の2018年1月号から2019年4月号に連載されたものを、2019年6月に単行本として出版し、現在もなお書店に平置きされ、売り上げ上位に位置しています。
日本人の母親(著者)と白人英国人の父を持つ息子の中学校生活によって、イギリスの今が描き出されています。レイシズム、LGBTQ、貧困、差別といった様々な問題について考えることができるもので、是非とも読んでほしい一冊です。
赤坂ACTシアターに2度見に行ったミュージカル「リトル・ダンサー(原題ビリー・エリオット)」の背景にも触れられていて、そうだったのかと理解が深まったことも私としては面白く読めました。
著者のブレイディみかこさんは、マスコミにも頻繁に出るようになりましたので、知っている人もいるかと思いますが、本に書かれている著者紹介には、「保育士・ライター・コラムニスト。1965年福岡市生まれ。県立修猷館高校卒。音楽好きが高じてアルバイトと渡英を繰り返し、1996年から英国ブライトン在住。ロンドンの日系企業で数年間勤務したのち英国で保育士資格を取得、「最低保育所」で働きながらライター活動を開始。2017年に新潮ドキュメント賞を受賞し、大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション大賞候補となった『子どもたちの階級闘争-ブロークン・ブリテンの無料託児所から』(みすず書房)をはじめ、著書多数。」とあります。
ブレイディみかこさんの卒業した修猷館高校というのは、福岡県内屈指の進学校で、今年度の国公立大学合格者は299名、東大に16名、京大に11名、九州大に131名が合格しています。私の大学時代の剣道部の同期にも修猷館高校の卒業生がいますが、母校に対する誇りを持っていました。卒業生は著名人も多く、元総理大臣の広田弘毅もその一人です。第二次世界大戦後の極東国際軍事裁判で文官としては唯一のA級戦犯として有罪判決を受け死刑となった人ですが、その生涯を描いた、城山三郎の『落日燃ゆ』を読むと、彼の生き様に感慨を覚えることと思います。
因みに、私は高校時代、城山三郎の小説を貪るように読んだ時期がありました。きっかけは、総理大臣として金解禁を断行し、東京駅で凶弾に倒れた浜口雄幸を描いた『男子の本懐』を読んだこと。そこから、『落日燃ゆ』、来年のNHK大河ドラマの主人公となる新一万円札の顔、日本資本主義の父である渋沢栄一を描いた『雄気堂々』、三井物産社長から国鉄総裁となった石田禮助を描いた『祖にして野だが卑ではない』、『官僚たちの夏』、直木賞を受賞した『総会屋錦城』と続きました。
さて、話しを『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』に戻します。とにかく引き込まれます。優れた文章力です。出会うべき一冊と言えるでしょう。
次回は、映画に戻って、浅田次郎さんの『地下鉄(メトロ)に乗って』です。
次回は映画を離れて、ブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』ですと予告してから、ちょうど2ヶ月が経ってしまいました。申し訳ありません。
この本は、私が2019年に読んだノンフィクション、エッセイの中で、最も面白く、最も生徒に読んでほしいと思ったものです。
新潮社が発行する文芸雑誌『波』の2018年1月号から2019年4月号に連載されたものを、2019年6月に単行本として出版し、現在もなお書店に平置きされ、売り上げ上位に位置しています。
日本人の母親(著者)と白人英国人の父を持つ息子の中学校生活によって、イギリスの今が描き出されています。レイシズム、LGBTQ、貧困、差別といった様々な問題について考えることができるもので、是非とも読んでほしい一冊です。
赤坂ACTシアターに2度見に行ったミュージカル「リトル・ダンサー(原題ビリー・エリオット)」の背景にも触れられていて、そうだったのかと理解が深まったことも私としては面白く読めました。
著者のブレイディみかこさんは、マスコミにも頻繁に出るようになりましたので、知っている人もいるかと思いますが、本に書かれている著者紹介には、「保育士・ライター・コラムニスト。1965年福岡市生まれ。県立修猷館高校卒。音楽好きが高じてアルバイトと渡英を繰り返し、1996年から英国ブライトン在住。ロンドンの日系企業で数年間勤務したのち英国で保育士資格を取得、「最低保育所」で働きながらライター活動を開始。2017年に新潮ドキュメント賞を受賞し、大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション大賞候補となった『子どもたちの階級闘争-ブロークン・ブリテンの無料託児所から』(みすず書房)をはじめ、著書多数。」とあります。
ブレイディみかこさんの卒業した修猷館高校というのは、福岡県内屈指の進学校で、今年度の国公立大学合格者は299名、東大に16名、京大に11名、九州大に131名が合格しています。私の大学時代の剣道部の同期にも修猷館高校の卒業生がいますが、母校に対する誇りを持っていました。卒業生は著名人も多く、元総理大臣の広田弘毅もその一人です。第二次世界大戦後の極東国際軍事裁判で文官としては唯一のA級戦犯として有罪判決を受け死刑となった人ですが、その生涯を描いた、城山三郎の『落日燃ゆ』を読むと、彼の生き様に感慨を覚えることと思います。
因みに、私は高校時代、城山三郎の小説を貪るように読んだ時期がありました。きっかけは、総理大臣として金解禁を断行し、東京駅で凶弾に倒れた浜口雄幸を描いた『男子の本懐』を読んだこと。そこから、『落日燃ゆ』、来年のNHK大河ドラマの主人公となる新一万円札の顔、日本資本主義の父である渋沢栄一を描いた『雄気堂々』、三井物産社長から国鉄総裁となった石田禮助を描いた『祖にして野だが卑ではない』、『官僚たちの夏』、直木賞を受賞した『総会屋錦城』と続きました。
さて、話しを『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』に戻します。とにかく引き込まれます。優れた文章力です。出会うべき一冊と言えるでしょう。
次回は、映画に戻って、浅田次郎さんの『地下鉄(メトロ)に乗って』です。
0
県の警戒度が引き上げられました。
新型コロナウイルス感染症に対する栃木県の警戒度が、「感染観察」段階から「感染拡大注意」段階に引き上げられました。
生徒の皆さんは、学校再開前後の緊張感を思い出し、3密の回避、マスクの着用、手洗い、換気、消毒の徹底などの基本的な感染症対策に心がけて通常登校が続けられるよう協力してください。
生徒の皆さんは、学校再開前後の緊張感を思い出し、3密の回避、マスクの着用、手洗い、換気、消毒の徹底などの基本的な感染症対策に心がけて通常登校が続けられるよう協力してください。
0
0
0
5
2
7
0
9
1
4
証明書等の交付申請
卒業生の方で各種証明書等を必要とされる場合は
証明書等の交付申請
のページをご確認ください。
学校情報・入試情報
一日体験学習
特殊詐欺にご注意ください
栃木県警本部より、本校の同窓生に対する特殊詐欺の事案が発生しているとの連絡がありました。同窓生の皆様におかれましては、ご家族・関係者とも連絡を取り、特殊詐欺の電話には十分にご注意いただきますようお願いいたします。また、学校といたしましても個人情報の取り扱いには十分に注意しているところですが、同窓会名簿等の個人情報の取り扱いには十分にご注意いただきますよう、併せてお願いいたします。
主な相談窓口
教育相談の窓口一覧(PDF形式、令和7年5月栃木県教育委員会)です。