 |
 |
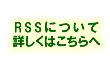 |
 |
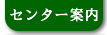 |
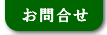 |
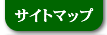 |
  |
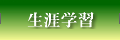 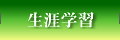 |
  |
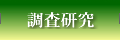 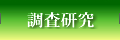 |
 |
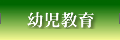 |
 |
 |

| 目 的 | 主幹教諭としての職務、今日的な教育課題、学校経営の在り方等について理解を深め、主幹教諭としての資質の向上を図る。 | ||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年12月4日(火) 9:30~16:00 | ||||||||||||||||
| 対 象 | 小・中学校の新任主幹教諭(高・特と合同) | ||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話・演習「学校評価マネジメント(2)」 2 講話「主幹教諭の役割」 | ||||||||||||||||
| 講 師 | 国士舘大学体育学部こどもスポーツ教育学科教授 北神 正行 氏 総合教育センター職員 | ||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| ||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度、研修へのニーズ ①満足度
②研修ニーズ
1 講話・演習「学校組織マネジメント(2)」 【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
【研修の目標】
【講話を通しての主な意見・感想】
|
| 目 的 | 学習指導主任の職務・役割や学習指導の今日的課題について理解し、校内における実践を通して、学習指導主任としての資質の向上を図る。 | ||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年10月29日(月) 9:30~16:00 | ||||||||||||||||
| 対 象 | 小・中学校の新任学習指導主任 | ||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「これからの学習指導の在り方」 2 研究協議「学習指導の充実を図るための工夫と改善」 | ||||||||||||||||
| 講 師 | 早稲田大学教育・総合科学学術院教授 藤井 千春 氏 総合教育センター教育研修専門員 総合教育センター研修部長 総合教育センター生涯学習部長 総合教育センター幼児教育部長 | ||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| ||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度、研修へのニーズ ①満足度
②研修ニーズ
1 講話「これからの学習指導の在り方」 【研修の目標】
【感想や参考になったこと】
【研修の目標】
【感想や参考になったこと】
| ||||||||||||||||
| 目 的 | 学校教育の当面する諸課題と教務主任の職務について理解を深め、教務主任としての資質の向上を図る。 | |||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年11月19日(月) 9:30~16:00 | |||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の新任教務主任 | |||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話・演習「学校組織マネジメントの手法を生かした学校評価」 | |||||||||||||||
| 講 師 | 総合教育センター研修部指導主事 | |||||||||||||||
| 研修の様子 |
| |||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度 満足度
1 講話・演習「学校組織マネジメントの手法を生かした学校評価」 【研修の目標】
【学校組織マネジメントの手法を用いて、自校の学校評価システムをどのように活性化しようと考えたか】 <指標化について>
<重点化・重点目標について>
<職員間の共通理解について>
<学校評価システムの見直し>
<その他>
|
| 目 的 | 教頭として、今日的な教育課題に対応した学校経営の在り方等について理解を深め、実践的な学校経営能力の向上を図る。 | ||||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年8月23日(木) 9:30~16:00 | ||||||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の新任教頭 | ||||||||||||||||||
| 研修内容 | 1.講話「学校における人権教育の推進と教頭の役割」 2.講話・演習「学校のミッションと現状分析」 3.講話「人材育成の取組」 4.講話・演習「人材育成」 | ||||||||||||||||||
| 講 師 | 県教委事務局総務課人権教育室職員 県立高等学校長 総合教育センター職員 | ||||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| ||||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度 満足度
1 講話「学校における人権教育の推進と教頭の役割」 【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
|
| 目 的 | 教頭として、今日的な教育課題に対応した学校経営の在り方等について理解を深め、実践的な学校経営能力の向上を図る。 | |||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年8月10日(金) 9:30~16:00 | |||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の新任教頭 | |||||||||||||||
| 研修内容 | 講話・演習「学校における組織マネジメント」 | |||||||||||||||
| 講 師 | 兵庫教育大学大学院学校教育研究科 教授 浅野 良一 氏 | |||||||||||||||
| 研修の様子 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度
1 講話・演習「学校における組織マネジメント」 【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
|
| 目 的 | 教頭として、今日的な教育課題に対応した学校経営の在り方等について理解を深め、実践的な学校経営能力の向上を図る。 | ||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年9月4日(火) 9:30~16:00 | ||||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の教頭経験2年目に該当する者 | ||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 研究協議「学校における危機管理」 2 講話「危機管理」 | ||||||||||||||||
| 講 師 | 千葉大学ジェネラルサポーター 星 幸広 氏 | ||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| ||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度、研修へのニーズ ①満足度
②研修ニーズ
1 研究協議「学校における危機管理」 【研修の目標】
【研究協議に参加しての主な意見・感想】
【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
|
| 目 的 | 教頭として、今日的な教育課題に対応した学校経営の在り方等について理解を深め、実践的な学校経営能力の向上を図る。 | |||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年8月10日(金) 9:30~16:00 | |||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の教頭経験2年目に該当する者 | |||||||||||||||
| 研修内容 | 講話・演習「学校における組織マネジメント」 | |||||||||||||||
| 講 師 | 兵庫教育大学大学院学校教育研究科 教授 浅野 良一 氏 | |||||||||||||||
| 研修の様子 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度、研修へのニーズ ①満足度
②研修ニーズ
1 講話「教職員評価制度」 【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
|
| 目 的 | 学習指導主任の職務・役割、学習指導の今日的課題についての理解を深め、学習指導主任としての資質の向上を図る。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年5月31日(木) 9:30~16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の新任学習指導主任 | ||||||||||||||||||||||||||
| 研修内容 | 【全体】 開講あいさつ 説明「とちぎ教育振興ビジョン(三期計画)」 【高等学校】 1 講話「学習指導の現状と課題」 2 講話「学習指導主任に求められるもの」 3 事例発表「確かな学力の育成に向けた本校の取組」 4 研究協議「確かな学力の育成に向けた学習指導部の取組」 【特別支援学校】 1 講話「学習指導の現状と課題」 2 事例発表「学習指導の充実に向けて」 3 研究協議「学習指導の充実に向けて」 | ||||||||||||||||||||||||||
| 講 師 | 県立学校教員 学校教育課職員 特別支援教育室職員 総合教育センター職員 | ||||||||||||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度、研修へのニーズ ①満足度
②研修ニーズ
〔高等学校〕 【研修の目標】
【講話を聞いた感想・参考になったことなど】
【研修の目標】
【講話を聞いた感想・参考になったことなど】
3 事例発表「確かな学力の育成に向けた本校の取組」 【研修の目標】
4 研究協議「確かな学力の育成に向けた学習指導部の取組」 【研修の目標】
〔特別支援学校〕 【研修の目標】
【講話を聞いた感想・参考になったことなど】
【研修の目標】
【自校での運営に生かせると思ったこと・参考になったことなど】
3 研究協議「学習指導の充実に向けて」 【研修の目標】
|
| 目 的 | 進路指導主事の職務について理解を深め、進路指導主事としての資質の向上を図る。 | ||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年6月11日(月) 9:30~16:00 | ||||||||||||||||
| 対 象 | 中学校の新任進路指導主事 | ||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「進路指導の意義と進路指導主事の職務」 2 実践発表「進路指導主事の職務の実際」 ※ 午後は、中学校進路指導主事研究協議会と合同 | ||||||||||||||||
| 講 師 | 総合教育センター教育研修専門員 宇都宮市立晃陽中学校教諭 | ||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| ||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度、研修へのニーズ ①満足度
②研修ニーズ
1 講話「進路指導の意義と進路指導主事の職務」 【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
【研修の目標】
【実践発表を聞いての主な意見・感想】
|
| 目 的 | 生徒指導主事の職務・役割、生徒指導上の諸問題等についての理解を深め、生徒指導主事としての資質の向上を図る。 | |||||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年6月29日(金) 9:30~16:00 | |||||||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の新任生徒指導主事 | |||||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 説明「とちぎ教育振興ビジョン(三期計画)」 2 講話「不登校の理解と支援」 3 講話・演習「ネットトラブルの予防と対策」 4(1) 事例研究「組織的な指導体制の在り方-いじめへの対応-」(高) (2) 事例研究「組織的な指導体制の在り方」(特) 5 講話「生徒指導主事の職務の実際」 | |||||||||||||||||||
| 講 師 | 県教委事務局総務課副主幹 総合教育センター職員 県立高等学校教諭 | |||||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| |||||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度、研修へのニーズ ①満足度
②研修ニーズ
1 講話「不登校の理解と支援」 【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
【研修の目標】
3 (1) 事例研究「組織的な指導体制の在り方-いじめへの対応-」(高等学校) 【研修の目標】
(2) 事例研究「組織的な指導体制の在り方」(特別支援学校) 【研修の目標】
4 講話「生徒指導主事の職務の実際」 【研修の目標】
|
| 目 的 | 教頭として、今日的な教育課題に対応した学校経営の在り方等について理解を深め、実践的な学校経営能力の向上を図る。 | ||||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年6月8日(金) 9:30~16:00 | ||||||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の教頭経験2年目に該当する者 | ||||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「教職員評価制度」 2 研究協議「教職員評価制度を活用した教職員の育成」 3 講話「教職員のメンタルヘルスケア」 4 講話・研究協議「教育の情報化への対応」 | ||||||||||||||||||
| 講 師 | 県教委事務局教職員課副主幹兼管理主事 三楽病院精神神経科部長 真金 薫子 総合教育センター職員 | ||||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| ||||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度、研修へのニーズ ①満足度
②研修ニーズ
1 講話「教職員評価制度」 【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
【研修の目標】
【研究協議に参加しての主な意見・感想】
3 講話「教職員のメンタルヘルスケア」 【研修の目標】
4 講話・研究協議「教育の情報化への対応」 【研修の目標】
|
| 目 的 | 校長としての職務、今日的な教育課題、学校経営の在り方等について総合的に理解を深め、校長としての資質の向上を図る。 | |||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年6月4日(月)9:30~16:00 | |||||||||||||||||
| 対 象 | 小・中学校の新任校長 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「私の学校経営」 2 講話「学校組織マネジメント」 3 研究協議「学校経営上の諸問題」 | |||||||||||||||||
| 講 師 | 総合教育センター職員 | |||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| |||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度、研修へのニーズ ①満足度
②研修ニーズ
1 講話「私の学校経営」 【研修目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
【研修目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
3 研究協議「学校経営上の諸問題」 【研修目標】
|
| 目 的 | 校長としての職務、今日的な教育課題、学校経営の在り方等について総合的に理解を深め、校長としての資質の向上を図る。 | |||||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年4月16日(月) 9 30~16:00 | |||||||||||||||||||
| 対 象 | 小・中学校の新任校長 | |||||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「新任校長への期待」 2 講話「人権教育と校長の役割」 3 講話「特別支援教育における校長の役割」 4 講話「学校経営に関する諸問題-指導関係-」 5 講話「学校経営と教育関係法規」 | |||||||||||||||||||
| 講 師 | 県教委教育次長 県教委事務局総務課人権教育室長 県教委事務局特別支援教育室長 県教委事務局学校教育課長補佐 県教委事務局教職員課長補佐 | |||||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| |||||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度、研修へのニーズ ①満足度
②研修ニーズ
1 講話「新任校長への期待」 【研修目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
【研修目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
3 講話「特別支援教育における校長の役割」 【研修目標】
4 講話「学校経営に関する諸問題-指導関係-」 【研修目標】
5 講話「学校経営と教育関係法規」 【研修目標】
|
| 目 的 | 学校教育の当面する諸課題と教務主任の職務について理解を深め、教務主任としての資質の向上を図る。 | |||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年6月14日(木) 9:30~16:00 | |||||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の新任教務主任 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「特別支援教育の概要」 2 講話「県立学校の諸課題 -指導関係-」 3 講話・演習「県立学校の諸課題 -服務関係-」 | |||||||||||||||||
| 講 師 | 県教委事務局特別支援教育室長補佐 県教委事務局学校教育課長補佐 県教委事務局教職員課長補佐 | |||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| |||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度 ①満足度
1 講話「特別支援教育の概要」 【研修の目標】
【主な意見・感想、参考になったこと】
【研修の目標】
【主な意見・感想、参考になったこと】 <学業指導に関して>
3 講話・演習「県立学校の諸課題 -服務関係-」 【研修の目標】
<職員に対して>
|
| 目 的 | 生徒指導主事の職務・役割、生徒指導上の諸問題等についての理解を深め、生徒指導主事としての資質の向上を図る。 | ||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年6月8日(金) 9:30~12:25 | ||||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の新任生徒指導主事 | ||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「児童・生徒指導の意義と生徒指導主事の役割」 2 研究協議「生徒指導上の課題と取組」 | ||||||||||||||||
| 講 師 | 県教委事務局学校教育課児童生徒指導推進室副主幹 | ||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| ||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度 ①満足度
1 講話「児童・生徒指導の意義と生徒指導主事の役割」 【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
【研修の目標】
|
| 目 的 | 学年主任の職務・役割、学校教育の諸問題、学年経営上の課題について理解を深め、学年主任としての資質の向上を図る。 | ||||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年5月18日(金) 9:30~16:00 | ||||||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校の新任学年主任 | ||||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講 話「学年主任の職務」 2 講 話「高校生段階における発達障害の理解と対応」 3 事例発表「本校における学年経営」 4 研究協議「学年経営上の課題」 | ||||||||||||||||||
| 講 師 | 県立高等学校教員 総合教育センター職員 | ||||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| ||||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度、研修へのニーズ ①満足度
②研修ニーズ
1 講話「学年主任の職務」 【研修の目標】
【講話の感想や参考になったこと】
【研修の目標】
3 事例発表「本校における学年経営」 【研修の目標】
4 研究協議「学年経営上の課題」 【研修の目標】
|
| 目 的 | 進路指導主事の職務・役割、進路指導の現状と課題等について理解を深め、進路指導主事としての資質の向上を図る。 | |||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年6月5日(火) 9:30~16:00 | |||||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の新任進路指導主事 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 事例発表「進路指導主事としての実践」 2 研究協議「進路指導の実際と課題」 3 講話「今求められる人材とは」 | |||||||||||||||||
| 講 師 | 県立那須清峰高等学校教諭 県立矢板東高等学校教諭 県立のざわ特別支援学校教諭 NPO法人キャリアコーチ理事長 髙木義博 氏 | |||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| |||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度 ①満足度
1 事例発表「進路指導主事としての実践」 【研修の目標】
【主な意見・感想、参考になったこと】
【研修の目標】
3 講話「今求められる人材とは」 【研修の目標】
|
| 目 的 | 学習指導主任の職務・役割や学習指導の今日的課題について理解し、校内における実践を通して、学習指導主任としての資質の向上を図る。 | ||||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年5月28日(月) 9:30~16:00 | ||||||||||||||||||
| 対 象 | 小・中学校の新任学習指導主任 | ||||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「学習指導主任に求められるもの」 2 説明「とちぎ教育振興ビジョン(三期計画)」 3 講話「本県の学習指導の現状と課題」 4 講話「学習指導主任の職務と実際」 5 講話「組織力の向上を図る校内研修の充実」 | ||||||||||||||||||
| 講 師 | 総合教育センター教育研修専門員 県教委事務局学校教育課副主幹 鹿沼市立北小学校教諭 栃木市立栃木南中学校教諭 総合教育センター研究調査部副主幹 | ||||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| ||||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度、研修へのニーズ
②研修ニーズ
1 講話「学習指導主任に求められるもの」 【研修の目標】
【講話を聞いての主な感想や参考になったこと】
2 講話「本県の学習指導の現状と課題」 【研修の目標】
【 講話を聞いての主な感想や参考になったこと 】
3 講話「学習指導主任の職務と実際」 【研修の目標】
【実践発表を聞いて、自校の取組に生かせそうなこと 】
4 講話「組織力の向上を図る校内研修の充実」 【研修の目標】
【参考になったことや、自校の取組に生かせそうなこと】
|
| 目 的 | 校長としての職務、今日的な教育課題、学校経営の在り方等について総合的に理解を深め、校長としての資質の向上を図る。 | |||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年6月4日(月) 9:30~16:00 | |||||||||||||||||
| 対 象 | 高等学校、特別支援学校の新任校長 | |||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「事務室の財務と事務室との連携」 2 講話・演習「学校経営ビジョンの構築と学校経営」 3 研究協議「学校経営上の諸課題」 | |||||||||||||||||
| 講 師 | 県立学校主幹兼事務長 総合教育センター職員 | |||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| |||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度、研修へのニーズ ①満足度
②研修ニーズ
1 講話「事務室の財務と事務室との連携」 【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
【研修の目標】
3 研究協議「学校経営上の諸課題」 【研修の目標】
|
| 目 的 | 主幹教諭としての職務、今日的な教育課題、学校経営の在り方等について理解を深め,主幹教諭としての資質の向上を図る。 | ||||||||||||||||||
| 日 時 | 平成24年5月15日(火) 9:30~16:00 | ||||||||||||||||||
| 対 象 | 小・中学校の新任主幹教諭 | ||||||||||||||||||
| 研修内容 | 1 講話「主幹教諭への期待」 2 講話「校長が期待する主幹教諭像」 3 事例発表「主幹教諭としての実践」 4 講話・演習「学校組織マネジメント(1)」 | ||||||||||||||||||
| 講 師 | 県教委事務局教職員課長補佐 小・中学校長 小・中学校主幹教諭 総合教育センター職員 | ||||||||||||||||||
| 研修の様子 |
| ||||||||||||||||||
| 研修評価・振り返りシートから | 0 研修の満足度、研修へのニーズ ①満足度
②研修ニーズ
1 講話「主幹教諭への期待」 【研修の目標】
【講話を聞いての主な意見・感想】
【研修の目標】
3 事例発表「主幹教諭としての実践」 【研修の目標】
4 講話・演習「学校組織マネジメント(1)」 【研修の目標】
|