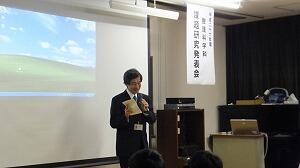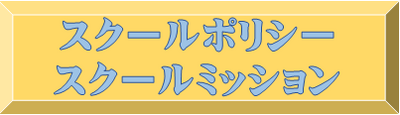数理科学科の活動の様子を紹介します
数理科学科1年 日光自然探究合宿 報告会
各班が今まで行った事前学習、日光での探究合宿(現地調査)、事後考察をまとめ、情報を編集構成しました。そして、パソコンを用いてプレゼンテーションを行うとともに、互いの発表を視聴し、評価しました。
今回の報告会で1年間の日光自然探究合宿に関する探究学習が終わりました。1年間の学習を通して、将来学んでいく科学的・論理的思考力を養うとともに、情報を編集、発信する能力を身につけることができました。




1班:日光の動物について
2班:動物が環境に及ぼす影響
3班:日光の植物
4班:日光の蝶
5班:日光と小山の蝶の違い
6班:小山と日光の鳥の違い
7班:日光の地衣類
8班:日光のキノコ
9班:日光の地質
平成26年度 数理科学科課題研究発表会(クラス発表)
今回は、12月9日に発表できなかったテーマについて、発表を行いました。 発表テーマは下記のとおりです。校長先生、教頭先生にもお越しいただき、様々テーマについて発表を行いました。 今年の数理科学科の課題研究テーマは全部で17テーマあり、これまでになく幅広い研究・発表になりました。これも生徒達が一生懸命、様々な活動に参加した成果です。自ら実験を行っているテーマも多く、先生方からも高い評価をいただきました。
○発表テーマ マイナス200℃の世界(宇都宮大学SPP) 光とその性質(宇都宮大学SPP) 運動の背後に潜むもの(宇都宮大学SPP) 放射線の基礎について(日本原子力文化振興財団出張講義) 金属の性質(サイエンスキャンプ) パソコンの作製(個人研究) 光の回折(サイエンスキャンプ) ゲル電気泳動法で酵素を分離(宇都宮大学SPP) |


平成26年度 数理科学科課題研究発表会
|
12月9日(火)に数理科学科2年生で行っている課題研究の成果を発表する課題研究発表会が行われました。講師として、宇都宮大学教育学部の山田洋一先生をお招きしました
|
発表テーマは下記のとおりですが、宇都宮大学でのSPP、全国各地で体験してきたサイエンスキャンプ、神奈川工科大学連携講座、個人研究と幅広いテーマで発表が行われました。
今回の研究に関しては、体験してきたものだけで終わらせるのではなく、高校に帰ってきてから新たに実験を行ったテーマも多く、講師の先生方の評価も非常に高いものでした。プレゼンテーション能力は社会的の素養としてとても注目されています。今回の経験は将来の研究者を目指す数理科学科の生徒にとって大きな意味があったのではないかと思います。
○発表テーマ
ナノサイエンス(サイエンスキャンプ)
守りたいお肌がそこにある(サイエンスキャンプ)
熱気球の製作(個人研究)
海洋試料から探る地球環境(サイエンスキャンプ)
液体金属 水銀(宇都宮大学SPP )
火星探査プロジェクト(神奈川工大連携講座)
牛と牛肉(サイエンスキャンプ)
染色体の異常(宇都宮大学SPP)
血圧が上下するしくみ(サイエンスキャンプ)


課題研究発表の様子は12月13日の下野新聞にも掲載されました。
PDFファイルはこちら→新聞掲載記事.pdf
科学の甲子園 栃木県大会
11月22日に数理科学科代表6名が「科学の甲子園」栃木県大会に参加して参りました。 |
11月22日に数理科学科代表6名が「科学の甲子園」栃木県大会に参加して参りました。
「科学の甲子園」とは6人でチームを組み、理科・数学・情報の知識を活用し、協力して科学的問題解決を図る競技です。今年度は14校、35チームの参加がありました。午前中は筆記試験として6人で協力して解答を導き、午後は実技試験として実験結果から課題を考察する競技を行いました。結果は12月中旬に発表されます。
参加した生徒の感想は、みんなで話し合って答えが出せるので、学校での実力試験などとは違い、とても楽しく取り組めたとのことでした。科学技術の進歩は日進月歩なので、今後の科学の研究では科学的問題解決の力が必要とされています。生徒達は競技の結果よりも将来に向けて大きな経験を得られたと思います。
○参加生徒
2年6組 小澤 光莉
2年6組 青木 大介
2年6組 菅沼 幸起
2年6組 髙橋 祐太
2年6組 玉野 巧也
2年6組 寺井 孟


宇都宮大学SPP
9月6日、数理科学科の特別授業として宇都宮大学で行われたSPP(サイエンス・パートナーシップ・プログラム)に参加しました。内容は以下の通りです。 テーマⅠ:光とその性質 宇都宮大学教育学部 堀田先生 テーマⅡ:液体の金属、水銀を体験しよう 宇都宮大学教育学部 山田先生 テーマⅢ:ゲル電気泳動法で酵素を分離 宇都宮大学教育学部 井口先生 |