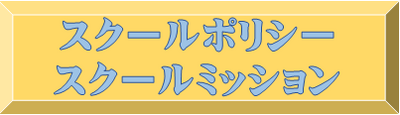数理科学科の活動の様子を紹介します
神奈川工科大学連携講座
8月21日、数理科学科の特別授業として神奈川工科大学連携講座を小山高校で行いました。講座の第3回目となります。内容は以下の通りです。 センシング技術の講義 神奈川工科大学 兵頭先生 プログラミングの実習 神奈川工科大学 兵頭先生 センシング技術の講義ではロボットの歴史や生まれた背景、今後必要とされる技術などについて説明していただきました。現在の製品は様々な技術が組み合わさりできていることから、技術者として必要なことは、深い専門知識だけではなく、広い関連する分野の知識も必要であるという話が印象深かったです。 プログラミングの実習では、簡単なプログラミングソフトを使い、指示通りにロボットキットを動かす実習を行いました。プログラミングをしっかり考えて入力しないとロボットが指示通りに動かないことを実感できたと思います。遠い星では、直接動きを指示することができないので、そういった状況でのシミュレーションができたと思います。 |





神奈川工科大学連携講座
7月30日、数理科学科の特別授業として神奈川工科大学連携講座を神奈川工科大学で行ってきました。この行事は公益財団法人中谷医工計測技術振興財団 科学教育振興助成により行っております。講座名『火星探査プロジェクトの立案』のもと、火星探査を行うにはどのようなプロジェクト、ロケット、ロボットが必要かを生徒自身が課題研究として考えるものです。 活動としてはロケット、航空機の飛行技術・理論、ロボットの操作技術・理論を3回の講座によって学び、最終的に自分の火星探査プロジェクトをまとめるというものです。 今回はこの第1回目として、神奈川工科大学にて講座を行って来ました。内容は以下の通りです。 航空宇宙工学の講義 神奈川工科大学 大久保先生 フライトシミュレーターの実習 神奈川工科大学 武田先生 モデルロケットの作製 神奈川工科大学 中根先生、水野先生 |




神奈川工科大学連携講座2
8月5日、数理科学科の特別授業として神奈川工科大学連携講座を神奈川工科大学で行ってきました。講座の第2回目となります。内容は以下の通りです。 ロケット工学の講義 神奈川工科大学 武居先生 モデルロケット発射の実習 神奈川工科大学 中根先生、水野先生 モデルロケットの高度測定実習 神奈川工科大学 中根先生、水野先生 |






数理科学科自然探究合宿
8月1日(金)・2日(土)の2日間、日光(戦場ヶ原・光徳・湯の湖周辺)にて、数理科学科自然探究合宿を行いました。
1日目は、2つのグループに分かれ、千手ヶ原周辺で『奥日光における動植物の生態を中心とする観察』を行いました。野生動物の共生や人間生活と環境の関わりなどについて考えました。2日目は、動物・植物・地質・菌地衣類・昆虫・鳥類の6分野ごとの班に分かれ、『班別探究活動』を行いました。事前学習で設定したテーマについて調査・探究・発見・考察をしました。
この合宿を通して、環境保護、自然を大切にする心を養うとともに将来理系を学んでいくのに必要とされる科学的思考力を養うことができました。また、集団生活を通して、クラスメイトとの親交を深めることができました。




宇都宮大学SPP
7月19日、数理科学科の特別授業として宇都宮大学で行われたSPP(サイエンス・パートナーシップ・プログラム)に参加しました。内容は以下の通りです。 テーマⅠ:運動の背後に潜むもの 宇都宮大学教育学部 堀田先生 テーマⅡ:マイナス200℃の世界 宇都宮大学教育学部 山田先生 テーマⅢ:染色体の異常性 宇都宮大学教育学部 上田先生 |