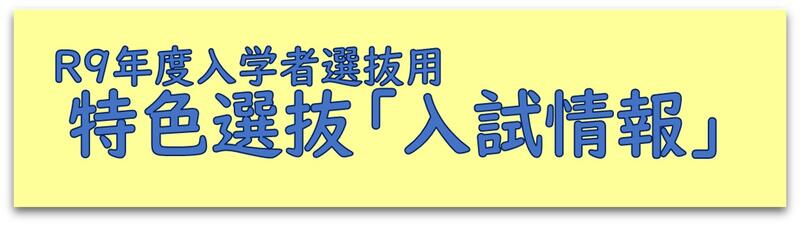文字
背景
行間
2年次生「総合的な探究の時間」について
探究活動の概要 1年次に、テーマに対する仮説の立て方、リサーチクエスチョンの設定、情報収集の方法、データの分析、考察、まとめの方法など、研究の過程や手法を学びます。 2年次では、ほぼ1年間をかけて、自分の興味のあるテーマについて研究を進め、報告書にまとめ、口頭発表を行います。
本校の探究活動のねらい
1 「漠然とした興味・関心・疑問」を「自分なりの結論が導ける問い」にするプロセスを学ぶ。
2 結論を導くために何をどうすればよいのか、自分で考え、立案し、実行できる。
3 得た情報を多面的・批判的に検討し、集まった証拠から論理的に結論を導ける。
4 自分が探究活動を通して得たこと、学んだことを他に分かりやすく伝える。
〇現在の活動状況はこちらをご覧ください。
探究活動の大まかな日程
|
1年次 |
|
3月 |
2年生の発表会への参加、2年次の探究活動のガイダンス |
|
2年次 |
|
4月 |
探究活動のテーマ設定、分野別ガイダンスや講義等 |
|
|
5月 ~ |
テーマ確定、計画立案、分野別で必要な講義や実習 |
|
|
|
9月 |
各自で探究活動 |
|
|
|
10月 |
中間発表会、今後の計画立案、探究活動 |
|
|
|
12月~ |
各自で探究活動、報告書作成、分野別内口頭発表会、報告書完成 |
|
|
|
3月 |
分野別代表の全体発表会(1・2年生全員、保護者、他校生対象)、探究活動のふりかえり |
活動の単位
教科に準じたまとまり(「分野」と読んでいます)をつくり、担任・副担任以外の多くの教員が探究活動をサポートしています。
|
分野
|
| 言語・文学 |
| 地歴公民 |
| 数学 |
| 理科 |
| 芸術 |
| 健康・医療・生活・スポーツ |
| 言語・国際理解 |
教員と生徒の関わり方
探究活動は、生徒自身がゴールを設定し進めて行くものです。教員は、生徒の探究活動を応援するという立場で関わっています。
①研究を進めるにあたって必要な基礎知識や手法を伝える。
②漠然としたテーマ(問い)を解決できる課題にしていくときの声かけ役。
③研究のペースメーカー。
④研究に行き詰まったとき、実験等失敗したときの相談役。
⑤大学等の外部機関の専門家や研究者と皆さんをつなぐ仲介役。
探究活動の成果物
探究活動の成果物の提出方法は、①か②のどちらかを選択します。
①報告書(A4版 1枚。グループ研究の場合も。様式は示しますが、内容によって改変可です。)
②自由研究の様式にしたがった研究報告書 →自由研究作品として、審査、表彰します。
口頭発表
分野内やクラスで中間発表や成果発表を行い、優れた探究活動については、3月に、1・2年生、保護者、他の学校の生徒さんを対象に公開発表会を行います。
〇2018年度以前の活動については公開を終了しました。
活動状況報告
探究活動成果発表会
R7年3月13日(木)宇都宮市文化会館において、探究活動成果発表会が行われました。これは総合的な探究の時間の授業の成果を発表する会です。2年次生はテーマごとにグループに分かれ、一年をかけて研究してきた成果を発表しました。1年次生は今年、研究とは何かを学びました。一年次生は成果発表会での2年生の発表を参考に、次年度各自が興味のある研究テーマを設定し、一年間研究を行う予定です。




探究活動 各種講座・体験実施
今年から2年生は「総合的な探究の時間」に、全員が「探究活動」に取り組んでいます。
分野分けが終わり、個人・グループでテーマ設定や研究計画立案等を行っています。また、分野毎に外部から講師をお招きして講座や体験も実施しています。
6月5日(水)には、歴史分野では、県立博物館から職員の方に来ていただき「平安貴族の服飾体験」を、理科分野では、獨協医科大学の野中先生に来ていただき、「実験ノートの書き方講座」を実施しました。



分野分け
個人やグループで、自分(達)が設定したテーマで研究を進めていきます。17日水曜日6時間目に各自がどの分野で探究を進めていくかの分野分けを行いました。
まず、生徒は全員、体育館に集合。各分野の担当の先生が分野名が書かれたプラカードを持ち体育館のそれぞれの場所に待機し、生徒は希望する分野の先生のところに集合。人数調整を行い、どの分野でどの生徒が活動していくか名簿で確認しました。
次週以降、分野毎に生徒は集まり、探究活動を行っていきます。



分野説明会
個人やグループで、自分(達)が設定したテーマで研究を進めていきます。研究を進める上で、とても大切でかつ難しいのがテーマ設定です。
そこで、テーマが決まらない生徒の手助けとなるように「言語・文学」「地歴・公民」「数学」「理科」「芸術」「健康・医療・生活・スポーツ」「言語・国際理解」の7分野にわけ、それぞれの分野で取り組めるテーマ、内容を指導者が考え用意しました。
今日は、1年間の活動計画と、各分野でのテーマ例の説明会を行いました。次週は、分野ごとに生徒に集まってもらい、内容の確認や人数の調整を行います。