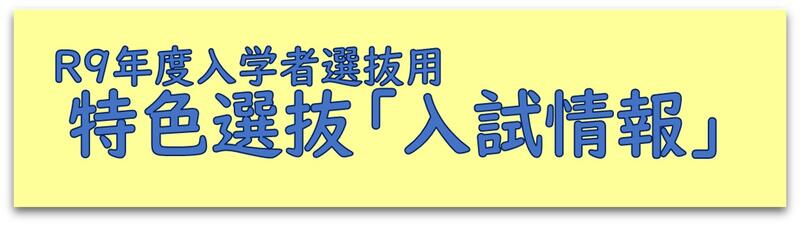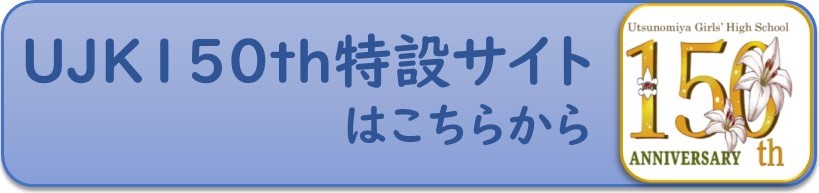文字
背景
行間
SSH日誌
【SSH】大学実験講座
大学実験講座
平成29年8月24日(木)
宇都宮大学教育学部
1・2年生希望者
【生徒の感想】 ・分光器やビーズを作った実験はいつもみている光が異なる色に見えてとても面白かった。(物理) ・今まで物理で学んだ波は音波だけであったが、光も電磁波であり、同じ波なので関係があることがわかった。(物理) ・冷やすと体積が小さくなることはどの物質にも共通していたが、酸素は色が変化したりゴムが伸びなくなったりという違いがあった。(化学) ・様々なものをマイナスの温度まで下げると、普段の生活ではみることができない液体の二酸化炭素や酸素をみることができて貴重な体験になった。(化学) ・タンパク質の大きさや形によって種類を区別できる電気泳動の原理が良く分かった。(生物) ・生物は幼生と成体で酵素の種類が異なることに驚いた。生物の分野は新しい発見がたくさんあって、世界初の研究も沢山あるとあらためて感じた。(生物) |
|||||||||||||||||||||||