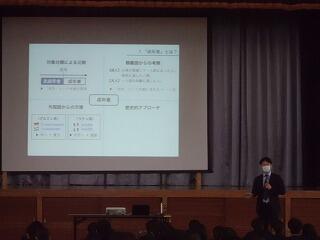キャリアクション・プロジェクト
キャリアクション・プロジェクト第1学年「栄養・教育・スポーツ分野」
1学年キャリアクション栄養・教育・スポーツ各分野の生徒たちが、豊田小学校において児童の皆さんと交流しました。今までの学習成果を実践・発表する場となったと同時に、素直で活発な小学生の皆さんから元気をもらうことができました。本校生の感想や振り返りは、後日キャリアクション通信にてお伝えします。
〇栄養分野
12月15日(木)5~6年生を対象に、食育講座を実施しました。栄養分野の1年生が3グループに分かれ、それぞれ「食品ロス(給食等の食べ残し)」「偏食」「郷土食」をテーマに、クイズ形式で行いました。
〇教育分野
12月16日(金)4~6年生を対象に、SDGsの14番目の目標「海の豊かさを守ろう」をテーマに授業を行いました。クイズを交えて、海のない栃木県に住む私たちも海の汚染の原因を作り出していることなどを伝えました。
〇スポーツ分野
12月19日(月)、豊田小学校の持久走大会において、補助員として先導・後走、コースの誘導・監察、片付けを担当しました。天気にも恵まれ、筑波山を後方に背負いながらのスタート。児童の皆さんも本校生の声援を受け、一生懸命に走っていました。帰り際、温かいお茶を振舞っていただき、小西生も終始笑顔あふれる中での支援となりました。
キャリアクション・プロジェクト第1学年「まちづくり分野」
〇11月17日 豊田小学校での「まちづくり教室」
1学年まちづくり分野の25名が小山市立豊田小学校を訪問し、「まちづくり教室」を開催しました。3年生から6年までを対象とし、小山市の魅力や豊田南小・北小の校舎や跡地利用について小学生と意見交換をしました。小学生は自分の住む地域についてよく知っており、たくさんのアイデアをもらうことができました。
〇11月22日 大学生とのディスカッション
宇都宮大学地域デザイン科学部より石井大一朗准教授と大学生5名に来校していただき、廃校利用等による小山市の活性化についてディスカッションを行いました。今後小山市に提案する企画書の作成のためのアイデアを出し合いました。大学生のアドバイスにより、先行事例やアンケート結果をもとに、様々な視点から物事を捉えることの大切さを学びました。
キャリアクション・プロジェクト第1学年「情報モラル教室」
今年の情報モラル教室は、11月11日(金)に豊田小学校にて行われました。
新しい校舎と子供たちの元気な挨拶に、大変癒やされました。
6年生は、教室の大型テレビを使っての説明です。
難しい用語にはイラスト等もつくので、分かりやすいです。
担当生徒は緊張しながらも、落ち着いた雰囲気の中、説明できました。
5年生は、広い体育館のスクリーンを使っての○×クイズです。
隣同士で話し合いをしながら、答えを考えています。
司会役の生徒を中心に、どんな質問にも明るく答え、場を盛り上げてくれました。
キャリアクション・プロジェクト出前授業「栃木県経済同友会」
10月31日(月)、1~3年生の希望者を対象に、栃木県経済同友会より株式会社古口工業の代表取締役である古口勇二先生を講師にお迎えし、「モノ造りとひと造り~継続は力なり~」をテーマにお話を伺いました。古口先生の働くこと・生きることに対する前向きな姿勢と、重責を担う会社経営者としてのパワフルな語り口が非常に心に残る授業でした。受講した生徒からは、「人生、社会人として大切な事を学んだので、将来自分が社会人となったときに当たり前の事ができる人になりたいと思った」「学生は探究心や真面目に生きる努力、大切な身体を造り続ける継続力が大切だとわかったのでこれらを意識して生活していきたい」などの感想が寄せられました。
キャリアクション・プロジェクト出前授業「宇都宮地方検察庁」
10月31日(月)7限、宇都宮地方検察庁より検察広報官の菊地佳美先生、検察事務官の阿久津泉美先生を講師にお迎えし、出前授業を実施しました。1~3年生の希望者を対象に、検察庁の組織や仕事の内容、その難しさややりがい等について、わかりやすくお話しいただきました。特に、検察官を支える検察事務官の職務内容が多岐に渡ることや、検察と警察の違いなど、初めて知ることも多い授業でした。「講義全体を通して、とてもやりがいのある仕事なのだろうなと思った」「ドラマをきっかけに検察という仕事に少し興味を持っていたが、具体的に何の仕事をしているかはあまり理解していなかったのですごく勉強になった」「正義感や責任感が仕事を続ける上でとても大切な事だとわかった」「新しい職業を知ることができて、また将来自分がどんな職業に就きたいか考えるきっかけになった」などの感想がありました。
第2学年「高校卒業後に待っている成年者としての世界」
10月25日(火)、東洋大学法学部より根岸謙先生をお迎えし、成年年齢の引き下げをテーマとした講義をお聞きしました。「”成年者”になると、法律上、どのような権利・義務を有するようになるのか」。民法を扱う一見難しそうなテーマでしたが、コンビニでの買い物やお年玉などの身近な例えや根岸先生の楽しい語り口によって、非常に分かりやすく興味深い講義となりました。大学とは何をする場所なのか、大学で学ぶためには何が必要なのかのお話も盛り込まれ、来年度18歳になる2年生にとって、大学での講義の雰囲気も感じられた有意義な時間でした。「成年になると自由が増えるけど、その分義務を負い、自分で責任を取らなければならないことが改めて分かった」「”大学とは自分の価値観をブラッシュアップするところ”という言葉が印象に残った」「大学で学ぶのが楽しみになった」などの感想がありました。
キャリアクション・プロジェクト「看護の出前授業」
10月11日(火)7時間目、新小山市民病院にお勤めの現役看護師、飯島翼様を講師にお迎えし、「看護の出前授業」を実施しました。受講者は看護職に関心を持つ1~3年生の希望者40名です。
看護職の仕事内容だけでなく、やりがいや難しさ、病院勤務以外にも活躍の場があること、ライフスタイルの変化に合わせて働き方を選べることもお話しいただき、看護職を希望する生徒たちはその目標を更に明確にすることができました。「高校や大学の時よりも、看護師になった今のほうが多くのことを学んでいる」という飯島先生のお言葉が印象に残った生徒も多く、特に入試を控えた3年生たちには学習へのモチベーションにつながったようです。
第3学年コミュニケーション・トレーニング
8月19・22・25日の3日間、「コミュニケーション・トレーニング」が行われました。受験予定先の試験で面接やグループ討議が行われる生徒、看護医療・教育・福祉・心理など対人コミュニケーション能力が要求される分野に進学したい生徒など、希望者を対象にしたプログラムです。
普段ぼんやりと考えていることも、改めて言葉にしようとするとなかなか難しいものです。聴き方・話し方・志望理由や自己PRの話し方などについて、実践的に学べるこのプログラムは、入学時の「構成的グループエンカウンター」と合わせて本校が長年取り組んでいる特徴的な活動の一つです。
25日は、「幸せの定義」についてグループ・ディスカッションを実施しました。写真は各自の定義を発表した後に、それらがどのように分類されるか話し合っている様子です。先生方のリードで、参加生徒たちは自ら挙手して発表し、仲間達の意見にも熱心に耳を傾けていました。
キャリアクション・プロジェクト⑥2学年「先輩の話」

キャリアクション・プロジェクト⑤1学年出前授業(その3)
○情報分野 宇都宮大学 共同教育学部 自然科学系技術分野 教授 川島芳昭 先生
サイバー犯罪の被害から自分の身を守るだけでなく、無自覚なまま加害行為を行わないためにも、情報モラルについて学ぶことの重要性を実感した講義でした。「ネット上のやりとりで、想像上の人物を作り上げてしまってはいけない」「『知識として知っている』を『やっている、守っている』へ」という先生のお言葉が印象的でした。
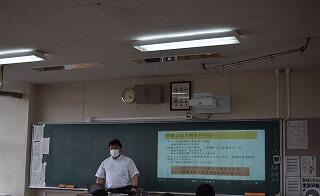
○保育分野 石橋おはなし会
保育分野では、小学校での読み聞かせ「小西おはなし会」を計画しています。絵本の持ち方、読み方、間の取り方など、読み聞かせの技術を石橋おはなし会の皆様から学びました。短い時間でしたが実習をすることもでき、今後の実践に繋がる講習会となりました。

○国際分野 JICA国際理解講師 大貫 文 先生
青年海外協力隊員として、ネパールに派遣されていた大貫先生。ネパールの地理や食生活、文字や学校の様子など、豊富な写真とともに非常に具体的にお話しくださいました。現地で活動する中で、国際援助の現実に葛藤を抱いた経験も語られ、求められる国際協力とはどのようなものなのか、非常に考えさせられる内容でした。