

文字
背景
行間

こんにちは! ASAHIとDAIGOです!!
今回はみんな大好きジャガイモとキャベツを栽培します
ジャガイモの植え付け
頂部を上にして押さえながら覆土
たねいもの向きがバラバラだと・・・
芽が出るタイミングもバラバラに(>_<)

キャベツの定植では深さに注意!!
浅すぎると水の吸収が悪く
深すぎると葉茎から根が出てしまうかも

根を切らないように丁寧に(*^▽^*)
水をしっかりあげて・・・
暑さに負けず元気に成長してね(^o^)丿
これであなたも定植マスター!!
挑戦してみて下さい!
図は境界点A・B・C・Dを直線で結んだ土地を表したもので,
土地を構成する各境界点の座標値は下のとおりである。
土地ABCDの面積の90%となる長方AEFDに整えたい。
このとき境界点FのX座標値を求めなさい。
図
点 X座標(m) Y座標(m)
A -20.630 -17.800
B +79.370 -17.800
C +39.370 +86.200
D -20.630 +78.200
こんにちは!農業工学科2年の塩澤と嶋﨑です!
私たち農工の2・3年生は5/19㈰の測量士補試験に向けて
勉強しています。
塩澤
『模擬試験を受けていますが、初めはなかなか点数が取れませんでした。
徐々に点数が上がっているので今後も頑張りたいです。』
嶋﨑
『公式や専門用語など覚えることが多く、理解するのにとても時間がかかります。
途中で諦めてしまいそうになりましたが、少しずつ努力し続けた結果、
今では合格圏内まで解けるようになりました!!
早い準備や他の問題と関連付けて考えるなど、
努力と工夫をすることで効率よく勉強出来ることを実感しました!!』
みんなで頑張ります!
初めまして!
農業工学科1年、ASAHIとDAIGOです!!
今後、授業の様子やFarmについて楽しくお届け致しますヾ(≧▽≦)ノ
新参者のですが、よろしくお願いします!
今回の実習はトウモロコシの播種とレタスの定植です
初めての実習でみんな興味津々です
トウモロコシの播種は
気持ちを込めてしっかり鎮圧しました!

レタスの定植では
マルチの穴が小さいので破れないように植えるのが難しかったです
定植直後の苗は赤ちゃんのような柔らかさなので
しっかり鎮圧するのがポイントです

初めての播種・定植なので元気に成長してほしいです(^^)/
『農業と環境』での野菜栽培を通してプロジェクト学習を行ってきました。
その内容を『農業と情報』の授業でパワーポイントにまとめたものを発表しました!
自分たちでどの作物を栽培するか考えプロジェクトの内容、実施計画、播種から収穫までの栽培など
班のみんなと協力して頑張りました!!
特に毎日の観察(Teamsの投稿)が意外と大変でした(>_<)
発表会は工夫されたスライドがたくさんあり、緊張しながらも一生懸命に発表していました。
遠藤「パワーポイントで活動内容をまとめることやみんなの前で発表することが楽しかったです。
また、先生方やみんなに『表現力が豊か』と言ってもらえたことが嬉しかったです!」


こんにちは!
農業工学科2年のゴウシです!
昨年11月、宇都宮市にある上欠沼の
『ブルーギル駆除ボランティア』に参加しました。
1年生4名、2年生4名の計8名で活動を行いました。
沼の両岸から大きな網をみんなではり、魚を追い込んでいきます。
沼の中に入る人と両岸から網を引っ張る人に分かれました。


沼の中担当は
水が冷たい
深いところは胸まで水が来る
泥で足が埋まる
転んで泥だらけの場面もありました!笑
岸の担当は
100mを超える網を引っ張りながら進めるのはとても重かったです。

成果は・・・
在来種もたくさんいましたが、
ブルーギルを含めた外来種の多さにビックリ!!
当初は数える予定でしたが、
ざっと見て数千尾いたため断念しました。


お昼には赤飯とけんちんうどんをご馳走になり、
冷えた体に沁み、とても美味しかったです。
こういった環境問題が身近なところで起きていることに驚きました。
今後も出来る範囲で色々なボランティアに参加していきたいです。
キャリア形成支援事業において
本校卒業生の谷口 様、福井コンピュータ(株) 様、(株)コアミ計測機 様に
講話と測量機器の実演をして頂きました。

『これまで』『現在』『これから』の建設業について、
経験談や『ICT化』によって効率化された現場、
今後求められる知識や技術などを説明して頂きました。
普段学ぶことができない貴重なお話で、
難しいところもありましたが生徒からは『すごい』『おもしろそう』
と言った声が上がっていました。
感想
しおざわ
「最新の測量器械や技術はとてもすごかったです。
スマホと連動したトータルステーションやドローン、
3Dモデルの技術を知ることが出来ました。」

農業工学科3年生が1年間の活動内容を1・2年生に発表しました。
3年生は緊張した様子でしたが一生懸命発表しており、1・2年生も真剣に聞いていました。

各班の活動内容は以下の通りです。
〇養蜂班 養蜂プロジェクト 養蜂箱の設計・製作
〇造園班 木枠プランター製作と和風庭園施工
〇竹班 竹の有効活用 竹製品の製作
〇施工班 土砂流出防止プロジェクト コンクリート擁壁の製作

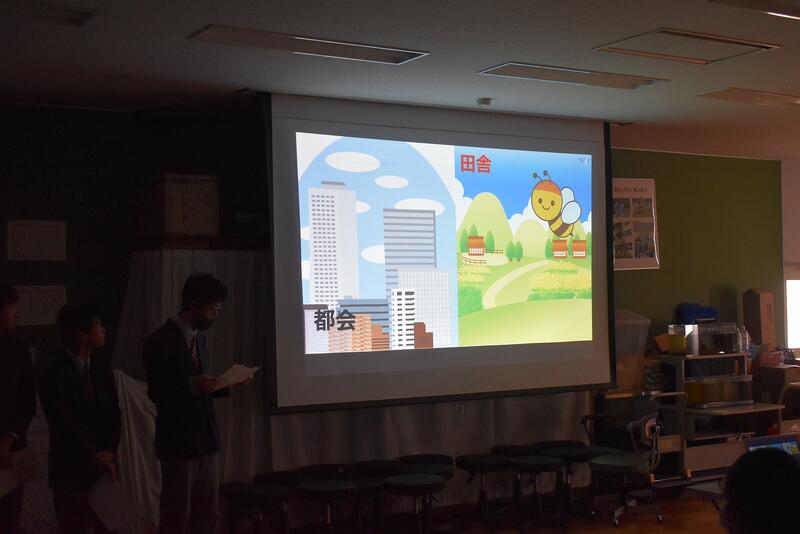

感想
2年マツモト
各班ともやりがいや難しさがあり、来年度の課題研究が楽しみになりました!
また、イラストや写真を利用したパワーポイントがとても見やすかったです。
2年ヤマダ
僕は竹班の発表が一番印象に残りました。
竹でサッカーゴールを作るための設計図がとても大変そうでした。
また、竹林の問題にも触れていて深刻なことを知りました。
来年度は竹班で、活動していきたいと思いました。
3年タナカ
木枠プランターは先輩の活動を参考に進めてきたので、スムーズに行えました。
庭園を一から考え作ることで楽しさや、大変さがわかりました
3年アサノ
1・2年生の前での発表は緊張しましたが、自分たちの活動を後輩に伝え、
興味を持ってもらいたいと思い頑張りました!とても有意義な時間となりました!
こんにちは!ニンジン班のシュンタです!
僕たちは
『3つの区画において追肥の回数を変え、ニンジンの大きさと肥料の関係を調べる!』
という内容でプロジェクト学習を行いました
品種 『陽明五寸』
播種 『すじまき』
『間引き』 2回行った
1回目 播種から6週間後
2回目 1回目から3週間後
収穫 収穫のタイミングは地上に出ている部分が5cmくらいになったら
結果
左から追肥なし・追肥1回・追肥2回
以上のことからニンジンの大きさが追肥の回数によって変化することが分かった
感想
ニンジンは栽培期間が長く、潅水や観察が大変だった
またたくさん収穫でき、プロジェクト学習も成功させられて良かった
【 葉ねぎ日記 】
葉ねぎB班 清水・三上・大房・小林・黒﨑
今回、僕たちは冬の寒い時期にも育てることが可能な【葉ねぎ】を栽培することにしました。
実習内容
間引きをするとしないとでは、見た目や味、収量に変化は出るのか。
結果 間引きアリ 間引きナシ
30本収量 188g 115g
総収量 656g 1390g
味と見た目には変化はなかったが、収量には差が出ました。
感想
プロジェクト学習を進めていくうちに 農作物への探求心が強まり、
計画的に実行することができました。 収穫した葉ねぎは美味しくいただきました。
【 これが俺らの葉ネギだぜ!! 】
葉ネギA班のリクです!
僕達は葉ネギ栽培を通してプロジェクト学習を行いました。
内容 収穫時期を3回に分けた場合、味や食感に変化はあるのか
管理 播種、水やり、除草、間引き等
結果 味はあまり違いを感じられませんでしたが、食感には少し違いがありました。
早い収穫は少し硬い 遅い収穫は少し柔らかかった
感想 葉ネギは乾燥に弱いので1回も忘れずに水やりをするのが大変でした。
また、最初の頃は葉ネギの子葉と雑草が似ていたので間違えて抜かないように注意しました。
【 僕たちとカブの成長 】
こんにちは、カブ班です。
プロジェクト課題 『1番美味しい収穫時期はいつか』
カブは収穫時期を過ぎると玉割れ・ス・根割れ、味が落ちてしまう
本当なのか?!
収穫時期を週ごとに区切り、味の評価・大きさ・重さ・色合いは
どの週が良いのか、最も美味しいのは?を検証しました!
9月中旬 大カブは1条、小カブは2条で播種
9月下旬 1回目の間引き 発芽数が多く間引きが大変だった
10月上旬 2回目の間引き 間引きが遅くなってしまった
11月上旬 小カブの収穫 そこから1週間ごとに収穫
11月下旬 大カブの収穫 そこから1週間ごとに収穫
大カブは聖護院カブなので横長かと思いきや縦カブでした!!


結果 小カブは時期を遅らせると大きくなるが、根割れが多かった
大カブも時期を遅らせると根割れ・スなどが多かった
また、食味が落ちてしまうことが分かった!
振り返り
間引きが少し遅かった
収穫を区切る期間を短くしたほうが良かった
カブのように僕たちもまだまだ成長していきたいです!
こんにちは!ユウタです!
僕たちホウレンソウ班の課題は
『播種時期を変えて収穫を同時にすると味は変わるのか』です!
種まき → 水やり → 間引き → 収穫
まず初めに種まきをしました。『すじ播き』をして覆土、
水で流されないように鎮圧をしました。
水やり 乾燥に弱いので最初の頃は毎日交代で水やりをしました!
苗が少し大きくなったら間引きをしました。
最後に収穫です!
みんなで協力してできました!
研究結果は・・・
普通が1番!!