文字
背景
行間
平成29年度 SPH活動報告・ニュース
SPH活動報告・ニュース
本校のSPHを発信 in 県総合文化センター(その1)
11月2日(木)午前中に、県総合文化センターで開催された「とちぎの高校生課題研究等発表会」において、SPHの研究指定校となって3年目となる現在の取組と、研究を通して得られた成果等についての発表を行ってきました。
「とちぎの高校生課題研究等発表会」は、県内代表5校がそれぞれのテーマで発表を行うことにより、互いに学びを深め合うことを通して、社会や世界とのつながりを意識することを目的として、県教委が今年度初めて開催したものです。
発表会には、本校を代表して、建築デザイン科3年の伊藤夏洋さん、加藤大貴さん、菊地郁哉さん、小村赳央さん、福岡健太郎さんの5人が参加し、『世界に羽ばたくグローバルエンジニアの育成を目指して~「木造建築物の耐震実験」と「美観を備えた耐力壁の開発」~』というタイトルで、発表を行いました。
本校SPHの取組内容を、パワーポイントにまとめ、わかりやすく明確にプレゼンテーションすることにより、多くの成果を、来場者を通し、県内高校に広く発信することができました。


「とちぎの高校生課題研究等発表会」は、県内代表5校がそれぞれのテーマで発表を行うことにより、互いに学びを深め合うことを通して、社会や世界とのつながりを意識することを目的として、県教委が今年度初めて開催したものです。
発表会には、本校を代表して、建築デザイン科3年の伊藤夏洋さん、加藤大貴さん、菊地郁哉さん、小村赳央さん、福岡健太郎さんの5人が参加し、『世界に羽ばたくグローバルエンジニアの育成を目指して~「木造建築物の耐震実験」と「美観を備えた耐力壁の開発」~』というタイトルで、発表を行いました。
本校SPHの取組内容を、パワーポイントにまとめ、わかりやすく明確にプレゼンテーションすることにより、多くの成果を、来場者を通し、県内高校に広く発信することができました。


0
アクティブ・ラーニングを活用した実習 ~流速はどう計るか~
10月30日(月)に、環境設備科3年生の設備実習において、アクティブ・ラーニングの手法を取り入れた公開実習を行いました。
今回の実習は、水理実習装置を用いて、「流速をどのように計るか」、「流量をどうのように求めるのか」を考える実習です。
生徒達は、ベンチュリ管(流体の流れを絞ることによって流速を増加し、低速部にくらべて低い圧力を発生させる効果を応用)や、オリフィス板(流量を求める装置)により「流れる力」が変化することに興味を持ち、話し合いを通して考えを深めながら、流速や流量を求めることができました。




今回の実習は、水理実習装置を用いて、「流速をどのように計るか」、「流量をどうのように求めるのか」を考える実習です。
生徒達は、ベンチュリ管(流体の流れを絞ることによって流速を増加し、低速部にくらべて低い圧力を発生させる効果を応用)や、オリフィス板(流量を求める装置)により「流れる力」が変化することに興味を持ち、話し合いを通して考えを深めながら、流速や流量を求めることができました。




0
栃木県伝統工芸品展2017に「鹿沼組子の耐力壁」を出展
10月28日(土)~29日(日)に、栃木県庁昭和館で開催された「栃木県伝統工芸品展2017」において、「鹿沼組子の耐力壁」を展示、説明しました。
「栃木県伝統工芸品展」は、本県の風土と生活の中で育まれ、受け継がれてきた栃木県伝統工芸品を見て、触れていただく展覧会です。益子焼、結城紬などの伝統工芸士による製作実演のほか、伝統工芸品の販売や製作体験コーナーが開設されました。
本校の「鹿沼組子の耐力壁」を出展したことで、たくさんの県民の方々に、これまでの取組みを理解いただき、多くの成果を発信することができました。




「栃木県伝統工芸品展」は、本県の風土と生活の中で育まれ、受け継がれてきた栃木県伝統工芸品を見て、触れていただく展覧会です。益子焼、結城紬などの伝統工芸士による製作実演のほか、伝統工芸品の販売や製作体験コーナーが開設されました。
本校の「鹿沼組子の耐力壁」を出展したことで、たくさんの県民の方々に、これまでの取組みを理解いただき、多くの成果を発信することができました。




0
国土交通大臣の「耐力壁認定」に向けた試験が始まる!
10月23日(月)~25日(水)に、一般財団法人建材試験センター(埼玉県草加市)で、建築デザイン科3年の課題研究班11名による「国土交通大臣の耐力壁認定」に向けた、「鹿沼組子による耐力壁」の性能評価試験が始まりました。
今回の試験では、高さ2,700㎜×幅1,800㎜×奥行90㎜の試験体を製作し、板厚22㎜の交差部分をピン接合とした耐力壁と、交差部分をピン接合しない耐力壁の性能評価試験を、それぞれ行いました。性能評価試験は、耐力の再現性を確認するため、3回実施し、計12体の組立と解体を含めて、3日間かかりました。
(一財)建材試験センターを利用した性能評価試験は初めてで、生徒達は、非常に緊張した面持ちで作業を分担しながら、意欲的に性能評価試験に取り組んでいました。




今回の試験では、高さ2,700㎜×幅1,800㎜×奥行90㎜の試験体を製作し、板厚22㎜の交差部分をピン接合とした耐力壁と、交差部分をピン接合しない耐力壁の性能評価試験を、それぞれ行いました。性能評価試験は、耐力の再現性を確認するため、3回実施し、計12体の組立と解体を含めて、3日間かかりました。
(一財)建材試験センターを利用した性能評価試験は初めてで、生徒達は、非常に緊張した面持ちで作業を分担しながら、意欲的に性能評価試験に取り組んでいました。




0
「知的財産」について in サンフェア秋田(その3)
10月21日(土)~22日(日)、「第27回全国産業教育フェア秋田大会サンフェア秋田」で、「知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業成果展示・発表会」が開催されました。この展示・発表会は、「知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業」における各校の取組内容や成果の展示・発表になります。
参加13校の実践例を見学することにより、「知的財産」に関する知識が高まり、さらに「起業」への興味・関心を高めることができました。


参加13校の実践例を見学することにより、「知的財産」に関する知識が高まり、さらに「起業」への興味・関心を高めることができました。


0
「白熱トーク」 in サンフェア秋田(その2)
10月22日(日)に、「第27回全国産業教育フェア秋田大会サンフェア秋田」で、「白熱トーク」が開催されました。これは、グローバル社会で活躍するために求められる起業家精神の育成を目的とし、地域の企業についての調査・研究発をもとに、28人の高校生と4人の企業関係者等によりパネルディスカッションが行われました。
本校の建築デザイン科3年の岩井真央里さん、野口颯汰さん、伊藤夏洋さんが出場し、自己紹介のあと、参加企業に「海外進出の状況」を質問しました。
企業についての調査・研究発表や、企業関係者の話から、グローバル社会で活躍するために必要なことを学ぶごとができました。


本校の建築デザイン科3年の岩井真央里さん、野口颯汰さん、伊藤夏洋さんが出場し、自己紹介のあと、参加企業に「海外進出の状況」を質問しました。
企業についての調査・研究発表や、企業関係者の話から、グローバル社会で活躍するために必要なことを学ぶごとができました。


0
本校のSPHを発信 in 「サンフェア秋田」(その1)
10月20日(金)~22日(日)に、秋田市内で開催された「第27回全国産業教育フェア秋田大会サンフェア秋田」において、SPHの研究指定校となって3年目となる現在の取組と、研究を通して得られた成果等についての発表を行ってきました。
発表会には、本校を代表して、建築デザイン科3年の岩井真央里さん、野口颯汰さん、伊藤夏洋さんが参加し、『世界に羽ばたくグローバルエンジニアの育成を目指して~「木造建築物の耐震実験」と「美観を備えた耐力壁の開発」~』というタイトルで、発表しました。
本校SPHの取組内容を、パワーポイントにまとめ、わかりやすく明確にプレゼンテーションすることにより、多くの成果を、来場者を通し、全国に向け発信することができました。




発表会には、本校を代表して、建築デザイン科3年の岩井真央里さん、野口颯汰さん、伊藤夏洋さんが参加し、『世界に羽ばたくグローバルエンジニアの育成を目指して~「木造建築物の耐震実験」と「美観を備えた耐力壁の開発」~』というタイトルで、発表しました。
本校SPHの取組内容を、パワーポイントにまとめ、わかりやすく明確にプレゼンテーションすることにより、多くの成果を、来場者を通し、全国に向け発信することができました。




0
祝!「第26回AP展」で日本工業経済新聞社長賞を受賞しました
10月14日(土)~15日(日)に、マロニエプラザで開催された「第26回AP(Architect People)展」において、本校建築デザイン科「鹿沼組子壁」が、日本工業経済新聞社長賞を受賞しました。

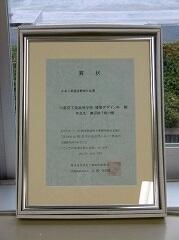


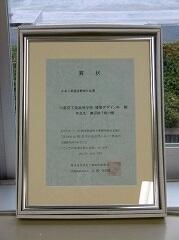

0
「外部講師による特別英語講座」始まる~第2弾を開講~
 10月6日(金)放課後、多目的室で希望者を対象として、「外部講師による特別英語講座」を開講しました。
10月6日(金)放課後、多目的室で希望者を対象として、「外部講師による特別英語講座」を開講しました。この講座は、グローバルエンジニアの育成にあたって、外国語(英語)の活用能力の向上を図るためのものです。(株)イーオンの鈴木貞仁先生を講師とした、本年度、第2弾となる10回シリーズのGTEC英語講座です。この講座では、主にGTEC for STUDENTSの受検対策をしますが、英検準2級や英検2級受検を目指している生徒にも適しているものです。
1回目となる今回は、オリエンテーションを兼ねた講座でしたが、生徒たちは、とても真剣な眼差しで、講義に臨んでいました。
0
「技能五輪」を知る~第2弾~
10月4日(水)、1年生の全員を対象として、学校設定科目「科学技術と産業」の時間を利用し、(株)日立製作所、技能五輪機械製図職種主査の鳴海裕一先生を講師として、大講義室と会議室で「機械製図CAD」の講習会を実施しました。生徒達は、左手で電卓、右手でマウスを操作する様子に驚き、「集中して繰り返し練習すること」や、「限界を決めないで挑戦し続けること」を学びました。
前回は、講話やDVDから競技を理解しましたが、今回は、「機械製図CAD」の作業を間近で見学できたことで、さらに刺激を受け、「技能五輪」について理解を深め、「技能力向上」に向けて興味・関心を高めることができました。


前回は、講話やDVDから競技を理解しましたが、今回は、「機械製図CAD」の作業を間近で見学できたことで、さらに刺激を受け、「技能五輪」について理解を深め、「技能力向上」に向けて興味・関心を高めることができました。


0
アクティブ・ラーニングを活用~コンクリートの圧縮強度試験~
9月20日(水)、9月27日(水)に環境土木科2年生が、土木実習において、アクティブ・ラーニングの手法を取り入れた公開実習を行いました。
コンクリートの強度は、配合する材料やその量によって変わり、従来の実習では、教科書の配合を基本にしてコンクリートを作っていました。今回の実習は、この基本配合を元に、水、セメント、砂、砂利をどのように調合すればさらに強度が高まるかを考えました。2日目には、万能材料試験機で圧縮強度試験を行い、実験結果より強度と材料との関係を考えることができました。
生徒達は、今まで学んだ基本的な知識や技能を組み合わせ、問題を発見し、話し合いながらそれを解決し、自分たちで考え、工夫し、互いに協力する様子が見られました。




コンクリートの強度は、配合する材料やその量によって変わり、従来の実習では、教科書の配合を基本にしてコンクリートを作っていました。今回の実習は、この基本配合を元に、水、セメント、砂、砂利をどのように調合すればさらに強度が高まるかを考えました。2日目には、万能材料試験機で圧縮強度試験を行い、実験結果より強度と材料との関係を考えることができました。
生徒達は、今まで学んだ基本的な知識や技能を組み合わせ、問題を発見し、話し合いながらそれを解決し、自分たちで考え、工夫し、互いに協力する様子が見られました。




0
第3弾!「鹿沼組子による耐力壁」の性能試験
9月26日(火)、栃木県林業センター(宇都宮市下小池町)のご協力を得て、建築デザイン科3年の課題研究班が、「鹿沼組子による耐力壁」の性能試験を行いました。9月8日(金)に次いで、今年度3回目の性能試験となります。前回の試験では、ピンの径を細くした耐力壁と、組子のデザインを変更した耐力壁の性能試験を、それぞれ行いました。
今回は、交差部分のピンがない状態で性能試験を行いました。壁倍率は、前回の壁倍率を下回る試験データになりましたが、ピン有無の効果が確認できました。
また、NHKのTV取材や、読売新聞社、下野新聞社からの取材があり、本校の取組の様子が、各種メディアで紹介されました。


今回は、交差部分のピンがない状態で性能試験を行いました。壁倍率は、前回の壁倍率を下回る試験データになりましたが、ピン有無の効果が確認できました。
また、NHKのTV取材や、読売新聞社、下野新聞社からの取材があり、本校の取組の様子が、各種メディアで紹介されました。


0
アクティブ・ラーニングを活用した実習 ~ロボット制御~
9月25日(月)、機械システム系1年C組の工業技術基礎において、アクティブ・ラーニングの手法を取り入れた公開実習を行いました。
この実習は、制御を学ぶ実習で、自立型ロボット・マインドストーム(LEGO社)を利用し、基本的な命令・動作を学び、光センサを用いて、ロボットにライントレースをさせるものです。生徒達には、学んだ知識や技能を組み合わせ、問題を発見し、自分たちで考え、工夫し、互いに連携する様子が見られました。
アンケート結果から、「実習」について、意欲的に参加し、主体的に学び、議論する力(思考力・判断力・表現力)が高まったことが確認できました。


この実習は、制御を学ぶ実習で、自立型ロボット・マインドストーム(LEGO社)を利用し、基本的な命令・動作を学び、光センサを用いて、ロボットにライントレースをさせるものです。生徒達には、学んだ知識や技能を組み合わせ、問題を発見し、自分たちで考え、工夫し、互いに連携する様子が見られました。
アンケート結果から、「実習」について、意欲的に参加し、主体的に学び、議論する力(思考力・判断力・表現力)が高まったことが確認できました。


0
アクティブ・ラーニングを活用した実習 ~電気工事士~
9月12日(火)に電気情報システム系1年B組が、9月14日(木)に電気情報システム系1年A組が、それぞれ工業技術基礎において、アクティブ・ラーニングの手法を取り入れた公開実習を行いました。
この実習は、1学期に学んだ「電気工事」を振り返り、4人一組でチームを組み、材料選別作業からスタートし、5分交代で屋内配線の単位作業を完成させるものです。生徒達は、グループの中で、今まで学んだ基本的な知識や技能を組み合わせ、問題を発見し、話し合いながらそれを解決しており、自分たちで考え、工夫し、互いに連携する様子が見られました。これらのことから、「電気工事」の知識や技能が生徒たちに、確実に定着している様子が確認できました。




この実習は、1学期に学んだ「電気工事」を振り返り、4人一組でチームを組み、材料選別作業からスタートし、5分交代で屋内配線の単位作業を完成させるものです。生徒達は、グループの中で、今まで学んだ基本的な知識や技能を組み合わせ、問題を発見し、話し合いながらそれを解決しており、自分たちで考え、工夫し、互いに連携する様子が見られました。これらのことから、「電気工事」の知識や技能が生徒たちに、確実に定着している様子が確認できました。




0
第2弾!「鹿沼組子による耐力壁」の性能試験
9月8日(金)、栃木県林業センター(宇都宮市下小池町)のご協力を得て、建築デザイン科3年の課題研究班が、「鹿沼組子による耐力壁」の性能試験を行いました。6月6日(火)に次いで、今年度2回目の性能試験となります。前回の試験では、板厚18㎜、交差部分をピン接合としたものの性能試験を行いました。今回は、柱・粱との一体化を図り、板厚を厚く、ピンの径を細くした耐力壁①と、組子のデザインを変更した耐力壁②の2体の性能試験を、それぞれ行いました。
その結果、耐力壁①の壁倍率が3.59程度と、今までの壁倍率を大きく上回る試験データが得られました。この試験結果により、さらに強度を高めるための新たな対応策等を確認できました。


図1 耐力壁① 図2 耐力壁②
その結果、耐力壁①の壁倍率が3.59程度と、今までの壁倍率を大きく上回る試験データが得られました。この試験結果により、さらに強度を高めるための新たな対応策等を確認できました。


図1 耐力壁① 図2 耐力壁②
0
「南極観測」を通してグローバルな視点を養う!
9月6日(水)、1年生全員を対象として、学校設定科目の「科学技術と産業」の時間を利用し、大講義室で「企業人による講話」を行いました。
国土交通省国土地理院(つくば市)から吉高神充先生(本校OB)を講師にお招きし、国土地理院の業務内容、新技術の開発・研究やその動向、南極観測隊の経験から観測の重要性、観測隊の活動について、スライドや動画を用いてわかりやすく説明いただきました。事後アンケートからは、62%の生徒が「南極観測隊に参加したい」、「どちらかといえば参加したい」と回答があり、事前アンケートと比べて4倍以上もの生徒が、南極観測に強い興味・関心を持ったことが分かりました。温暖化や気象の観測を通して、国際的に活動している吉高神先生の講話により、生徒達は「グローバル」な視点から活動することの意味を実感できる良い機会になりました。


写真:南極の氷(2万年前の大気を観察する)
国土交通省国土地理院(つくば市)から吉高神充先生(本校OB)を講師にお招きし、国土地理院の業務内容、新技術の開発・研究やその動向、南極観測隊の経験から観測の重要性、観測隊の活動について、スライドや動画を用いてわかりやすく説明いただきました。事後アンケートからは、62%の生徒が「南極観測隊に参加したい」、「どちらかといえば参加したい」と回答があり、事前アンケートと比べて4倍以上もの生徒が、南極観測に強い興味・関心を持ったことが分かりました。温暖化や気象の観測を通して、国際的に活動している吉高神先生の講話により、生徒達は「グローバル」な視点から活動することの意味を実感できる良い機会になりました。


写真:南極の氷(2万年前の大気を観察する)
0
「鹿沼組子の耐力壁」一般住宅へ設置される!
8月28日(月)、青木様邸(下野市駅東)の新築工事(添野工務店施工)で、本校の建築デザイン科3年の課題研究班(8名)が、「鹿沼組子の耐力壁」を設置しました。
この「耐力壁」は、光の透過性に着目した「デザイン壁」です。当日は、下野新聞や東京新聞、とちぎテレビから取材を受け、今までの取組の様子が紹介されました。
今回の設置工事は、生徒一人一人にとって、「伝統技法に関する研究」の取組の成果を確認し、外部に発表できる良い機会になりました。


写真1:耐力壁を取り付ける 写真2:青木様と生徒たち
この「耐力壁」は、光の透過性に着目した「デザイン壁」です。当日は、下野新聞や東京新聞、とちぎテレビから取材を受け、今までの取組の様子が紹介されました。
今回の設置工事は、生徒一人一人にとって、「伝統技法に関する研究」の取組の成果を確認し、外部に発表できる良い機会になりました。


写真1:耐力壁を取り付ける 写真2:青木様と生徒たち
0
建築デザイン科の12名が「下野新聞」で紹介されました!
8月29日(火)付け「下野新聞」に、「鹿沼組子で耐力壁制作~新築民家に設置~」という記事に、建築デザイン科の12名の取り組みが紹介されました。

(8月29日付下野新聞)

(8月29日付下野新聞)
0
「鹿沼組子による耐震壁」を新築工事へ!
8月28日(月)、青木様邸(下野市駅東)の新築工事(添野工務店施工)で、本校、建築デザイン科3年の課題研究班(12名)が、「鹿沼組子による耐力壁」の設置を行うことになりました。
今回の新築工事における「鹿沼組子による耐力壁」は、光の透過性を活かしたデザインに注目したものですが、一般住宅に設置されることは今までの研究の大きな成果です。
実際の住宅への設置方法や段取りについて、添野工務店様に技術指導を受けながら生徒たちは学習していきます。


今回の新築工事における「鹿沼組子による耐力壁」は、光の透過性を活かしたデザインに注目したものですが、一般住宅に設置されることは今までの研究の大きな成果です。
実際の住宅への設置方法や段取りについて、添野工務店様に技術指導を受けながら生徒たちは学習していきます。


0
テクノプラザから発信~その2~
8月16日(水)、本校テクノプラザの掲示コーナに、SPHで取り組んだ「鹿沼組子による耐力壁」のポスターを掲示しました。
「伝統技術への挑戦!鹿沼組子を耐力壁に!!」をタイトルに、本校の伝統技法への取り組みを地域の方々をはじめ、JR雀宮駅や市立南図書館を利用する多くの方に発信していきます。


「伝統技術への挑戦!鹿沼組子を耐力壁に!!」をタイトルに、本校の伝統技法への取り組みを地域の方々をはじめ、JR雀宮駅や市立南図書館を利用する多くの方に発信していきます。


0

