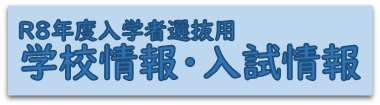 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
バナーをクリックすると各学科のページに移動します。

9月22日(月)5~6時限目、大進電気工事(株) 様を講師にお迎えし、電子科1年生を対象に電気工事に関する技能講習会(スイッチ付き電源コードの製作)を実施しました。
電源コードの加工や圧着工具を使用した丸形端子の取り付け、プラグ内のフォーミング手順など説明して頂きました。また、製作した電源コードの使用方法や許容電流についても学習しました。最後にランプを点灯させる動作テストを行い、生徒全員が達成感を味わうことのできた講習会となりました。


2月26日(水)1限~4限、大進電気工事(株)様を講師に迎え、電子科2年生を対象に電気工事に関する技能講習会(エアコン設置工事)を実施しました。
冷暖房の仕組みや、エアコン工事に必要な真空引き工事等を実演を踏まえながら説明して頂きました。さらに、真空引き工事で行う銅管の「フレア加工」を体験することが出来ました。参加した生徒たちも興味深く見学し、積極的に参加していました。




本日、令和7年1月16日(木)に電子科3年生が1年間取り組んできた課題研究の成果を発表する、課題研究発表会を開きました。聴衆として電子科1・2年生が参加しました。
3年生はどの班も一生懸命に堂々と発表に臨んでおり、聴衆していた1、2年生は自分たちの課題研究のテーマ設定に参考にすべく真剣に3年生の発表を聴いていました。
今年の課題研究テーマは以下の6つです(発表順)。
1.ギガスクール教育用端末の有効活用について
2.動画編集
3.逃げるゴミ箱
4.自動栽培装置の研究
5.風力発電の研究
6.電気工事
また、「ギガスクール教育用端末の有効活用について」班は、明日行われる令和6年度第35回工業関係高等学校生徒研究発表大会(栃高教研工業部会主催)に矢板高校代表として参加して参ります。
2024年7月27日(土曜日)令和6年度栃木県高校生ものづくりコンテスト(電気工事部門)が行われました。電子科からは3年生2名が出場いたしました。競技は県内7校から11名が参加して行われました。十分な空調設備がない会場で、選手たちは汗だくになって課題に挑みました。
結果、本校電子科3年平山君が5位に入賞することが出来ました。




本日、2024年7月27日(土)に行われた令和6年度栃木県高校生ものづくりコンテスト(電子組込部門)に、電子技術研究部(兼電子科3年)の生徒2名が出場いたしました。
今年度の3年生は、1年次からArduinoマイコンを勉強し続け、3年間磨いてきた技術の集大成となる大会となりました。結果は惜しくも上位入賞はできませんでしたが、本校がものコン(電子組込部門)に出場し始めてから3年目となりますが、本校にとって過去最高の結果となりました。
これで今年度の大きな大会は終わりになりますが、11/2(土)に開催を予定している矢高祭に向けて、来校されるお客様に楽しんで貰える展示を準備していきます。そこで、今回の大会に使用した制御基板も展示する予定です。是非、私たち電子技術研究部の活動を見て頂きたいので、11/2(土)の矢高祭に遊びに来てください。
6月18日(火)、電子科1年生は、産業施設見学として午前に日本大学工学部(郡山キャンパス)様と午後に株式会社アローテックス様に見学に伺いました。
日本大学様では、主に電気電子工学科を見学させていただきました。大学の概要説明(勉強、生活、進路など)や、研究室における研究内容の説明と体験をさせていただきました。
見学の様子が大学のHPに掲載されております。→こちら

株式会社アローテックス様では、会社の概要説明と工場内の見学をさせていただきました。製造機械と人のそれぞれが行うはんだ付けや製品ができるまでを見学させていただきました。こちらは、矢高の先輩が働いていたり、2年生がインターンシップでお世話になっています。
生徒たちは、熱心に話を聞いてメモを取り、積極的に質問をしていました。進路について考える機会になったと思います。
お忙しいところご対応いただいた日本大学様およびアロテックス関係者の皆様、ありがとうございました。
6月18日(火曜日)電子科はキャリア形成支援事業産業施設見学を行いました。
3年生はブリヂストン株式会社那須工場と株式会社栃木ニコンへ行って参りました。
ブリヂストン(株)那須工場様では企業説明やタイヤ製造工程の講義の後、ゴムタイヤ
の製造現場を見学いたしました。またVR(バーチャルリアリティー)体験もさせてい
ただきました。

栃木ニコン様ではカメラやレンズなどの講義の後、レンズの製造工程を見学させてい
ただきました。

どちらも栃木県を代表する企業です。この経験が今後の進路選択につながることを期待
しています。
本日、6/19(水)に電子科2年生は、産業施設見学として午前に沼原発電所(電源開発株式会社)、午後に電力中央研究所塩原実験場に見学に行きました。
本日の見学を通して、発電や電力送電の仕組み、雷の危険性など電子科にとって大切な電気に関する学習ができ、充実した一日になりました。
11月16日(木曜日)工業技術コンクールが行われました。
電子科3年生が3年間で習得した専門的な技術の成果を競う行事です。
今年度は以下の4種のテーマで実施いたしました。
・ダイオード静特性の測定
・C言語プログラミング
・リレーシーケンス制御
・電圧降下法による抵抗値の測定
生徒は真剣な態度でコンクールに臨んでいました。
上位3名は栃木県高等学校教育研究会工業部会から表彰されます。
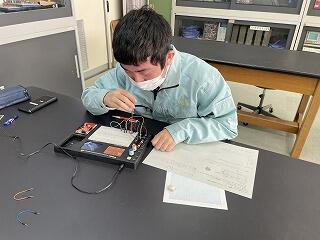
ダイオード静特性の測定 C言語プログラミング

リレーシーケンス制御 電圧降下法による抵抗値の測定
10月1日(日曜日)矢板市本通りで行われた第15回やいた軽トラ市に参加いたしました。

電子科では缶バッジ製作ワークショップと課題研究作品の展示と実演を行いました。

小学生を中心にたくさんの方々に参加していただきました。
課題研究作品は共鳴管スピーカー、ArduinoによるLED制御装置、全方向移動ロボットを展示いたしました。
生徒たちは不慣れな接客にも果敢に挑戦していました。今後の活動に大いに役立つ経験ができたと思います。
令和5年度栃木県高校生ものづくりコンテストが7月29日(土)宇都宮工業高校で開催されました。
本校電子科からは電気工事部門に3年生の螺良颯希君と2年生の平山大翔君の2名が参加いたしました。
十分な空調設備の無い過酷な作業環境でしたが、生徒たちは普段の練習の成果を発揮し、電子科3年螺良颯希君が見事3位入賞を果たしました。電気工事部門では本校初の入賞です。
今回残念ながら入賞を逃した平山君には来年度関東大会への出場権を得られる2位以内の入賞を目指して欲しいと思います。



本日、令和4年7月30日(土)に行われた令和5年度栃木県高校生ものづくりコンテストに、旋盤部門に機械科から2名、電子回路組込部門に電子技術研究部から2名、電気工事部門に同じく電子技術研究部から2名が出場しました。
電子回路組込部門には昨年度から出場を始めて、今年度出場した3年生は、去年の3年生と一緒にArduinoと呼ばれるマイコンを使った制御プログラムを約1年半勉強してきました。また、この大会に出場するため、昨年度の3年生が利用した大会基板セットを1つのボードにまとめるなど、昨年度よりパワーアップをして出場しました。
結果としては、上位入賞は果たせませんでしたが、これまで培ってきたプログラミング技術を少しでも多く発揮できたと思います。
明日7/29(土)に行われる令和5年度栃木県高校生ものづくりコンテストに電子技術研究部から電気工事部門に2名、電子回路組込部門に2名(計4名)が出場予定です。
電子回路組込部門においては、プログラミング環境を大会会場となる宇都宮工業高校のPCを利用させて頂く関係で、本日7/28(金)の午前中に大会会場での動作確認を行うための事前練習会に大会出場者と補助員となる3年生4名で参加いたしました。
今年度出場する3年生は、昨年度の3年生と一緒に約1年半かけてプログラミングの勉強を重ねてきました。これまで勉強を重ねた成果を明日発揮するできることを期待しています。
6月20日(火)電子科3年生が企業見学を実施しました。
今回ご協力いただいたのは、清原工業団地内の株式会社長府製作所 宇都宮工場 様とカルビー株式会社 清原工場 様です。
午前の長府製作所様では「給湯機器」の製造過程(製造-検査-出荷)についてとショールームでは給湯機器と空調機器、浴室などを見学させていただきました。
午後のカルビー様では「かっぱえびせん」と「フルグラ」の製造過程(製造-検査-出荷)について工場内を見学させていただきました。
また、社会人になっても大切なこと(笑顔、挨拶、感謝)についてお話しいただきました。
どちらの企業様も社員の方が丁寧に説明してくださり、とても分かりやすかったです。
生徒たちは見学中メモを取るなどして学ぼうとする姿勢が見られ、進路決定を控えた3年生の真剣さを感じられました。
各企業の皆様、お忙しいところ受け入れていただきありがとうございました。
電子科2年 産業施設見学 栃木県川治第一発電所、電力中央研究所塩原実験場
電子科産業施設見学を6月20日(火曜日)に実施いたしました。
電子科2年生は栃木県営の水力発電所である栃木県川治第一発電所と、送電や落雷の実験を行っている電力中央研究所塩原実験場に行って参りました。
川治第一発電所では、栃木県が所有するダムや水力発電所の概要説明の後、発電所内の発電設備を見学いたしました。この発電所は遠隔操作で運営されており、通常時は無人で運転されています。生徒は、水力発電に関する知識を深めることができたと思います。



午後は、一般財団法人電力中央研究所塩原実験場を見学いたしました。こちらでは送電に関する研究や落雷の研究を行っています。人工的に落雷を起こす放電実験の見学後、直流送電実験施設などを見学させていただきました。生徒は施設の規模や雷鳴などに驚くとともに電気に対しての興味関心を深めることができたと思います。



今回の産業施設見学を通して、今後の学習や進路に役立つ貴重な経験ができたと思います。
本日(令和5年6月20日(火))に電子科1年生は、
午前:日本大学工学部電気電子工学科
午後:(株)アローテックス
に産業施設見学としてお邪魔させて頂きました。
進学と就職がまだはっきりと決まっていない1年生にとって、進学か就職を考える上、非常に勉強になった1日になったと思います。本日の見学を進路決定に役立てて欲しいです。
電技研部が教職員研修の手伝いをしました
令和5年3月21日(祝・火)に特別支援学校の先生を中心とした「おにぎりVOCA作り」の研修(会場:宇都宮・栃木県教育会館)が行われ、その研修に使われた材料の一部を本校電子技術研究部が加工(協力)しました。
本校生徒が加工した材料が先生方の研修に役立たれて、研修に関わった先生からも感謝のお言葉を頂き、間接的ではありますが、本校生徒が活躍できたことが非常に誇らしいです。
今後も校内だけでなく校外でも生徒が活躍できるよう、様々なところで協力していこうと思います。
※おにぎりVOCAとは
おにぎりケースを用いたVOCA(Voice Output Communication Aid)であり、障害を持つ方々のICT支援における機器や支援方法の一種です。事前に録音された音をボタン一つで再生することができる機器で、発声が難しい方が周囲とコミュニケーションを取るための補助機器として使用されるなど、様々な用途で使用されています。
材料加工の様子
研修当日の様子
加工した材料とおにぎりVOCA完成品
電子科3年生の課題研究発表会を開催いたしました
本日、令和5年1月19日(木)に電子科3年生が1年間取り組んできた課題研究の成果を発表する、課題研究発表会を開きました。聴衆として、電子科全生徒が参加し、校長先生を始めとする多くの先生方も聴衆して頂きました。
3年生はどの班も一生懸命に堂々と発表に臨んでおり、聴衆していた1、2年生は自分たちの課題研究のテーマ設定に参考にすべく真剣に3年生の発表を聴いていました。
今年の課題研究テーマは以下の7つです(発表順)。
1.水耕栽培
2.移動するゴミ箱
3.ソーラーパネルを用いた製作
4.Wi-Fiのサイトサーベイ
5.シーケンス制御実習装置(PLC)の製作
6.Arduinoを用いた制御
7.電子回路を用いたものづくり
また、「Wi-Fiのサイトサーベイ」班は、明日行われる令和4年度第33回工業関係高等学校生徒研究発表大会(栃高教研工業部会主催)に矢板高校代表として参加して参ります。

8月3日(水)午前、矢板高校一日体験学習を開催いたしました。
電子科では下記の4テーマで実施いたしました。
1.ロボット制御+シーケンス制御
2.プログラミング実習(Arduino)
3.電気工事実演
4.オシロスコープによる波形観測と赤外線通信
まずはリモートで全体会. ロボット制御の見学
シーケンス制御の実験 プログラミング体験
電気工事実演 波形観測と赤外線通信
たくさんの中学生と保護者の方々に参加いただきありがとうございました。案内と説明をさせていただいた電子科2年生にとってとても良い経験になりました。







