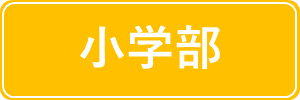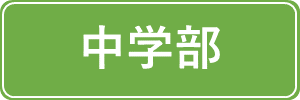進路指導室より
進路相談状況について
2月22日(木)
まもなく今年度もまとめの時期に入ってきました。今年度は、保護者の皆様の進路に関する不安や疑問を少しでも解消できるように、個別相談の充実を目指し、取り組んできました。その結果は以下のとおりです。
《個別進路相談件数》
中学部7 高等部4
《主な相談内容》
・一般就労と福祉就労について
・地域の障害福祉事業所の情報について
・今からやっておくべきことについて
・中学部から高等部にかけての進路学習について
・保護者の方が見学してきた事業所についての感想や情報共有
・産業現場等における実習はどこに行くのが良いか
・障害基礎年金や各種手当について
・その他雑談も
今後も相談機能の充実を目指していきますので、保護者の皆様は進路に関する疑問等がありましたら、どんなことでも結構ですのでぜひ相談にいらしてください。
仕事を辞めたくなるとき
2月1日(木)
今回は「仕事を辞めたくなるとき」というテーマです。残念ながら、本校卒業生にも毎年必ず離職するケースが出てきます。その一報を耳にすると、「実習では頑張っていたのに…」「入社してからも順調に仕事をしていたのに…」「事業所の皆さんからも良くしていただいていたのに…」と、進路に関わってきた身としては、何ともやりきれない気持ちになります。
とはいえ、多くの人にとって、定期的に「仕事を辞めたい」という気持ちの波は来るもので、本校卒業生にとっても例外ではありません。では、卒業生はどういった理由で仕事を辞めたくなってしまうのでしょうか。
辞めたくなる理由その① 「人間関係」
どの業種でも辞めたい理由のトップにランクされるのが「人間関係」の悩みです。“どんな悩みも突き詰めれば人間関係”とも言わるぐらいですから、誰しも覚えがあることでしょう。ただ、本校卒業生の場合は「厳しく言われた」程度のことがほとんどで、仕事上の注意を誤解し、怖がってしまうようです。「守られ過ぎて叱られ慣れていない現代の若者は、障害がなくても同じ理由で辞めますよ」と、ある企業担当者は言っていました。
辞めたくなる理由その② 「モチベーション」
入社当初は満ちていたやる気が、慣れるに従って徐々に薄れていく。これは誰しも経験することです。単調な繰り返しの仕事に飽きてしまう方がいる一方、より良い待遇を求めて積極的な転職をする方もいます。ステップアップしたいという気持ちで、きちんと手順を踏んで退職するのであれば、きっとみんなが応援してくれることでしょう。
辞めたくなる理由その③ 「プライベート」
家庭環境に左右されることは、皆さんが考えている以上に多いです。親御さんや周囲の適切な支えが就労には不可欠です。特にスマートフォンの使い方(SNS、ゲーム、ショッピング)には要注意。これは人間の欲求のメカニズムを分析し尽くして、依存症になるよう仕向けるツールです。障害者がスマートフォンを介して陥っている困難事例を、とても多く耳にします。
また、交友関係に足を引っ張られるケースもあります。夜遅くまでの遊びの誘いに乗ってしまったり、それぞれの自宅に入り浸ってしまったり等、“楽しいこと”の誘惑に負けてしまう方もいます。しっかりと監督し、サポートしてくれる存在が必要です。
辞めたくなる理由その④ 「向いていない」
これも離職理由の上位にランクされる理由です。しかし、朝起きると嘔吐してしまうとか、仕事のことを考えると一睡もできないとかいうレベルでなければ、大抵は仕事に飽きただけ、辞めるための後付けの理由に過ぎません。あるいはそういった体調の異変も、仕事そのものではなく人間関係や、さぼりたい心が引き起こしているものだったりします。
以前視覚障害をもつ知人が、「運転以外はどんな仕事もできる。させてくれるかは別の話だけど。」と言っていました。結局は「向き不向き」というのはやる気の問題でしかないのかもしれません。いつでも人は、隣の芝生が青く見えるものです。
辞めたくなる理由その⑤ 「遊びたい」
身もふたもない理由ですが、高等部を卒業したばかりで働きに出ることになる卒業生には、同情する点が確かにあります。就労することで社会の中での役割を果たし、地域の一員として暮らすことの大切さを在学中にどのように教え育てていくか、困難ですが取り組まなければならない課題だと思います。
【定着支援について】
企業就労する本校卒業生は、必ず『障害者就業・生活支援センター』への登録を行い、就職後の支援はそちらの機関にお願いすることになっています。センターでは定期的に企業を訪問し、企業が抱える困りごとや卒業生の悩みを聴き取り、対応しています。生活支援も行っていて、金銭管理や交友関係等にアドバイスをします。また、学校も元担任が中心となり、状況確認を随時行います。
産業現場等における実習が始まりました
1月23日(火)
昨日から、今年度最後の「産業現場等における実習」が本格的にスタートしました。高等部3年生にとっては、学校生活最後の実習となります。
また、2年生にとっては2回目の実習ですが、ほとんどの生徒が前回とは違った事業所を選んでいます。良い経験とし、今後の進路選択に生かしてくれるよう期待しています。
今回も御協力いただきました事業所の皆様、誠にありがとうございます。


保護者対象進路研修会
12月28日(木)
去る12月20日(水)、グループホーム「あやめはうす真岡」管理者の礒様と、本校卒業生保護者の風山さんを講師にお招きし、「保護者対象進路研修会」を行いました。
《風山様より》
子育てで親としてこれだけは守らせた3つのこと
・22時までに寝る
・はみがきを毎食後する
・毎日学校に行く
社会に出て大切なこと
・挨拶
・身だしなみ
・素直さ
《礒様より》
GH利用者で気になること
・電気や水道を「ぱなし」にする
・洗濯機の使い方を知らない
・スマートフォンの「出会い系」や「決済」でピンチに
GHで働いていて
・職員として大変だと思ったことはない「自立に向けて」「ありがとう」の言葉
《参加者の感想》
・日常に追われて将来のことまで考える余裕がないが、少しずつでもできる範囲で心がけていきたい。
・進路選択はまだ先だが、将来像がなんとなく見えた。
・卒業生保護者からの話はとても参考になったので、いろいろな方からの話をもっと聞いてみたい。今後も研修会を続けてほしい。
・我が子と照らし合わせて聴きながら、少し不安が軽くなった。一番大切なことに気づくことができたので、有意義な時間だった。
・グループホームも会社等によっていろいろと違うことなど、詳しく知ることができた。
・地道にこつこつと、できることに取り組んでいきたい。
障害福祉サービス事業所ガイドブックの追加について
内定通知が届き始めました
12月5日(火)
今年度も、企業からの内定通知書が届き始めています。企業担当者の皆様にはこれまでの御指導に感謝申し上げます。内定通知書は、校長から授与させていただきます。
3学期には最後の実習の機会が控えています。最後まで御指導くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

企業向け学校公開を実施しました
11月22日(水)
ハローワーク真岡との共催により、地域の企業等をお招きし、学校公開を行いました。生徒たちの授業の様子を御覧いただいた後、本校卒業生を雇用していただいている「有限会社関研磨工業所」の取締役、関幸子様による講話を聴いていただきました。今回御参加いただかなかった企業の御担当者様で、今後障害者雇用をお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひ本校進路指導部まで御連絡ください。
福祉施設即売会に御協力いただきました(ましこ祭)



就労系サービスに必要な力とは?
10月23日(月)
2学期の産業現場等における実習も終了し、高等部3年生は進路選択の時期が目の前に迫ってきました。この度の実習も多くの事業所様にお受入れいただき、誠にありがとうございました。
さて、今回の実習において、進路担当から福祉就労事業所へアンケートを取らせていただきました。タイトルは「就労系サービス利用に必要な力について」。こちらで設定した「知識・技能」「思考・判断・表現」「意欲・態度」「その他」に関する計22の質問項目に、各事業所が考える優先順位を1~5位までつけていただきました。また、同様のアンケートを本校進路指導部教員にも取り、結果を比較してみました。御覧ください。
|
福祉就労事業所(回答総数12) |
本校進路指導部教員(回答総数12) | ||||||
| 1位 | 挨拶・返事 | 9票 |
(平均順位1.7) |
1位 | 挨拶・返事 | 11票 | (平均順位2.1) |
| 2位 | 素直さ | 8票 | (平均2.3) | 2位 | 報告・確認 | 11票 | (平均3.1) |
| 3位 | 休まない | 5票 | (平均1.6) | 3位 | 休まない | 6票 | (平均2.0) |
※平均順位は、順位の合計数を票数で割ったものです。数が小さいほど重要度が高い、ということです。
※福祉就労事業所は、以下「意思伝達」「仕事への意欲」「協調性」と続きます。
※進路指導部教員は、以下「素直さ」「身だしなみ」「うそをつかない」と続きます。
前回の「進路指導部より」に書いた「挨拶」の重要性は、多くの関係者が認識しているという結果が出ました。本校職員も保護者の方から「挨拶を返してくれない」という指摘をいただくことがあります。この結果も踏まえ、改めて考えていかなければならないと思いました。
最後に、特記事項に記載していただいた事業所からのコメントを紹介します。
・「素直さ」とは「従順」という意味ではなく、「ごめんなさい」が言えて直せること。
・失敗も前向きにとらえてチャレンジする気持ちがあると、大きく成長することができる。
・22項目すべてが重要で順位をつけるのが難しかったが、「挨拶」と「素直さ」は全職員の共通認識だった。
等価交換の原則
9月21日(木)
本日は進路指導担当として仕事をする中で、ふと思うことを書いてみます。
20年ほど前のアニメーションに「人は何かを得るためには相応の対価を支払わねばならない」という台詞がありました。資本主義社会の市場原理では至極当然のことなのですが、進路を決めていくにあたっても的を射た表現だな、と思うことが多々あります。子どもたちは学校での学習、校外での実習、余暇の過ごし方、いろいろなことの積み重ねで進路を決めていくわけですが、忘れてならないのは「必ず他者(支援者)との関わりの中で、支援を受けて生活していく」ということだと思います。
支援する側にも「感情」があります。できるのにやらない、態度が横柄な人間と、できることは少なくても挨拶や返事はいつも元気一杯、ひたむきに頑張っている人間とでは、どちらに来てもらいたい、支援したいと思うでしょうか。
最近、「挨拶をしない自由も認めるべきだ」という主張を耳にすることがあります。昭和世代の私からしたら驚きの主張ですが、まあこれも「相応の対価」を支払う覚悟があるなら個人の自由なのかもしれません。ただ、本校高等部生徒には、普段から「挨拶・返事・言葉遣い」について口酸っぱく伝えています。できることをできる範囲で精一杯やっていれば、必ずサポーターが周りに増えていくと思います。まさに「等価交換」ですよね。いや、むしろ対価以上の利益をもたらすことでしょう。
たかが挨拶、されど挨拶。作業能力等を身につける前にできる「簡単なこと」について、今一度見直す必要があると感じています。
(C) 2013 Mashiko special needs School
(不許複製・禁無断転載)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
本校では、障害者スポーツ団体等によるスポーツ活動の振興を図るため、体育施設(体育館・グラウンド)の貸出しを行っています。
利用につきましては、本校までお問い合わせください。
【お問合せ】
平日9:00~16:30
TEL0285-72-4915