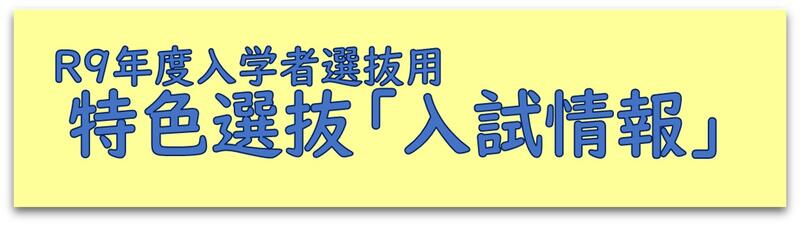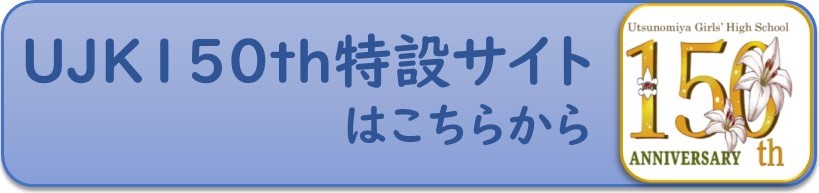文字
背景
行間
日誌
記事
卒業生との座談会
9月12日(木)に、以下の9名の卒業生を招いて、「卒業生との座談会」を実施しました。
一橋大学 経済学部 経済学科 4年 お茶の水女子大学 文教育学部1年
立教大学 文学部 日本文学専修1年 埼玉大学 理学部 分子生物学科1年
山形大学 医学部 医学科1年 獨協医科大学 医学部 医学科1年
大東文化大学 スポーツ健康学部 健康科学科1年
自治医科大学 看護学部 看護学科1年 星薬科大学 薬学部 薬学科1年
始めに、それぞれ大学・学部・学科の紹介、大学生活の様子、在校生へのアドバイス等を話してもらい、その後卒業生を囲んでの質疑応答を行いました。


参加生徒の感想の一部を紹介します。
○文理関係なく様々な学部の先輩の話が聞けて視野が広がりました。また、アドバイスもらえ参加して良かったです。
○分かりやすく熱のこもった話を聞くことができてとても良かったです。特に「自分のやりたいことをやる」「最後まであきらめない」「後悔しないように進路を選ぶ」という言葉が印象に残りました。
○先輩方が高校時代をどのようにすごし、どのように考えて今の大学を選んだのかなどを聞くことができ、自分の進路を考え直すきっかけになりました。
台風15号による臨時休業について(9月9日・月曜日)
◆本日は、台風15号の影響により宇都宮線、日光線、烏山線などが始発から運転を見合わせています。
◆最新の情報では、再開の見込みが午前10時以降と発表されましたので、本日は臨時休業とします。
◆最新の情報では、再開の見込みが午前10時以降と発表されましたので、本日は臨時休業とします。
台風15号への対応について(9月9日・月曜日)
【保護者、生徒の皆様へ】 ◆台風15号は、今夜、関東地方に上陸するおそれがあり,荒天ピークは8日(日)夜から9 日(月)の早朝と予想されています。 ◆現段階では,9日(月)は始業を3時間遅らせ,4限目からの授業開始を予定しています 。 ◆ただし、学校及び自宅付近で警報がでている場合には、自宅で待機してください。 ◆警報がでていない場合には、交通機関や通学路の状況を確認し、充分に注意して登校 して下さい。 ◆なお、宇都宮線、日光線、烏山線などについては、明朝の計画運休が発表されていま す。 (2019年9月8日18時17分現在) 鉄道各社のホームページ等で、最新の運行情報を確認してください。 (参考)JR東日本運行情報https://traininfo.jreast.co.jp/train_info/kanto.aspx ◆登校が遅れる場合や登校できない場合には、学校に電話連絡をお願いいたします。
高大接続事業 宇都宮大学大学実験講座を実施
後期課外最終日8月23日(金)午後、宇都宮大学教育学部で大学実験講座を行いました。
開かれた講座は化学(山田洋一先生 本校生8名)・生物(井口智文先生 本校生4名)の2講座でした。
化学は、「化学反応の追跡」というテーマで、ベンゼンからニトロベンゼンを合成する反応をTLC(薄層クロマトグラフィー)を用いて、ニトロベンゼンができたことを確かめていく実習でした。ガラス管からキャピラリを作るところから始め、クロマトグラフィーの原理を簡単な実験をしながら理解してからニトロベンゼンを合成し、クロマトグラフィーを用いてニトロベンゼンが合成されたことを確認しました。
生物は、「消化酵素の種類を決めよう」というテーマでした。まず、イモリの内部機関の観察を行いました。ゲル電気泳動の原理を理解した後、実際の動物から酵素試料を取り出し調整し、実際にゲル電気泳動を行いました。そしてその結果について、試料にどんな酵素が含まれているのか考察しました。




開かれた講座は化学(山田洋一先生 本校生8名)・生物(井口智文先生 本校生4名)の2講座でした。
化学は、「化学反応の追跡」というテーマで、ベンゼンからニトロベンゼンを合成する反応をTLC(薄層クロマトグラフィー)を用いて、ニトロベンゼンができたことを確かめていく実習でした。ガラス管からキャピラリを作るところから始め、クロマトグラフィーの原理を簡単な実験をしながら理解してからニトロベンゼンを合成し、クロマトグラフィーを用いてニトロベンゼンが合成されたことを確認しました。
生物は、「消化酵素の種類を決めよう」というテーマでした。まず、イモリの内部機関の観察を行いました。ゲル電気泳動の原理を理解した後、実際の動物から酵素試料を取り出し調整し、実際にゲル電気泳動を行いました。そしてその結果について、試料にどんな酵素が含まれているのか考察しました。




出前授業Ⅱ(医工学)実施
8月22日(木)後期課外の午後、出前授業Ⅱを実施しました。
今回は東北大学工学系女性研究者育成支援室の主催で、鶴岡典子先生、渡邊智子先生をお招きしました。
鶴岡先生からは、医工学においてどんな研究や開発を行っているかという具体的なお話や、ご自身の高校時代から医工学の研究に取り組むまでの経緯をお話してくださいました。渡邊先生からは、東北大学での女子学生、女性研究者に対してどんな支援を行っているかをお話していただきました。
全体へのお話の後、質疑応答、そして個人的な質問や相談にもお答えいただきました。



生徒の感想の一部を紹介します。
○医工学というとレントゲンやMRIのような大きな医療機器の開発というイメージしかありませんでしたが、とても小さな医療機器の開発も行っていることを知り驚きました。また、ヘルスケアに関する機器の開発も行っている事を知りとても幅広い分野であることが分かりました。
○医療への関わり方は様々な方法があることを学びました。人を助けることができるものの開発はとてもやりがいがあり魅力的だと思いました。
今回は東北大学工学系女性研究者育成支援室の主催で、鶴岡典子先生、渡邊智子先生をお招きしました。
鶴岡先生からは、医工学においてどんな研究や開発を行っているかという具体的なお話や、ご自身の高校時代から医工学の研究に取り組むまでの経緯をお話してくださいました。渡邊先生からは、東北大学での女子学生、女性研究者に対してどんな支援を行っているかをお話していただきました。
全体へのお話の後、質疑応答、そして個人的な質問や相談にもお答えいただきました。



生徒の感想の一部を紹介します。
○医工学というとレントゲンやMRIのような大きな医療機器の開発というイメージしかありませんでしたが、とても小さな医療機器の開発も行っていることを知り驚きました。また、ヘルスケアに関する機器の開発も行っている事を知りとても幅広い分野であることが分かりました。
○医療への関わり方は様々な方法があることを学びました。人を助けることができるものの開発はとてもやりがいがあり魅力的だと思いました。