 |
益子焼 |
|---|---|
| 成形:ろくろ(手) |
ろくろ(轆轤)について
円形の盤の上に陶土を置いて回転させ、遠心力を利用して、薄く延ばして成形する道具です。
昔は、「手まわしろくろ」「蹴りろくろ」が使われましたが、現在は「電動ろくろ」を使うことがほとんどです。
作家の中には「蹴りろくろ」を使う人もいます。
陶土を台の中心に乗せ回します。
うまく中心を出さないと、回転させた時にバランスがくずれてしまいます。
水と手どろをつけながら表面を滑らかにします。
親指を中心に押し込むと穴がすうっと開きます。
あとは、作りたい形に手をそえていきます。
内側はコテを使って形作ります。
どの製品も大きさが一定になるように、入口の大きさをものさしで測りますが、そのようなことをしなくても、熟練者は慣れで同じ大きさに作ることができます。
最後に濡らした鹿皮を口にあて滑らかにし、糸で底を切り離します。

電動ろくろ

ろくろの中心に陶土を置きます

ろくろを回しながら中心を出します

ろくろを回しながら形を作ります

ろくろを回しながら形を作ります

内側はコテを当てます

ふちをなめし皮でなめらかにします

トンボで大きさを確認します

最後に糸で底を切り離します

トンボ

柄ゴテ(えごて)

柄ゴテ

パス

トンボ

切糸

なめし皮

ろくろ(手)で成形した茶碗



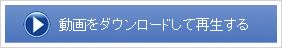
 前のページへ
前のページへ
