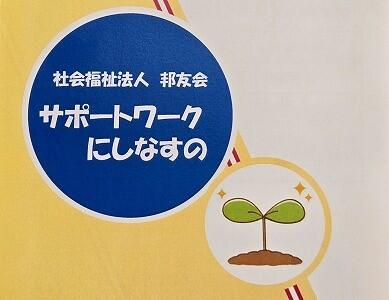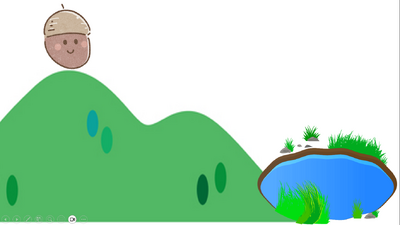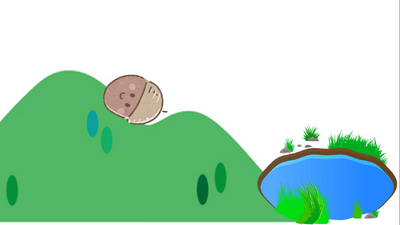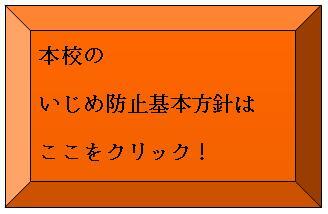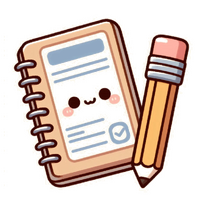令和7(2025)年度
職員研修「施設見学」
児童生徒の卒業後の進路について理解を深めるために、福祉施設の見学に行ってきました。
◆就労継続支援B型事業所ひゅっげ
ひゅっげさんは、就労継続支援B型と自立訓練、2種類の福祉サービスを提供されています。
見学させていただいた日には、焼き菓子のセットアップ作業、自動車部品の検品などを行っていました。
施設についての説明では、利用者さん一人一人に合った働き方ができること、障害特性に合わせた支援、工賃アップ制度、送迎サービスなど詳しくお話ししていただきました。
利用者さんもステップアップを目指して働いている方が多く、短時間勤務だった方が少しずつ働く時間を延ばしていったり、就労継続支援A型の事業所へ移っていったりする方もいるとのことでした。
◆社会福祉法人邦友会 サポートワークにしなすの
サポートワークにしなすのさんは、就労継続支援A型のサービスを提供されています。
国際医療福祉大学病院と周辺関連施設内において、清掃やベッドメイキングなどの仕事を行っています。
人と会話するのが苦手な方、少し話しながら仕事がしたい方など、それぞれの利用者さんにとって働きやすい場所を提供されているとのことでした。また、仕事の悩みなどをじっくりと支援スタッフが聴く「傾聴」の時間を重視されているとのことでした。
就労継続支援A型は、雇用契約を結び、最低賃金保証があります。働くための体力、分からないことをすぐに質問できることなど、求められるものも多いですが、やりがいをもって仕事に取り組んでいる利用者さんがたくさんいるとのことです。
今回の研修では、各施設の皆様にはお忙しい中にも関わらず、御対応いただきありがとうございました。見学させていただいたことで、利用者様の仕事に取り組む様子、施設内の運営について、理解を深めることができました。今後の教育活動に役立てていきたいと思います。
夏休みプチ研修「おにぎりVOCAの製作と修理」
7月30日、おにぎりVOCAの製作と修理を行いました。
みなさん、おにぎりVOCAをご存じでしょうか。
15秒のボイスレコーダーをおにぎりケースに内蔵して作る手作りのVOCAのことです。
VOCAについての話をしたあとさっそく製作です。
先生方はおにぎりVOCAケースに穴をおけるところから始めました。

始めて工具を使う先生もいましたが、皆さんきれいに穴を開けていました。
次はボイスレコーダーの電池を外したり、電池ボックスにつなげたりします。
ここで半田ごてを使うのですが、始めて使う先生や中学校以来久しぶりの先生も、、、
みんな集中してハンダ付けをしていました
半田ごてを使って、配線を付け替えてボタンスイッチにつなげます。
「音が出た!」成功です
最後に、、、作ったおにぎりVOCAに感想を吹き込んで、みんなで発表をしました。
参加された皆さん、製作お疲れ様でした
授業でぜひ、活用してくださいね


夏休みプチ研修「スライド教材の作成」
みなさん、パワーポイントを使いこなせると、とっても面白いことができることをご存じですか?
私たち教員は、パワーポイントを使って、授業のスライドを作っています。
ということは…パワーポイントを駆使して、面白いスライドを作れたら、子どもたちが興味をもって授業を受けてくれるはず!
ということで、趣味でたくさんのスライド教材を作り、パワーポイントの使い手であるF先生に、すてきなスライド教材の作り方を教えていただきました
例えばこちら!
みなさんご存じの「どんぐりころころ」ですが、F先生の手にかかれば…
音楽に合わせて、どんぐりがころころころころ…そしてどじょうとこんにちは!
イラストが動いたり、音が鳴ったりするものは、子どもたちは大好きなんです
そんな素敵なスライド教材が作れるよう、先生方も真剣にパワーポイントに向き合いました。
イラストを選択したら、アニメーションを付けて…さらに傾きや動き方、秒数を入力して…
と、普段は触ったことがなかったタブやオプションを使って、面白いスライド教材を作ることができました。
操作が難しいパワーポイントですが、上手く使いこなせれば、子どもたちの「分かった!」に繋げることができるんですね
今回学んだことを生かして、子どもたちが楽しく興味をもって受けられる授業を考えていきたいと思います
夏休みプチ研修「ICT活用に関する講義」「生成AIを活用した校務効率化について」
「みなさん、(校務にかかわらず)生成AIを使ったことがある人はどのくらいいますか?」
参加した約半数の手が挙がり、初めて生成AIに触れる人もいる中、研修がスタートしました
まずは、情報部長より、
「生成AIとは」
「栃木県立学校における生成AI使用上の注意」
についての講話を聞きました
そして、実際に、それぞれの校務用PCで、生成AIを使ってみました
私達教員は、「自分たちで文章を考えてパソコンに打ち込む」という仕事が多々ありますが、それを第3者が見たときに、読みやすいか、誤解を与えるような表現になっていないかなどを、何人もの教員でチェックをしていきます
そのチェックの第1段階に生成AIを使ってみようという研修です
情報部長が、私達がよく文章で使う表現を生成AIに学習させ、互審チェックをする際に使いやすいように「生成AI互審くん」というものを作成・準備しておいてくれました
実際に、よく使う表現で修正部分があると色がついて表示されるような設定がされており、直すべきところが一目瞭然
参加した先生達の
「すご~い」という声があちこちから聞こえていました
続いて、研修講師がK先生にバトンタッチ
生成AIを使ってイラストを作ってみよう
私達は視覚支援教材を作るときに、イラストをよく使いますが、ちょうどぴったりくるイラストがなかったりして、絵のうまい先生にかいてもらったり…
…なんてことがありますが、それを解消できる使い方です
今回は参加者でチームを作り、お祭りのイラストを作成
「アニメタッチで」「おみこしを入れて」など、グループで条件を加えてイラストを作成しました
それがこちら

これ以外にもたくさんのお祭りのイラストができあがりました
みなさん、それぞれのグループの個性が表れていますよね
この中で1つ、違和感があるイラストがあることにお気づきになったでしょうか…
そうです ここです
金魚すくいの金魚が入るべき器にかき氷が
便利なAIですが、使うのは人間
全てAI任せにしてはいけないことがわかる、研修としては良いイラスト素材を生成してくれました
できあがったイラストに
「もっと○○にして」
と条件をつけるとイラストを修正してもらえるので
「女の子の手に持っている器を金魚を入れる器にして」
とでも追加で条件をつけると、金魚入りの器に修正したイラストができあがります
歌も作ってくれるAI
テーマに沿った歌詞とギターコードをつけてくれ、参加者で歌いました
先生達のこの笑顔が、楽しく充実した研修になったことを物語っていますね
生成AI
活用して校務効率化
上手に活用していきたいなと、参加者一同、強く思いました
夏休みプチ研修「包丁を研ぐ」
~包丁を研いで心を研ぎ澄まそう!切れないストレスからあなたを解放~
こんな興味深いサブタイトルで実施されたこの研修。
「家庭科室の包丁の切れ味が悪い…」と困っていた家庭科のO先生。
包丁を研げる職員を増やして、こまめに包丁のメンテナンスをしよう!
ということで、企画されました。
まずは砥石の選び方や研ぐポイントなどを学び、
いよいよ、実践!
コツをつかむまでに時間がかかりましたが、研ぎ終わってみると
トマトはスーっと切れ、
なんと、新聞紙も切れる!
この研修で24名の研ぎ師が養成されました
もちろん、心も研ぎ澄まされ、切れないストレスから解放されたことは言うまでもありません。
これからは、家庭科室の包丁は切れ味抜群を維持できますね