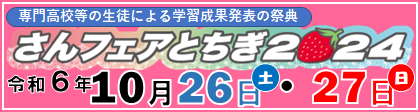文字
背景
行間
ここでは、各学科の活動を紹介しています
 「高大連携プロジェクト」スタート!
「高大連携プロジェクト」スタート!
今年度から、国際医療福祉大学医療マネジメント学部の学生の皆さんと交流を持つことにより、教育効果をあげようという目的で、「高大連携プロジェクト」が始まりました。
国際医療福祉大学医療マネジメント学部の酒井健先生のゼミナールに所属している3、4年生から、本校商業科3年生の「課題研究」の授業で行っている調査研究について、大学生の知識と技術のアドバイスを受け、さらに研究内容の深化が期待できるところです。
すでに2回の交流を実施しましたが、具体的なアドバイスを直接伺うことができ、生徒たちは調査研究に対して意欲的な態度で頑張っています。
今後の予定は、7月に行われる「生徒商業研究発表会」に向けてのプレゼンテーション力向上について意見交換をしていきます。
今後の活動に是非ご注目下さい!


本校の春の様子をドローンで撮影
本校の校庭の桜が満開を迎えました。昨年度、建設工学科で導入したドローンを使い、建設工学科3年生が本校の春の様子を上空から撮影しました。実際に生徒自らドローンを操作し、楽しく意欲的に取り組んでいました。
ドローンはこのような写真を撮るだけではなく、建設や測量の現場で導入が進んでいます。建設工学科では、生徒が最新の技術に触れる機会を設け、ドローンを使った実習にも積極的に取り組んでいく予定です。
学校等で撮影の希望がありましたら建設工学科までご相談ください。




建設工学科 ドローン操作講習会
ドローンに関わる航空法を説明して頂き、実際にドローン操作の体験をしました。

小川小学校へプランターケース寄贈
今年度、1年生の工業技術基礎の授業では、課題の1つとして「プランターケース」を製作しました。3月15日、そのプランターケースを那珂川町立小川小学校へ寄贈してきました。
このプランターケースは木製で、周囲の環境と調和するように配慮しました。組立をした後に、防腐塗料を塗布して腐食しないように工夫しました。
那珂川町からも多くの生徒が清峰高へ通学しています。自分の出身地域へプランターを寄贈することで、地域との連携を深めるとともに、恩返しができたと思っています。

電子機械科 技能検定
電気機器組立て(シーケンス制御作業)3級に電子機械科2年生8名が合格しました。


実技:配線作業 実技:プログラム入力・確認
職種・試験内容について
1999年秋に新設された国家技能検定試験です。1級・2級および3級があり、学科試験と実技試験に分かれています。電気機器組立て(シーケンス制御作業)では、自動化された生産設備の制御に関わる専門知識、技術・技能について出題されます。
ITパスポート試験合格
合格者 情報技術科2年 浜 中 嶺 君
電 気 科2年 瀧 健太郎 君

商業科「商品開発」出張講義
商業科の「商品開発」の授業の一環として、竹工芸師の八木澤先生をお招きして、地域伝統工芸について出張講義をして頂きました。
生徒は、身近な伝統工芸に直に触れ、時間が経つのも忘れるほど集中して講義を受講していました。また、実際に竹工芸製作にチャレンジし、試行錯誤を繰り返しながらも夢中になって作業していました。
このような貴重な経験をさせて頂き、八木澤先生をはじめご協力を頂いた方々に大変感謝致します。有難うございました。




機械科高大連携事業
○実施日:平成29年2月17日(金)
○講 師:帝京大学 機械・精密システム工学科 森 一 俊 教授
○講 義:次世代自動車の展望 ~ HEV,FCV,BEV ~
○内 容:
自動車の変遷や開発、実用化されつつある多様な自動車及び環境対策等の課題などを動画を交えて講義をいただき、機械科の生徒達にとってたいへん興味深い内容のものでした。
また、自動運転やシステムの進化に伴い自動車や社会環境が近未来において、どのように変化していくのかを学習する良い機会を得ることができました。
建設工学科2年生インターロッキング舗装実施
2月15日(水)、建設工学科2年生土木コースの生徒が、インターロッキング舗装実習を行いました。この実習は、(一社)栃木県建設業協会の将来の建設業界を担う人材育成事業として、株式会社生駒組に協力していただき実施しました。
この実習では、歩道やガーデニング等で見かけるインターロッキングの施工技術につい学びました。
株式会社生駒組土木部長臼井様はじめ多くの方に、事前準備から当日の指導まで行っていただき、有意義な実習を行うことができました。生徒にとってインターロッキングブロック敷きは初めての経験で、おっかなびっくり行っていましたが、完成が近づにつれて出来映えに感動していました。
今後も、建設工学科では様々な事業を通して、将来の建設技術者としての素養を高める努力をしてまいります。

商業科課題研究発表会
平成29年1月18日(水)、商業科課題研究発表会を実施しました。
課題研究発表会では、商業科3年生の各研究グループが、マーケティングやビジネス経済の内容について、課題解決を目指したプレゼンテーションを行いました。研究内容は次の7つでした。
(1)栃木でGO(観光)
(2)ラーメンこげんをPR
(3)スターバックス
(4)お菓子
(5)コンビニスイーツ比較
(6)ユニバーサルスタジオジャパン
(7)ご当地グルメマップ
生徒は、研究内容(1)から(7)について、市場の動向、消費者の行動及び商品の企画・流通・消費、産業構造の変化や経済の国際化、観光・地域産業などを調査研究します。発表準備(プレゼンテーションの練習を通して)で、パソコンソフトの効果的な利用、聞きやすい発声や話す速度、聞き手を引き付ける表情や姿勢、提案の趣旨を正確かつ簡潔に伝える話の構成などを学習します。
1年間の学習(テーマ設定から発表や各グループ相互の評価)により、思考力・判断力・表現力が向上し、言語活動の充実が図られました。そして、生徒間のディスカッション、ディベートや外部との交渉などの実践を通して、コミュニケーション能力を大いに向上させることができました。
NEW
このホームページ内の
写真や文章の無断転用は
固くお断りします。