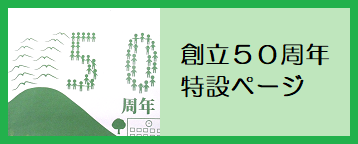文字
背景
行間

2
1
9
2
7
2
1
日誌
2014年5月の記事一覧
サツマイモの苗を植えました
5月29日(木) 高等部の生徒によってサツマイモの苗が植えられました。この花壇は、平成25年12月「学校環境緑化モデル事業」(公益社団法人 とちぎ環境・みどり推進機構)によって造成された多目的花壇です。
従来の花壇は、耕土も浅く、花壇の縁石が無かったことから、土がフェンスを超えて沼に流出してしまいましたが、今回の造成によって縁石が設けられ、新しく土も入れられました。そのため、耕土も5倍近く増加し、いろいろな草花や野菜を育てるのに適した多目的な花壇が誕生しました。
まずはサツマイモの栽培から挑戦することになり、生徒たちによる心のこもった栽培がスタートしました。

従来の花壇は、耕土も浅く、花壇の縁石が無かったことから、土がフェンスを超えて沼に流出してしまいましたが、今回の造成によって縁石が設けられ、新しく土も入れられました。そのため、耕土も5倍近く増加し、いろいろな草花や野菜を育てるのに適した多目的な花壇が誕生しました。
まずはサツマイモの栽培から挑戦することになり、生徒たちによる心のこもった栽培がスタートしました。

シジュウカラが巣立つ!
このコーナーでご紹介してきたシジュウカラが無事に巣立ちました。「おめでとう!」この巣箱を利用してくれた親鳥は、学校周辺に架けられた巣箱で育ったのかも知れません。巣だった子供たちもぜひ利用してほしいものですね。

ところで、ひなたちが巣だった後の巣箱の中は、いったいどうなっているのでしょうか?

ところで、ひなたちが巣だった後の巣箱の中は、いったいどうなっているのでしょうか?
下の写真が巣立った後の巣箱の中の様子です。

どうでしょう、ずいぶんきれいになっていることにお気づきでしょうか? シジュウカラなどの小鳥たちは、巣をたいへんきれいに保ちます。その第一の理由は、外敵から巣を守ること。ひなたちの糞は、巣箱の中はもちろん、その周囲には落とさず、遠くにくわえて運びます。巣を発見されないための工夫ですね。
それと驚いたことに、このシジュウカラが繁殖した巣箱の4m四方内にある巣箱で、なんと2箇所でスズメが巣をかけて子育てをしていました。下の写真は、スズメならではの巣作りの特徴を見ることができます。それは、巣箱の丸窓から巣材がはみ出るほどに、ワラやビニールテープなどがぎっしり詰まっています。

思いも寄らぬほど、なわばりが狭い小鳥たちの紹介をしました。これからも、一緒に観察をしていきましょう。

どうでしょう、ずいぶんきれいになっていることにお気づきでしょうか? シジュウカラなどの小鳥たちは、巣をたいへんきれいに保ちます。その第一の理由は、外敵から巣を守ること。ひなたちの糞は、巣箱の中はもちろん、その周囲には落とさず、遠くにくわえて運びます。巣を発見されないための工夫ですね。
それと驚いたことに、このシジュウカラが繁殖した巣箱の4m四方内にある巣箱で、なんと2箇所でスズメが巣をかけて子育てをしていました。下の写真は、スズメならではの巣作りの特徴を見ることができます。それは、巣箱の丸窓から巣材がはみ出るほどに、ワラやビニールテープなどがぎっしり詰まっています。

思いも寄らぬほど、なわばりが狭い小鳥たちの紹介をしました。これからも、一緒に観察をしていきましょう。
ミカンの花が咲きました。
校庭の「野鳥の庭」にある温州ミカンの花が咲きました。白くて卵のようなつぼみがだんだん大きくなって、星の形の花を咲かせました。周囲には、甘い香りを漂わせ、ミツバチたちを誘っています。
このミカンの木は、平成11年の県立学校個性化アクションプランによって植樹されました。今では約3mにまで育っています。本校には、この温州ミカン(2本)の他に、平成23年ふるさと“とちぎ”みどりづくり事業によって、プール西側に6本植えられています。
ところで、先日ご紹介したサクランボの木に架けた巣箱のシジュウカラのヒナたちですが、今日も元気に鳴いていました。
(お詫びと訂正:4月28日付けの本ホームページ「ナガサキアゲハを飛んで来い!」の記事の中で、アオスジアゲハと記載しましたがジャコウアゲハの誤りでした。お詫びいたします)
このミカンの木は、平成11年の県立学校個性化アクションプランによって植樹されました。今では約3mにまで育っています。本校には、この温州ミカン(2本)の他に、平成23年ふるさと“とちぎ”みどりづくり事業によって、プール西側に6本植えられています。
ところで、先日ご紹介したサクランボの木に架けた巣箱のシジュウカラのヒナたちですが、今日も元気に鳴いていました。
(お詫びと訂正:4月28日付けの本ホームページ「ナガサキアゲハを飛んで来い!」の記事の中で、アオスジアゲハと記載しましたがジャコウアゲハの誤りでした。お詫びいたします)

「野鳥の庭」の巣箱に・・・!
本校の「野鳥の庭」に架設した巣箱に、なんとシジュウカラが営巣していました。「チィー、チィー」というひな鳥の声を近くで聞いた先生は、きっとスズメだろうと思っていたようです。それもそのはず、あまりにも身近すぎる場所だったからです。そして、校庭の南側にある「野鳥の庭」の木々に架けられたすべての巣箱は、校舎の軒下に架けられた巣箱を移動したものでした。
以前にご紹介しましたが、軒下や人工物の周辺に巣箱を架けると、ほとんどスズメが巣を作ります。まして、この巣箱は北向きに架けられているばかりか、風が吹くとゆらゆら揺れてしまうほど不安定でした。さらに、2,5mという低いところに架けられており、人通りもあるところでした。
とにかく、思いも寄らない身近なところで、野鳥のひなが観察できたなんて幸運でした。写真からもわかるように、巣立つまで、それほど日数はかからないでしょう。元気に飛び立ってくれることを祈るばかりです、



以前にご紹介しましたが、軒下や人工物の周辺に巣箱を架けると、ほとんどスズメが巣を作ります。まして、この巣箱は北向きに架けられているばかりか、風が吹くとゆらゆら揺れてしまうほど不安定でした。さらに、2,5mという低いところに架けられており、人通りもあるところでした。
とにかく、思いも寄らない身近なところで、野鳥のひなが観察できたなんて幸運でした。写真からもわかるように、巣立つまで、それほど日数はかからないでしょう。元気に飛び立ってくれることを祈るばかりです、



ビオトープはおもしろいよ!?
本校の中庭にあるビオトープは、平成10年に絶滅危惧植物「ミズアオイ」のプランター栽培と共に、3m(縦)×5m(横)×30cm(深さ)の観察池に土を入れて改良したものです。
このビオトープには、準絶滅危惧植物である「ミクリ」をはじめ、「サンカクイ」、「ガマ」、「スイレン」などが植えられています。そして、「メダカ」、「クチボソ」などの魚類や、「ヤマトヌマエビ」、「ヤゴ」などの水生生物もたくさん同居しています。さあ、片手に網を持って、小さな仲間たちをすくって観察してみよう。(スイレンの花が咲きました:5月15日)


このビオトープには、準絶滅危惧植物である「ミクリ」をはじめ、「サンカクイ」、「ガマ」、「スイレン」などが植えられています。そして、「メダカ」、「クチボソ」などの魚類や、「ヤマトヌマエビ」、「ヤゴ」などの水生生物もたくさん同居しています。さあ、片手に網を持って、小さな仲間たちをすくって観察してみよう。(スイレンの花が咲きました:5月15日)


学校風景
連絡先
〒326-0011
栃木県足利市大沼田町619-1
電話 0284-91-1110
FAX 0284-91-3660
ナビを利用して本校に来校される場合には、
「あしかがの森足利病院」で検索されると便利です。
リンクリスト