文字
背景
行間
寄宿舎
10月の寄宿舎
・寄宿舎には、舎生による舎内自治活動「若草会」があります。
感染予防対策のため、集会ができない代わりに、ホワイトボードに「若草会コーナー」を作り、お知らせ等を掲示しています。
「月のお知らせ」は、若草会役員と職員で作成しています。
「ひとり ひとこと」では、10月のお題「秋にイメージするもの」ということで、毎日順番に記入したり、絵を描いて作成しました。(定番の)さつまいも等の他に、「秋田新幹線」「運動会」「彼岸花」等、様々なイメージがありました。


・10月14日(水)第3回社会自立学習Ⅰ「コミュニケーション」を実施しました。
今回は、「質問の仕方」について学習を行いました。ワークシートをもとに、質問をするときの言葉遣いやマナー、必要に応じて手話、指文字、筆談を使い分けることを確認しました。


・入浴に関しては、気温が下がり寒くなってきたため、浴槽の使用を始めました。
感染予防対策については、産業医に御助言をいただき、入浴するためのルールを作って順番に入っています。


・感染予防対策のため、空気清浄器を導入しました。


感染予防対策のため、集会ができない代わりに、ホワイトボードに「若草会コーナー」を作り、お知らせ等を掲示しています。
「月のお知らせ」は、若草会役員と職員で作成しています。
「ひとり ひとこと」では、10月のお題「秋にイメージするもの」ということで、毎日順番に記入したり、絵を描いて作成しました。(定番の)さつまいも等の他に、「秋田新幹線」「運動会」「彼岸花」等、様々なイメージがありました。


・10月14日(水)第3回社会自立学習Ⅰ「コミュニケーション」を実施しました。
今回は、「質問の仕方」について学習を行いました。ワークシートをもとに、質問をするときの言葉遣いやマナー、必要に応じて手話、指文字、筆談を使い分けることを確認しました。


・入浴に関しては、気温が下がり寒くなってきたため、浴槽の使用を始めました。
感染予防対策については、産業医に御助言をいただき、入浴するためのルールを作って順番に入っています。


・感染予防対策のため、空気清浄器を導入しました。


9月の寄宿舎




NPO法人うつのみや百年花火「2020うつのみや花火大会おうち花火 3万人でチャレンジ!」プロジェクトより、手持ち花火をたくさんいただきました。
夕食後に寄宿舎の裏庭で、それぞれ手持ち花火を楽しむことができました。新型コロナウイルス拡大により、お祭りや花火大会が中止された中、嬉しいサプライズとなりました。




9月30日(水)季節行事『お月見』を行いました。
白いおり紙の紙風船を月見だんごに見立て、ススキや秋野菜を飾りました。また、お月見の由来をクイズにして掲示し、楽しみながら学習することができました。
夏を迎えた寄宿舎
これまでと同様の感染症予防対策を取りながら、より楽しく生活をするために寄宿舎の玄関や各部屋前に、七夕飾りや夏らしい飾り付けをしました。
七夕の願いでは、「早く新型コロナウイルスが無くなりますように」などの願いが沢山ありました。








七夕の願いでは、「早く新型コロナウイルスが無くなりますように」などの願いが沢山ありました。








新年度の寄宿舎
文部科学省や栃木県からの指針を受け、集団生活の場である寄宿舎には、基本的な感染予防対策として、あらゆる生活場面で「3密」な状態を可能な限り避けることが求められます。寄宿舎を安全に運営していくため、一部の保護者の皆さまには、お子様の当面の通学をお願いするなど異例の対応へのご協力をいただいております。
6月から再開した寄宿舎は、栃木県から新型コロナウイルス感染予防対策のため一室一人利用という指示が出ているため、遠方の幼児児童生徒を対象としています。
6月から再開した寄宿舎は、栃木県から新型コロナウイルス感染予防対策のため一室一人利用という指示が出ているため、遠方の幼児児童生徒を対象としています。
★寄宿舎における感染症予防対策について★
・寄宿舎入口で手指と上履きの消毒をします。
・会話は、2ⅿの距離をあけます。
・うがい、食事、運動、入浴する以外の場面ではマスク着用を基本とします。
・看護師指導による手洗い、うがいの徹底。
・当面の間は、大人数で集まり密になる行事は中止又は延期しています。
社会自立学習Ⅰ
2月17日(月)社会自立学習Ⅰ反省会を行いました。
高等部生による社会自立学習は今年度、2つのグループに分かれて活動しました。
Bグループの反省会では、産業現場実習の反省会のスタイルを導入し、PowerPoint資料を活用した活動発表を行いました。
中学部3年生も見学に訪れ、堂々と発表する先輩方の様子を見て、次年度の自分の姿をイメージすることができました。


Aグループは1年間の活動を振り返り、今後活かせる学習と自分で伸ばしたいところを話し合いました。高等部3年生は卒業後、自分で責任を持って行動することが増えること。高等部2年生は調理学習をステップアップしたい、と目標を示していました。


高等部生による社会自立学習は今年度、2つのグループに分かれて活動しました。
Bグループの反省会では、産業現場実習の反省会のスタイルを導入し、PowerPoint資料を活用した活動発表を行いました。
中学部3年生も見学に訪れ、堂々と発表する先輩方の様子を見て、次年度の自分の姿をイメージすることができました。


Aグループは1年間の活動を振り返り、今後活かせる学習と自分で伸ばしたいところを話し合いました。高等部3年生は卒業後、自分で責任を持って行動することが増えること。高等部2年生は調理学習をステップアップしたい、と目標を示していました。


ひな祭りの会
2月26日(水)ひな祭り会を行いました。
ひな祭りの由来について学んだ後に、みんなでひなチョコあられを食べました。
みんなとおやつを食べながら、楽しく会話する様子が見られました。


ひな祭りの由来について学んだ後に、みんなでひなチョコあられを食べました。
みんなとおやつを食べながら、楽しく会話する様子が見られました。


卒業生を祝う会
2月25日(火)卒業生を祝う会を行いました。卒業生が寄宿舎生活を振り返り、作文を発表し、また思い出の写真をスライドショーを皆んなで懐かしく観賞しました。
小学部1名、中学部2名、高等部4名卒業します。


豆まき
2月5日に豆まきを行いました。
悪いものや災いを追い払うために赤鬼と青鬼に豆をまき、1年間元気に過ごせるように恵方巻きの代わりにふ菓子を食べました。


悪いものや災いを追い払うために赤鬼と青鬼に豆をまき、1年間元気に過ごせるように恵方巻きの代わりにふ菓子を食べました。


歳末お楽しみ会
12月16日に歳末お楽しみ会を行いました。
今回は、グループに分かれてケーキ作りを行いました。
どのケーキもとても美味しかったです。


9月18日(水)お月見会

曇り空で月は見えませんでしたが、飾ったおそなえを見たり、由来について話を聞いたりしました。









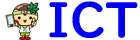
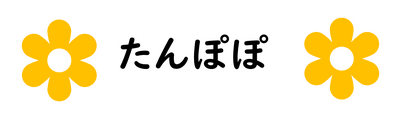

 tochigi-edu.ed.jp
tochigi-edu.ed.jp