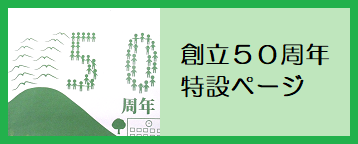文字
背景
行間

2
2
5
2
4
7
4
日誌
自然いっぱいコーナー
巣箱の清掃をしました。
野鳥たちが利用した巣箱の清掃をしました。昨年繁殖に利用された巣箱にはコケ類で作られた産座が残されています。下の写真の巣には、残念ながら卵が2個取り残されていました。他の卵は、きっと元気にかえって、大空に飛び立っていったことでしょう。
この季節、シジュウカラなどが巣箱をねぐらとして利用することが多く、翌年、その巣箱で繁殖することが多いことが今までの観察で明らかになっています。
巣箱もきれいになって、来春の繁殖を待つばかりです。以前、ヤマガラが3月に産卵した記録も残っています。みんなで、やさしく見守りましょうね。



この季節、シジュウカラなどが巣箱をねぐらとして利用することが多く、翌年、その巣箱で繁殖することが多いことが今までの観察で明らかになっています。
巣箱もきれいになって、来春の繁殖を待つばかりです。以前、ヤマガラが3月に産卵した記録も残っています。みんなで、やさしく見守りましょうね。



校庭に果実がいっぱい!
秋もいよいよ深まり、校庭の果樹の枝も、たくさんの実をつけてたわわになってきました。
この果樹たちは、平成11年、県立学校個性化アクションプランによって、「野鳥の庭」を野鳥の食べる実のなる木として、柿、サクランボ、ミカン、アケビなどがを植栽されました。
そして今年度は、公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構による、学校環境緑化モデル事業が実施されることとなり、野鳥の庭周辺の花壇の整備やリンゴ(ふじ)が植栽される予定です。

この果樹たちは、平成11年、県立学校個性化アクションプランによって、「野鳥の庭」を野鳥の食べる実のなる木として、柿、サクランボ、ミカン、アケビなどがを植栽されました。
そして今年度は、公益社団法人とちぎ環境・みどり推進機構による、学校環境緑化モデル事業が実施されることとなり、野鳥の庭周辺の花壇の整備やリンゴ(ふじ)が植栽される予定です。

絶滅危惧植物「ミズアオイ」開花
6月に播種した絶滅危惧植物「ミズアオイ」の花が咲きました。
この「ミズアオイ」は、平成8年5月から本校で栽培し続けられてきました。
「ミズアオイ」は1年草ですから、花が咲いた後、慎重に種をとって、翌年に引き継がれています。
今年も生徒の手によって、プランラーで育てられ、花を咲かせることができました。絶滅が心配されている「ミズアオイ」の花を見ることができ、生命の尊さを身近に感じています。
まさに、本校におけるささやかな命のリレーは17年余を迎えてました。

この「ミズアオイ」は、平成8年5月から本校で栽培し続けられてきました。
「ミズアオイ」は1年草ですから、花が咲いた後、慎重に種をとって、翌年に引き継がれています。
今年も生徒の手によって、プランラーで育てられ、花を咲かせることができました。絶滅が心配されている「ミズアオイ」の花を見ることができ、生命の尊さを身近に感じています。
まさに、本校におけるささやかな命のリレーは17年余を迎えてました。

「野鳥の庭」と「ビオトープ」
校庭の片隅にある「野鳥の庭」に、リニューアルされたプレートが立ちました。これは、1998年に、子どもエコクラブ全国フェスティバル(名古屋)に栃木県代表として参加した記念にいただいた「乙女椿(オトメツバキ)」のものです。
校内の樹木には、名前を記したプレートが付けられていますが、現在では50数種類にも及んでいます。
これからも、児童生徒や地域の皆さんに、木々の名前を覚えていただくために、少しづつ増やしていく予定です。

校内の樹木には、名前を記したプレートが付けられていますが、現在では50数種類にも及んでいます。
これからも、児童生徒や地域の皆さんに、木々の名前を覚えていただくために、少しづつ増やしていく予定です。

カブトムシ
昨年6月にマイチャレンジでお世話になった、『ミカモライディングクラブ』さんからカブトムシをたくさんいただき、手作りの特製ケースで飼育しました。写真はおがくずにもぐっているカブトムシです。夕方になると元気に這い出して昆虫ゼリーを食べています。
夏休み前に児童生徒に『カブトムシの里親』を募集しました。カブトムシ14匹、クワガタ4匹全員無事に巣立っていきました。


夏休み前に児童生徒に『カブトムシの里親』を募集しました。カブトムシ14匹、クワガタ4匹全員無事に巣立っていきました。


学校風景
連絡先
〒326-0011
栃木県足利市大沼田町619-1
電話 0284-91-1110
FAX 0284-91-3660
ナビを利用して本校に来校される場合には、
「あしかがの森足利病院」で検索されると便利です。
リンクリスト