文字
背景
行間
校長室便り
校長室便り
身近な風景 ~ヤマユリ
休みの日は、両生類の調査などで野外に出ることが多いですが、最近、自生している「ヤマユリ」が見事に大輪の花を咲かせています。「ヤマユリ」を見かける場所は、北向きの山の斜面が多いです。




地味な里山の風景に似つかないほど、豪華で華麗な風貌です。花の匂いを嗅いでみると、甘く濃厚で強烈であることに驚かされます。さすがに「ユリの女王」と呼ばれるだけのことはあります。

花の数が多いと、花の重さに耐えきれず、茎がたわんできます。

山の斜面には、こんな立て札がありました。
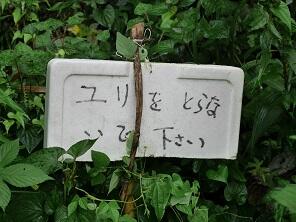
幸いなことに、花を持って行く心ない人は、いないようです。
ほんの少し、里山に足を延ばせば、見事な「ヤマユリ」の花を目にすることができます。佐野高校では、この時期、ミンミンゼミが鳴いていますが、ヤマユリの咲く里山では、ヒグラシが鳴いていました。


佐高ミュージアム㉛
今回は、「佐高ミュージアム 番外編 No.1~5」を公開します。
前回で、佐野高校で過ごした8年間(1986年から1993年)で発行した「すっかんぽ」をすべて公開しました。しかし、次の勤務校である小山西高校でも、しぶとく「すっかんぽ」を発行していました。そこで、その間に発行した「すっかんぽ」14回分を「佐高ミュージアム 番外編」として公開することにしました。「自ら体験した身近な自然のおもしろさを生徒に知ってもらう」というコンセプトは変わりませんが、佐高を名乗るのはさすがに気が引けるので、「番外編」としました。
これまで読んでくださった方は、その続きとして読んでいただければ幸いです。
佐高ミュージアム 番外編 N0.1 「菜の花いろいろ」.pdf
佐高ミュージアム 番外編 N0.2 「野菜の花」.pdf
佐高ミュージアム 番外編 N0.3 「赤トンボ予備軍」.pdf
佐高ミュージアム 番外編 N0.4 「カンピョウstory in 夏休み」.pdf
佐高ミュージアム 番外編 N0.5 「緑色の繭」.pdf
前回で、佐野高校で過ごした8年間(1986年から1993年)で発行した「すっかんぽ」をすべて公開しました。しかし、次の勤務校である小山西高校でも、しぶとく「すっかんぽ」を発行していました。そこで、その間に発行した「すっかんぽ」14回分を「佐高ミュージアム 番外編」として公開することにしました。「自ら体験した身近な自然のおもしろさを生徒に知ってもらう」というコンセプトは変わりませんが、佐高を名乗るのはさすがに気が引けるので、「番外編」としました。
これまで読んでくださった方は、その続きとして読んでいただければ幸いです。
佐高ミュージアム 番外編 N0.1 「菜の花いろいろ」.pdf
佐高ミュージアム 番外編 N0.2 「野菜の花」.pdf
佐高ミュージアム 番外編 N0.3 「赤トンボ予備軍」.pdf
佐高ミュージアム 番外編 N0.4 「カンピョウstory in 夏休み」.pdf
佐高ミュージアム 番外編 N0.5 「緑色の繭」.pdf
高校野球2回戦(佐野高対栃木商業高)
本日、13:40頃から、清原球場の第3試合として、栃木商業高との2回戦を戦いました。
結果は、見事、1対0で、佐野高校が勝利を収めました。おめでとうございます!
球場に流れる「佐野高校の校歌」に感動しました!
この大会は、保護者2名までしか入れず、応援も禁止という中で行われました。
以下、簡単に試合の様子を写真で紹介します。

結果は、見事、1対0で、佐野高校が勝利を収めました。おめでとうございます!
球場に流れる「佐野高校の校歌」に感動しました!
この大会は、保護者2名までしか入れず、応援も禁止という中で行われました。
以下、簡単に試合の様子を写真で紹介します。

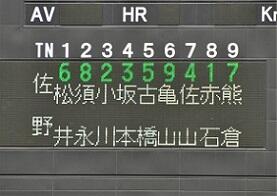
いよいよ試合が始まりました。


ピッチャーの赤石君は堂々たる投球で、力のある球をぐいぐい投げこんできました。3ボールからでも三振を取る度胸の良さには感心させられました。
また、全員の守備も完璧でした。安心して見ていられました。


投打に圧倒していましたが、なかなか1点がとれない展開でした。
しかし、とうとう最後の7回に貴重な1点をもぎ取りました。


須永君(8)がヒットで出塁。


打者小川君(2)の時、須永君が盗塁を決める。


最後にキャプテンの小川君(2)が見事に打ち返し、2塁ランナーの須永君がホームイン。
その裏、最後の打者を打ち取り、ゲームセットとなりました。

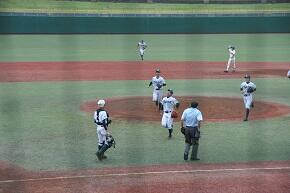
念願の校歌が、球場全体に響き渡りました。素晴らしい試合でした。


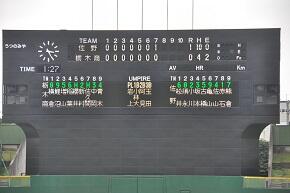

よく頑張った! 素晴らしい感動をありがとう!
次の試合(8月2日)も応援します!
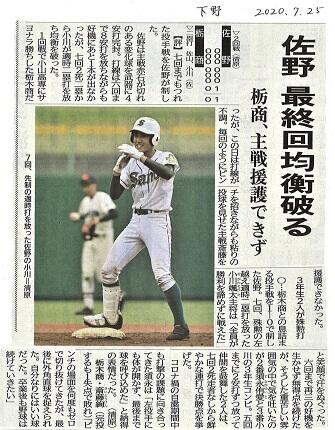
休日の部活動
今日は、13:30から野球部の試合があるので、午前中に学校に立ち寄ったところ、多くの部が活動していました。
①テニス部
→8時半ころ、西門付近を車で通過した際、テニスコートで生徒が草取りをしていましたので、まずは中学のテニス部から見学しました。今年は1年生がたくさん入部してくれたので、総勢33名の大所帯となったそうです。服部先生、富永先生の指導の下、今日は33名全員が参加しています。


①テニス部
→8時半ころ、西門付近を車で通過した際、テニスコートで生徒が草取りをしていましたので、まずは中学のテニス部から見学しました。今年は1年生がたくさん入部してくれたので、総勢33名の大所帯となったそうです。服部先生、富永先生の指導の下、今日は33名全員が参加しています。


②ラグビー部
→顧問の柾木先生とともに、朝早くから熱心に練習していました。男女が全く同じ練習をこなしていました。とにかくよく走っていました。


③中学野球部
→部員たちは、まずはキャッチボールから練習を始めていました。


④バレー部
→高校のバレー部は、ちょうど他校との練習試合を始めるところでした。新入部員も入部しずいぶん人数も増えました。チーム力も上がり、めきめきと力を付けてきているそうです。今日の練習試合はどうだったでしょうか。

→中学のバレー部も部員数が増え、充実した練習をしていました。だんだん強くなってきているようです。

⑤高校バスケットボール部
→高校生たちは第2体育館全面を使って、のびのびと練習をしています。


⑥吹奏楽部
→中高合同で練習しています。高校生がパートリーダーとして、中学生を良く指導してくれています。各パートごとに今日は8か所で練習をしていました。
高校生の指導は、非常に的確で感心しました。
<音楽室>打楽器のパートです。


<パソコン室>バスのパートです。

<英語演習室>トランペットのパートです。

<選択4教室>クラリネットのパートです。

<選択3教室>トロンボーンのパートです。
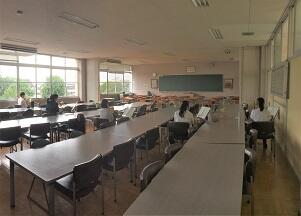
<教育相談室>サックスのパートです。

<教育相談室>ホルンのパートです。

<教育相談室>フルートのパートです。

*コロナの影響で、なかなか全体練習がやりにくい状況なのかと思いますが、中高合同の練習が、非常にうまく機能していると感じました。旭城祭での発表に向けて、頑張ってください。
PTA本部役員会が開かれました
本日、本校の選択3教室で「PTA本部役員会」が、以下の日程で開催されました。
本部役員会 9:00~10:10
専門部会 10:10~10:30
支部打合せ 10:30~11:00
PTA役員が一堂に会する集まりは、今年度で初めてでしたので、PTA会長、PTA会長代行、校長の挨拶に続いて、全員の自己紹介から始まりました。
議事としては、
(1)PTA総会資料について
(2)旭城祭への参加・協力について(仮)
(3)学校HPのリニューアルについて
(4)専門部会年間活動計画について
(5)支部会活動計画について
(6)その他
以上について、協議しました。
本部役員会 9:00~10:10
専門部会 10:10~10:30
支部打合せ 10:30~11:00
PTA役員が一堂に会する集まりは、今年度で初めてでしたので、PTA会長、PTA会長代行、校長の挨拶に続いて、全員の自己紹介から始まりました。
議事としては、
(1)PTA総会資料について
(2)旭城祭への参加・協力について(仮)
(3)学校HPのリニューアルについて
(4)専門部会年間活動計画について
(5)支部会活動計画について
(6)その他
以上について、協議しました。
その後、専門部会ごとに分かれて話し合いが行われ、最後に、支部会ごとに話し合いを行いました。

各支部ごとに集まっています。

この部屋は、足利支部の集まりです。
緊急情報
特にありません。
カウンター
0
9
8
9
9
3
4
6







