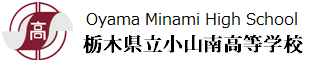平成30年12月19日(水)に、3年生による「卒業研究発表会」を実施しました。
発表者は、事前審査結果により選出された10名で、研究内容は以下の通りです。
(1)落合楓華(3S1)「フリースローにおけるルーティーンとシュート率の関係性~ルーティーンの種類~」
(2)小山琳花(3S1)「バレーボールのサーブは回転と無回転ではどちらが効果的なのか」
(3)川崎光唯響(3S1)「スナッチにおいて強い選手とフォームが同じほうが強いのか」
(4)丸山侑子(3S2)「液晶画面を見ている時間と視力の関係」
(5)福嶋歩(3S2)「~先頭打者の出類似への関係性~またヒット時と相手のミスでの出塁について」
(6)石川港人(3S3)「ファーストストライクは打者にどのように影響するのか」
(7)田中玲奈(3S3)「フルセットまで行った試合で1セット目と2セット目どちらを取ったほうが3セット目を取る確率が高いのか」
(8)伴瀬唯斗(3S3)「サッカーにおけるボールの飛距離とその関係性」
(9)星野太河(3S3)「球速と投球内容の関係」
(10)松本大地(3S3)「トレーニングと回復法~効率の良い回復法~」
1年間の研究の成果を感じられる発表となりました。
<校長挨拶>

<全体の様子>

<発表の様子①> <発表の様子②>